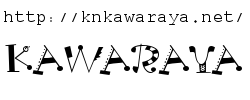
小説を連載しています。 / ブログ
柊木香月は空を見ていた。
漆黒の夜、雲一つない空を見て、彼は小さく溜息を吐いた。
黒いパーカー、ただし帽子の部分はネイビーブルーとなっている、は彼が『任務』の時にしか着ることのない服装である。これを着ることで、気合が出るというわけではないが、どこか普段とは違う――ここが自分の『世界』なのだ――ということを実感させられる。
すう、と息を吸う。
世界はとても大きくて、自分という存在がとても小さいことを実感させられる。
「そこでモノローグに浸っている少年魔術師サン? ちょいと宜しいかしら」
そう言って、香月の隣に腰掛ける女性。
ここで、場所を確認しよう。
木崎市中心部にあるとある高層ビル、その屋上。そこに香月と女性は居た。香月は屹立し、女性は腰掛けている。お互い、その場所が屋上だとは思わせない。
「誰かと思えば優花じゃないか。どうした?」
優花、と呼ばれた和服姿の女性は小さく溜息を吐くと、持っていた紙束を手渡す。
「あなたに依頼よ、ランキング七位のあなたに、うってつけの任務ではないかしら」
ランキング。
魔術師のレベルを決める唯一の指標である。その基準は様々で、とくに一番基準とされているのは実行することが出来る命令である。
魔術師の命令はいずれも魔術を行使出来る『コンパイラ』によって行われる。魔術師の編み出す魔術はその魔術師にしか使えないようにコピーガードという形で暗号化されているのが大半である。そのコピーガードを外し、魔術詠唱の形に直すのがコンパイラの役目ともいえる。
そのランキングで十位以内ともなれば、世界から称賛されるのが大半である。それとは別に称賛されることなく、むしろその手法が批判されている魔術師も居るのだが。
「任務、ねえ」
香月は紙を捲り、内容を確認していく。
魔術師は無所属(フリーランス)とする者は殆ど居らず、大半が組織に所属している。そうでないと魔術師の仕事がやってこないためである。
魔術師の仕事――任務は組織を通じて、その組織の『任務番』が直々に伝える。
彼女、予野優花は香月の所属する組織『ヘテロダイン』の任務番、その一人だ。
任務の内容はいたってシンプルであることを理解し、その紙束を優花に返す。優花はそれを受け取ると笑みを浮かべる。
「どう? やってくれるかしら」
「やってくれるか、くれないかではなくて。やらなくてはいけないのだろう? もう何年もヘテロダインに所属しているのだから、それくらい理解しているよ」
「そう……。ならいいのだけれど」
優花は立ち上がる。風が吹き、彼女の髪が乱れる。
それを香月は見つめていた。見惚れていた、というわけではない。監視している、というのが正解だ。
香月はもう何年も組織に入っているが、それはあくまでも魔術師として食べていくためだけのこと。齢十五歳の少年が一人で生きていくためにはこのような一般社会とは外れた生き方をしないといけないのである。
「さて、と……。それじゃ、早速やっていただけるかしら。もちろん、あなたのような優秀な魔術師に行ってもらえるのだから、報酬もそれなりに弾んでくれるはず」
「そうでなくては困るけれどね」
そう言って、香月はあるものを取り出す。
それは魔術師ならば誰もが持っているもの――コンパイラ。
しかし魔術師は敢えて、それをこう呼ぶ。
_ ――魔術詠唱コンパイラ(コンパイルキューブ)。
_ 魔術師が用いることでその効果を発揮する、手のひら大の立方体である。普通の人間が持つだけでは何の効果も発揮しない。寧ろ必要ない存在といえるだろう。しかし魔術師が持つことによって、それは魔術を詠唱するために必要不可欠な存在へと昇華し得るのだ。
香月は目を瞑り呟く。
「ej・yf・sy・em・va・nu・hscj」
日本語でも英語でも無い、発音。それこそが魔術師の詠唱――その基礎コードであった。
基礎コードがコンパイルキューブに通される。
そして、魔術の完成。詠唱が完了し、彼の身体がふわりと浮かび上がる。
「それじゃ、行ってくるよ」
「……どこまで?」
優花の言葉に、知っているはずだろ、とだけ言って彼は手を振ることも無く、その場所へと飛んでいった。
その姿が消えるまで、優花は見つめるだけだった。
少女は走っていた。
木崎第一中学校。木崎市にある中学校であり、何の変哲もない。全校生徒六百三十人、運動部よりも文化部の活動のほうが活発である、ごく普通の中学校。
その廊下を、彼女は走っていた。普段ならば廊下を走ることなんてしない、規律を守る彼女だったが、このときは違った。このときばかりは規律よりも自らの命を守るほうを優先した。
彼女は追われていた。
背後から追いかけてきているのは、一人の少年だった。髪も、服装も、凡て白で統一されている。唯一、その目が赤いことだけが不気味に浮き上がっていた。
なぜ狙われなくてはならないのか。
なぜ攻撃されなくてはならないのか。
彼女は解らなかった。当然だ、なぜなら彼女はただの一般人なのだから。
「追われている理由が解らない、とは言わせないよ?」
――呼吸が止まったような、気がした。
気付けば目の前に、追いかけてきていた相手が立っていた。いったいどういう近道を使えばこんなことが可能だったのか――。
「まったく。魔術師ランキング二十一位、それも『移動魔術』専門の僕にどうにかしようなんて無駄だよ、無駄。まったくの無駄。そんなことをするのであればさっさと降伏して、君のその力を解析させる。それしか方法は無いわけだよ?」
「あの……力……って」
彼女は力が抜けてしまったのか、床にへたり込む。
それを聞いた自称魔術師は高笑いした。
「はははははははは! 今、君はなんて言った? 『力、って』そう言ったね? 何を言っているんだ。その力は君が魔術師となった瞬間、とてつもない力となることは間違いない。そんな力だ。裏を返せば僕たち魔術師にとっては脅威であるとも言えるのだけれど」
魔術師。脅威。
その言葉の意味を彼女は理解できなかった。
理解する余裕も無かった、と言ったほうが正しいかもしれない。
「君の力は、君が一番理解しているだろうよ。追われている立場である理由が解らない。自分は一般人です。そう思っているのならば大きな間違い。君はもう魔術師の領域に片足突っ込んでいる。それくらい解ってくれないかな?」
とどのつまり。
彼女はもう一般人ではないことを、彼は告げていた。
一般人からしてみれば、ある種の死刑宣告に近いそれを聞いた彼女は絶望した。自分がなぜそのような目に合わなくてはならないのか――嘆いた。
「まあ、仕方ないよね。君の血筋もそうだ。そもそも、君はそういう生まれにならざるを得なかったのだよ。ただ、どちらかの血が強かったのか、純粋な魔術師には成り得なかったようだけれど」
魔術師は立方体をポケットから取り出す。
それは魔術師が魔術を行使するときに必要とする――コンパイルキューブだった。
コンパイルキューブに囁くように、彼は呟く。
「ej・ei・fr・et・ff」
その瞬間、魔術師のコンパイルキューブから炎が放たれ、彼女の身体は消し炭に――。
――なるはずだった。
「あ?」
魔術師はどこか抜けたような声を出す。目の前に居たのだから魔術は成功しているはずだった。だから、彼女が魔術師でなければそれを避けることは出来ないはず――。
「……まさか!」
そう。
それだけではない。
彼女が救われる方法は、もう一つあった。
「……魔術を使うことの出来ない一般人を魔術で嬲り殺し、か。魔術師の風上にも置けないね。それでほんとうにランキング二十一位? 笑える話だ。ランキングの定義も随分と地位が落ちてしまったのだろうか?」
窓枠に腰掛ける、一人の少年。
黒いパーカーを着た少年の下に少女が横たわっていた。
「貴様……それは俺が狙っていた獲物だ! それを奪うっていうのか?!」
「獲物……。君、もしかして無所属なわけ? だとしたら珍しい魔術師だね。生計を立てている魔術師なんて、たいていどこかに所属しているのが殆どだというのに」
「お前が無所属だと思うのならば、そういうことにしておいてやろう」
「違うことは、最初から解っているよ。僕を誰だと思っている? ……ああ、そうか。月明かりが無いから僕の姿を見ることが出来ないのだね。残念、残念。もし君が僕の姿を見ることが出来たのならば、さっさとここから姿を消していただろうからね」
窓枠から降りて、ゆっくりと歩き出す少年。
その姿が見えるまでに、そう時間はかからなかった。
「お前……何者だ?」
それはわざとか、わざとではないのか、少年には解らなかった。
だが、少年は敢えて答えた。
「僕の名前は『ヘテロダイン』所属、ランキング七位の柊木香月だよ。……さすがにここまで聞けば誰なのかくらいは理解できると思うのだけれどね?」
それを聞いて魔術師の顔が青ざめた。
彼の言ったランキング二十一位がほんとうであったとしても、香月のランキングは七位。到底勝てる相手ではない。彼が香月に魔術を当てるには、ネズミがライオンに攻撃出来る確率が必要となるだろう。
要するに不可能。
今の状況を鑑みるならば、逃げるしかないだろう。
だが、香月は違った。
「……普通に慈悲のある魔術師ならばここで逃げることを選択させただろう」
溜息を吐いて、ポケットからコンパイルキューブを取り出す。
「――だが、僕は違う」
声色が、変わった。
「ej・bek・bb・et・clp」
予兆は無かった。
直後、魔術師の身体は――完全に崩れ去った。
「破壊する魔術だ。それくらい覚えておけば、まだ僕に勝てるチャンスはあっただろうにね」
呟いて、踵を返す。
改めて問題点に着目して、香月は頭を掻いた。
「さて……この問題、どう解決しようかね?」
未だ気絶している少女――彼女を見つめながら、そう呟いた。
木崎市中心部より少し離れた場所にある今宮病院。
その五階にある総合診療科に香月は居た。回転いすに腰掛けて、目の前に居る白衣を着た女性と話をしていた。その女性は見た目だけで言えば香月と同じくらいの年齢に見える。
「少年魔術師、では無く本名で言ってくれないかな。ここは普通の病院だぞ? 僕だって柊木香月という立派な名前があるのだよ?」
「ああ、そうだったな」
しかし、女性はそれに悪びれる様子も無かった。
「それにしても、だ。どうして君は私という存在がありながら女性を連れ込みたいのかな? 嫉妬の炎を私に燃やさせて、三角関係へと発展させるための伏線かな? そうだと言ってくれると逆に安心するのだがね」
「……そういう言動さえ無ければ天才なのだがなあ。人間というのは、どうしてこうして、欠陥が必ず一つはあるのだろうな」
女性は笑う。
「私は天才だよ。それは誰にだって否定させない。……まあ、冗談はほどほどにしておいて」
冗談だとは思えなかった。
女性は横にあるベッドにて眠っている――少女のほうに目をやった。
「彼女はただ気絶していただけだよ。それに疲労が溜まっていたようだ。……魔術師に負われていて、何も怪我が無かったことだけが驚きだよ。まったく、人間というのは面白いものだよ」
「あんただって人間だろう。それに、彼女はただの人間だ。コンパイルキューブも持っていなかったし、基礎コードをいっても理解していないそぶりを見せていた。もちろん、演技の可能性だって考えられるが……。だが、コンパイルキューブを持たずに魔術師と邂逅するのははっきり言って、ただの馬鹿だ。それを考慮すると……やはり彼女はただの一般人としか考えられない」
「それがそう言えないかもしれないよ?」
そう言って女性は机上に置かれていたカルテを見せた。
香月は驚いた――だがそれを表に見せることはしなかった。
「カルテは機密情報だろう……。見せていいのか、そんなものを」
「とっくに亡くなっている人間だ。それに……今回のことに無関係だとは言えなくなるよ」
カルテを手に取り、香月はそれを見る。
名前は城山義実。年齢は四十二歳。五年前に亡くなっている。
そしてその名前と顔を見て――彼は思い出し、女性のほうを見た。
女性は笑みを浮かべつつ、言った。
「なあ? 関係があると言っただろう?」
城山義実――魔術師が聞けば、武者震いで震え上がると言ってもおかしくない程、『最強』と謳われた魔術師であった。過去形なのは、すでに彼が亡くなっているからである。
彼の死因は、現在一位となっている『ホワイトエビル』代表増山敬一郎との勝負に負けたからだと言われている。増山は残忍な男だと、その界隈では有名であり、彼は卑劣な方法で殺されたのではないか――などという噂も立っている程。
「……そもそも死因が焼殺だということを知っていたか?」
「それは噂でも流れてきているからな。全身が真っ黒になるくらい焼けていたとも聞いている」
「そうだ。その通りだ。……あの時、私が検死を行った。はっきり言って、ひどいものだったよ。魔術師同士の戦いで敗れた人間は、こうなってしまうのだということを、まざまざと見せつけられた。あれを見て吐き気を催さなかったのが珍しいくらいだ」
女性は立ち上がり、少女の頭を撫でた。
「……だが、少女と城山義実に関係が……」
「城山春歌」
唐突に、女性が名前を言った。
「……今ここに眠っている少女の名前だよ。城山春歌、彼女はかつて最強の魔術師として謳われた城山義実の娘だ」
_ 城山春歌が目を覚ました時、そこにあったのは天井だった。
「ここは……!」
起き上がると、漸く彼女がどこに居るのかを理解する。
カーテンと、消毒用アルコールのにおい。
ここが病院だと判断するまでに、そう時間はかからなかった。
「目を覚ましたかい? ここは今宮病院だ。個人経営、とまではいかないけれど、そこそこ大きい病院に比べれば小さいものだよ」
「どうして、私はここに……?」
「気絶していたからだろうね。彼が連れてきてくれたよ」
そう言って白衣を着た女性は親指である場所を指した。
そこに居たのは――黒いパーカーを着た香月だった。
「あなたが……私を?」
春歌が声をかけたと同時に、彼は春歌を睨み付ける。
少し怯える彼女に、女性が香月の頭にチョップする。
「何するんだっ」
「何をするんだ、というのはこっちのセリフよ? 彼女は今起きたばかりで精神も安定していない。というのに恐怖を植え付けるとか何を考えているつもり?」
「だって俺の『任務』は終わったからな。あとは組織から金を貰えば、あとはまた別の任務待ちだよ」
それを聞いて女性は溜息を吐く。
「……なんというか、まあ。いったい誰に似たのだろうね、香月クン」
「あの……あなたたちは知り合いなのですか?」
かけた眼鏡の位置を直しながら、春歌は言った。
「知り合いというよりは腐れ縁だよ。小さいときから、湯川のことを知っていただけだ」
溜息を吐いて答えたのは香月。
湯川と呼ばれた女性は頬を両手で押さえながら照れている素振りを見せる。
「いやだなあ、香月クン。昔みたいに果(このみ)お姉さんと呼んでもいいのだぞ?」
果はそう言って、香月を抱きしめる。屈んでいる彼女の胸付近に、香月の顔が当たる形になる。
「ちょっと待て! そもそもこんなことされる筋合いなんて無いし!」
「いいじゃないか。昔はこうやって遊んだだろう?」
――春歌がこのテンションについていけないのと、果と香月のテンションに引いているのを見た果は、香月を解放する。
「済まなかったねえ。これがいつもなのだよ。最近、香月クンは遊びに来ないし。来るとしてもこういう風に怪我をしたか厄介事を背負い込んだ時くらい。まったく、病院を便利屋扱いしないでほしいね」
「毎日のように、怪我もしていないのに病院行くわけがないだろ! それこそ破産する!」
「じゃあ、養ってあげようか?」
「そういう問題じゃない!」
「あ、あの……? もうほんとうに大丈夫ですので……」
「そうかい? だったら僕はもう帰らせてもらうよ。仕事が簡単すぎたというのもあるけれど、明日は明日でやることがあるからね」
そう言って欠伸を一つし、香月は診療室を後にした。
春歌と果だけの部屋となったが、別段果はそれを気にする様子も無かった。というのも、時間的にもう夜間診療の時間となるらしく、ナースも先生も患者も少ないらしい。
となると仮に患者が来た場合、ここに居る春歌も診療出来る先生の対象になるのだろうが――。
「ああ、もし夜間診療を私もやるのではないか……と思っているのならば心配しなくていいよ。私は君の治療につきっきりということになっているから。もし何かあっても、君の治療をやっているという体で頼むよ」
「ほんとうにあの人に言われたように天才なんですよね……?」
「ああ、天才だよ。君の心の奥にある、魔術師に対する負の感情も感じ取れるくらいに、ね」
それを聞いた彼女は顔を顰める。それを感じ取られるとは思わなかったのだろう。
それを気にせず、果は話を続ける。
「彼は強い人間だよ。あの年齢であれ程の魔術を使うことが出来るのだからね。過去にいろいろあったのは確かだが……それでも彼は強く生きている。それゆえに、甘えることを知らないのだよ」
「何か……あったのですか……?」
果が口を噤んだのを見て、春歌はしまったと思った。
そんなことを言ってしまって、完全に失言だと思った。
だが、そのようなことを気にすることも無く、果は話を続ける。
「香月クンの両親、彼が小さいころに死んでしまったのよね。二人とも、優秀な魔術師だったらしいけれど……。それゆえに、ライバルが多かったようよ。だから、殺されたのではないかなどと言われているけれど……そもそもあの事故じゃ……魔術師の仕業とは一概に言えないし」
「事故?」
「十年前、木崎湾に落下した飛行機事故……聞いたことは無い?」
春歌は頷く。この市に住んでいる人間ならばその大半は聞いたことがあるからだ。
木崎湾飛行機墜落事故。
木崎湾に墜落した飛行機に居た乗客乗員合計二百二十名のうち、生き残ったのは四名。当時その四名は『奇跡の四人』などと言われメディア・マスコミに取り沙汰されていたものである。
「あれは……ほんとうにひどいものだった。今だって思い出したくないくらいだ。私は、あの事故の検死を担当してね。命が無い人間を何百人も見ていくのは苦痛のほか言いようが無かったよ」
果の言葉を聞いて、春歌はその言葉に相槌を打つことすらできなかった。しなかったのではない。彼に隠されたその過去を聞いて、何もできなかったのであった。
だのに春歌は彼に冷たい目線を送った。送ってしまった。
「君に、そのような心を示す必要はないよ。知らなかったことは罪ではない。それに、彼は孤独が好きなだけだよ」
――彼女は、ここで思った。
もしかしたら、彼にならば――彼にならば、私を助けてくれるかもしれない、と。
唯一の希望。光。それを見つけた気がした。
「お願いします」
だから、言った。
「――彼の居場所を、教えてください」
_ 2
_ 柊木香月は夜の街を歩いていた。
すでに時刻は深夜零時を回っている。
木崎市は港湾都市としてその栄華を築いた都市である。木崎市の南部には木崎湾が広がり、世界各地から様々な荷物が輸入及び輸出される。
そういうわけで。
木崎市はワールドワイドに対応しており、その明かりが二十四時間尽きることは無い。木崎市が直営する原子力発電所もあり、電力は充分に賄えるのだという。環境団体は原子力発電所以外の発電所を作ることを反対しており、また市にとっても原子力の方が、他に比べてコストパフォーマンスが良いということから、火力発電所よりも原子力発電所が多いという結論に至っている。
二十四時間営業のコンビニエンスストアに入り、商品棚を物色する。棚には様々な商品が展示されており、最終的に缶コーヒーとおにぎりを手に取る。
レジを通し、お金を払い、袋に入れてもらい、それを受け取り、外に出る。たったそれだけの行動であり、時間も僅か数分。効率性を求めて、彼は任務の後の食事は必ずコンビニと決めている。コストパフォーマンスを考えて、これがベストであると決めたからだ。
何だかんだで、食事を作ろうという気はないのであった。
おにぎりの封を開け、一口頬張る。彼が手に取ったおにぎりのうち一つは、大抵いつも食べているものだ。
ツナマヨネーズ。
それを食べないと身体が落ち着かないくらい、彼はツナマヨネーズのおにぎりを食べていて、彼はそれが無くてはならない体になってしまった。
彼が住んでいる家は木崎市にある小さなマンションである。そのマンションに帰れば、あとは眠るだけ。それで充分だった。
退屈なんて、思っちゃいなかった。
むしろ、これだけでいいと思っていた。これで充分だと思っていた。
だからこそ、彼は――ほんの一瞬だけ油断していた。
_ ドゴッ!!!!!! と彼が歩いていた横にあったビルが崩落した。
_ 突如と無く。かつ予兆も無い。
ビニール袋は手に持ったまま、しかしそこから逃げることも無く、ビルを見る。
――すでに破壊されたビル、その瓦礫の上には、誰かが立っていた。
迷彩柄のワンピースを着た少女だった。金髪が青白い月光に照らされ、輝いている。風に靡くその光景は、切り出せば一つの絵になるかもしれないと思う程であった。
「……ランキング七位、柊木香月。専門は……おや、未登録ですか。何というか、珍しいですね。『データベース』に登録が無い魔術師が、未だこの世界に住んでいたなんて」
少女は取り出したスマートフォンの画面を見ながら、ぶつぶつと呟く。しかしその声は様子を窺っている香月にも聞こえるくらい大きなものだった。
聞いていた香月は鼻で笑い、答える。
「今のこの世界、情報を持つものが制する。それは昔、聞いたことがあったからね。そう簡単に登録するのは避けているというわけだ。そもそも、登録しなくてはならないという理由は無いからね」
「成る程。至極御尤もでありその通りの発言であるね」
スマートフォンに口を近づけながら、少女は言った。
香月はそれが何を意味しているのかそれに気付かなかった。もし彼が気付いていたのならば、もう少し戦いは有利に進んでいたかもしれない。
「ej・ei・bb・et・ff・ff・ff!」
それが詠唱――基礎コードであることは彼も解っていた。
だが、少女が持っているスマートフォンがコンパイルキューブであることに気付くには、少し時間を要した。
直後、轟! と炎が彼の周りに渦巻き始める。
「スマートフォンにコンパイルキューブを組み込んだ……だと!?」
香月の返答に、高笑いで答える少女。
「そうだ! ランキング七位と言っていたから、強いものかと最初から本気出してみたけれど、これくらいも解らないのか……。ランキングの基準って解らないものだね!」
「……どうかな。実際解らないぞ。案外面白く、単純に決まっているかもしれないな」
「負け犬の遠吠えかい? ……どちらにせよ、そのままじゃ死んじゃうよ?」
「そう思っているならそれでいいさ。……君は殺せるのかい?」
それを聞いて、少女は首を傾げた。
「何が言いたい?」
「当然のこと。君は人を殺したことがあるのか、そして今も殺そうとしているが、殺せるのかということだよ。ランキング一桁を倒そうとしているのだから、それくらいの覚悟はしているのだろうね……という話だけれど」
「ff・ff・ff!!」
その言葉によりさらに強くなる。
香月は炎の中から少女の姿を見つめるだけだった。
そして、炎の渦が香月の身体を飲み込んだ。
_ ◇◇◇
_ 少女は消し炭となった、その場所に立つ。コンクリートが熱で少し溶けたこと以外は、何の変哲もない。よもやここで『人を焼いた』など思うはずもないだろう。
これで彼女のランキングが幾らか繰り上がる。十位以内に入っているランキングホルダーを倒したのだから、当然のことだ。
それにしても、あの若い少年がほんとうに魔術師で、しかもランキングホルダーだとは思いもしなかった。魔術師のランクは年齢に比例しない。かといって反比例もしない。年齢はただの指標に過ぎないのである。
少女は腰につけていたカバンから煙草のようなものが入っている箱を取り出す。
そしてそれを、炎を付けぬまま口づけた。
それが彼女の日課であった。敵を倒した後の、至福の瞬間。これが彼女の一番好きな時であったし、一番大好きな瞬間であった。
だからこそ、油断していたのかもしれない。
瞬間、彼女は――違和感に気付いた。
それが、彼女の身体を突き刺す、何者かの腕であることは解るのには、少しだけ時間を要した。
「……な、ぜ?」
背後には、香月が立っていた。
笑みを浮かべて、彼が立っていた。
「僕が何もしなかったことに疑問を浮かべたのはいいだろう。だけれど、そこから何も考えなかったのは及第点をあげるには無理だったね。そこで、『なぜ僕が何もしなかったのか』ということについて考えて、せめて一つの結論を導いていればよかったというのに」
「……結論?」
ぐちゅり、という音を立てながら、一気に腕を引き抜く香月。
「がああああああああああ!!??」
激痛による絶叫。それを聞くことも無く、彼はというと。
「あーあ……お気に入りのパーカーが血で汚れてしまった。どうするか、責任を取ってくれるのだろうね?」
戦闘よりもパーカーの汚れをきにしていた。
血を吐きながら、それでも彼女は未だ香月を見つめていた。睨み付けていた。
「……お? まだ戦える感じ? いいなあ、僕はそういうの好きだよ。及第点を一つ、あげてもいいくらいだ」
だけれど、と言って踵を返す。
それをチャンスと思った少女はスマートフォンを取り出し、基礎コードを詠唱しようと考えるが――。
「――だが、もう遅い」
その直後、彼女の身体が炎に包まれた。
「ああああああああ!!!!」
「ああ、言っておくけれど、それで簡単に殺す程僕も甘くない。何せ僕は殺されかけたのだからね? 一瞬とはいえ、だ。だから、君には情報を言う義務がある。僕に君の知っている情報を伝える義務があるというわけだ」
炎に燃やされながらも、なお生きている。
それは地獄というほかならない。
少女は舌を噛み切ろうかとも思った。
「ああ、舌を噛み切ろうなんてのはやめたほうがいいよ。最悪、舌くらいは復活させられる。どちらにせよ君ははなさなくてはならないということ。解っていただけたかな?」
「……さすがはランキング七位。嘗めていたのは失敗だったか……」
「当然でしょ? ……さてと、こうやっていると身体が燃え尽きてしまうな。質問をしようか、さっさと質問を済ませてしまいたいからね」
そう言って、香月は再び踵を返す。
少女の焼けている身体と向き合って、香月は笑みを浮かべた。
「単刀直入に質問しよう。……なぜ僕を狙った? その口ぶりからして、ランキングホルダーだから狙ったわけではないだろう?」
「ああ、そうだ」
少女は意外にもすぐに返答した。
「ならば、なぜ?」
「――お前は今日、ある魔術師を倒し、少女を救った」
「速いね。いったいそれはどこから回ってきたのか、気になるものだけれど、伝えてくれることは出来ないのだろうね」
「それは伝えることなんて出来ない。私が殺されてしまうからね」
殺されてしまうという言葉に思わず香月は吹き出しそうになった。なぜなら現在進行形で殺されているというのに。
少女の話は続く。
「……まあ、それはいい。その少女が私の上……そうだな、雇い主とでも言えばいいか。そちらさんが欲しがっている」
「お前に任務を与えた人間が居る、と?」
少女は首肯。
「その任務が、少女を手に入れること――だと」
少女の名前を知っているだろうが、取り敢えずその名前を隠しておく。
「そうだ。その少女がどういう力を持っていて、なぜ欲しがっているのかは解らないが……。まあ、任務を与えられたのだからやるしかない。それが魔術師というものだ」
「少女を手に入れる? 彼女には魔術を使える力があるとは思えないが……。まあ、いい。それさえ聞けば十分だ。……ff」
最後、コンパイルキューブに囁きかけて、踵を返す。
直後、少女の包まれている炎が、さらにその勢いを増していく。
そして彼女の身体は燃え尽きた。
_ 3
香月は夜道を歩きながら電話をしていた。少女を組織が狙っているという話を聞いたからとはいえ、それは香月には関係のないことだった。
「そう。彼女は出ていったか。……なに? 僕の場所を聞いた、だって?」
それを聞いて溜息を吐く香月。これで漸く解放されたと思ったから、また忙しくなるのかと思うと溜息しか出ないものだ。
マンションに着いて、エレベーターに乗り込む。五階のボタンを押して、扉を閉める。
――閉めようとしたのだが。
「待ってください!」
それに割り入るように、誰かがエレベーターの中に入ってきた。
その姿は彼も見覚えのある少女だった。
「確か、君の名前は……」
「城山春歌、です」
そう言って春歌は頭を下げる。
香月は鬱陶しそうな表情を浮かべながら、購入した缶コーヒーを開ける。
エレベーターの扉は閉まり、ゆっくりと目標の階に向けて動き始める。
「……それで? どうしてこうして、僕を呼び止めたわけ? 君は魔術師から救われた。僕は魔術師を倒したから報酬がもらえる。それでいいじゃないか。ウィンウィンな関係というわけだよ。それの何が不満だというのか。怪我とかは病院で見てもらっただろうし、きっと湯川のことだろうから完璧に治してもらったのだろうけれど」
「いえ、そういうことでは……。あ、あの……」
苛立ちを隠せない香月は缶コーヒーをもう一口。
「何だね。言ってみればいいんじゃないかな。取り敢えず、考え事をまとめてから」
「ありがとうございます。助けていただいて」
再び頭を下げる春歌。
それを見て目を丸くする香月。
頭を上げてもなお、香月は目を丸くしたままだった。
「あ、あの……。どうしましたか?」
「いや、まさか……。それだけを言うために来たのではないだろうね?」
「はい」
同時に扉が開く。どうやら目的の階に着いたらしい。
そしてそれと同時に目に入ったのは、黒いスーツの男だった。背丈は二メートル以上ある。
男は春歌を見つめながら、言った。
「城山春歌で、相違ないな?」
「……不味い!」
刹那、香月は春歌の腰を手に取り、彼女を引き寄せた。
直後、春歌の居た場所に網が張り巡らされた。
「……流石というか、なんというか。やはり、ランキング七位の魔術師だけはある」
コキコキと首を鳴らし、男は鼻で笑った。その目つきはサングラスをしているためか、薄らとしか見ることが出来ない。
「――だからこそ、殺し甲斐があるというものだ」
男はポケットからあるものを取り出した。
それはナイフだった。ナイフを舐めながら、ゆっくりと香月の方に近付いてくる。
「|快楽殺人鬼(シリアルキラー)って聞いたことがあるか? 殺人を主にして行動する犯罪者、だったか。まあ、ここで定義のことをとやかく言うのはあまりよろしくないが……俺はそういうものに属する存在というわけだ」
「魔術で人を殺す……ということか。そのナイフは魔術伝達の媒体ということだろう?」
男は頷く。その表情は笑みを含んでいた。
「流石だな。そこまでまるわかりとは。……だからこそ、俺も全力を出せるというもの……!」
男は手首に口を近づけ、呟く。
基礎コード――その入力。
それに気付いたからこそ、彼は背を向ける。
そこにはエレベーターの壁があるだけだった。
「恐れをなしたか!」
男の言葉を無視して、彼はコンパイルキューブに基礎コードを入力する。
「ej・bek・afl・zz!」
基礎コードがコンパイルキューブに通され、『コンパイル』される。
直後、香月の目の前にあった壁が崩落し、穴が出来た。その大きさはちょうど一メートル六十センチ程。香月も春歌も少しだけ屈めば入ることの出来る大きさだ。その穴からは空が確認できる。
「逃げるつもりか!」
「残念ながら、一般人が居るからね」
そして、香月は春歌を抱えたまま空へ飛び込んでいった――。
急いで後を追ったスーツの男だったが――あいにく飛行魔術を使えず――ただ下を眺めるだけだった。
スーツの男はスマートフォンを取り出し、ある場所に電話をかける。
電話はすぐに繋がった。
「もしもし、俺だ。ターゲット及び魔術師が逃走した。ああ、申し訳ない。急いで後を追ってくれ。今、座標を転送する――」
_ 4
_ 夜の街を滑空する香月。そして彼にお姫様抱っこをされている形の春歌。
春歌はその様子がとても恥ずかしかったが、しかし今自分が置かれている状況を無視して、この風景がとても綺麗だと感じていた。
空から見上げた木崎市の夜景は、彼女が思っている以上に幻想的だ。
それに対比して、先ほど彼らが居たマンションは煙を上げている。
「……まったく、失敗だ。残念だったよ。あそこにはあまりものを置いていなかったとはいえ、魔術師の潜入を許してしまうのだからな」
「あのマンションって……特別なマンションだったのですか?」
「いいや。そんなことは無い。強いて言うならば、僕の住んでいる五階だけは結界を貼っている。それは魔術師でなければ解らないように細工をしているがね。それくらい、安心して暮らしたいものだが……。どうも、ランキングホルダーを狙うのは予想以上に多いのだよ」
「マンションに結界を……」
「そうだ。最悪マンションが全壊するような魔術をかけられたとしても、五階だけは無事に浮遊している状態になる……。それくらい強力な結界だよ。しかも、僕が認めた魔術師以外は完全に排除する。多分入った瞬間にお陀仏だろうね」
それを聞いて春歌はぞっとした。そのような場所に何の確認もせずに、自分は中に入ったのか――そう思うと自分の警戒心のなさが浮き彫りになる。
春歌の不安そうな表情を見て、香月は微笑む。
「だからと言って人間に被害が生じるわけではない。寧ろ人間を救うための結界だよ。あそこは普通のマンションだ。満室とまでは言わないが、それなりに人が入っている。しかもその大半が魔術師ではない、ただの人間だ。そのような人間を無碍に巻き込んではいけない……僕はそう思っているわけだよ。だから、あのようなことをするというわけだ。まあ、このような人間は魔術師の中でも少ないほうだよ。今は魔術師の権利を主張して、現実世界に反旗を翻そうと思っている魔術勢力だって居るくらいだからね」
「そのようなことが……」
そんなことを話していると、目の前にビルの屋上が見えてきた。彼女が気付かないうちに、香月は飛行高度を上げていたようだった。
屋上に足を付け、ゆっくりと重力を実感する春歌。そして彼女は、地面に足を付けた。
「……あの、ここは?」
「待っていたよ、香月クン」
聞き覚えのある声――振り返るとそこには果が立っていた。
香月はそれを見て果の方へ大股で歩いていく。
そして果と香月が向かい合った。
「どうして彼女に僕の住処を教えた。あれは僕が安心して教えることの出来る人間にしか伝えていないこと、そしてそれを教える人間は僕がそれを口外しないだろうと絶対的に信頼している人間にしか伝えていないということを」
「そうだったかな? まあ、いずれにせよ、彼女は困っているようだったからね。仕方ないよね。まあ、いいじゃないか。結果として、助かっているのだから」
「そういうことじゃない! ……まあ、確かに助かったのならばそれでいいかもしれない。今回は、ね。でも次はどうなるか解らないだろう。魔術師同士の戦いはそう簡単に解決するものではないんだよ」
香月の発言に果は首を横に振る。
「いいじゃないか。今が良ければそれでいいだろ。……さ、とにかくここで話すのはちょっと難儀だ。寒いこともあるからね、ここは屋上ということもあるし。病室を一つ貸し切っている。そこを使って話をするといい」
まるで自分がここのオーナーのようだ――春歌はそう思った。
香月はそれに悪びれる様子もなく頷くと、立ち去っていく果の姿を追った。
_ 5
_ 果に案内されたのは七階にある特別病室Aと書かれた部屋だった。
扉の施錠を確認した果は小さく溜息を吐いた。
「……さてと、いったいどういうことになってしまったというのかな? 少しご説明願おうか」
「それは僕も気になっていることでね。ぜひともここにいる城山春歌さんにお訊ねしたいのだが」
二人に言い詰められて、思わず目を丸くする春歌。
しかし春歌のそういう表情を見ても、彼は態度を変えない。
「君は何かを隠している。そしてそれをこちらに言おうとしているのだろう。どちらにせよ、それはとても大変なことなのだろう。僕が君を匿っていれば、僕も殺されてしまうほどの、ね。だからこそ、君が知っている凡てを教えてほしい。でないと、僕はとんでもないことになってしまう」
「彼女から依頼を受け入れる、ということ?」
「違う。これは正式な依頼のシステムではないからね。僕は組織に所属している身分だし、それくらいは選択の余地があってもいいだろう?」
「そういうものかねえ……」
果はそう言って、パイプ椅子に腰掛ける。
「さて、それじゃ物語を戻そう。君は何を知っている? 魔術師ランキングホルダーだった父親を持っていただけで、ほかの魔術師から追われているとは、到底思えないのだが」
「……ええ、そうです」
頷いて、春歌は告げる。
そして――彼女は、絞り出すように、言葉を紡いだ。
「私は――『見え』過ぎるんです」
「見えすぎる? ……何かの能力を持っている、ということか?」
再び頷く春歌。
『見える』という言葉の意味は、様々なものがある。例えば視覚的に見える――遠くの物理対象が視認出来れば、それは『視力がいい』と言えるだろう。でも、それは見えすぎるとは言わない。そう、どちらかといえば、ネガティブめいた発言はしない。
だが、魔術師にとって『見える』となれば――それは別の意味となる。
「まさか、その見えるというのは――」
香月は頭の中に一つの仮説を立てた。
それは、もしその通りならば、恐ろしいことだった。魔術師が狙っている理由も、彼女が怯えている理由も、凡て解決するのだから。
「はい」
春歌は頷く。
「私が見えるのは――『流れ(フロウ)』です」
やはりそうだったか――香月は春歌の言葉を聞いて小さく舌打ちした。
それは、出来ることならばあたってほしくなかった。間違っていてほしかった。
「お、おい……フロウ、ってどういうことだ?」
唯一、状況を理解していない果は香月に訊ねる。
香月は小さく溜息を吐いて、
「……『流れ』とは、大まかなものだ。物が動く線、とでも言えばいいか……。それが見えるということだ。それは何だっていい。水の流れ、空気の流れ、血の流れ……何でも見えるということだ」
「見えたら、何か問題なのか? むしろ便利にも思えるが」
「ああ、便利だよ。便利だからこそ、僕たちのような存在にとって脅威に思えるというわけだ」
「?」
首を傾げる果に説明するため、香月はコンパイルキューブを取り出す。
「僕たち魔術師は、コードは違えどこのコンパイルキューブにコードを通す。それをコンパイルすることによって魔術が実行される。その時、コンパイルキューブと僕たち魔術師の肉体間では魔力の流れが発生しているということだ」
魔力。
魔術師が持っている力である。これが発生できないと、魔術を行使することが出来ない。……要するに魔術師失格ということだ。
「で、その魔力の流れがどうかしたの?」
「魔力の流れが解ると、魔術師はそれだけで魔術が何だか解ることがある。また、仮にコンパイルキューブを隠されて実行されたとしても魔力の流れさえ解っていればどこから魔術が使われるかも解るということだ。……これまで言っても、解らないか?」
「まさか……」
いくら魔術師としての知識が疎いとしても、これくらいは解った。
「魔術の知識を得ることが出来れば、彼女は容易に最強の魔術師となるだろう。……魔術の知識に疎いのは、もしかしたら君を守るために両親がしてくれたことなのかもしれないが……。死人に口なし、とも言うからね。実際には解らない」
その事実は、出来ることなら香月も信じたくなかった。
でも、それ以外――納得のいく結論は見当たらなかった。
「話は分かった」
果は思ったよりも早く理解したらしい。
「でも、問題はここからだ。……どうするつもりだ? まさか、彼女を追っている敵を全員潰すというわけにもいかないだろう?」
それは当然ともいえるだろう。
香月はそう考えていた。
「だろうな。僕が考えるに……おそらく殆どの魔術師が欲しがる代物だろうよ。それをどう使うかは魔術師の自由だが……、どちらにせよ、殺すなり活かすなりするには、先ずはその手に置いておきたいしね」
「……成る程。確かにそれは有り得るな。でも、そうだとしても、私の質問はまだ解決していないぞ、香月クン? 一体全体どうやってこの状況を打破するつもりだい?」
「敵は、魔術師は、彼女に魔術師の知識を与えないことを目的としているはずだ。即ち、魔術師との邂逅、そして魔術師と仲良くなることは最悪のケースだ。そこで魔術の知識を得てしまえば、彼女は魔術師となる。両親が魔術師として優秀だったのなら、その素質があってもおかしくはない」
香月はそう言って、春歌のほうを見た。怯えている彼女だったが、香月の目線を感じて、そちらを向いた。
香月は小さく笑みを浮かべる。
「――さあ、こちらも少し抗ってみることにするかね」
空には飛行船が怪しげに飛んでいた。
_ 6
_ そしてその飛行船。
飛行船は幾つも常に空を飛んでおり、そのどれもが、富裕層のために使われている。
そのうちの一つ――中でも一番大きい飛行船。その名前をグランドブルー号といい、それはとある人間の専用飛行船であった。
ワイングラスを傾けながら、木崎市の夜景を見つめる男。
「……美しい」
男はワイングラスと夜景を交互に見つめながら、小さく呟いた。
男はこの街で一番の勢力、そのリーダーを務めていた。その勢力は厳しい規律の上に成り立っており、だからこそ、今まで固持してきた。
彼が今、目標としているのは――ある少女だった。
どんなものの流れでも見ることの出来る少女は、彼にとって、魔術師にとって、脅威だった。
脅威だからといって、それを取り除こうとは思わなかった。
脅威を脅威ではなく――いっそ利用してしまおう。
彼はそう考えていたのだ。
彼は気配に気づき、背後に目を向けた。
「どうした、何か進展はあったか?」
そこに居たのは黒スーツの男だった。
黒スーツの男は汗をだらだらかきながら、どうすればいいか考えていた。
彼は目の前にしてその対象と一緒に居た魔術師を取り逃がしてしまった。それは彼の部下であるあの少女も同様である。
だから、彼の処遇について――彼自身恐ろしかった。考えたくなかった。
「はい。申し訳ありませんが、現在において進展は……」
だが、嘘を吐くわけにもいかない。彼は諦めて真実を告げることにした。だからといって、助かるわけでもないのだが。
彼は目を瞑り、処遇を待った。何があるか解ったものではない。目を瞑っただけでそれに耐えられるというわけでもない。もしかしたら殺されてしまうかもしれない。
「目を開けろ、井坂。私がそう厳しい人間なわけがないだろう」
「……?」
目を開けて、再び視界が開ける井坂。
「井坂、一度の失敗で人間は評価できるものではない。切り捨てていいかどうかを判断するかは、少なくとも私だけで出来ることだが……。君は部下からの信頼も厚い。そんな君を、たった一度の失敗で排除するのは心苦しい。だから一度だけ、たった一度のチャンスをやろう。それで成功すれば、今回の失敗は帳消しにしてやる」
「あ、ありがとうございます……ありがとうございます……!」
井坂は何度も頭を下げて、そしてその部屋から立ち去っていく。
井坂が出ていったのを見て、男は深い溜息を吐いた。
もともと、彼にそれ程の期待を寄せていたわけでは無かった。それで成功すれば御の字だが、もともと成功するはずもないことだったから、それ程落胆することでも無かったのである。
「まあ、次で成功すればいい。そう焦ることは無い――」
彼が見たその先には、小さな病院。
「――先ずは抗うといい、柊木香月。君と会い見える時を、楽しみにしているよ」
飛行船は夜の木崎市をゆっくりと進んでいた。
病院の一室、深夜の授業が始められていた。
講師は香月、そして生徒は春歌と果だ。彼の狙いからして果がこの授業に参加する必要は無い。だが、彼女曰く暇だから、ということで彼女も受講しているのだった。
今彼が使っているのは何処からか持ってきたホワイトボードだった。まぁ、正確に言えば彼ではなく果が持ってきたのだが。
「魔術は基礎コードで構成されている。そして基礎コードを魔術の形式に変換するのが……コンパイルキューブというわけだ。コンパイルキューブには謎が多いところもあって未だ解明されていない機能もあったりするだろうが……まぁ、概ねこれくらいを覚えておけば問題も無いだろう」
「はい、質問です」
春歌がちょうどの区切りで香月に訊ねるべく手を挙げた。
香月はそれを見て無言で頷く。
「……そもそもの話をしたいんですが、どうして私が魔術について学ぶことと敵が苦しむことが合致しているんですか?」
「いい質問だな。確かに実感が湧かないかもしれないが、君のその『目』とも関係がある」
春歌の目はどんなものの流れでも見ることが出来る、特殊な目である。
「君の目は随分と特殊な目だ。その目さえ使いこなせられれば文字通り魔術師のパワーバランスが逆転するだろうね。血筋としてはエリートだが、まだ『無名』の魔術師が一極に力を得る」
「それが……駄目なことなのですか?」
「うん。だって魔術師はあくまでも裏の世界に栖を持つ存在だ。そんな魔術師が、そんな一人の魔術師が、もともとあったパワーバランスを逆転させる程の力を所持した……としたら? きっと裏と繋がりのある『あちら側』の人間はこちら側を潰しにかかるだろうね。……魔術を知らない人間が魔術を潰そうなんて、非現実的な話ではあるけれど」
あっけらかんと語っているが、その言葉に嘘は含まれていない――どことなく春歌はそんなことを思った。
香月の説明は続く。
「そもそも魔術師は幾つかの勢力に分かれている。僕が所属しているのは『ヘテロダイン』、ここは比較的穏健派だ。機会があれば紹介することとしよう。……まぁ、案外その機会というのは早くやってきそうではあるのだがね」
そう言いながら、ホワイトボードの中央にお世辞にも綺麗とは言えない字体でヘテロダインと書く香月。
それを見つめる春歌と果。その表情はどこか上の空だ。
「……まぁ、確かに解らないのは致し方ない。だが、理解しようとは思ってくれ。せめて、それはあなたたちの身を守るものだということを理解してくれれば、未だ話は違っているのだろうけれど」
そう言って香月は小さく溜息を吐く。魔術師のパワーバランスというものは同じ魔術師である彼にも理解出来ている話ではない。そんな簡単な構造で構成されているならば、誰一人として苦労はしないだろう。
「……魔術師のパワーバランスは非常に面倒となっている。ランキング、などと誰かは言っていたかもしれないが、それだけで凡てが決まるのならばはっきり言って苦労しない」
「ランキング……。強さを指標化しているのですか?」
春歌の言葉に香月は頷く。
しかしながら、彼女の理解には、少々の誤解を孕んでいた。
「正確に言えば強さだけではない。魔術師のレベルというのも関係している。例えば、魔術の使える量。魔術をどれだけ『編み出している』かどうか、それも含まれている。もっとも、魔術は魔術師が作り上げるものだから、そのテンプレートに沿っていくのみ。テンプレートさえ解ってしまえば、案外魔術の解析も楽に進む」
「魔術の……テンプレート?」
頷く香月。
「魔術のテンプレートは簡単なことだよ。主語・述語・述語修飾・対象、そしてオプションからなる。例えば、『僕は空を飛ぶ』という魔術を使う場合、主語は『僕』、述語は『飛ぶ』、述語修飾は『空』、対象は……たぶん『自分自身』、と言った感じかな?」
香月はそう言って笑みを浮かべる。
春歌は理解できなかった。手を挙げ、質問をする。
「それじゃ、英語に少し似ている……ってこと?」
「そうとも言える。そうではないかもしれないがね。魔術師が魔術を作り出すが、その基準は予め決定されている。そうしなくては意味がないからだ」
「それじゃ、それさえ理解していれば……」
漸く意味を理解したらしい。そう思った香月は――薄らと笑みを浮かべる。
「そうだ。それさえ理解することが出来れば、容易に魔術を生み出すことが出来る。魔術を生むことが出来るということは……コンパイルキューブさえあれば、魔術を行使することが出来る。魔術師の完成、というわけだ」
_ ◇◇◇
再び飛空艇。
男は井坂に任務を与えていた。それは非常に単純な任務であり、彼もどうしてこのような任務を与えるのか解らない程だった。
しかし今は、そのようなことを言って居られる立場ではない。
彼は任務に失敗し、本当ならば切り捨てられてもおかしくない立場にあった。
にもかかわらず目の前に居る男は、井坂を捨てることなく、新しい任務――柊木香月の監視という任務を行わせた。
ここで挽回せねばならない。彼はそう思っていた。
「はい。現在、ターゲットに魔術を教えているように思えます」
「成る程。根拠は?」
「コンパイルキューブを見せていたことと、ホワイトボードに魔術の基礎構文が書かれていたためです」
それを聞いて男は微笑む。彼の予想通りだったためである。
「成る程……。柊木香月は、彼女を魔術師として育て上げるつもりだね?」
頷く井坂。
男はそれを見て舌なめずり一つ。
「ならば、構わない。……こちらもそれなりの準備をしてきた。今更ターゲット変更などあり得ない。彼女を魔術師にするのならば、彼女をそう仕立てあげるならば構わない。少し放置しよう」
「……よろしいのですか?」
「私がいいと言ったのだ。いいのだよ。それでも君自身が独自にダメだと言える証拠でも存在するのかね? それをもとに証言して、私が納得するようであれば君の話すように動くが」
「い、いえ。何でもございません」
井坂は委縮して、何も言えなかった。
男は溜息を吐いて、井坂を部屋から下がらせた。
監視を今まで通り続けるよう、命令をして。
_ 2
_ 講義も順調に進んでいた。
夜は明け、空は白んでいく。
「……そろそろ、今日の講義は終わりにしよう。ところで、城山」
「春歌でいいよ。そのほうが呼びやすいでしょう?」
「……ああ、そうだな。春歌。今日は学校か?」
「まあ、そういうことになるね。学生だよ。あなたは?」
「香月でいい。僕も学生だ。学生は学校に行って授業を受けるという義務がある。義務教育というものだね。義務教育を受けるのは大変だが、仕方のないことだ」
「……あなた、中学生だったの?」
「まあ、そういうことになる」
香月は頷く。
「中学生、なの……? ほんとうに?」
「嘘を吐いてどうする。本当だ。だが、それをクラスメイトに話したことは無いけれどね。話したところで、胡散臭い話と思われるのがオチだ」
それは確かに、と春歌は小さく頷いた。
柊木香月は紛れも無い、中学生である。
仕方がない、と思いつつ彼は生徒手帳を彼女に見せた。
それを見て驚く春歌。
「……あなた、木崎一中だったの?」
「まあ、そういうことになるね。木崎一中は僕のホームグラウンドといっても過言ではない。だからこそ、あのような動きが出来たわけであって」
「木崎一中は……私も通っているのよ」
へえ、と答える香月。
まるで興味も無さそうな表情をしている。
朝日を見つめながら、彼は言った。
「取り敢えず、ここから出よう。急がないと、学生に見られてしまう。そのような事態はさすがにまずいだろう?」
それを聞いて、彼女は小さく頷いた。
_ ◇◇◇
_ 柊木香月の家はマンションの五階にあった。
しかしながら、先ほどの事件で破壊されており、朝から警察が実況見分を行っていた。
「はっきり言って、あの状況は不味いな。……まあ、おそらくヘテロダインが何とかしてくれるだろうけれど。先ずは、制服をどうにかせねばなるまい」
「そういうとおもっていたよ」
声を聞いて香月は横を見る。
そこにあったのは一台のバイクだった。バイクに乗り込んでいたのは、豊満な胸を備えたセンパイ系女子だった。正確に言えば、そのセンパイというのは学校の先輩ではなく、組織の先輩ということになるのだが。
「風花さん、ですか?」
「ええ、そうよ。何でも部屋が爆発したと聞いたから、替えの洋服及び制服を持ってきたのよ。組織には保存しているから、もっていってほしい、とね」
そうですか、と言って渡された鞄を見る香月。
その中身は制服と数日分のジャージだった。
「……下着とかあると嬉しかったのですが。まあ、それは仕方ないでしょう」
「残念だったわね! そのパンツ、私がかぶっているわ!」
……残念だったのは、風花の頭だったようだ。そう思うと、香月は溜息を吐いた。別にこれが今に始まったことではないので、別にどうでもよかった。
橘風花は香月を弟のように可愛がっている。組織でもそれは認定されており、よくしているのだが、最近それがブラザーコンプレックス(ブラコン)なのではないかと危惧されている。
そもそも、風花には弟が居ない。一人暮らしである。かつては両親と暮らしていたらしいが、諸般の都合により今は一人で暮らしているとのことだ。
その理由は、彼も知っていた。
_ ――突然種魔術師。
_ 魔術師とは普通、魔術師から生まれるものである。魔術を放つために必要な『魔力』が、大抵は遺伝によるものだからである。しかしながら、奇跡的な確率でそれが遺伝しない或いは魔術師ではない両親から魔力を持った子供が生まれることがある。後者のことを『突然種』と呼ぶ。
突然種の発生確率は一億分の一。即ち日本人の男女比率が等価であるとしたとき、その全員が二人子供を生んで、ようやく一人突然種が生まれるかどうか――という程だ。
それ程に、突然種が生まれることは難しい。
そして、それゆえに、魔術が近くにない環境で生まれる魔術師というのは――許容されないものである。
「……どうしたの、香月くん?」
風花の声を聞いて、我に返る香月。
香月の顔を見て心配してくれたらしい。
「あ、問題ないですよ。大丈夫です。少し、考え事をしていただけなので」
「ああ、この間保護した『彼女』のこと? どうやら魔術師にしようとしているんですって? なんというか、君らしいよ」
「僕らしい?」
「だって、そんなことするのは君しかいないでしょう? 別に君の行動を卑下するつもりは無いけれどさ。だとしても、おかしいよ。彼女は赤の他人なのだよ? 普通なら見捨ててもおかしくは無い。けれど、君は見捨てなかった。それってすごいことだよ。私だったらお金が絡まないのであれば、見捨てるけれどね」
「仕事じゃなければ動かない、ってことですよね。何というか、風花さんらしい」
「それって褒めているのかー? それとも貶しているのかー?」
「どっちだと思います?」
これ以上やり取りを続けていては、学校に遅刻してしまう。
そう思った彼は強引に会話を切り、その場から立ち去った。
_ 3
_ 木崎第一中学校。
二年四組。
「うーい」
教室に入ると何人かの男子生徒が適当な挨拶を交わしてくれる。彼の友人でもある。挨拶を交わした後は、窓際の列の後ろから二番目の席へ。それが彼の定位置だった。
「本当に、香月殿は素晴らしい位置に座っておりますな。私ならば一番にそこを狙うのに!」
すぐに後ろに座っている亀戸から声がかかった。亀戸はアニメに詳しい。だから、時折アニメの知識を言ってくるのだが、あいにく香月には解らなかった。
「その……席がいいのかどうかわからないが、別にいいだろう。ここならば、最悪眠っていてもばれることはない」
「それっていいのでしょうか……? 悪い風にも見えてしまうのですが……」
確かにそうかもしれないが、そんなこと彼には関係ない。
夜は仕事、昼は学生。
その任務を果たすためには、そういうことも大事なのである。
_ ◇◇◇
_ 三時間目の社会が終わると、昼休み。
学生にとっての、一番のイベントである昼食の時間である。
普通学生は数名のグループで席を取り囲み、話題を持ちながら昼食という時間を楽しんでいる。
しかしながら、柊木香月はそのようなことをしない。
コンビニで購入したサンドイッチを頬張りながら、スマートフォンを操作するだけだ。スマートフォンで見ているのは大抵ニュースサイトとなっている。ニュースサイトを見ることで、そのニュースに『魔術師が絡んでいるかどうか』が解る。絡んでいる事案ならば、ヘテロダインを経由してすぐに依頼が入る。依頼を受けなければ彼は学校へ通うことも一日の食事にありつけることも出来ないのだ。
少なくとも、暫くは家も崩壊しているのだから、その代わりが見つかるまでをどうにか工面しなくてはいけないのだが。
「柊木香月はここかしら」
それを聞いて、教室がしんと静まった。
香月はその言葉を聞いて、振り返った。
二年四組の入り口に、一人の女子生徒が立っていた。
その女子生徒は紛れも無い、城山春歌だった。
「一人で食事をしているなんて、さみしいとは思わない? だから、私と一緒に食事でもどうかしら?」
満足そうに、誇らしげに語る春歌。
対して香月はそれを聞いて顔を引き攣らせながら、頷いた。
_ 4
_ 屋上。
香月と春歌が昼食を取っていた。
春歌は自分で作っただろう小さな俵型の弁当。
香月はコンビニで購入したサンドイッチ二つだ。
「……別に人の食生活にツッコミを入れるつもりは無いけれど……、それってどうなの?」
「その時点でツッコミを入れているからね? いいんだよ、これで。一番コストパフォーマンスがいいだろう?」
「洗い物が少なくて済む、ってこと?」
「それもあるね」
香月はサンドイッチを頬張った。
「というか本当に学生とは思わなかったですよ」
「そうか? 別にいいだろ。そもそも僕にとって魔術師は裏の顔だ。差し詰め、この顔が表の顔だと言えるだろう。学生の顔がね」
そう言って残りのサンドイッチを口に放り込む香月。
「ふうん……。それじゃ、保護者とかどうなっているの?」
それを言って、まずいと思った春歌は口をふさぐ。
溜息を吐いて、香月は話す。
「その様子だと果さんに何か言われたのだろうけれど……、果さんが保護者代わりになってくれているよ。実際、果さんは僕の遠縁だからね。叔母、と伝えてある。遠縁だから、遠からず近からずということで組織も納得してもらっているけれどね……?」
そこで香月は何かの気配を感じた。
――が、すぐにそれも消えた。
「どうしました……?」
「いや、何でもない。どうやら、気のせいのようだ」
そして昼食を再開する二人――。
井坂は屋上のタンクの上から、二人を監視していた。
そんな見晴らしのいいところで監視をしていて、実際、ターゲットに発見されることは無いのだろうか?
そんなことは対策済みである。透過魔術を、すでに井坂の身体にかけていた。
だから見つかるはず等――無かった。
だが、気配を察知された。
これを偶然と取るべきだろうか?
それとも――。
「いや、今は考える必要も無い。それにしても、有意義な情報を手に入れることが出来た」
そして、井坂の姿は今度こそ綺麗に消えた。
_ 5
_ 放課後。
その帰り道。
香月は一人で歩いていた。
目的地はヘテロダインのアジト。理由は単純明快――昨日、彼の家が爆発したからである。一応組織は『原因不明の爆発』として情報操作を進めると言っているが、そうだとしても敵組織が襲い掛かってくるのは確かである。ならば、アジトに身を潜めておいたほうがいいだろう。香月はそう結論付けていた。
「あ、あの」
そこで、聞き覚えのある声が聞こえた。
振り返ると、そこに立っていたのは――城山春歌だった。
「どうした? 確か帰り道はこちらでは無かったはずだが」
「私が連れてきたのよ」
隣にはなぜか風花がバイクに乗って待機していた。
「風花さん、が?」
「そ。まあ、私としてもここに居る理由は一つしかない。ここまでくれば、あんただって解るでしょう?」
「まさか、依頼とでも?」
「その通り。依頼だよ、柊木香月。彼女を見守ること。もっと強めに言えば……『監視』すること、だね」
――はあ、と溜息を吐く香月。
それはさすがに予想しなかったことだろう。
風花の話は続く。
「私も予想外だったけれどね。助けた少女をそのままにしていない香月を処罰しない組織も組織だったし。だが、これを聞いてはっきりしたよ。これは組織の命令だよ。彼女を失ってはならない――組織はそう考えているらしい。そのためには魔術師にしても構わない。そう告げている」
「ということは……彼女の持つ『目』についても知っている、ということですか」
「……目、だと?」
「彼女は凡ての流れを見ることが出来る。それがたとえ魔力の流れであっても」
風花は頷く。凡てのピースがうまくはまったようだ。
「成る程ね。組織がこの子を欲しがっている理由も、あちらさんが彼女をつけ狙う理由も解ってきたよ。それならば、喉から手が出る程欲しいだろうからね。鍛え方によっては最強の魔術師になるだろうし」
それは香月も考えていた。そして、香月が考えているプランの一つだった。
「だとしても、それは難しいことだと私は思うよ」
しかし、風花はそれを否定した。
それは彼にとって、若干イレギュラーなことだった。
「……理由を聞かせてもらっても?」
「第一に、彼女は一般人よ。たとえ『流れ』を見ることが出来たとしても、魔術の才能があるかどうかは解らない。魔力が無い可能性だって考えられる」
「それについては実際に魔術を行使させてから、考えればいいでしょう。もし魔力が無いと判断すればこちらで守らなくてはならない」
風花は溜息を吐く。
引き下がらない香月の特徴として、一つ挙げるべき点があるからだ。
「あなた……『涙』を見たね?」
「……っ」
香月は顔を引き攣らせる。
「やっぱりそうだと思った。だとするならなおさらやめるべきだよ。ただ彼女を監視するだけでいい。戦いは魔術師だけでいい。無碍に彼女を魔術師とする必要はない」
「何故ですか」
「敵が『ホワイトエビル』だと知っても、あんたはこの子を魔術師とするのかい」
ホワイトエビル。
魔術師最大勢力として魔術師の中で実しやかに語られる。
その勢力は計り知れない。そしてそのホワイトエビルが『実しやかに』語られる理由の一つとして、拠点とする都市がいまだに判明していない点が挙げられる。どこに暮しているのかも解らないのである。
「まさか……」
「そのまさかよ。ホワイトエビルの拠点はこの辺りだろうという組織の推測も立っている。そうだとしたら最悪よ。この街には二つの魔術組織が混在しているのだから」
「ヘテロダインと、ホワイトエビル……ですか」
「ええ。別にあなたの戦いに茶々を入れるつもりは無い。私だってそんな余裕無いからね。だからこれは、忠告。ホワイトエビルを敵に回してでも、香月くん、君は彼女を魔術師にするのかい? この状況を知っていてなお、戦いに投じさせるのかい?」
香月は何も答えられなかった。
春歌の真っ直ぐな目を、見てしまったからだ。
その目線は真っ直ぐ、こちらを捉えていた。
彼女は香月を信頼しているのだ。信頼しているからこそ、魔術の講義を受けた。信頼しているからこそ、風花とともにここまでやってきた。
だから、すぐに答えを返すことが出来なかった。
「……別に今答える必要はない。だが、考えておくのね。彼女を魔術師とさせる、その意味を」
風花はそれを捨て台詞として、バイクを走らせてどこかへと消えていった。
春歌と香月は会話を交わすことなく、歩き始めた。
_ 6
_ 木崎市中心部から少し離れた場所には高層マンションが建ち並んでいる。そのどれもが高級マンションであり、一カ月の家賃が何十万とするのが普通な場所となっている。
そういう場所だから、歩く人たちもそんな雰囲気を醸し出している。マダムももう数え切れない程見ている。
香月はもう何度もここを歩いているからか堂々としているが、春歌はどこかおどおどとした様子だった。先程もマンションが混在するエリアに入るときあまりにも怯えていたため警備員に不審がられた程だ。
「……別にそんな緊張することでも無いだろうに。というか制服でいる段階で僕たちの素性は半ば判明していると言ってもいい。だから、堂々としているがいい」
「堂々と、って言われても……。やっぱり来たことの無い場所とか考えると緊張しちゃうよ」
春歌の言葉にも一理ある。現に香月が初めてここを訪れた時も、少なからず緊張したものだ。もしかしたらそれを投影しているのかもしれない。
香月は微笑むと、そのまま歩き続ける。
「ところで、どこまで歩くんですか? もう暫く歩きましたよ……」
「もう直ぐだ。あと少しで到着するよ」
暫くして、香月が歩を止めた。
目の前にあったのは小さな廃ビルだった。廃ビルには工事現場によく見られる柵が置かれていた。
そこにある小さな扉に、躊躇なく入っていく香月。
「わ、わわ……。待ってよ!」
それを見て慌てて彼の姿を追う春歌。
ビルの中は閑散としていた。荷物は凡て持ち去られており、床にゴミすら落ちていない。こんなところにどうしてやってきたのか――そう思う程だ。
二階に昇る。二階も状況は変わらない。ゴミも無いし、家具も無い。
だが、一つだけ違うところがあった。
「自動……販売機?」
そこにあったのは自動販売機だった。電気も点いておらず、販売中を示すランプも消えていた。
そこで香月はあるものを春歌に手渡した。
それはチップだった。百円玉でも五百円玉でも十円玉でも一円玉でも五円玉でも無い。ついでに言うなら五十円玉ですらない。火の鳥の模様が描かれているチップだった。
そのチップを手渡されても、春歌はそれがどういう意味なのか理解できなかった。
「あ、あの……これは?」
「チップだよ。それを使うんだ」
そして、チップを自動販売機へと入れる。
同時に、自動販売機はスライドしていく。
「ええっ!?」
「驚くのはここからだ」
そう予告すると、香月は自動販売機からチップを回収する。
そして、壁が上にスライドしていく。
そこから姿を現したのは、扉だった。扉の隣には三角形のボタンがある。
「これってもしかして……エレベーター?」
その言葉に頷く香月。
そして香月はゆっくりと中に入っていく。
その後を追う形で、春歌も中に入って行った。
エレベーターの中は思ったより広かった。柱の中に隠れているとは思えない程の広さだった。
「……というか、柱の大きさよりも大きくない?」
「どうした、春歌?」
「はい? い、いやなんでも」
春歌は咄嗟に嘘を吐いてしまい、それに気付いたのはその言葉を言った直後だった。だが、それを訂正することも無く、香月の行動を見ることにした。
香月はエレベーターのボタンを押す。エレベーターのボタンは一つしか無いため、おのずとそれを押すしかない。
その同時にゆっくりとエレベーターが降下していく。
暫くしてエレベーターが停止する。扉が開くと、そこに広がっていたのは通路だった。通路の終わりはここからでは見ることが出来ない。それ程長い通路となっていた。
「ついてくるがいい。まだここからは遠い。歩くことになるからね」
その言葉に頷き、香月の後をついていく春歌だった。
_ 通路を暫く歩いていると、壁に突き当たった。通路も見当たらない。ここで行き止まりになるのか――と考えていた春歌だったが、それを他所に、壁に手を当てた。
すると――壁がゆっくりと動き始める。
それが扉であることに気付くのは、そのタイミングだった。
「ようこそ、ヘテロダインへ」
そして二人はヘテロダインのアジトへと足を踏み入れる。
_ 7
_ 香月の部屋ははっきり言って汚かった。
だが、春歌はそれを見て汚いということも無かった。
よく考えれば彼女は初めて男性の部屋に入ったということになる。だが、不思議とそのような感じは無く、むしろ好意的に感じ取ることが出来た。
「適当に腰掛けてくれ。もし座布団が必要なら……」
「ああ、大丈夫です。普通に、しますから」
春歌はそのまま腰掛ける。
香月は一つ咳払いして、話を続ける。
「とまあ……僕が君の監視をすることになったわけだが、要するに体のいいボディガードということだろう。きっと、組織もそういう風に依頼したに違いない。まったく、風花さんも人使いが荒い」
「あの……すいませんでした」
「ん? どうして君が謝る必要がある? 悪いのは……いや、別に悪い意味ではないけれど、それを考えたのはヘテロダインだ。たとえ君が依頼したとしても、ヘテロダインがそのように命令したのならば、そちらを優先せねばならない」
「そうですよね……」
香月はそこで違和感に気付く。
「どうした?」
訊ねる香月。
春歌は顔を赤らめて、観念したように言った。
「……お手洗いはどこに?」
「ああ、お手洗いか」
溜息を吐いて、左を指差す。
「左に真っ直ぐ行くとトイレがある。一応言っておくが、男女別だぞ」
「解りました! ありがとうございます!」
小走りに駆けだしていく春歌。
「そんなに我慢していたのか……?」
香月はそんなことを呟く。もし本人に聞こえていたら鉄拳が飛んできたことだろう。
一人になった香月はラックから資料を取り出した。
「ホワイトエビル……。まさかここで戦うことになるとは」
ホワイトエビルの情報が詰まったファイルだった。それを持っている人間はヘテロダインのボスを含めて僅かな人間だけとなる。
ならば、なぜ彼がそれを所有しているというのか?
それは彼がホワイトエビルを追っているからである。彼にとってホワイトエビルは仇敵と言っても過言では無い。なぜならホワイトエビルは――。
「十年前、父さんと母さんを殺した敵、まさかここで晴らせるなんて……」
――十年前、二人の魔術師を抹殺するためだけに飛行機事故を引き起こしたのだ。
_ ◇◇◇
_ 十年前。
木崎湾、飛行機の残骸。
幼い彼が親の無事を確認しているとき、そいつは現れた。
白髪、背が高いそれは確実に両親を『殺した』。
救助されたのち、彼はそれを訴えたが警察はまともに取り合わなかった。
その時、現れたのは――。
「君は魔術師の才能がある。どうだい? ヘテロダインに来ないか?」
「ヘテロ……ダイン……」
それが、彼とヘテロダイン――組織との出会いであった。
_ ◇◇◇
香月は目を覚ました。時計を見ると二十分程。
……女性のトイレが長いことは、彼の『叔母』から知っていたが。
「そうだとしても、長い。まさか、何かあったんじゃあるまいな……」
彼は立ち上がり、自分の部屋を後にした。
ちょうどその時だった。彼のスマートフォンがかすかに揺れた。
「メールか……」
画面を見るとメールのようだった。差出人は『heterodyne』。即ち、組織からのメールということになる。
そこにはある場所に来るよう明記されていた。
「成る程ね……。先ずはあちらから接触した、と」
そう呟いて、改めて香月は自分の部屋を出ていった。
_ 8
_ 香月がその扉の前に立ったのはメールを受け取ってから五分後のことだった。
「『組織』も相変わらず粋な計らいをするものだ」
皮肉混じりに呟く。
その扉には交差した二本の槍が描かれていた。ちょうどその中心で扉は分かれており、観音開きのような(ような、ではなく実際そうなのだが)仕組みとなっている。
香月がここに入るのは、決して初めてでは無い。かといって定期的に入る場所でも無い。
息を吸い込み、ゆっくりと吐き出す。やはりこの部屋に入る時は緊張する。それは仕方ないことだったりする。
「……失礼します」
そう言ってノックしようとした――その時だった。
その観音開きの扉が左右にスライドした。そして中から何者かが飛び出してきた。
銀髪、メガネ、少しおっとりとした顔。彼女の特徴を述べるなら、それだけであっさりと済んでしまう。
服装は白衣。理由は「例え白衣一枚でもこれが過ごしやすい格好だから」。そんな理由で白衣を着てもらっては困るのが本音だが、流石にそのようなことを口に出すのは憚られる。
彼女は今、白衣一枚でこちらに突撃している。色んなものが香月に丸見えであることは(当然)理解出来ているはずだ。
にもかかわらず、彼女は香月に出撃してきた。
「……!」
香月はそれを見て一瞬慌てたが、それももう慣れてしまった。何回もやられるわけにはいかない。
彼は右と左を見る。右と左はそれぞれ通路であり、誰も来る気配は見られない。
「……こっちだ!」
香月は瞬時に判断し、左を選択した。左に横飛びし、一先ずは衝突を避けられる――。
「甘いね」
――はずだった。確かに香月の作戦にも一理ある。だが、それだけでは不可能だ。
正面から走ってきた女性は霧のように消えてしまった。
「何……だと?」
香月はその光景を見て、信じられなかった。
魔術は忍術ではない。だから火遁や土遁、影分身なんて出来るはずも無い。
だが、精巧に自分の人形を作り出し、それを動かすことが出来たなら?
「まさか……正面はダミー!? 左か右に誘導するための囮だった、というわけか!!」
「ご名答」
左の耳元に女性が囁いた。
その声を聞いて、瞬間で理解した香月は質問する。
「……まさか、そのような作戦を使うとは、思いもしませんでしたよ。負けです、僕の」
それと同時に女性は両手を伸ばし――。
_ ――思い切り抱きついた。
_ 香月の左腕付近に男なら自ずと反応せざるを得ない胸の塊が二個くっつき、その感触が伝わる。しかも白衣以外何も身に纏っていないのならば尚更だ。
「香月くん……会いたかったよぅ。僕は寂しかったんだぜ? 最近君も任務について大変だとか聞いていたし。だから僕も声をかけづらかったのだよ。ならば、このタイミングを考えていたのだよ。このタイミングなら、君と思う存分遊ぶことが出来るからね」
「遊ぶ、って……。仮にもあなたはここの代表じゃないですか。遊ぶ暇なんてあるんですか?」
「暇は見つけるものではないよ。作るものだからね」
「いいこと言ったようなオーラ放っていますけど、それ完全にダメ人間の言葉ですからね!?」
香月と女性の口論がヒートアップしている最中、部屋から春歌が出てきた。
「あの……盛り上がっているところ申し訳ないんですけど、私たち二人をここに呼んだ理由をお話していただけませんか?」
春歌の言葉に女性は踵を返した。
「まぁ、慌てることは無いよ。二人にはある任務を受けてもらいたい……というだけだから」
「任務、だって? それはまた急な話だな」
「緊急の任務だからね。それについては致し方ないことよ。もちろん報酬もそれなりの額となるはず」
香月はそこまで聞いて首を傾げる。
「そんな急拵えで魔術師に頼むことがあった……ってことですか」
魔術師に仕事を依頼するには、主に二つの方法が挙げられる。
先ずはじめに『組織』に連絡する必要がある。電話でもメールでも手紙でも構わない。組織は受け取った仕事を任務とし、難易度を査定する。その難易度に合った所属する魔術師に任務を与える。ここまでが一般的な任務の流れだ。
もうひとつは直接魔術師に仕事を依頼する方法である。これは魔術師本人との連絡手段が求められるが、交渉に応じては費用が前者より安く済む場合がある。
「あちらさん……即ち客はあなたに仕事を依頼している。表向きにはヘテロダインに、となっているけれど魔術師の指定つき」
「任務の内容は?」
「ある都市伝説を調べて欲しい、とのことよ。君……『深海の民』という都市伝説は知っているかい?」
『深海の民』。
シチュエーション等は異なるが、共通して『海の上に人が立っていて、それがゆっくりと海へと沈んでいく』というものだった。見ると海に引きずり込まれて自分も深海の民になってしまうとか、深海の民は海の中でしか行動することが出来ないとか言われているが、結局は謎のままである。
「……その都市伝説を調べて欲しい、とは言うがどうすれば? 全容を解明しろ、とでも?」
「この依頼人の娘さんが深海の民に見初められて行方不明になったらしい。警察に言っても取り合ってくれない、とのことだ。深海の民に見つめられた彼女は、ゆっくりと、自分の足でそこまで向かったらしい」
「深海の民……私もよく学校の友達と話をしますけれど……、行方不明になると二度と見つからないか、運が良ければ死体で見つかるかの何れからしいですよ。海難事故で死体が出てこない時も『深海の民』が海に引きずり込んだ、って話題にしていましたもん」
「話題……ねえ。どうして女性はそういうものを好むのか。人が何人も死んでいるというのに」
そこまで香月が言ったところで、女性が手を叩いた。
「……香月くん、この任務受けてくれるかな?」
「別に構わない。あちらは僕を指名しているのならば、それに従わなくては僕の名誉に関わる」
「せめてそこは組織の名誉にも、と付け足してくれると有り難かったんだけどなぁ……」
「何か言ったか?」
「僕は何も言ってないぜ。いいからそのコンパイルキューブを下ろしてくれよ。僕は君と一戦交えるつもりなんて毛頭無いし。それに、今ここで戦えば君は確実に負けると思うけれど?」
それに香月は何も言わないで、踵を返した。
「……期限は。いつまでに終わらせればいい」
「概ね一週間程度。ただし、これはあくまでも努力目標。依頼人は『なるべく早く』としか言っていないからね」
「……解った」
香月は短く返事をすると、そこを後にした。
春歌は小さく頭を下げてから、彼の後を追った。
_ 9
_ 通路を歩く香月と春歌。
「あ、あの……」
春歌が訊ねる。
「どうした?」
香月は歩きながら、春歌の言葉を聞く。
「あの『任務』……受けるのでしょうか?」
「受けるのか、とは? あの時点ですでに任務を受けることは決定している。相手側から僕のことを指定しているのならば、猶更だ。それともあれか? 君はこの任務を受けるべきではないと、そう言いたいのか?」
「いや、そういうわけではないのですけれど……」
「何だ、さっさと言ってくれないか。僕はこれから『深海の民』に関する情報を集めなくてはならない。だから手短に頼むよ」
「……深海の民を解決することと、私の敵について、それは関係性があるのでしょうか?」
それを聞いて香月は行動を停止する。
香月は踵を返し、彼女に語り掛けた。
「今は関係が無いかもしれない。だが、この事件……何か裏があると考えている」
「裏がある、ですか……」
頷く香月。その目線はしっかりと春歌を捉えていた。
「『深海の民』、それの全容が解らないとはっきりとは言えないが……嫌な予感がすることは確かだ。それによって何かが生み出されてしまうのか、何かが解決するのかは不明だと言ってもいい。そうだとしても、やりきるのが魔術師というものだ。仮にそれに魔術師が絡んでいるというのならば、猶更」
「どうしてですか」
「魔術師は魔術師にしか殺すことが出来ない。……まあ、ただの逸話になるがね、魔術師を一般人が殺すには相当な努力を必要とする。それを考えると、魔術師が魔術師を殺すのが一番だということだ」
魔術師が魔術師を殺すのに一番適している。
それは事実なのかもしれないが――それと同時に、悲しいことでもあった。
「魔術師を倒すためには……魔術を使う必要がある。相手と同じ舞台に立たなくてはならない。そのためにも、君は魔術師としてならなくてはならない」
彼は、彼女は、突き進まなくてはならない。
それがたとえいばらの道であったとしても。
_ 10
_ 昔々、その昔。
一人の少年が夢を見ていました。
その夢は、普通の少年が、世間一般の少年が夢見るものと同じでしたが、ある事件を発端として、それを変えざるを得なくなりました。
彼の両親はある事件で亡くなってしまいました。
そして、彼は次第にあることを想い始めました。
それは圧倒的な恨み。
それは圧倒的な妬み。
それら凡てが、事件を引き起こした諸悪に向けられました。
もし目の前に諸悪が居るならば、彼は凡ての方法を使って息の根を止めていたことでしょう。
しかし、残念ながら、彼にはその方法がありませんでした。
そのため、彼はある人を師匠としました。敵を殺すための方法を身に付ける――そのために。
しかし、師匠は復讐など望んでいませんでした。
師匠曰く、復讐からは何も生み出されない――と。
それを聞いて、いつしか少年は復讐ということを忘れていった。
だが、師匠すら知らなかった――。
彼の心は、まだ癒えていないということを。
_ 11
_ 飛行船にて。
「それでのこのこ戻ってきた、と?」
ホワイトエビル代表、増山敬一郎は井坂の方を見つめて言った。彼の右手にはワイングラスが握られている。ワイングラスの三分の一程度には、赤ワインが満たされている。
井坂は頭を下げたままだった。
「申し訳ありません……! 私たちとしても、急いで探している方針ですが……! まさか、あそこまで気配察知の能力が高いとは思いもせず!」
「言い訳は結構。しかし、私たちが監視しているということは未だ見つかっていないな?」
頷く井坂。
それを聞いてワインを飲み干す増山。
「成る程。ならば、宜しい。若干手間は増えてしまうが……作戦に異常はない。あの魔術師が何を調べようとしているのかは未だ判明していないが。まあ、それもじき解ることだろう」
井坂が頭を上げ、立ち上がる。
それを見て、増山は首を傾げる。
「どうした?」
「あの……、私も作戦に参加するため、ひとまず戻ろうかと」
そう答えた瞬間――井坂の右手は切断されていた。
まるでそこから先が最初から無かったかのように――真っ直ぐに、肩から切断されていた。
痛みは、意外と無かった。
そして、彼が違和感に気付き右腕の方を見て――それと同時に痛みが襲い掛かる。
「うがあああ!!??」
「やだなあ。まさか、二度も失敗を重ねておいて、作戦に参加したいなんて言い出すのか。幾らなんでも虫が良すぎる話だよ。一回は未だ認めてもいい。ただ、二回目はダメだ。それはダメだよ」
右手を抑えつつ、増山の方を見る井坂。その表情は苦悶に歪んでいた。
「僕を見つめたって無駄だ。女性に見つめられるならともかく、脂汗を浮かばせた表情でそれを言われても困るって話。二度も失敗しておいて、むしろまだ自分が出来るとでも思ったのかい? だとすればそれはお目出度い精神をしているね……。矯正する必要があるかも」
もっとも、と付け足して増山は右手を口元へと運ぶ。
一瞬だった。
井坂の身体はバラバラに切断された。まるで鎌鼬が、彼の身体を切り裂いたかのように。
重力に従って彼の身体は落下する。それを見て、増山は微笑む。
「掃除をしなくてはならないねえ……」
増山は井坂を失ったことよりも、ここの掃除のことを考えていた。
そしてワインボトルを開けると、ワイングラスにそれを注いだ。
「魔術で生活が便利になるのも、案外困りものかもしれないねえ」
増山の言葉に誰も答える人間等居ない。
彼の部屋に転がっている死体が、答えるはずもない。
今の言葉は完全なる独り言である。
増山は立ち上がり、窓から外を眺める。外は夜になっていた。夜景がとても綺麗だ。その夜景は百万ドルの夜景とも勝負できるほどだと言われている。
彼はこの夜景を見下ろすのが好きだった。見下ろすことで何が生み出されるのか――と言われてもそれは現実的に有り得ない。しかしながら、彼はこの夜景を見下ろすことで精神的に安定していたこともまた事実である。
「次の段階に移る必要があるな」
ぽつり、呟いて彼は再び席へと戻った。
飛行船は、今日もゆっくりと木崎市の上空に浮かんでいる。
_ 12
_ 香月は街を走っていた。
春歌は病院に預けて、コンパイルキューブを使う前の状態――即ち魔術コードの暗記を行っている。それが出来ればコンパイルキューブに言葉を紡ぐ。そうして魔術は実現される。
香月ははっきり言っていらないと思ったからこそ――任務を一人でこなすこととした。
ホワイトエビルに狙われてしまう可能性もあったが、それは果に任せることにした。
それは彼が果に絶対的な信頼を寄せているからだろう。
だからこそ、彼は安心して行動することが可能だと言える。
「先ずはここだ」
立ち止まり、目の前を見る。
目の前に広がっていたのは、海だった。
聳え立っているのは、大きな石碑。
_ ――石碑にはこう書かれている。『木崎湾飛行機墜落事故慰霊碑』と。
「こういう機会じゃないと行くことが出来ないのは、本当に悲しいことだよな……」
香月は呟きながら、石碑を撫でる。
「母さん……」
その言葉には、怒りが、憎しみが、悲しみが、こめられていた。
彼の両親はこの事故によって失われた。
それについて彼は怒りを抱いていた。この状況を引き起こしたのは、ほかでもないホワイトエビルであることも突き止めていた。
だが、警察が介入することも出来ないことだ。魔術師が引き起こした『災害』は、魔術師の手で解決せねばならない。
それは魔術師でなくては魔術師に立ち向かうことが出来ないからである。
彼が今まで時間がかかったのは、彼自身弱いと思っていたからだ。彼自身立ち向かうことが出来ないと思っていたからだ。
「……さて、向かうか」
彼がやってきたのは、この石碑に祈りに来ただけではない。
それ以上の理由がある。
海を見る。
海は波一つ立つこともなかった。穏やかな気持ちにさせてくれる、そんな海だった。
「海、か」
海は嫌いだ、と香月は語る。
別に海を嫌いだという人は当然なことかもしれないが、彼にとって、出来ることなら海を見たくないのが実情だった。
だが、そう言って居られないこともまた事実。
「……行きますか」
呟いて、香月は行動を開始する。
目的地は決まっている。木崎湾を臨む場所にある図書館である。
図書館にはもちろん十年前の事故における文献も残っている。そこに向かえばおそらく情報も収集することが出来るだろう。
そして彼は一歩踏み出す。
_ ◇◇◇
_ 図書館に入ると、静かな気配が彼を包みこんだ。
書籍を探すために、棚と棚の間に入っていく。
次第に古い本が増えていくが、それでも彼の捜索は終わらなかった。
「それにしても多いな……」
最終的に十冊近くの本が集まった。発行年を見ても去年のものから五十年ちかく昔のものまで幅広い。
しかし、彼が欲する情報を得るためにはそれ程幅が広くなくてはならない。一つ一つの文献だけでは、見えてこないことだって沢山存在する。複数の文献を見比べ、それにより一つの歴史を仮想的に再現する。
「文献は全部で……八冊か。少ないが、致し方ない。これを見て整合性を取るしか無い」
そして彼は文献を見始める。彼が必要とする、ある情報を追い求めるために。
_ ◇◇◇
「そうねぇ」
その頃、病院のとある一室。春歌と果がお茶を飲みながらのんびり過ごしていた。
因みに今日、果は休診となっている。別にこの為にわざわざそのようなことをしている訳ではなく、いつもこの日はお休みとなっているのだ。
「……それにしても、香月くんはどこに行ってしまったのかしらねぇ。こんな可愛い子を置いて……」
「それって私のことですか!? 私のことなんですか!?」
顔を紅潮させながら言う春歌。
それを見ながら、いい弄り相手が見つかったとほくそ笑む果。
春歌はお茶を一口。
「そんなことより、彼……香月くんはどういう人間なんですか?」
それを言われた果はきょとんとした表情で春歌を見る。
「どう、って?」
「だから……こどもの頃からああいう落ち着いた人間だったのか、とかそういうことです。あの人に教えてもらったり助けてもらったりとされているのに、私は彼のことを知らないから……」
それを聞いて果は察した。
「ははぁん……。成る程ね、春歌ちゃん、あなた香月くんのことが好きになっちゃったんだ?」
直後。
ぼんっ! と音が出たようなそんな感じで瞬間的に彼女の顔が真っ赤に染まった。茹で上がった蛸か、直ぐに沸いてしまう電気ポットか――今の果には彼女がそのように見て取られた。
「……解りやすいわねぇ」
「え……、あの……、その……。いつ、解ったんですか?」
「ボーイミーツガールには在り来たりな展開だったし」
「それ全然証拠になってないですよ!! ただの仮定じゃないですか!!」
「でも現状、あなたの顔は真っ赤に染まっているわけだけれど?」
何も言い返すことが出来なかった。
一つ咳払いをして、果は話を戻した。
「取り敢えず、話を元に戻しましょうか。香月くんの人となりについて……だったよね。彼は寡黙で真面目な少年だよ。あれで中学生だと言われても耳を疑うレベルだ」
「そうですよねぇ……」
香月の年齢は十四歳だ。しかし、彼の落ち着いた行動の数々を見て来た彼女にとって、それはやはり信じられないことだった。
「確かに彼は昔から落ち着いていた。私が彼ときちんと話をするようになったのは……あの『事故』が起きてから暫く経ったときのことだった」
「……あの事故はそれ程までにひどいものでしたからね」
彼女も彼女の親族も、あの事故で何かを失った訳ではない。だからラジオやテレビ、或いはインターネットで得た情報からしか語ることは出来ない。
しかし香月と果は、それぞれ両親と親戚を失っている。心に負った痛みは、計り知れないものだろう。
だが、たとえ彼女がそう思っても――それはただの慰めにしかならない。
そのような言葉をかけていいのだろうか? 彼女はそんなことを考えていた。
「私たちのことを、気にかけなくてもいい。彼も私も、少しずつではあるけれど、あの事故を乗り越えようとしつつあるのだから」
香月も果も、乗り越えようとしている。
春歌は考えた。自分も父親が亡くなった。その衝撃を、そのショックを……本当に『乗り越えた』といえるのだろうか?
時折、不安になって理由もなく涙することがあった。普通に考えればそれは、未だ乗り越えられていない証なのではないだろうか?
「大丈夫」
果は春歌を抱き締めた。
彼女は優しくて暖かい抱擁を受ける。受け入れる。
「あなたは大丈夫。一人だけで抱え込まなくていい。あなたのお父さんだって、きっとそう思っているはず」
「そう……ですか?」
「ええ」
果は笑顔で春歌の方を見つめる。
それと同時に、彼女の堰がゆっくりと崩壊していく。
一度皹が入ってしまえば、もう崩壊は止まらない。
「うわぁぁぁん……」
涙が、涙が止まらない。
果の白衣を濡らしてしまう程に。
そんな春歌に対して果は、優しく頭を撫でるだけだった。
_ 涙が収まり、ティッシュで涙を拭う。すっかり果の白衣は濡れてしまったので洗濯に出すこととした。
「すいません、本当に……」
「何が? あぁ、もしかして白衣のこと?」
少しだけ顔を赤らめて、恥ずかしそうに頷く春歌。
「それなら特に問題ないよ。こういうことは職業上よくあることだからねぇ……。手術が怖くて受けたくないと駄々を捏ねる子供を何とかさせたり、殺してくれとせがむ患者を宥めたり……。さながら私は病院の交渉人みたくなってしまったよ。最近は面倒臭い患者さんを全部私の方に丸投げだからねぇ……。そういう手当てくらい出して欲しいものだよ」
思った以上に病院にもそのような不条理があるのだ。そう思った春歌だった。
_ ◇◇◇
_ 夕方になっても未だ図書館に居た香月。彼は休憩ということで、カフェオレを飲んでいた。休憩コーナーにある自動販売機で売っていた、百三十円の缶飲料だ。
八冊の文献に追加して、その文献を読み解くための知識を得るために二十一冊の文献を読み解いた。そのため現時点でも未だ半分しか読み進めていない。
「これは思ったより骨が折れる……な」
時間がかかる作業だということは彼も理解していた。しかしながら、ここまで時間がかかってしまうのは少々予想の範疇を越えていた。
カフェオレを飲み干し、テーブルに置く。直ぐに開いたままになっている文献の解読に取りかかった。
文献解読は七割程終了している。しかしこの状態でも彼の仮説には充分合致している。
出来ることならばその仮説は合致して欲しくなかった。ただの思い違いならばいいと思っていた。
しかし現実はそう甘くない。
「何で……こういう時だけ僕の不安は的中するんだ……!」
思わず図書館で大声を出してしまいそうになったが、すんでのところでそれを抑え込む。
彼が言っているのは、この図書館に文献を漁りに来た理由にもなっている。ある仮説を『否定』するためだった。
その仮説を肯定してしまえば、彼の今までが、根幹が覆されかねない。だから、出来ることならばただの机上の空論であって欲しかった。
しかしそれは呆気なく打ち砕かれた。そんな希望等無い――そう語りかけるように。
「『深海の民』が騒がれるようになったのは十年前から、そして木崎湾の飛行機事故もまた十年前だった……。これから導き出せるのは……」
_ ――深海の民と木崎湾飛行機事故には何らかの因果関係がある。
本当にそう言えるのだろうか?
彼の脳内で誰かが語る。
信じたくないと思っていても、その可能性がある以上突き止めなくてはならない。
……どちらにせよ、テーブルに散乱した資料をどうにかしないと話にならないのだが。
_ ◇◇◇
_ 片付けを終えると時刻は午後五時を回っていた。
「あぁ。だから今から春歌を迎えに行く。準備をしておいてくれ」
香月は電話をしていた。
「……安全面を考えればこちらに泊まったほうが安心だ。え? 何を馬鹿なことを……。そんなことをするわけが無いだろう。客人として丁重におもてなしするまでだ」
首を傾げながら、通話を終了する。
「……ったく、どうして『丁重におもてなしする』と言ったのに怒られなくてはならないのか。甚だ疑問だよ」
そんなことを呟きながら、病院へと向かっていた――その時だった。
「ちょっといいかな」
声をかけられ、呼び止められたのは香月の数歩前を歩くスーツ姿の男だった。普通に見ればただの帰宅途中のサラリーマンにしか見えない。
だが彼は、そこに何処か違和感を覚えた。
「どうしたかね。何か気になったことでも?」
踵を返したサラリーマンは右手をポケットに突っ込みながら訊ねた。
「……気になりたくなくても気になっちまうものなのだよ、魔力のオーラというものは」
ぴくり、とサラリーマンの眉が動いたのを彼は見逃さなかった。
右手をポケットに突っ込んだまま、サラリーマンは言った。
「魔力、と言われてもまったく解らないのだが。最近の若い者は……」
「しらばっくれても無駄だ。だったら右手に隠しているものを見せてみろ。恐らく、というか確実にそれはコンパイルキューブのはずだ」
「ほほう……。いつのタイミングで解った?」
サラリーマンはポケットに入っていた右手を引き抜いた。
その右手は確かに、しっかりとコンパイルキューブを手にしていた。
「普通に考えて当然だろう? 先ず、サラリーマンはこのような時間にたった独りで居ることなんてしない。するかもしれないが、その可能性は限りなくゼロに近い……そう言っていいくらいだ。そもそもここは通勤の人間はあまり通らないんだ。だから直ぐに解るよ。だが、その時は未だ疑念を抱いただけに過ぎなかった」
「ならば、何故?」
「疑念が確信に変わったのは、出そうとしない右手と、魔力の流れだ。『彼女』程では無いが、僕もそれを見ることが出来てね……。魔力の濃度くらいは可視化することくらい容易なんだよ」
「そしてその濃度が一番高かったのが私の右ポケット……か。成る程、鋭い考察だよ。完璧と言ってもいい」
手を疎らに叩きながら、男は言った。
「だが、終わりだよ。気付かなければ、楽に死ぬことが出来たというのに。本当に馬鹿だ」
「馬鹿かどうかはこれから決めれば良いことだ。戦いが終わった頃には、屈服しているかもしれないぞ?」
「果たしてどうかな」
そして。
衝突が、起きた。
_ ◇◇◇
_ その頃、病院でも小さな爆発があった。
病室で話をしていた二人は振動と爆発音でそれに気付いたが、直ぐに動くことはしなかった。先ずすることと言えば、安全確保になる。
「いったい何があったの……!?」
果は慌ててポケットに入っている携帯を取り出す。同じフロアに居るかどうか解らないので、同僚と連絡を取るためだ。
「電話は出来ないよ」
背後から声が聞こえた。
そこに立っていたのは白衣を着た小さい少年だった。
白衣の似合わない少年――背格好に対して白衣の大きさが合致しない。まるで誰かの白衣を奪ったようにも見える――は一歩近づいて、言った。
「今日は二人が離れて行動するという話を井坂から聞いた時は正直信じられなかったが、彼の話も当たるものだね。最近はイマイチだから、ダメだと思っていたよ」
「あなたは……いったい?」
果の質問に答えることなく、白衣を着た少年はポケットから何かを取り出し、囁いた。
それを見て果は直ぐに理解した。
「避けて!!」
春歌を守るように彼女の身体を押し出した。彼女は小さく悲鳴をあげて倒れ込んだ。
それと炎が彼女たちの居た場所に襲いかかったのはほぼ同時のことだった。
「コンパイルキューブ……あなた、魔術師ね?」
少年は微笑む。
「ご明察。まさか魔術師を知っている人間が居るとは思わなかったよ。魔術師ではない、普通の人間しか居ないはずだったのに」
「魔術師以外でもコンパイルキューブの存在を知っているのは、たくさんいるわ。私みたいに、魔術師を家族に持つ人間ならばなおさら」
「うるさい!」
言葉を聞かずに、再び言葉――基本コードをコンパイルキューブへと吹き込む少年。
「どうして、火に油を注ぐようなことをしたんですか!」
「まあ、見てなさい」
このような状態においても、果は冷静だった。状況を判断していた。
だから春歌も果に従うしかなかった。
「人間が魔術師に勝つことは出来ない! なぜなら魔術に対抗する術がないからだ! 見縊るなよ、人間! 魔術師を敵に回すことの恐ろしさを、思い知るがいい!」
そして。
今度こそ二人に火の玉が命中し、天井からコンクリート片が落下した。
_ ◇◇◇
_ 魔術師と魔術師の戦い。
その優劣を判断するのは魔術の技量である。魔術の技量が高ければ高い程相手に強いダメージを与えることが出来る。
これは覆すことなど容易ではない、きわめてシンプルな優劣の付け方ともいえるだろう。
柊木香月と、その魔術師。
二人は戦っていた。
周りから見れば、手のひらサイズの立方体(コンパイルキューブ)に何か語り掛けることで火炎や水流、或いは氷柱が生み出されているだけだ。
魔術に疎い人間から見れば、それだけで済まされる。
しかし、視点を変更して。
魔術師からその戦いを見ると、一般人の視点とは違うことが見えてくる。
たとえば用いている魔術。
相手は高度な魔術を多用している。高度な魔術、というのは単純に言って難しい魔術のことを言う。その『難しさ』には発音の有無は問わない。発音が難しくとも、テニスボール程の火の玉を一つ生み出すだけならば、それは簡単な魔術と分類されるのだ。
魔術の難易度を規定するにはいくつかの条件が存在する。
一つは、その構成。
魔術の基本コードは主語、述語、述語修飾、対象、オプションの五つから構成されている。この五つはそれぞれ単語及びその合成により成り立っており、基本的にはこれらを満たせば魔術は実現される。
ここで注目するべきところは『オプション』だ。飛行魔術なら場所を、攻撃魔術なら範囲や強度などを指定することが出来、比較的自由に設定することが出来る。
裏を返せば。
ここを活用することでテクニカルな魔術を行使することが可能となる。
たとえば針の孔程の大きさの火の玉を作り上げるとか。
たとえばギリギリ殺さない程度に相手を痛めつけるとか。
使い方によってはどんなことだって可能になる。それが魔術の基本コードにおけるオプションだ。
相手の魔術師はそれを行使しているため、非常に高度な魔術が実現されている。
しかし、柊木香月は違う。
非常に基本的なオプションしか用いていないのだ。
火炎魔術ならば『強く』しか使わないように。
防御魔術ならば『自分の近く』しか使わないように。
自分の魔術を――信頼しているようにも見えた。
行使している魔術が高度であっても、劣勢と感じられるならばその魔術師は二流と言われている。
行使している魔術が容易なものばかりだとしても、優勢ならばその魔術師は一流と言われる。
それが柊木香月と敵の違いだった。
「……つまらないね」
「はあ?」
防御魔術を行使したことで形成された緑色の薄膜を通して、香月は言った。
サラリーマンを模した敵の魔術師はその言葉を聞き捨てならないと思いながら、見つめる。香月はそれを気にせず、話を続ける。
「おそらく『ホワイトエビル』が送ってきた相手だろうから、もう少し骨のある奴かと思っていたけれど……僕の実力を測る為なのか、至極つまらない戦いだ。高度な魔術ばかり極めようとして、このありさま。しかも極めれば極めたでいいのだが、中途半端なクオリティになってしまっているから、ダメージが削ぎ落とされている。この魔術なら、本当はこのシールドくらい十秒もかからずに破壊されてもおかしくない。にもかかわらず破壊されないということは……もうこれ以上は言わなくても解るよね?」
「言わせておけば……! Ff・ff・ff!!」
コンパイルキューブにコードを通す。
それは単純に魔術を強くするためのオプション。
それを聞いた香月はぽつり、小さく呟いた。
「ej・ei・fr・et・tfac」
それだけだった。
コンパイルキューブを通して、魔術は放たれた。
その炎は、彼が放った魔術とまったく変わらなかった。一般的に魔術師の中では有名な魔術の一つでもあった。
にもかかわらず。
それは彼の放った炎よりも格段強く、轟々と燃え盛り、何しろ――綺麗だった。
「チェックメイト。これでおしまいだ」
そして。
魔術師はその炎の中に飲み込まれていった――。
魔術師の身体が燃え尽きるまで、そう時間はかからなかった。
「所詮、二流だったということだ。いや、或いは三流か……。そのいずれかということだ」
香月はそう言葉を吐き捨てて、空を見る。
「未だ時間はそうかかっていない……。おそらく、あちらも被害にあっているだろう。だとするなら、危険だ」
そして、香月はパーカーのフードを被る。
パーカーは、彼が仕事の時に着用する、いわば『仕事着』だ。
_ ◇◇◇
_ その頃、病院に居る果と春歌。
崩れたコンクリート片が山となった、それを見て魔術師は微笑んでいた。
やはり一般人は、魔術師にとってみれば赤子も同然だ。即ち、魔術師が一般人を殺すことなど容易いということである。だから、この勝負はほかの魔術師が客観的に見れば、勝負では無く『虐殺』というのかもしれない。
「……他愛も無い。やはり、魔術師が人と戦うのは、蹂躙しているのと一緒ということになるのだろうな」
魔術師は微笑んだまま、踵を返し、立ち去っていった。
――その時だった。
魔術師は咳き込んだ。それだけならば、風邪かもしれないと疑うだけだったのだが――。
手を抑え、咳き込んだ魔術師。
魔術師はその手を見る。
その掌は、真っ赤なものが点在していた。
それが血であると理解するまでに――そう時間はかからなかった。
「――え?」
同時に魔術師は膝から崩れ落ちる。
「一つ、いいことを教えてあげるわ……魔術師サン。それはあなたの敗因よ。あなたは私たちを魔術師ではない、ただの一般人だと考えた。その仮定が大きく間違っているということ、それを理解したほうがいいわ。まあ、もう死んでしまうのだけれど」
「な……んだと?」
魔術師は振り向く。
背後に立っていたのは、そこには居なかったはずの春歌と果だった。
果はあるものを持っていた。
「なぜ、なぜお前が持っている!」
「別に持っていても問題ないでしょう?」
果はコンパイルキューブを手に、笑っていた。
「――まあ、一つ補足するのならば、私は、十年前を最後に魔術を使わなくなった。理由は単純明快。柊木香月という最強の魔術師に成り得る人財を育てるため」
「柊木香月を……か。ハハハ、成る程ね! これほどの魔術師が見つからないわけだ! ランキング上位にも成り得る魔術師が、こんな病院の一医師になっているとは!」
「笑っている場合? 私の左手に持っているものを、見ていないのかしら?」
は? と呆気にとられた魔術師は再び彼女の身体を見る。
右手にはコンパイルキューブ、そして左手には――心臓が握られていた。
「まさか……!」
見る見るうちに青ざめていく彼の顔。
「そうだ。ここにあるのは君の心臓だよ、名もなき魔術師クン?」
心臓は完全に抜き出されていて、独立しているにも関わらず、いまだ脈打っていた。
まるで、心臓が未だ生きているように――。
「未だ、ではない。ほんとうに生きているのだよ。これも魔術による賜物だ。私は職業柄医術に近い魔術を使うことが多くなってね……。おかげで、それを使うようになったわけだよ。いまではそれがエキスパートってこと。専門家というのも大変だねえ?」
「エキスパート……だと?」
「そう。医術と魔術は似ている。似ているようにしたのは私だがね。……どちらにせよ、ホワイトエビルも最悪の相手を見つけたと思っているのだろうな。どうせ、私のことは前々から知っていたのだろうが、末端のお前には知らされていなかったのだろう? その驚くような表情からして」
「まさか、組織(ホワイトエビル)が?」
「さあね。どちらにせよ、あんたが見捨てられているのは事実。……さてと、そうだとしても私に戦いを臨んだのも事実。あんたをどうやって料理していこうか?」
そして、心臓を持つ腕に力を込め始める。
「お、おいやめろ……。やめるんだ……!」
命乞いを始める魔術師。
それでも、力を込めることはやめない。
「ねえ、あなた知っているかしら。魔術師と人間の戦いじゃ、魔術師に対抗する手段が無いから、そう感じるらしいのよ。私はそれが嫌でね。だから、私の素性を知っている人間はそう言わない。『魔術師と人間のパワーバランスについて、人間を侮蔑するような発言』はしないのよ。した時点で……私が何をするか、解っているから」
「まさか、何を」
「何をするのかは、あなたが一番解っているのではなくて? 心臓は一生鼓動を刻み続けるから、筋肉がそれなりに固い。だから、潰すのは難しくてね。いつも力加減が難しい。あまり強すぎると私の身体が血まみれになってしまうからね。それははっきり言って勘弁してもらいたいのよ。あらぬ疑いをかけられてしまうからね。魔術師と魔術師の戦いに、魔術師以外の属性の人間が介入されることは、魔術師のルールからして許されないからね」
そして。
魔術師の心臓が、耐え切れず――破裂する。
同時に魔術師は白目を剥いて、気絶した。……正確に言えば、気絶したように見えるだけで、実際には死んでしまっただけなのだが。
「さて、と」
掌に付いた魔術師の血をぺろりと嘗めて、言った。
「これは高い講義料になるよ、少年魔術師サン?」
窓から空を見て、果は微笑んだ。
その笑顔が月に照らされて、とても綺麗だった。
夜の街をモノレールが走っている。
木崎市を一周するようにモノレールが走っており、連日深夜まで走行している。
モノレールの線路を見つめながら、少年は立っていた。
少年は世界が嫌いだった。少年は世界に絶望していた。
どうして自分がこのような目に合ってしまうのか、ということを考えていた。
考えるだけで嫌だった。
自分がなぜこうなったのか、なるべく考えないようにと言われ続けた。
だが、そんなこと出来るはずもない。彼は独自で捜索を開始した。
復讐は復讐しか生み出さない。そう言われたにもかかわらず。
彼はとある組織に拾われた。
魔術師に育てられることとなり、その魔術師は一線を退いた。
そして魔術師は医師となり、少年を陰から支えた。その魔術師は、一人だけで魔術師組織を壊滅させるほどの実力を持つと言われていた。
それゆえに、魔術師の引退は衝撃となった。
魔術師は言った。魔術師の仕事よりも彼を育てる方が重要である、と。
なぜ一人の少年に、そこまでする必要があるのか――事情を知らない魔術師は考えた。
組織の一部の人間は語る。
少年は、ある魔術師の子供である、と。
その魔術師の素質を持った子供は、貴重である。
魔術師としての才能があるならば猶更――そう語っている。
少年はその魔術師の下、魔術を学ぶこととなった。
しかし、その魔術師は少年に魔術を教えたくなかった。
少年の目を見てしまったからだ。
少年の目は、一つの火が宿っていた。
燃え盛るその火は――復讐の炎そのものだった。
魔術という手段を手に入れれば、それを使って復讐をするのではないか――その魔術師はそのようなことを考えていた。
復讐は復讐しか生み出さない。
それはその魔術師が常々少年に告げていたことでもあった。
だから、魔術を教えることはしたくなかった。
だが、組織は魔術を教えることを強要し――少年を組織へ同行させた。
魔術師はその命令を逆らうことが出来なかった。
組織は少年に魔術の授業を受けさせた。それにより、少年は組織が考えた通り、魔術師の才能をめきめきと見出していった。
だが、少年にはまだそれに見合う精神が育っていなかった。
それから五年後、少年は魔術を行使、ヘテロダインのアジトの一部を破壊した。
僅かな魔術であったが、被害は甚大。拘束するまで一時間を要した。
拘束後、除籍も考えられたがヘテロダインの上層部によりそれは無くなった。
カウンセリングと称して少年が連れてこられたのは、あの魔術師が勤務している病院だった。
魔術師は保護者となることを了承、カウンセリングを行った。
その一年後。
少年は再びヘテロダインの門戸を叩いた。
それは、魔術師として生きていくことを決意した、ということだった。
_ もう、あれから四年が経った。
少年は空を見ていた。
遂に両親を殺した相手の足がかりを掴んだ。
それどころか、相手の方からこちらにやってきた。
これは彼にとってチャンスだった。このチャンスを使わない機会は無かった。
「……さあ、始めるとしよう。十年前の反撃を。充分とツケが溜まっているからな。利子もたっぷりつけて返してあげるよ」
少年は呟くと、モノレールの線路がかけられた橋の下を歩き始める。
目的地である病院は、すぐそこまで迫っていた。
_ ハインリヒの法則を聞いたことはあるだろうか。
簡単に言えば、一つの大きな事件や事故に隠れて三十或いは三百の小さな事件事故が隠れていることである。
香月は図書館であの事故について調べ、ふとその法則が頭に浮かんだ。
_ ――ハインリヒの法則にあの事故が当てはまっているとしたら?
_ それは、はっきり言って最悪の結果ともいえるだろう。ただし、その結果が正しければ……話は全く真逆になる。
「考えたくは無い」
彼はぽつり呟いた。
「だが可能性も考慮せねばならない。どんなに小さなリスクであっても、それは確認し、排除する必要がある」
それが柊木香月の考え方。
それが一番簡単で単純な取捨選択。
「……だとして、だ。問題はここからだよな……」
ここで考えは原点に戻る。
ホワイトエビルは、ほんとうにハインリヒの法則を適用させていたのか?
適用させていたとしたら、何を隠そうとしていたのか?
「解らんな……。とにかく、先ずは病院に戻って、彼女を助けるしかない」
彼女を助けなくては、任務失敗となる。
任務を失敗すれば、魔術師の信頼にかかわる問題になる。
だから彼は走る。
彼女を救うために。
_ 2
_ 香月が病院に着いたのはそれから十分後のことであった。
「……静かだな」
やけに静かだった。
人の気配が無い――と言えばいいだろうか。
「おかしいな。これほどまでに、この時間に静かなわけがない」
病院の中に入り、階段で上に登っていく。
人の気配は、やはり無かった。
_ そして、ある病室。
その病室だけ電気が点いていた。それを見て香月は少し安心した。この病室も人の気配が無ければ、それこそ大変なことだと思ったからだ。組織に報告して、判断を仰がなければならない。
「……果さん? 居ますか」
「はいはい、いますよ。まったく、骨が折れたよ。あんな軟弱な魔術師を相手にするとはね」
「復活戦だと思えばいいじゃないですか。……それにしても、戦ったんですか。魔術で」
「ああ、久しぶりにね」
果の右手にはコンパイルキューブが握られていた。
それを見て香月は溜息を吐く。
「戦うとは思っていましたけれど……、これ程までに早いとは思いませんでしたよ」
「私の性格を知っていて、言っていることなのかな?」
頷く香月。
それを見て笑みを浮かべる果。次いで、コンパイルキューブをポケットの中に仕舞った。
「ところで、君の元にも来たのかな? ……ホワイトエビルの使いが」
「ああ。そうだよ。ホワイトエビルは冷酷だよ。ホワイトエビルの使いは簡単に退くことは出来たが……。きっとまた来るだろうね。こちらにも。恐らくあちらの狙いは、彼女だろうからね」
「彼女……城山春歌の事だね。確かにそうだね。『凡て』を見ることが出来るのならば、それを狙うのは当然の事。そして、その当然を突いて、魔術師に仕立てあげるのが、香月クンの目的だったね?」
「クン付けは止してくれよ……。まあ、そうだ。その通りだ。正しいことだよ」
香月は病室を見わたす。
瓦礫の山の隣に、春歌が腰掛けていた。
春歌の元に近付くと、春歌はそれに気が付いて顔を上げた。
「無事か、春歌」
「ええ。何とか。……果さんが、魔術師なんて知らなかった」
「正確には魔術師『だった』かな。僕が生まれて少ししてから、果さんは魔術師を引退したから。だから、その証拠に、ほら」
コンパイルキューブを取り出す香月。
「僕のコンパイルキューブと、果さんのコンパイルキューブ。見比べて何か違いが見えてこないかい?」
言われた春歌は、香月と果のコンパイルキューブを見比べる。
「うーん……なんというか、香月クンのコンパイルキューブは、果さんのものに比べて小さいような気がする……」
「そう、その通りだ。大きさの違いだよ。果さんが利用しているコンパイルキューブは、簡単に言えば旧式のものになっている。対して、僕が持っているものは新しいヴァージョンだ。別に新しいほうがいいというわけでもないが……」
「新しい方が使い勝手もいいでしょ。それに、処理速度も速いんじゃない?」
果が補足する。
香月は頷きながら、さらに話を続ける。
「確かに新式の方が処理能力は高いと言われていますね。僕は旧式で訓練したこともありますけど、全然処理速度が速いとか遅いとか解らないですけれど」
「訓練じゃ解らないよ。実際に戦ってみないとね。戦闘中に魔術をコンパイルするときに、その処理速度が実感できると思うよ」
「戦闘中、ですか……。それはそうかもしれないですね。実際に魔術師同士の戦闘では、新式のコンパイルキューブでしか戦闘したことがありませんから」
「あ、あのー?」
話が若干どころかまったくついていけていない春歌が、何とか二人の会話に割り入ろうと声をかけた。
それを聞いた香月が春歌の方を見て頭を下げる。
「ああ、申し訳ない。つい話が盛り上がってしまって。君が悪いわけではないのだけれど」
「つい魔術の話になると、盛り上がってしまうんだよね。特に、私の場合はもう十年近く最前線から身を退いているわけだから、現時点で最前線に居る香月クンの話はかなりタメになるのだよ」
「成る程」
専門家の話というのは専門家だけしか盛り上がることが出来ない。
それは春歌も聞いたことがあった。だから、自然にその流れには納得することが出来た。
「まあ、細かい話は本部に向かってからにしよう。そこならば、少なくとも安全は保障される。ほかの魔術師も暮しているし、常に魔術師が居るからね。果さん、いいですよね?」
「私も来ていいということかい?」
「そりゃもちろん。来ていただくと、百人力ですよ」
それを聞いて果は頷く。
「だったらついていくことにするかね。私も、魔術師だし。当事者になってしまったようなものだからね……」
果の了解を得たところで、香月はスマートフォンに操作してある場所へと電話を掛ける。
短い通話ののち、電話を切る。
「了解は取れた。急いで向かうことにするよ。先ずは体制の取り直しだ」
_ 3
_ ヘテロダイン基地、香月の部屋。
「久しぶりだなあ、香月クンの部屋にやってくるのも」
「そうだったか?」
「魔術師を半分引退してから、私はヘテロダインの基地に訪れないようにしていたからね。香月クンの部屋に訪れるのも……五年ぶりくらいか? ボスにはお世話になったものだよ」
「ボスは相変わらずああいう感じだよ。覚えているだろう? 魔術師じゃなかったらただのマッドサイエンティストと言われてもおかしくない感じだよ」
「マッドサイエンティストね、笑える」
果は笑みを浮かべる。
「笑っている場合じゃないですよ。ボスの対応を一手に背負う僕の気持ちにもなってほしいですよ」
「私は旧知の仲だから、そう言われると『あー、やっぱそうなっているのかー』ってなるよ。うん」
「だから! そういう問題では無くて! ええい、面倒だ! 取りあえず、今回の報告をする必要がある。ボスの部屋へ向かうよ」
そう言って香月は部屋を後にした。
「私たちも向かうことにしましょうか」
「向かう……って?」
「当然。ボスの部屋だよ。私たちも当事者になってしまったからね。春歌ちゃんはもともと当事者だったとして、私はついさっきホワイトエビルと戦った。それは即ち、今回の事件に関与したということになる。そうなると魔術師組織(ヘテロダイン)としても、関与した人間は明らかにしておきたいわけ。それは解るでしょう?」
「……まあ、確かにそうかもしれないですけど……」
「話が解ったようで何より。それじゃ、一緒に向かおう。香月クンと同じタイミングで行ったほうが楽だ。『彼女』との付き合いは長いが、どうもいまだに慣れない部分があるものでね……」
「あら、言ったかしら?」
それを聞いて、果の背中に電気が走ったような衝撃を受けた。
すぐに振り返ると、そこに立っていたのは。
白衣を着た女性だった。銀髪で眼鏡を付けた女性は、果の方を見てにっこりと笑っていた。
「久しぶりだね、果たん♡」
「……私は出来ることなら会いたくなかったよ」
溜息を吐いて果は言った。
女性は手を背後の方に回して、
「ええっ? 別にいいじゃないか、僕は寂しかったんだよ? 香月クンがああだから仕方ないかもしれないけれど、君が魔術師を辞めて香月クンの育成に専念したときはね。そりゃ三日三晩泣き叫んだものさ」
「嘘を吐かないでもらえるかしら、ユウ?」
「ユウ?」
「ユウというのは僕の名前だよ、城山春歌」
言ったのは白衣の女性――ユウだった。
「ユウ・ルーチンハーグ。それが僕の名前。どこの人間なのか……というのは少しだけ内緒にさせてもらうよ。それはね、僕の最重要事項であるからね。致し方ないことではあるよ」
ユウは溜息を吐いて、
「僕はヘテロダインの代表として、ずっと活動してきた。ヘテロダインは僕が設立したわけだけれど、その前身……もともとの場所と言えばいいかな? その団体はたくさんあったわけだけれど、それをまとめ上げたのが僕、ってこと。案外大変なんだよ? この組織をまとめ上げるのはね。香月クンや果たんみたいにまともな人間ばかりが居るわけではないからねえ。特にならず者ばかりが集まっている『シークエンス』とかは」
「シークエンスは未だならず者ばかりが集まっているのか。区画整理とかすればいいのに」
「区画整理をするほどまでではないのよね。実際問題、それ程までにすることではないのだから。区画整理をすることで、逆に秩序が乱れるかもしれないし」
「何を話しているのかと思えば。僕の部屋に居たのか」
話を中断させたのは香月だった。
香月の声を聞いてユウと果はそちらを向いた。
「やあ、香月クン。ここに戻ってきたということは、深海の民について情報がまとまったのかな?」
「何を言うのか。そういうわけもないだろう。確かに情報は少しばかりまとまってきたとはいえ、まだまだ不足なところも多い。だから図書館での情報を集めて、これからレポートにまとめようとはしているが……、それよりも先に奴らが攻撃を仕掛けてきた。だから、ここにやってきた。逃げ込んできた、と言ってもいいかもしれないな」
「ホワイトエビル、か?」
それを聞いてこくりと頷く香月。
「何を笑っているのかな。こちらは生死をかけていたというのに」
ユウは笑みを浮かべていたが、香月に苛まれてそれを止めた。
「別にそれはいいだろうに。笑うことくらい構わないだろう。実際問題、君たちが無事なのだから、何の問題も無いだろ?」
「それはそうかもしれないが……」
香月はイライラを募らせる。
「……さて、それじゃ状況を整理しようか」
瞬間、ユウの顔が真剣になる。
今まで『遊び』であったが、今からは『ヘテロダインの代表』だ。
「だが先ずは、ここから別の場所に移ることとしよう。理由は単純明快、話が長くなるかもしれないからだ。話が長くなると、立っているのがつらくなるからね。僕もつらいし。君たちもきっとつらいだろう? だから、そうすることにした」
「部屋を移す……どこで? 会議室とかか? 会議室は確か別の会議をしていて、凡て埋っていたと記憶しているが」
「会議室は会議室でも、僕の部屋だ。そこは会議室の役割をも担っている。だから、一番いいんだ。別に相違ないのならば、そこでやる予定なのだけれど。問題ないかな?」
「まあ、別にいいだろう。そこまで指定することでもないし。こちらとすれば、情報を提供し、共有し、課題を解決出来ればそれでいい」
「それじゃ決定だな。急いで向かおう」
そして、ユウの指示に従って、香月たちは会議室へと向かった。
_ 4
_ ユウの部屋の後ろにあった会議室。
そこには香月、ユウ、果、春歌が一同に会していた。
「……さて、それじゃ報告会と洒落込もうか」
ユウはワイングラスを片手にそう言った。とてもじゃないが、会議の緊張感など皆無だ。
もともとユウはそういう人間だった――と言えばいいかもしれない。香月とユウの付き合いは長い――それはユウと果の付き合いに比べれば短いものかもしれないが――しかしながら、未だ彼女の凡てというものは理解できていない。
それどころか。
彼女の日常を知る人間など、そう居ないのである。少なくとも彼女とは仕事上の付き合いをする人間ばかりなのは殆どである。香月もその一人だ。
だからこそ、恐ろしいのだ。
香月は、このユウという女性が、恐ろしかった。
それはボスと部下という主従関係によるものではない。
ユウ・ルーチンハーグと柊木香月、その個人関係でのことだ。
ユウ・ルーチンハーグという人間にはブラックボックスがあまりにも多い。いや、ユウ・ルーチンハーグという人間そのものがブラックボックスなのかもしれない。
ユウが外界に出ることは殆ど無い。ヘテロダインの業務は一般的に香月のような普通の魔術師によって行われる。
普通に考えればそれは正しいことだ。ユウ程の実力をもった魔術師が、そう易々と外に出てしまえば、命を狙われるのは確実だ。
力を隠している、と言えばいいかもしれないが、実際には隠れることで安寧を得ていると言ってもいいだろう。
それを知っている魔術師からすれば、ユウを『女王』と呼ぶ魔術師も居る。それはヘテロダインの態勢を羨んでいるのか蔑んでいるのか、その何れかだ。
「先ずは香月クンから頼むよ。君の情報を聞いておくことで、『深海の民』について理解も深まるということだ」
「そうだったな」
そう言って香月はスマートフォンを取り出した。
スマートフォンのロックを解除し、メモ帳アプリを起動する。メモ帳アプリに書かれている内容を、そのまま読み上げていく。
「図書館で調べたことなのだが、事故と『深海の民』出現には何らかの因果関係があると考えられる。だが、その因果関係までは解明できていない。残念なことではあるが」
「因果関係がある……それだけ? 香月クン、今日一日使って見つかった情報がそれだけだというの?」
「仕方ないだろ! こっちだって時間が無かったんだよ。それに、急いで伝えようとは思ったが、ホワイトエビルの刺客が現れたし……。まったく、こっちの身にもなってくれよ」
「それは解らないよ。顧客は君を選んだのだから。君が選ばれた以上、君はその仕事をやり遂げなくてはいけないのだよ。それくらい、充分に理解しているつもりだと思うけれど?」
「それは理解しているよ。寧ろ、理解していなかったら、僕はとっくに魔術師なんて仕事をやっちゃいない」
ユウはワイングラスを傾けて、中身の赤い液体を口の中に流し込む。
「まあ、それは置いておくとして。問題はホワイトエビルだね。まさかこちらにやってくるとは思わなかった。もしかしてこちらの行動を常に監視でもしているのかな? それとも、君がスパイの目に見つかったとか?」
「僕はそんなスパイに見つかったことなどないよ。それくらい情報セキュリティはきちんとしているから」
「そうだろうね、そうだと思ったよ」
「……ホワイトエビルは、もともと魔術師組織の中ではどれくらいの実力だったんですか」
訊ねたのは春歌だった。この中では一番魔術師の情勢についての知識が乏しい。だから、その質問が降りかかってくるのはもはや当然のことでもあった。
質問に答えたのは果だった。
「ホワイトエビルは古参の魔術師組織だよ。コンパイルキューブが開発されてからすぐ、魔術師が組織を作った。そしてその魔術師組織が、ホワイトエビルの起源であると言われている。私もそこに所属していたことがあるからね、それくらいは有名なことだ」
「因みに私も、だよ。春歌クン。私と果たんは、その組織……名前はなんて言ったかな。忘れてしまったよ、何せ随分と昔のことだし」
「そうねぇ。確かに昔のことね。あの頃はやんちゃだったものだよ。何せ魔術師が組織を組んで、組織と組織で争う時代では無かったからね。組織と、特定の個人が戦うものばかりだったよ。無論、全戦全勝だったがね」
「あれはいい時代だったよ」
果の話に入ってきたのはユウだった。お酒が入ったからか、もしくはそもそもそういう性格なのか、早口でまくし立てるように言った。
「そもそもホワイトエビルと他の組織は元を糺(ただ)せば同じ組織だった。何が違うかと言えば、その根源にある考え方くらいだろうね」
「……対立した、ってことですか?」
春歌の言葉にユウは頷く。
「コンパイルキューブがいつ生み出されたのか、それがどのような仕組みで動いているのかは未だ解明されていない。コンパイルキューブ自体、ブラックボックスなところが多いのだよ。だから初めは手探りだった。親切にもそこには『説明書』があったがね」
「説明書?」
「コンパイルキューブの説明書だよ。そもそも、コンパイルキューブというのは現代の人間が開発したものではない。かつて魔術師と呼ばれていた存在が作り上げて、我々の時代に託したオーパーツ的なものがある。それが発見されたのは……確かどこかの遺跡だったか? 魔術の行使に生涯を費やし、遂にはコンパイルキューブを発見し利用した……我々魔術師からすれば『神』のような存在が居た。残念なことに、もう亡くなってしまったがね。彼の弟子たちがその意志を引き継ぎ、コンパイルキューブの量産化に成功した。ブラックボックスをブラックボックスのままにするという、致命的なミスを残したまま……」
ユウの話は続く。
「ブラックボックスは誰も解明させることが出来ないからブラックボックスというのだ。決してそれについて諦観の気持ちがあったとか、そういうことは無い。ブラックボックスではあったが、量産化は容易に出来たためだ」
「……その技術が解明されていなかったにもかかわらず?」
「あぁ、なんというか不思議な話だろう? そう思うのも仕方ないかもしれないな……。ともかく、ブラックボックスは解明されなかったが、コンパイルキューブの量産化及び実用は成功した。それと同時に『魔術』は浸透していき、魔術師は生まれた……」
「魔術師はコンパイルキューブの浸透とともに増えていった。それは当然な事由によるものだよ。魔術師を目指す人間はそれ程に多かったということだね。魔術師を目指す人間は、勿論様々な理由があった。例えば自分には何の取り得も無いから魔術を極めようという人間もいたな。はっきり言って、まったく愚かなことだ。そんな生半可な理由で魔術師になろうと思うのが間違っている」
「はっきりと言うんですね……」
「だってそうだろう? 魔術も才能だよ。才能が無ければ簡単な魔術を行使することだって出来やしない。それを知らず、コンパイルキューブが欲しいと戯言を言いだす。それは間違っていることだと私や他の人が言っても、だ。そしていずれ、あきらめる。それと同時に放たれる言葉はいつもきまっている」
_ ――魔術師はケチな存在だ。だから、邪悪と呼ばれる。
「さらっと言っていますけど、それって恐怖ですよ? 恐怖の一言に尽きますよ?」
春歌の言葉にユウは微笑む。
「まあ、そういう時代もあったということだ。若気の至りというやつだよ。今はさすがにそんなことはしないけれどね。目立ってしまう。実際問題、私の行動だけで組織の凡てが決まってしまうと言っても過言では無いからね」
「本当に、若気の至りよねえ……。今は私も魔術師以外の職に就いて実感しているわ。魔術師という職業が、どれほど人間の世界とは違う生き方をしているのかということを」
ユウはワイングラスを傾けたが、もうとっくにワイングラスの中身は空になっているので、それを確認して、ワイングラスをテーブルに置いた。
「それでは、話を戻しましょう。どれくらい戻す?」
「どれくらい、って……。ここに来たのはそもそも魔術師の歴史について語るためでも無いだろ? 先ずはホワイトエビルにどう立ち向かうか、それについて語るべきだ」
「そうね。流石香月クン。いい判断」
ユウの言葉で、会議の舵が大きく取られる。
「それじゃ話を再開しましょう。先ず、私が知っている情報について簡単に説明します。私が知っている情報は全部で三つ」
右手の指を三本立てるユウ。
だが、すぐに人差し指だけを立てた。
「一つ、ホワイトエビルについて。私は前々からホワイトエビルの凶行には常々頭を悩ませていた。彼らの影響力は強い。それによって魔術師の評判全体が下がることにもつながりかねないからね。だから、彼らによる事件が起きたときはすぐさま解決するように全力を尽くした。現に君が春歌ちゃんと出会ったあの依頼……あれもホワイトエビル絡みだからね」
「まあ、薄々気が付いていたよ」
香月は小さく溜息を吐いた。
それを聞いてユウは小さく首を傾げる。
「あら、知っていたの?」
「知っていた以前の問題だ。ホワイトエビルの情報が出始めてから、僕と春歌が狙われ始めた。そこからホワイトエビルの線を当たるのは、常識だろう?」
「常識かどうかはこの際考えないが……、そうか。知っていたのか」
「ただし、これが確信に変わったのは今さっきだけれどね。それまでは確証が掴めないけれど可能性がある程度に過ぎなかった」
ユウは一旦立ち上がると、会議室にある小さな扉の前に立った。
どこへ向かうか解らなかったので、全員目線を集中させていたのだが――。
「……どうした? 別に見ても何も面白くないぞ?」
「え? 本当に?」
「だってこの扉は――」
ギイ、といかにも立てつけの悪い音を立てて扉が開いた。
そこにあったのは――大量のワインだった。
「……へ?」
「ここはワイン収蔵庫だよ。私はワインが好きでね。毎日飲んでも飽きないくらいだ。まあ、たまには焼酎も嗜むがね」
「会議中に酒を嗜むのがうちの代表のルール的なものがあるからね。それについては致し方ない。でも、いまだに反対する人間も居るんだし、少しは自制した方がいいんじゃないのか?」
「ええ? こっちの方が頭も回るからいやよ。嫌です。嫌なんです!」
「三段活用と思わせて全然違うからな、それ……」
もはやギャグにしか見えない会議の流れに驚きを隠せない春歌。
それを見た果が彼女の肩をポンポンと優しく叩いた。
「こういうのは苦手かい?」
「い、いえ……。でも、初めて見たので、その……」
「ああ、慣れないってことか。でも何回か会議を経験すれば慣れてくるよ。確かにユウはああいうやつだけれど、根はいいやつだからね。きっと、君の役に立ってくれるはずだ。それは香月クンも変わらない。彼も君を助けるために全力で取り組んでいる。ホワイトエビルに喧嘩を売るということははっきり言って無謀だが……。そうだとしても、彼らはたちむかうだろうね。いや、現に立ち向かっている。ボロボロになるかもしれない、もしかしたら死んでしまうかもしれない。その可能性が高いというのに、ホワイトエビルに喧嘩を売ろうとしているわけだ。そもそも先に被害に遭ったのはヘテロダイン側だから、順当な理由があるにはあるけれどね」
_ 5
_ 結果として。
会議が終了するまでそれから一時間程かかった。内容は日常の会話の成分の方がどちらかというと多かったように思えるが、しかしきちんと結論は出されていた。
「ホワイトエビルとの全面戦争も辞さない、かあ……」
春歌は香月と歩きながら、会議での結論を呟いた。
「あくまでもあれは代表の言い分だからな? 実際問題、そのようなことをしてしまえば反対派は必ず出てくる。だからそう大っぴらに動くことは出来ない。出来たとしても、僕とあと数名が出られるくらいか。それもヘテロダインと言う名前は公開出来ない」
「どうしてですか」
「それが組織同士の争いに繋がりかねないからだ。全面戦争も辞さないと言っていたが、実際にはそれを避ける必要がある。いや、それは避けなければならない。そのために、今の時点で食い止める」
香月の言葉に春歌は首を傾げる。
「でも、どうすれば?」
「僕たちだけで解決するしかない、ということだよ。深海の民の依頼を引き受けたのもそれが理由だろうね。それによってホワイトエビルの悪事に関する証拠が見つかれば攻撃の正当化を理由づけることが出来るから」
「……あなたは深海の民とホワイトエビルに、何か関連性があると思っているんですか?」
「残念ながら確固たる証拠が無いのは事実だ。……しかし、実際問題、深海の民が現れた時期と飛行機事故には密接な関係がある可能性という状況証拠、それに飛行機事故を引き起こしたのはホワイトエビルという……こちらも状況証拠になるが、その二つがある。状況証拠はもう大丈夫だ、あとは物的証拠。しかもそれ一つでホワイトエビルの悪事を暴くことが出来るようなもの……。それさえあれば、後は楽なんだけれどなぁ」
香月はそう言うと頭をがしがし掻いた。そんなことを言うのは、彼にとってまったく道筋が立っていないという意味に等しいのだが――春歌には知る由も無かった。
香月の話は続く。
「それにしても……思ったよりヘテロダインも手を拱(こまね)いているようだったな……。はっきり言ってあれは丸わかりだ」
「ヘテロダインがホワイトエビルに手を出せない、或いは出そうとしない理由でもあるんですか?」
「いや、そんなことは……無いはずだ。彼らが守りたいのは組織の看板。ホワイトエビルは、残念ながらとても強固な組織だ。現代に魔術師が誕生した、その当初から活動していたのだからな。……対してヘテロダインは寄せ集めの集団に過ぎない。力だけをパラメータ化すれば、もしかしたらこちらが強いかもしれないが、自らの利益のみを追求する魔術師も少なくないからな……。それを考慮すれば確実に勝てない」
「……でも、ヘテロダインもそれをしっているんですよね? 自覚しているんですよね? だったら……」
香月はその言葉を聞くや否や、態度を一変させた。
鋭い目つきで春歌を睨みつけたのだ。睨みつけられた彼女が身震いしてしまう程に、殺意の籠もった視線だった。
香月は直ぐに我に返る――その理由は紛れもなく彼女の怯えた表情を見たからなのだが――と、顔を俯かせた。
「済まない。君にぶつけるべきでは無い。寧ろ僕の方がぶつけられる立場だと言うのに」
「いえ、別に……」
そんなことなど、考えてはいなかった。
ただ今の彼女は申し訳ない気持ちでいっぱいだったのだから。
「気持ちを切り替えよう」
香月は身体を伸ばした。凝り固まった筋肉を解すためと、その気分転換だ。
「ホワイトエビルが君を狙う理由……それはもう充分過ぎるぐらいに理解した。ともなれば次は、どうやってホワイトエビルから守り抜くか、だ……。ホワイトエビルの魔術師は精鋭揃いだ。今日のような連中はフリーの魔術師を適当に使っただけに過ぎないだろう。恐らくは、僕たちの力量を量るために」
「それだけのために……魔術師を使い捨てに?」
「充分考えられる可能性だ。勿論、間違っている可能性も大いに有り得るがね」
春歌は信じたくなかった。人間をそんな風に使い捨てにする人間を、知りたくなかった。
「……世界には知りたくない事実なんてごまんとある。知るべき事実の方が少ないくらいだ。この場合は知りたくないというよりも『知らなきゃ良かった』とでも言えばいいだろうか。まあ、それはただの言葉の綾だ。そんなものはどうでもいい」
香月は首を横に振り、話を続ける。
「だがね、知りたくなかった事実を受け入れなくてはならない。その凡てを知って、理解しろ……そこまでは強要しない。だが、せめて……それくらいはしてもいいんじゃないか?」
春歌は俯いたまま、何も答えない。
溜息を吐いて、話を続ける。
「確かに僕だって信じたくなかったことや理解出来ないこと、たくさんあった。特に魔術師という道を進んでからね。でも僕はそれを後悔していない。その人生を後悔しちゃいない。それをした途端、今までの自分が無かったことにされる気がしたからだ。今までの、僕の人生が全部無かったことにされると思ったから」
「後悔……それじゃ、あなたはあの時飛行機に乗ったことも後悔していないというの?」
香月の表情が一瞬歪んだ。
「……なぜそのことを知っているんだ?」
「果さんから聞いた。……いいえ、今はその情報源なんてどうでもいい。私が言いたいのはただそれだけ。……香月くん、あなた本当に……飛行機に乗ったことを……」
「やめなさい、城山春歌」
二人の会話が何者かによって中断された。
声のする方を振り向くと――そこに立っていたのは果だった。
_ 6
春歌は目の前に立っていた果の姿を見て、呟いた。
「果さん、あなたが言ったのか」
香月は苛立ちを隠さなかった。あえて隠さなかったのかもしれない。明らかに怒りを表面化していた。
香月は一歩果の方に近付く。
「おお、怖い。……君がそんな風に明らかな敵意をむき出しにしていたのは数年ぶりかな?」
「そんなことを言っている場合では無い。あなたが言ったことは、僕にとって隠し事であるということ。解っているね? 信頼を失ったということにも言えるということを」
「そりゃ解っているよ。解っているうえであの発言をしたのだから。二人で記憶を共有したのだから」
「記憶を共有した?」
「だって、あなたは彼女を魔術師に仕立てあげるのでしょう? 彼女の『目』さえあれば、もしかしたら最強の魔術師になるかもしれない。あなたはそう思って……魔術師にさせる道を選択したのでしょう?」
「そのためには僕の忌まわしき記憶を共有する必要があったのか……? 忘れて居たかったのに、ほかの人には騒いでほしくなかったのに」
「残念ながら、その通りよ」
果は溜息を吐いた。
未だ香月は果の言葉の意味が理解出来なかった。そもそも彼女は少ない言葉で大量の情報を伝えたがる人間だった。時間が無いときはそれでも問題無いのだが、端折る場所があまりにも解らないくらい自然なので、会話が成立しない時もある。
彼女曰く、魔術師だった頃の名残だと言うが、そうだとしてもその仮説が成り立つことは厳しい。
言葉が伝わらないということはコミュニケーションが成立しない、ということと同義だ。仲間意識が強い魔術師組織でそのようなことは御法度である。何をされるか解ったものではない。
「……敢えて言葉を付け足すならば、あなたは彼女を強くするために、あなたの凡てをさらけ出す必要がある。どこの馬の骨とも知らない奴よりも若干気心の知られた方がいいでしょう?」
「そういうもの……なのか?」
「ええ、そういうものよ。普通に考えられなかったのかしら? 女心ってものは世界の凡てを発見するよりも難しいことなのよ? 理解出来ないことだと一蹴してしまうのは、幾ら何でも……少し頭が悪い行動なんじゃないかしら」
「頭が悪い。そりゃ、僕は男だからね。女性の言葉、心、仕草……そこに込められた隠された意味なんてそう簡単に理解出来ない。いいや、理解できやしないよ。何せ、性別が違うという根本的な問題を抱えているのだからね」
「それがダメだと言っているのよ!」
人差し指を香月の鼻に突き刺す。とはいえ突き刺された方は人間の肌、そう簡単に押し込まれることは無く、若干凹む程度で後は戻ってしまう。
「ダメ、とは」
「あんたは女心をまったく解っていない、ってこと。あなたの話は以上、次に春歌さん」
果は言うだけ言って、春歌の方に身体を向けた。
その剣幕で見つめられたので少し彼女は物怖じしてしまった。
次の瞬間、彼女の頭を果がチョップした。果の名誉のために説明を補足しておくと、力を強く加えたわけではなく『おふざけ』でやったような、そんな感じだ。
「あなたもあなたで問題点があるから言っておくわ。香月クンの前であの『事故』の話は御法度。あなただってトラウマになっていて、もう触れられたくないことを何度もほじくり返してほしくないでしょう? つまり、そういうこと」
早口でまくし立てられて、後半何を言っているのか少し理解に乏しいところもあったが、前半の内容で何となく補足することが出来た。
果の話は続く。
「少しあなたも考えたらどう? あなたがされて嫌なことは、その人もされて嫌だということ。それを自覚しなさい」
「自覚……ですよね、そうですよね。ほんと私は馬鹿でした。すいません、柊木さん」
深々と頭を下げる春歌。
それを見て香月は慌てて、
「いや、君が謝ることじゃない。だからといって、きみのしたことが許されることでもないのは確かだけれど」
「……やっぱり未だ怒っているじゃないですかあ!」
「そりゃ怒っているよ。だって、僕の言ってほしくないことを目の前で言われたのだよ? 怒るのも当然だろう?」
香月は手を上げる。
「香月クン」
「解っているさ」
果の言葉を、彼は受け入れる。
そしてそのまま彼はその手を――彼女の頭に優しく押し当てた。
要するに、彼女の頭を撫でたということだ。
「……え?」
彼女は一瞬思考を停止させた。
香月がそんな行動をとったのが、まったく理解できなかったからだ。
「そんなことを言わせる状態にしてしまったこと……それは申し訳ないと思っている。それはすまなかった。それについてお詫びしたい。それが僕の意志であり、決定条件だ」
「べ、別に構わないよ、そんなこと……。悪いのはこっちなのに」
「どうやら、あっという間に解決したようで何より。これであとしばらく続いていたらとんでもないことになっていたよ。……さて」
果は白衣のポケットから紙切れを取り出した。
「その紙切れは?」
「これは情報だ。『彼女』から手渡されたものだよ」
彼女、というのはヘテロダインの代表――ユウにほかならない。
ユウはヘテロダインを動かしたくない。だが、ホワイトエビルは倒したかった。そのために香月に情報を渡したのだろう。秘密裡に彼女に渡したということだ。
「代表が提供した情報……相当な情報なのか?」
「さあ? それは私にも解らないよ。いい情報なのかまったく使えない情報なのか……それは君がこれを見て判断することだ」
香月は情報の書かれた紙切れを受け取った。
_ 7
_ ふるーるたうん木崎は、木崎湾に面する臨海地区に作られた比較的新しい大型商業施設(ショッピングモール)である。
深夜、もう電気もついておらず人通りも少ないくらい何も無い。
そんな場所に香月と春歌はやってきた。
「春歌、ここを知っているか?」
「……ここはショッピングモールですよね。去年完成したばかりの比較的新しい場所です。毎日大勢の人でごった返していますから、よく知っています」
「そう。ここはそういう場所だ。……だが、それと同時に人の思いが集まりやすい場所でもある。考えてみろ、たくさんの人間が集まっている場所……一人一人が負の概念を持っていても僅かなものだが、しかし、そういう概念が十人、百人と生まれた場合は? 同じ場所に姿を見せたとしたら?」
「……どうなるのですか?」
「簡単なことだ。それが一つとなり、一つの巨大な『塊』となる。それがどういう意味を為すのかは、魔術師のことを少しでも知った君ならば当然解る話だ」
「……それが魔力と言うんですか」
春歌は青ざめたような表情でそう言った。
香月はそれを聞いてゆっくりと歩き始める。出入り口から入れないかどうか、模索しているようだった。
「その通り。それが『魔力』だよ。人間の魂から得たエネルギー……それをコンパイルキューブによって最適化(コンパイル)された『コード』で魔術を使うことが出来る。人の魂、そのエネルギーを使うことは……はっきり言えば神への冒涜と言っても過言では無いだろうね」
「神への……冒涜」
「ま。僕は神様なんて一切信じていないけれど。そんな存在が居るなら救われるべき存在はとっくに救われている」
軽いニュアンスだった。しかしその言葉は彼女に重くのし掛かった。
間違いを否定しているわけではない。正論を徹底的に肯定しているのだ。そんなことをする必要が、と言われればそれかもしれない。しかしながら、香月はそんなニュアンスを敢えて使った。
「ニュアンスの問題だ。実際問題、ニュアンスの相互が満たされずうまくいかないことだってある。うまくいかなくなった場合は……問題を切り捨てる可能性だって肯定せざるを得ない」
「……ところで、どうして私たちはここに?」
春歌は小さく呟いた。何故ここに呼ばれたのかいまだに理解していないためである。
それを聞いた香月は首を傾げる。
「どうして、って……。寧ろどうして何も気が付かないのか。僕と君がここに来たのはこれが原因だよ」
「これ?」
香月が取り出したのは先ほど果からもらったメモだった。
メモには何が描かれていたのだろうか? 春歌は思ったが、香月に聞いても教えてくれなかったので半ばそのことを聞くのは諦めかけていた。
「……さっきは言えなかったが、これにはここの場所とあるものが書かれていた」
唐突に。
この場所について香月が話し始めた。
春歌はそれに耳を傾ける。
「あるもの、とはここを経営している人間の名前だった。名前に見覚えはないが……おそらくホワイトエビルの関係者なのだろう。ここにショッピングモールを作った理由は、はっきり言って理解できないが、何かあるのだろう。それは確かだ。そうでなくては、僕がここに来た理由も無い」
「そんな曖昧な証拠だけでここまで来たんですか?」
「そうだな。君にはそう言われるかもしれない。いや、魔術師以外の人間がそれを聞いたならばそう思うかもしれない。しかし、魔術師がそれだけの情報を受け取ればそのように認識できる」
「魔術師にしか認識できない、暗号でも混ざっているんですか?」
「暗号? 違うね。どちらかと言えば符号と言えばいいだろう。点字に近いものだ」
コツ、コツ、とショッピングモールの廊下を歩く香月と春歌。
誰も居ないショッピングモールは非常口の誘導灯だけが怪しく光っていた。
それが不気味で、彼女にとってとても気持ち悪かった。出来ることならすぐに帰りたかった。
「……あの、何も見つからないなら急いで帰った方がいいと思いますよ? 魔術師だからって、現代の法律を無視していいというわけでも無いですし」
「現代の法律を無視していい訳が無いだろう。魔術師だって社会に必要な存在として、認識されている。だが、社会からしてみれば『魔術』という危険なものを使っているテロリスト予備軍に過ぎない。そんな人間が、一人でもルールを無視してみろ? それを口実に魔術師の殲滅が行われかねない。いくら魔術が使えるとはいえ、科学技術に勝てるかと言われると難しいところだからね」
香月はある場所で立ち止まった。
そこにあったのは非常階段だった。
「非常階段……?」
「ああ、きっとここに地下室がある」
「それは魔術で?」
「ここの施工図を見たが、必要の無い地下空間が存在することが判明したからね。恐らくそこに何かがある」
非常階段の扉――そのノブをひねった。
ドアは開いており、ドアを押すと、ゆっくりとドアが動き始める。
それを見て、香月は頷く。香月はそのまま階段の中へと入っていく。春歌もそれに乗り遅れないように急いでその後を追いかけていく。
_ 8
_ 地下へと続く階段を下りていく香月と春歌。
「ほんとうにここに何か眠っているんですか……?」
訊ねる春歌に香月は頷く。
「ああ、その通りだ。ここに謎の空間がある。それが生まれた理由はまったくもって理解不明だが……。それについては、きっと施設に入った段階で理解できるだろう。たぶん」
「ひどく曖昧な言い回しですけれど、大丈夫なんですよね? ですよね?」
春歌の質問に香月は答えない。
それに不安がる彼女だったが、仕方なく彼に従って階段を下り続けることとした。
そこに何があるのか――何も分からなかった。
_ ◇◇◇
_ ゴウン、ゴウンという音が地下室の空気を覆い尽くしていた。
その音は機械が駆動している音そのものであり、その機械が駆動しなければこの空間の意味を失ってしまうほど、重要なものだった。
「……そうだとしても、さ。五月蝿いったらありゃしないよ。この音」
薄いブルーのショートカットをした少女が、鼻歌を歌いながら通路を歩いていた。
その傍らには一人の青年も歩く。青年は少女より頭ひとつ分大きい。白衣を着ているがその白衣も皺だらけで、お世辞にもかっこいいとはいえない。
「君の言いたいことも解る。だが、これは上の決めたことだ。上の決めたことには逆らっていけないことくらい君も理解していると思っていたけれどね」
「それくらい……知っているわよ。だけれど、私が言っているのは騒音問題。これ、絶対電車が相反して通過しているときよりも大きい騒音だとおもうけれど。こんなところでぐっすり眠れるわけがないじゃない」
「ノンレム睡眠ならば、問題ないのではないかな?」
どうだか、と言って少女は会話を終了する。
少女と青年は再び何も言うことなく通路を歩いていく。
通路の壁には時折ランプのようなものがつけられており、それが赤色であったり青色であったり、様々な色で点滅していた。
「……どうやら順調にエネルギーを溜め込んでいるらしい。流石だね、伊達に資金を注ぎ込んでいない」
「いったいいくら注ぎ込んだの?」
「そうだね。ひとつの大手企業、それも二千人規模の企業が売り上げる金額程度といえばいいか」
「ざっと一千億?」
「それくらいかな」
うわおー、と両手を挙げていかにもオーバーなリアクションをとる少女。
対してメガネの位置を直すだけというクールな態度を貫く青年。
二人の態度は対極的であったが、しかし不思議とそれは合致しているようにも思えた。
「それにしてもおじいちゃんも大変だよねー。あんな巨大なものをこちらで作ろうだなんて、さ。まだあの技術って完全に解明できていないんじゃなかったっけ?」
「仕方ありません。そう言われたのはほかでもない『あの方』です。私たちがどうこう言っても何も変わりませんよ。せいぜい命令違反だといわれて殺されるのがオチです」
「つまんないのー。それでも魔術師なわけ?」
くるくると回転して、青年のほうを向く少女。
それを聞いて溜息を吐く青年。
「ほんとうにあなたには振り回されっぱなしです。かつては世界を破滅に導いたというものを、人間が扱えるかもしれないという実験ですよ? それについて何も考えないのですか、あなたは」
「考えるも何も、ただの模倣品じゃない。かつての人間が作り上げたオーバーテクノロジーを現代風にアレンジしただけ。あとは何も変わらない。それについて何を言えばいいわけ? 一から百を作るより、零かから一を作ったほうが賞賛されるに決まっているじゃない」
「そりゃ当然そうだ。けれど、アレンジが成功したのだから少しくらい嬉しく思ってもいいのではないかい? 或いは素晴らしー! とかかっこいー! とかの一言でも言ってくれれば、今後頑張ることができるというものだよ」
「はいはいがんばってねー。これでいい?」
「何だろう! 思っていた温度とぜんっぜんちがう! 温度差がぱない!」
通路の終わりが見えてきたのは、そのときだった。
「ほら、見えてきたよ。終わり。そろそろ最終チェックに入るのでしょう?」
「ん。ああ、そうだった。そうだよ、もうすぐ終わるのだよ! 完成する、と言ってもいい。それがまさかこんなにも時間がかかるとは思いもしなかった! まあ、その分素晴らしい出来に仕上がったのだけれどね!」
通路を抜けたその先にあったのは――巨大な箱だった。
一辺が二十メートル以上ある、黒い巨大な箱。それがゴウンゴウンと音を立てて駆動している。
それを見上げて、少女は呟く。
「何度見ても思うけれど……圧巻よね、これ。こんなものよく開発出来たと思うわ」
「そりゃこの箱を作るまでに時間がかかったからね。ざっと……五年程度かな? もしかしたらそれ以上かかっているかもしれない。何度もリテイクがかかったからね。いやあ、それにしても大変だった。休んでもいいよね?」
「整備とかどーすんのよ」
「それは専門スタッフがいるから。僕は開発と研究をしたまでのこと! さあ、僕は仮眠室に横になるんだー! 昨日から寝ていないし!」
そんなハイテンション白衣はさておき、少女は再びそれを見つめた。
巨大な箱には何本もの線が接続されていた。その線はどれも機械に接続されている。機械にはエネルギー充填率などのパラメータが可視化されており、その場で見ることが出来る。
そんな巨大な箱の前から急いで立ち去りたいのか、少しだけ歩調を早めて、少女は呟いた。
「……それにしてもこんな巨大な箱を作って、何がしたいのかしら。ま、それはボスのみぞ知る、のかもしれないけれどね」
そして彼女は壁にいくつもある扉のひとつに入っていった。
_ ◇◇◇
_ 香月は扉を見つけた。
「……ここが終わりか?」
香月は首を傾げて、ドアノブに手をかける。
油断していたわけでは無い。瞬時にドアの向こう側にいる気配を確認し、誰もいないことを確認したまで――だから、安心してドアノブに手をかけることが出来るわけだ。
そして彼はドアノブに手をかけ、ゆっくりとそれを右に回した。
「やあ、久しぶりだね。お兄ちゃん」
背後から声が聞こえたとき、香月は一瞬だけ――その行動が遅れてしまった。
たったコンマ数秒の遅れだった。
「お兄ちゃん。私以外の女の子と一緒に歩いて、何がしたいの?」
「た、助けて……」
背後に立っていたのは、少女だった。黒い帯のようなものを全身に巻き付けた、一見独特なファッションをした少女だった。
その少女は透明なナイフのようなものを構え、それを春歌の首に当てていた。
「……何が『お兄ちゃん』だ。そんな作戦が僕に通用するとでも思っているのか?」
「お兄ちゃんはお兄ちゃんだよ。私だって一緒に手を繋いで歩いたことも無い……いや、あったかも。事故の前にあったかもしれない。けれど、それってもう十年以上前のことだし、忘れちゃうのも当然のことだよね?」
「いい加減にしろ。何が言いたいんだ」
香月の表情がどことなく焦っているのを、春歌は感じていた。
(きっと自分が捕まっているからだ)
自分が捕まっているから、その足枷となってしまっているということ。
それを春歌は感じていた。
「お兄ちゃん。変わったね。普通なら、いつもなら、容赦なく私を攻撃しただろうに。何があったのかな?」
「五月蠅い。それに僕はお前のお兄ちゃんじゃない。関係なんて全くない。いい加減にしろ。僕には妹なんていないぞ」
「ほんとうにそう言える?」
「……何?」
「柊木香月には妹なんていない。それがほんとうに、はっきりと言える?」
「言える。僕には妹なんているはずが……」
「無い、って?」
香月の心が揺さぶられる。
「もう一度思い出してみて。あなたの記憶に、ほんとうに妹は居ない? つらかったから、あの事故がつらかったから忘れただけでは無くて? 私の名前は柊木夢実。あなたの妹よ」
「何を言っている! 僕の妹は居るはずが……」
「――ったく、埒が明かない。このまま平行線をたどる議論を続けるくらいなら、さっさと終わらせてしまったほうが良かろう」
香月は夢実との議論に集中していて、背後から迫るもう一つの気配に気が付かなかった。
「な……!?」
そして。
突然香月の身体は崩れた。
香月の背後に立っていたのは、大柄な男だった。黒いスーツを着ており、エージェントのような恰好をしている。
「だーかーらー、私が全部やるって言ったでしょう? あなたが出てくる場面ではない、って」
「そうだとしても、時間がかかりすぎる。もしこちらが出てこなかったら、どれくらい時間をかけていたのか。そう時間もかけられないのだぞ。ボスが行う計画、それを実行するためには、あまりにも時間が足りな過ぎるのだから」
それを聞いて溜息を吐く夢実。
「……解っているわよ、それくらい」
「解っていたのならば、もう少し時間をかけないで効率的にやってほしいものだけれどね。あのタイミングで君の正体を晒すべきでは無かったと思うけれど?」
「それは別にいいのよ。私だって考えはあるし。……おっと、『彼女』が起きていることを忘れていた」
「あ、あなた……ほんとうに、香月クンの妹、なの……?」
「そうよ」
夢実は笑みを浮かべる。
「大丈夫。取って食うことなんてしないから。……さあ、ゆっくりとお休み」
夢実が春歌の頭上に手を翳すと、春歌に急激な眠気が襲い掛かってきた。
そして彼女が眠るまで、そう時間はかからなかった。
_ 9
_ 次に春歌が目を覚ました場所は牢獄だった。石造りのそれは普通ならば背伸びしたって届かない位置に穴が開いており、そこから光が漏れていた。
春歌は身体をゆっくりと起こしていく。生憎身体に痛みなどは無いようだった。
「目を覚ましたようだな」
少し離れた位置には香月の姿もあった。香月の両手首及び足首には鉄球が鎖を通して結びつけられていた。
どうやらそれは春歌も同じようだった。
「まったく……まったくもって迂闊だった。まさか妹の名を騙るとはね」
「……妹さんはほんとうに居るんですか?」
「あぁ」
香月は意外にもあっさりと彼女の問いに答えた。
「だが、あの飛行機事故で死んでしまったがね。だから生きているはずは無いんだ。生きているとすればそれこそホワイトエビルが彼女を騙している……そうとしか考えられん。いずれにしても、コンパイルキューブが無い以上魔術も使えないしね」
「手詰まり……ってことですか?」
「君はそう思っているのかい?」
香月の言葉に、春歌は首を横に振った。
「そうだろう、そう思ってくれないとね。……だが、残念ながら状況は非常に厳しい。ここから逆転することは難しいことじゃ無いと思う。だが、コンパイルキューブが取り返せないとね……。肉弾戦が苦手なわけでは無いが、やはり魔術師相手には魔術で攻撃しないとなんとも言えないのだよ」
「先ずはコンパイルキューブを取り返す必要がある……ってことですか」
「そういうことになるな」
香月は頷く。
簡単に言っているが、そう簡単にはできないことを彼は知っていた。彼が一番理解していた。
だが、それを言うことは彼女の不安を煽ることにほかならない。
だから、言えなかった。
彼女には少しでも希望を持っていて欲しかったのだ。
「はあい、お兄ちゃん」
牢獄の扉にある仕切り窓がスライドしたのは、ちょうどその時だった。
窓の向こうには夢実の顔が見えた。どうやら窓に顔を寄せて話をしているらしい。
「何が『お兄ちゃん』だ。お前のお兄ちゃんじゃない。第一、夢実はあの事故で……」
「ほんとうに私が死んだとでも思っているの? だとしたら殊勝なこと。目の前に生き別れの妹が居るというのにお兄ちゃんったらまったく……」
そう言って溜息を吐く夢実。
香月は話を続ける。
「そういう皮肉を言いに来るために、わざわざここまでやってきたのか? だとしたらそれこそ殊勝じゃないか。あぁ、嬉しいことだ。こんなに愛されているのだからね!」
皮肉しか込められていない香月の発言を聞いて、夢実は小さく舌打ちする。
その瞬間、一気に空気が変わった。
「……ほんと、お兄ちゃんって変わらないよね。人の言うことを聞かないというか、理解しないというか、理解したがらないというか」
「そのどれもが間違っているよ。僕は理解しないのでもしたがらないのでもない。『したくない』だけだ」
「……したくない?」
夢実は香月の言葉を反芻する。
「そう。したくないだけだ。それはただのエゴに過ぎないかもしれないけれどね。僕自身が理解するかしないか、判断するわけだよ。そして後者に入ったものはいかなる情報でもシャットアウトする。……それが『したくない』の答えだ」
「お兄ちゃん。それがあなたの選択?」
「ああ。これが僕の選択だ。まったく、間違っていないと言えるだろうよ」
それを聞いた夢実は舌なめずり一つ。
「ふうん、別に間違っていないかもね。それも一つの選択だと思うよ。けれどね、それは今の状況では間違っているんだよ。それを理解してほしいなあ。それとも、理解しているけれどその選択をしないだけ? だとしたら、お兄ちゃんはおかしいよ」
「そんなわけはないよ。僕はその選択をした。ただそれだけのことだ。それだけのことなのに、それに口出しをして欲しくないね。それが『妹』なのかい?」
「……私はお兄ちゃんのことを心配して、言っているのよ。お兄ちゃん、ヘテロダインなんて野良組織捨てて、こっちに来ない?」
「こっち、とは『ホワイトエビル』のことか?」
頷く夢実。
その言葉に鼻で笑う香月。
「……どうして、どうして鼻で笑うのよ! そっちのほうがお兄ちゃんだっていいに決まっている! お兄ちゃんのその魔術師としての才能も、こっちで生かすことが出来る! こっちなら、お兄ちゃんのことを全面でバックアップすることが出来る! だから……」
「そうだとしても、僕がホワイトエビルに抱いている感情を無碍にすることは出来ないよ」
「お兄ちゃん。あなたが抱いている感情は、別に間違っていない。けれど、今はアウト。アウトなんだよ。間違っていると言ってもいい」
それを聞いた香月は笑みを浮かべる。
そんなことは有り得ない――とでも言いたいのかもしれない。
「解った。取り敢えず考えておくことにしておこう。でも、僕はまだあきらめない。自分を曲げたくないからね。間違った方向に進むくらいなら、自分自身でこれを打ち切ってしまっても構わない」
「……ほんとう、お兄ちゃんって昔から強情だったよね」
「別にいいだろ、それくらい。話はそれだけか?」
「うん。それだけ。お兄ちゃんと、そこの『目』に対する判断はまだ下されていないから。時間の問題だとは思うけれどね」
それだけを言い残して、夢実は去って行った。
_ ◇◇◇
夢実が去って直ぐ、香月はぽつりぽつりと言葉を紡いだ。
「……だとしたら、どうして彼女はホワイトエビルに居るのですか? 実際問題、彼女が香月クンの両親が亡くなった事故を忘れているようにも見えませんでしたし……」
「問題なのはそこだ」
香月は春歌を指差して言った。
「どうして夢実がホワイトエビルに対して何も思っていないのか。いや、もっと言うなら、どうして彼女が魔術師としてホワイトエビルに所属しているのか? おかしい点が多すぎて頭がパンクしそうだよ」
彼が言うのも当然のことだ。
夢実の行動には疑問ばかりが残る。
寧ろ正当性がまったく見えないと言ってもいい。どうしてこのようなことをしているのか――普通に見て有り得ないところばかりだ。
「普通に考えてみれば……ホワイトエビルが事故を起こしたとは知らないのではないのでしょうか?」
「いや、それは有り得ないな。僕との問答を思い出してみろ」
春歌はそれを聞いて思い返す。
「あ――」
そう。
彼女はこう言ったのだ。
_ ――あなたが抱いている感情は、別に間違っていない。
_ それは即ち、『あの事故をホワイトエビルが起こした』ということを理解しているのだ。そうでなければその解答は出来ない。
「おかしな話とは言わない。けれど、変な話だと言われれば当然のように答えることが出来る。矛盾とは言わない。だが、おかしいんだよ。彼女がここにいる理由が、まったくもって理解できない」
「一先ず、コンパイルキューブをどうにかしないといけないんですよね……」
「ん? ああ、まあ、そうだが。今はそれを話している場合では……」
「いや、何か変な気配がしてふと思ったんですけれど……」
春歌は指を差した。
その先にあったのは――先ほど夢実が見せた窓である。
「窓か? この窓がどうかしたか」
「この窓、意外と広いですよね……。ここから手を伸ばしてどうにか出来ないかな、とか思ったんですけれど」
「馬鹿か。だったらとっくにやっている。見てみろ。あの窓の大きさ、僕が腕を出しても肩まで入るか解らない。仮に入ったとしても、その先に何があるか不明瞭な状況だぞ。そんな場所に進んで手を出そうなんてことはしたくないね」
「そ、そうですよね。確かにそうです……。あーあ、実はこの扉が開いてくれているなんてこと無いかなぁ」
「そんなことあるはずが無いだろ。間違っていても、断じて有り得ない」
春歌の言葉を直ぐに否定する香月。
「もう! 解らないじゃないですか。もしかしたら開いている可能性だってありますよ! 扉にきちんと触れるまで、まだ鍵がかかっているかかかっていないか解らないですからね!」
「なんだそれ……、シュレーディンガーの猫じゃあるまいし」
シュレーディンガーの猫と聞いて春歌は首を傾げたが、香月は特に説明することなどしなかった。別にする必要も無く、考える必要も無かったからだ。
――別に説明することが無いと解った春歌は再び話を続ける。
「あー、さっきの子……夢実さんでしたっけ? 彼女が扉の鍵を開けているなんてことあり得ませんかねえ……」
「有り得ないだろ、幾らなんでもそんなことは考えられない。そんなことをしたら意味が無いし、彼女が処罰されるのだぞ? こちらは捕虜で、あっちは正社員みたいなものだ」
「どうして正社員だけまともな観念で話をしたんですか……?」
魔術師組織の構成員、と言うのはとても言い辛いだろう? と香月は言って扉のほうに近付く。
「まあ、一応……確認だけな。それだけはしておこう」
そして彼はドアノブに手をかけて、手前に引いた。
_ ――扉は抵抗することなく、ゆっくりと開き始めた。
それは彼にとっても予想外のことだった。
そんなことは有り得ないと思っていた。信じられないと思っていた。
だからこそ、そんな間抜けな声を上げてしまったのだろう。
「やった! 開いていますよ! まさか、ほんとうに彼女が開けていてくれたなんて!」
ほんとうにそうなのだろうか――香月はそう思ったが、取り敢えず外へ出るためにはそれしか手段が無いのも事実であった。
そこで考えても何も変わらない――そう思った彼は、ひとまずそのチャンスを有効活用することとした。
_ ◇◇◇
夢実はそれを聞いて溜息を吐いた。どうせ呼ばれるだろうと思っていたからだ。それだけの行動をしたからだ。しかしあまりにも明らかになるのが早すぎる。まるで『眼』があったかのように。
その声がかかったのは井坂の部下である|延島(のべしま)であった。延島は女性だ。だからといってガールズトークが弾むわけでもなく、殆ど井坂と一緒に居る。噂によれば井坂と付き合っているのではないかと言われている程。
「何か、変なことを考えていません?」
「え? 何ですか。知りませんよ。それで、何を考えているんでしたっけ?」
「違う! そんなことを言っているわけでは無い! 私が言ったのはボスが呼んでいるということ、ただそれだけだ!」
「ああ、ボスが。はい、解りました、今向かうので伝えていただいていいですか? 少し用事を済ませてから行く、と」
「いや、その必要はない」
背後に気配を感じたが――あまりにも遅すぎた。
刹那、彼女の身体がノーバウンドで吹き飛ばされ、壁に叩きつけられた。
その時間、僅か一秒。
「がは……っ!」
彼女は床に倒れる。
それを見るべく、近付く男。
その声は誰の声だか解っていた。
「君、やってはいけないことをしたね? 認識しているかい?」
「増山……敬一郎……!」
「おやおや、君はわすれてしまったのかい? 僕のことをここではなんと呼ぶのか……ボスだよ、ボス。それを忘れてしまっては困るねえ。僕の名前を憶えて居ることに関しては、まだ僕のことを認識しているという考えでいいのかな?」
「五月蠅い! 私の両親を殺して、なおかつ『あれ』に使ったくせに! お前は人間じゃない、人間の皮を被ったバケモノだ!」
「バケモノ、とは」
溜息を吐く増山敬一郎。
「まったくもってその言葉には反吐が出るよ。この世界にはエネルギー問題ということが着いて回る。それをどうすればいいのか……そう考えたときに出てきたロストテクノロジー……、それがコンパイルキューブだった。それを使わない手は無いだろう? 残念ながら電気や水道、ガスといった現在のパイプラインをそのまま拡大することは出来ない。いずれも資源が必要となるからだ。電気ならば火力発電を行うための燃料、原子力発電は……出来なくなってしまったから割愛するとしようか。太陽光発電や風力発電などのエコエネルギーに力を注いでいるけれど、残念ながらその普及率も低い。ならば、どうすればいいか?」
踵を返し、増山敬一郎は夢実に背中を向けた。
敵を倒すことの出来る、千載一遇のチャンスだ。
だが、彼女はコンパイルキューブを取り出すことすらできなかった。
増山敬一郎を倒すことの出来るヴィジョンが浮かばなかったからだ。
「考えられたのは、精神力だよ、精神力を魔力に変換(コンパイル)することの出来るロストテクノロジー。それを使おうと考えたわけだ。しかしながら魔力は大変使い勝手が悪い。魔力だけでは何も出来ない。それを『魔術』で行使しない限り、魔力は何の意味も持たない。この意味が解るか? 魔力というのは選ばれた人間にしか、その使い方を知ることも出来ないし、仮に知ったとしても使うことが出来ないということだよ。これは素晴らしいことだ。なぜなら、私たち人間が最後に遺されたエネルギーなのだから」
「エネルギー……? エネルギー問題を解決だとか、そんな正論を述べておいて、実際はあなたの帝国を作るための布石にするのでしょう? コンパイルキューブを使うことで魔術を行使できるのならば、それを応用して軍隊だって作ることが出来る。それこそ、魔力の問題さえ解決すれば」
それを聞いた増山敬一郎は一瞬目を丸くしたが、すぐに笑い出した。
「ハハハ! やはり解っていたか。流石はあの『魔術師夫婦』の娘だけはある。忌まわしきあの二人の娘だな……。まあ、それくらい予想の範疇だったが」
「何ですって……」
「だって君たちは何も知らないではないか! 実際問題、世界はどうなっている? エネルギー問題だけではない! 食糧問題に人口問題! それ以外にも様々な理由が絡み合っている。この星に人間が増え続けることは、もうあってはならないのだよ。だから、僕が粛正する」
「そんなこと許されると思っているの!? 神にでもなったつもり!!」
「ああ。少なくとも、僕は神と同じ存在だ」
はっきりと。
言い切った。
「そんなつまらない考え方をしていたのかい? だとしたら、君はやはりあの二人の娘だということになる。観察力が高い。いや、それよりも、実際に問題となっていることを片付けなくてはなるまい。君も気になっているのだろう? あの巨大な筐を」
「当然でしょ。ずっとあれの保護を任されてきて、何も知りませんでしたなんて信じられる?」
「本当は教えたくないのだけれど……。別にいいか。あの筐は巨大なコンパイルキューブだ。コンパイルキューブだということは知っていたのかい?」
「何となく、ね」
「まあ、だろうね。それしか情報が流通していないからね。なら、君に教えよう。メイドの土産として受け取るがいいよ。あのコンパイルキューブは特別製だ。あれはエネルギーが特別でね。エネルギー源は何か、って? 簡単だよ、あの飛行機事故を思い出せばいい。飛行機事故では何が起きた? 君たち兄妹以外の人間がほんとうに死んだと思っているのか?」
ざわ、と鳥肌が立った。
同時に自分の考えたことがとんでもないことだと思って――悲しくなった。
「そう、その通りだよ。君が考えたこと、それがそのままだ。コンパイルキューブは人間の精神力を魔力に変換する。ならば、それをすればいい! だが、残念ながらその実験は人間の考えでは『異端』と言われる。当然だろう、人間の命を使うのと同じ実験になるのだからな。しかし、それでも私は諦めなかった! 諦めたくなかった! だから、僕はある事故に乗じて人間を奪うことにした。……そこまで言えば、それがどういうことか理解出来てくるだろう?」
「まさか……」
増山敬一郎はシニカルに微笑む。
「そうだ。あの飛行機事故は偶然ではない。我々ホワイトエビルの計画に……『コンパイルキューブ』の糧になってもらうために、わざと引き起こした事故なのだよ」
_ ◇◇◇
_ その頃、香月と春歌は廊下を走っていた。
「恐ろしいくらいに誰も居ないな……。罠だと思ってしまうほどだ」
香月は廊下を走りながら、部屋の様子を眺める。しかし人の気配が一切見られないため、何も言いようが無かった。
春歌はそれを後ろから追うだけだった。
「ここは……」
扉が開いていた。
そこからゴウンゴウンと音が聞こえてきた。
「何の音だ……?」
香月は慎重に、警戒をしながら中へと入って行った。
_ 10
_ 中に入ると、そこにあったのは巨大な黒い筐だった。
それについて春歌はまったく解らなかった――対して香月はすぐに理解出来た。
「まさかこれ……コンパイルキューブか?」
「え、コンパイルキューブ……って、こんな巨大なものが出来るのですか? だって今まで見てきたのは手のひら大の大きさ程のしか見たことが……」
「まあ、そう思うのも仕方ない」
コツ、と足音が聞こえた。
そこに立っていたのはスーツを着た男――そして彼は気を失った夢実を引きずっていた。
「やはり、コイツは裏切ったか。まあ、致し方ないことだ」
夢実をその場に投げ捨てる。
「これはコンパイルキューブだよ。もっと言うならば、このコンパイルキューブは巨大で、たった一人の精神力だけでは魔力に変換しても微力なものしか生み出さない。だから大量の人間の精神力を必要とするけれどね。それによって魔力は生まれ、魔術として行使される」
「魔術として……。だが、その精神力はどうするんだ。実際問題、人間一人ひとりの精神力なんて高が知れている」
「一人ひとりの精神力は少ない。それは当然のことだ。だが、考えてみてほしい。一人ひとりがダメならば、それが十人、二十人……百人となればどうなる? 単純計算で百倍になるだろう?」
「百人? いったいどうやって集めると――」
そこで――彼は理解した。
同時に、笑みを浮かべる増山敬一郎。
「――まさか!」
「そう、その通りだよ。――飛行機事故では、誰も死んじゃいない。死んだと見せかけただけに過ぎない。あの時の飛行機事故……乗客は二百人近くだったか? あの時の乗客は全員、コンパイルキューブに流し込むために精神力のタンクとさせてもらったよ。もちろん、君たち兄妹は出来なかったがね」
「貴様――っ!」
香月は我慢できなかった。
香月は拳をふるって、増山敬一郎の元へ走る――!
――だが。
「甘いな、甘い。それが若き最強の魔術師、柊木香月の実力か。だとすれば、最弱だよ。最低だとも言っていい。父上と母上が悲しむぞ?」
彼の腕は、増山敬一郎に抑え込められていた。
それも右手だけ、しかも人差し指だけだ。
「馬鹿……な?」
「考えてみろ、目の前にある巨大な黒き筐を。その筐は何だ? コンパイルキューブだろう? コンパイルキューブは自動的に僕に魔力を注ぎ込むようになっている。だから、倒すことなど出来やしないのだよ」
香月は一旦離れる。
増山敬一郎は両手を掲げる。同時にコンパイルキューブが鈍い音を立てて唸りを上げる。
「コンパイルキューブを使うことが出来る、僕こそが最強! 対して貴様はコンパイルキューブを奪われて、何もすることの出来ない最弱! お前と僕の差は、決定的なんだよ!」
「……」
香月は何も言えなかった。
「本当ならば君を我々ホワイトエビルに引き入れたかったが……致し方ない。そう思うのであれば、さっさと死ね」
短い詠唱だった。
増山敬一郎の頭上に現れたのは氷塊。
香月の身体の何倍もの大きさの、大きな氷塊が不気味に浮いていた。
「――軟弱者には、死を」
そして、香月の頭上に氷塊が落下する――。
_ 「そこまでだよ、増山敬一郎」
_ 香月の頭上にシールドが展開された。
緑色の薄膜だったが、それでも氷塊の方が力負けして粉々になる程の強度があるらしい。
「え……?」
香月と春歌は完全に死を意識していた。そして、それを待ち構えていた。
だが、死ぬことは無かった。
香月の目の前には、銀髪の白衣を着た女性が立っていた。
振り返り、微笑む。
「どうした、柊木香月らしくない。それとも君はこのような場所でやられるような魔術師だったのかね?」
「はっはあ! 柊木香月をおびき寄せたら、こんな大物が引っかかるとはね! ユウ・ルーチンハーグ! ヘテロダインのボスであり神出鬼没の『天才』が、こんな罠に引っかかるとは思いもしなかったよ!」
「……五月蠅い。それよりも、これはどういうことかしら? 増山敬一郎。あなた、人間がやっていいことと悪いことの分別もつかなくなったのかしら? 魔術師は、そんな頭の悪い人間では無かったと思ったけれど」
香月の目の前に立っていたのはユウ・ルーチンハーグだった。
「ホワイトエビルの『行動』は君の監視下にあったのではないかい? 僕はそうだと聞いているけれど。実際問題、そんなことをしているのは想像の範囲内だったよ。ユウ・ルーチンハーグは『組織』では優秀だったからね。それくらいの芸当が出来ても、何ら不思議では無い」
「……私のことを高く買っているようだけれど。手加減はしないよ?」
「寧ろして欲しくないね。そういうおべっかを嫌うのがほかでもないユウ・ルーチンハーグだ。君の特徴でもあり欠点とも言えるだろうねえ」
増山敬一郎は両手を広げ、首を振った。
「さあ、行きなさい。柊木夢実、そして香月クン。もちろん、春歌ちゃんも」
突然名前を呼ばれた三人は、理解出来ずユウの背中を見る。
ユウは魔術結界を行使したまま、振り返る。
「あなたたち、もう見て解っているでしょうけれど、コンパイルキューブは人間の精神力を使っている。それは即ち、精神力を吸い取られているだけの人間が格納されている空間があるということ。だから急いで探してきて! あのコンパイルキューブを止めないと、私も正直に時間ともたないでしょうね」
「了解」
短く答えて香月は立ち上がる。
春歌も頷き、最終的に夢実とともに背後の廊下に向かうため踵を返す。
「僕が素直に彼らを見逃すとでも?」
「ああ、一応言っておくけれどこちら(ヘテロダイン)も本気でね? 出来る限りの魔術師勢力をこちらに連れてきた。その意味が解るね?」
「ヘテロダインとホワイトエビル……全面抗争をするか。それもいいだろう。だが、最後に笑っているのはどっちだろうね?」
ユウは微笑む。
「――それは神のみぞ知る、ってやつだ」
そして彼女は魔術結界を逆流――増山敬一郎に反撃を開始した。
_ 11
_ 香月と春歌、夢実は廊下を走っていた。
横一直線に並んでいるのではなく、香月を先頭にして走っている――ということになる。香月、春歌、夢実の順だ。実際コンパイルキューブを持っているのは夢実だけなので、夢実を先頭に走らせるべきだという意見が彼女自身から出たが、後ろを見張りながら走った方がいいという香月の意見を尊重してこういう順番になった次第である。
「夢実、後ろは大丈夫か?」
「はい、お兄ちゃん」
背後を確認しながら答える夢実。
「……夢実さんはずっとスパイをしていたのですか?」
訊ねたのは春歌だ。それを聞いた夢実は首を横に振る。
「そんなことはありませんよ。だってスパイって第三者に得た情報を横流しするような……そういう感じでしょう? けれど私はスパイではない。裏切った、と言えばいいかもしれない。孤軍奮闘で活動してきた。けれど、それを実際にしたのはつい最近……。お兄ちゃんを魔術師で活動していることを知ってから。お兄ちゃんが魔術師になっているのならば、ホワイトエビルを倒す可能性が僅かでも高まると思った。だから、」
「僕を待った……ということか。ヘテロダインに逃げ込むことだって、考えられなかったのか?」
「ホワイトエビルは規律に厳しくてね。そういかなかったの。実際問題、ホワイトエビルのアジトはけっこう監視カメラが多い。きっと逃げる人が多いと増山も判断していたのでしょうね。だから逃げるのを監視するためにカメラを多く配置した――。だから不満を抱いていても、逆らうことも逃げることもしなかったのよ。魔術師最大勢力ホワイトエビルを強固なものにするために、帝国のような何かを作ろうとしたのではないかしら」
「帝国、ねえ……。自分が帝王にでもなれると思えていたのかねえ?」
「或いはなるべくして今まで活動していたのかも。そして、ホワイトエビルはその道中にある『過程』に過ぎないのかもしれない。あ、着いたよ」
そこにあったのは扉だった。
そして、その目の前には一人の少女が立っていた。
薄いブルーのショートカットをした少女は妖艶な笑みを浮かべていた。
「ようこそ、柊木香月。そして、裏切り者もこんにちは。まさかあなたが裏切るとは思いもしなかったわ……。まあ、きっとボスは想定していたのでしょうけれど。何せ、あの柊木夫婦の子供なのだから」
「エレーヌ……!」
「上司の名前は、『さん』付けで呼ぶと習わなかったのかしら?」
白いコンパイルキューブに口づけして、詠唱する。
刹那、彼女の身体が浮かび上がる。
「飛行……魔術!」
「柊木香月。ほんとうは魔術を使って魔術戦をしたかったけれど、コンパイルキューブを奪われているのならば仕方ない。それもボスの戦略だからね。まあ、別に問題も無いでしょう? コンパイルキューブを奪われても戦うのが、魔術師としても優秀なのだから」
「果たしてどうかなあ? さすがに魔術師としても、これはつらいと思うぜ。コンパイルキューブを奪ってもいいのか?」
「奪えるものならね」
そして、それぞれが走り出す。
「お兄ちゃん!」
夢実はコンパイルキューブに詠唱を行い、結界を張る。ただし先ほどのように魔術のみを弾くのではない。物理的なものですら弾く物理結界を築いた。
「まさか――!」
「私を部下だと思って甘く見ていたようですね、エレーヌ? 私はこんな上位魔術だって使えますよ、普段使っていないだけでね」
「貴様……」
物理結界が立方体に作られていく。それはまるで彼女を包み込むように。
彼女の敗因を言うならば、飛行魔術を使ったことだろう。飛行魔術を使い、地から離れた――それによって、物理結界での囲い込みが成功した。
これはある種の賭けでもあった。成功するとは思わなかった。寧ろ失敗すると考えていた。だからこそ、これは夢実にとって理想的な結末だった。
「く……!」
「無駄です。その物理結界は私が意識下に置く限り存在し続けます。ですから、諦めたほうがいいと思いますよ」
物理結界の中が、白い煙で満たされていく。
「ああ、忘れていました。暴れてもらうのも困るので、催涙作用のある薬を蒔きました。それでゆっくり眠られると思いますよ。最近寝不足なのではないですか? 目の下に隈が出来ていますよ?」
「く……そ……!」
そして――エレーヌの意識が遠のいていった。
香月は夢実の頭を撫でる。
夢実は笑顔になり、頬を赤くする。
「ありがとうございます♪ 嬉しいです。お兄ちゃんの役に早くたちたかったから!」
「そうか。……よし、あとはここに入ればいいんだな」
香月は頷き、ドアノブに手をかける。
そして、彼らは中へ入っていった。
_ ◇◇◇
_ 中には大きな試験管があった。それも一本だけではない。十本、二十本……百本近くあるのではないだろうか、どちらにせよ数えきれない量の試験管が置かれていた。
「これは……」
「おや……。君たちがここに居るということは、外に居たエレーヌをやっつけたということか。流石は魔術師柊木香月とその妹だね」
試験管を見つめるように立っていたのは白衣の男だった。
白衣の男は香月の声を聞いて振り返る。
「僕は何をしていないけれどね。実際問題、エレーヌとやらをやっつけたのは僕の妹だよ」
「ほう。エレーヌを倒したのは妹の方だったか。普段は魔術をあまり使わないから実力が無いと考えられていたが、実際はその真逆。魔術を使わないのではなくて、使わないことによって実力を隠していたか。流石だ」
白衣の男はゆっくりとこちらに振り向くと、一歩前へ踏み出す。
「僕の名前はハイド・クロワース。覚えておいてくれたまえよ、僕は君と出会うのを待っていた。君ほどの若くて優秀な魔術師に一度会ってみたくてね」
「ハイド……ねえ。ジキルとハイドって話を聞いたことがあるが、博士ならジキルの方じゃないのか?」
「それをあえて外しているわけだよ。ジキルではなくハイド。ハイドの方だよ。ジキルなんて知らないね。僕はハイドだ! ハイド・クロワースにほかならない!」
「別に否定はしていない。だが、ここはいったい……」
「ここかい? ああ、君たちは知ってか知らずかここにやってきたということだね! ここは『精神の部屋』だ。何故ここがそう呼ばれているかは知らないだろうねえ。知っているのかもしれないけれどねえ」
「知っている。コンパイルキューブに精神力を供給し続けているのだろう?」
「ほう! 知っていたか。……でも、これは未だ第一歩に過ぎない。考えてみろ、未だこれは足りないと思わないか?」
「足りない、だと?」
「そうだよ。こんなものじゃ未だ終わらない。終わらせてたまるか。未だ何も始まっていないし、終わってもいない。これは計画の前段階に過ぎないのだから。『失敗は終わりを意味し、負けは死を意味する』のだよ」
「は?」
眼鏡の位置を直し、ハイドは続ける。
「いや、どこかの世界に住んでいる、孤高の科学者の戯言だよ。戯言と言うにも烏滸がましいことだけれどね。実際には僕は負けることを知らない。負けたくないからね」
「それじゃ、今は退くか? 素直に負けを認めない、ということならば、いったいどうするつもりだ?」
「君と今戦っても、何の利益が得られない。だから、ここは退くよ。どうせ僕はここの管轄では無い。所属でも無いし。所詮僕は莫大な金と交換条件にこれを引き受けただけに過ぎないのだから」
「だから、逃げる――と?」
「ああ。充分な実験結果を得られた。これ以上争う必要も無い。いずれは、争うことになるかもしれないが、それは今では無い」
そして、男は香月にあるものを手渡した。
一つは香月の使っていたコンパイルキューブ。
そしてもう一つはコンパイルキューブより一回り小さいスイッチのようなものだった。
「君のコンパイルキューブだ。あとはスイッチを押せば拘束は解かれ、今ここで眠っている人間も起きることだろう。中身は冷凍保存と同じ状態だから全員生きている。仮死状態、とでも言えばいいだろうか」
香月たちを通り過ぎ、扉の前で立ち止まるハイド。
「待てよ。……お前はいったい、何を目的にこれを行った? それだけを聞かせてほしい」
「目的、ね……」
ハイドは溜息を吐く。
「強いて言うなら、世界の観察……かな?」
「何だと?」
「そうだ、世界の観察だよ。世界の強度ともいえばいいかな……。世界の強度がどうなっているのか、世界がいったいどうなっていくのか、世界をどうすればいいのか、それについて考えているということだ。学んでいる、と言ってもいい。研究者は一生学徒だからね。学ぶことは非常に多い。なにせ、この世界だぞ? 世界は何十億人と人間が住んでおり、それ以外の生き物も莫大な数が住んでいる。その世界を、研究するということは――とても面白い。人間の一生は……確か八十年だったか? それくらいあっても足りないだろうね。その数十倍は無いと無理かもしれない。それでも、研究をしている間にさらに新しい知識は出てくる。堂々巡りになってしまうことは、確定だけれどね」
香月は何も言わなかった。
それを見てハイドは一笑に付し――部屋を後にした。
残された香月たちは、香月以外の人間がその視線を香月に集中させた。
香月はコンパイルキューブが自分のものであるかを確認。そして残されたスイッチを確認していた。
「……これを押せば、あの巨大なコンパイルキューブは停止するのか?」
「あのハイドは、そう言っていましたね」
答えたのは春歌だった。
そして香月は一瞬考えたが――スイッチを押した。
躊躇うこともなく。
ハイドという科学者の言うことを、信じて。
_ ◇◇◇
_ その頃、ユウと増山敬一郎の戦い。
ユウは佳境に立たされていた。精神力を使い過ぎたのだ。
「このままでは……精神がもたない……」
ユウは一つの組織のトップとなっている。だから、精神力も普通の魔術師よりは多い。それこそ鍛えているからだ。
だが、そのユウが追いつめられているのだ。当然だ。相手は百人分の精神力を行使できるコンパイルキューブ、それに一人で立ち向かうことが間違っている。
それはユウも解っていた。ただ時間稼ぎになればいいと――そう思っていたのだ。
(香月は……間に合っただろうか……)
瓦礫に腰を預けて、彼女は思った。
香月がコンパイルキューブのシステムを破壊しない限り、増山敬一郎はその力を発揮し続ける。だから早急にシステムを破壊せねばならない。
「柊木香月は優秀な魔術師だよ。だが、少年だからか、まだ甘いところがある。致し方ないことかもしれない。少年は成長するうえで大人になり、そして精神も成長する。あの時点で優秀な魔術師となるほどの精神力を保持していることは、はっきり言って『異常』だ。両親があのすばらしい魔術師夫婦だったからかもしれないが」
「……ほんとうに、よく喋る男だ」
「君は嬲り殺しておきたかったからね。前から気に入らなかったのだよ」
増山敬一郎は一歩、また一歩近づいて、ユウの前に立った。ユウを見下ろす形となって、増山敬一郎は立っていた。
そして、増山敬一郎はユウの頬を叩いた。彼女の頬が赤くなる。
彼女は何も言わなかった。
増山敬一郎はニヒルな笑みを浮かべる。
「どおした? え? 何もできないか、ユウ・ルーチンハーグ! そうだよなあ、幾ら『組織』で天才と呼ばれていたお前であっても、この状況を脱することは難しいだろう! あの魔術師が行こうたってそう簡単にコンパイルキューブのパワーをオフにすることは出来ない!」
「そうだろうか? 君は若い世代を少々甘く見過ぎていると思うよ。若い世代は君が思っている以上に、私たちが若い時よりも強くなっている。それは魔術師としてコンパイルキューブに触れる時間が長くなっているからだ」
「いいや、そんなことは有り得ない。若い人間は軟弱者ばかりだ。どうした? 『弱い』魔術師ばかりと慣れ親しんだせいで思考が鈍ったか?」
それを聞いたユウは高笑いをする。
「思考が鈍った――か。君らしい考えだ。だが、あいにくそのようなことは無い。思考はずっと正常だよ。寧ろ鈍ったのは君の方だ、増山敬一郎。若い力に負けたくないがゆえに、このようなちんけな装置を開発したのだろう? 戦うなら、自分一人の力で戦ってみたらどうだ」
再度増山敬一郎はユウの頬を叩く。
「五月蠅い。五月蠅い、五月蠅い!」
叩く。叩く。叩く。彼女の頬が赤くなり、青くなっていく。
「……君は何もできないんだよ、解っているのか! 魔術師は一人の精神力にそのパワーランキングが比例する形になる。即ち君は精神力が多い、精神力が高いことになる。だが、一人では限界がある。だから! 精神力を複数の人間から集めたということだ。使われる人間も喜んでいるよ、自分たちに役割を見出すことが出来たのだからね!」
「……何を言っているの?」
ユウは立ち上がる。
彼女の精神力は自らの精神を保つ程――そのギリギリのラインしかなかった。
寧ろ、彼女はもう気合で立っていると言ってもいいだろう。
「あなたは間違っている。あなたは考えていない! 自分の事しか考えられていないのよ。役割をもっていない人間が、その役割を見出すことが出来る? 何を言っているの。この世界に役割をもっていない人間なんて誰一人としていないわ。そして! あなたがそういう役割を持つ権利なんて無い!」
「ほざいていろ。どちらにせよ――貴様には何もできない」
コンパイルキューブに口を寄せる。
彼女はもう限界だった。精神力が底を尽き、せいぜいあと一発撃てるか撃てないか程度の魔力しか残っちゃいなかった。
――その時だった。
巨大な黒き筐――増山敬一郎のコンパイルキューブから常時発せられていた振動が停止した。
「!? どういうことだ!」
増山敬一郎は振り返る。コンパイルキューブは停止して、何も言わない。
「まさか……いや、そんなことは有り得ない! コンパイルキューブが停止しただと!? ハイドはどうした、エレーヌはどうした? あいつらが簡単にやられるはずが……!」
「だから言ったでしょう――」
「ej・ei・fr・et・ff」
「――若い力は、すぐそこまで来ている!」
轟! と凄まじい炎が増山敬一郎目掛けて発射される。
増山敬一郎はその勢いを抑え込められずに――そのまま炎に巻き込まれた。
「ぐあああああああああ!?」
「どうやら、間に合ったようですね」
ユウの隣に立ったのは夢実だった。
「ええ。そうねえ。それにしても、案外ストレートな魔術を使ったものね、香月クンも。それとも余程怒りが溜まっていたのだろうねえ」
ユウは冷静に判断する。
未だに増山敬一郎の悲鳴は聞こえてくるが、炎の勢いが増していくにつれてその声も次第に静かになっていく。
「……いずれにせよ、これでホワイトエビルも終わりだ。何と言うか、あっけない結末だった。ほんとうにこいつは最強の魔術師だったのか?」
「彼は最強だよ。……ただし、それは『どんな手を使ってでも』という条件付きになるがね。どんな姑息な手を使っても、彼は戦いを制する。それが増山敬一郎という人間だった。だから、彼はこのような手を使って、魔術師の戦いを制そうと考えたのだろうね。だが――それがご覧のありさまだ。増山敬一郎、最後の最後まで自分を貫いた魔術師だったというわけだ」
ユウはゆっくりと立ち上がり、踵を返す。
そこにはたくさんの人間が立っていた。
木崎湾飛行機事故の死亡者『と言われていた』人間二百十六名。
そしてその先頭には――。
「お父……さん? あと、お母さんも……」
香月と夢実の両親、柊木夢月と柊木香が立っていた。
十年前のあの姿と――まったく変わらない形で、彼らは立っていた。
香月と夢実は泣きそうになって、そのまま駆け出した。
親子は晴れて――十年ぶりの再会を果たしたのだった。
中学校の屋上。
柊木香月と城山春歌は空の下、弁当を食べていた。
数日前終結したヘテロダインとホワイトエビルの全面抗争。結果としてヘテロダインが勝利し、その後魔術師組織のパワーバランスは大きく変化した。
ホワイトエビルに居た若い魔術師はそのままヘテロダインが引き取ることとなり、同時にヘテロダインが魔術師組織の最大勢力となった。
「ま、代表である増山敬一郎がああいう形で死んでしまったのだから、それに関しては致し方ないだろうね。実際問題、ホワイトエビルの支配は増山敬一郎による恐怖政治と同等だったらしいから」
「へえ。ユウさんも優しいのね」
「何言っているんだい。ボスはもともと優しいよ。慈愛の心を持っていると言ってもいいかな。確かに不安に思うのかもしれないけれどね」
「いや、別に不安に思ったわけでは……」
さて。
先ほど香月と春歌しかいないような描写をしたが――実はそうではない。
未だもう一人いる。
時代遅れのセーラー服に身を包み、自分の作った弁当を二人のやり取りを見ながら見つめている。
それは柊木夢実――香月の妹だった。
「それにしても夢実が同じ中学に入ることになるとは思いもしなかったよ」
「同じ中学に入れたほうが管理もしやすい、って言っていたよ。ただ、私は十年前から義務教育を受けていないから、どうやってそういうところを誤魔化したのか解らないけれどね」
「成る程ね。それは確かにそうだ」
香月はそう言ってサンドイッチの最後の一口を口の中に放り込んだ。
「兄(あに)さん。ちょっとお時間いいですか」
彼の背後に黒スーツの男が立っていた。
「どうしたんです、井坂さん」
井坂と呼ばれた男はホワイトエビルから引き抜かれ、今は情報屋としてヘテロダインに所属している。魔術はそれなりに使えるが、少し抜けたところがあるため、ユウはそこに配属を命じた。
井坂は恐縮した様子で、
「いえいえ、兄さんの用事があるのなら、そちらを優先してもらって構いませんよ」
「用事? どうせ井坂さんが来たってことは仕事のことだろ。別に構わないからここで言ってくれよ」
「……解りました」
井坂は香月を屋上の少し離れた場所へ連れていく。一応、同じ組織に所属しているとはいえ、秘密は守らねばならない。
香月が離れた隙を狙って、夢実が春歌の隣に座る。
「……ねえ、春歌さん。あなた、お兄ちゃんのことが好きなんでしょう?」
突然の言葉に飲んでいたお茶を吹き出してしまった春歌。
「な、何を……」
「見ていて解るよ。だって、ずっとお兄ちゃんのこと見ていたんだもの」
「そ、そう……」
わざとらしく香月から目をそらした春歌。
「――負けないよ」
「え?」
「お兄ちゃんの妹は私だけだから。お兄ちゃんを好きだと思う気持ちは一番だよ。絶対負けない。だから、二人で頑張りましょう?」
右手を差し出す夢実。
春歌はそれを見て――彼女も右手を差し出した。
白衣を着た科学者――ハイドは街を歩いていた。
人々はすれ違うが、それでもハイドの姿を視認していない。当然ながら、彼の住んでいる世界と人間が住んでいる世界は次元的に別物であるということが理解できる。
「コンパイルキューブを用いた多元精神力供給実験は、成功した。だが、キャパシティの問題と根底にあった人間の確保が難しい。それが課題となるだろう」
歌うようにハイドは言った。
今回の結末を。
まるで遊戯の如く、言った。
ハイドは思い出したように笑みを浮かべる。
「それにしても、あの魔術師――名前は柊木香月だったか。彼は面白い人間だったなあ。魔術師としても優秀な人材だったし、研究し甲斐のある存在だ」
白衣のポケットからメモ帳を取り出し、すらすらと何かを書いた。
「柊木香月。君のことは忘れないよ。また……いや、確実に会えるだろうね。その時を待っているがいい。今は平和な日常を味わっているといい。暫くしたら、僕はまた君に姿を見せる。その時君がどういう対処をするか……楽しみで仕方がない」
ハイドは姿を消えた。
彼の行く先は――誰にも解らない。
_ ◇◇◇
_ ヘテロダイン・会議室。
柊木夢月、香、ユウ・ルーチンハーグが話をしていた。
「……それにしても、ハイド・クロワース、か……。まさかその名前をここでまた聞くことになろうとはね」
ユウはワインを嗜みながら夢月に言った。
夢月は神妙な面持ちで答える。
「私も理解できなかったよ。まさかこんなことになろうとはね……。実際問題、私が捕まった時もコンパイルキューブは『封印されていた』。まるで何か別の力を使われたかのように」
「コンパイルキューブのブラックボックス……あまりにも深い闇、ということだ。まったくもって、理不尽と言える。人間が使うべきものではないのかもしれないな。まさにオーバーテクノロジーと言えるだろう」
「そうであっても、それを理解したとしても、魔術師はもはやコンパイルキューブなしでは魔術を行使できません。コンパイルキューブが無くなってしまえば、魔術師は魔術師では無くなるのです」
「解っている。だが……」
「ユウ。ひとまず、この案件私たちに預けてくれないか?」
夢月の提案に首を傾げるユウ。
「組織でこの案件を動かすには、少々フットワークが悪い。それにホワイトエビルとヘテロダインの再編でお前もいろんな問題を抱えていることだろう。だから、一先ずは私たちだけでやらせてはくれないか? もちろん逐次連絡はするつもりだ。もうこれ以上君に迷惑をかけたくない」
「そうか……。解った、ならば君たちに任せる。しかし、何かあったらすぐ連絡してくれ。報連相だ。よろしく頼むぞ」
了解、と短く答えて夢月と香は頷いた。
今回の物語は幕を閉じ、一先ずの平和を迎えた。
しかし、次の物語は――すぐそこに迫ってきている。
_ 終わり。
ÿþ< <br>