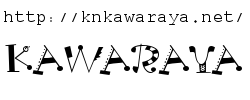
小説を連載しています。 / ブログ
とある町に、昔話を紙芝居にして話を聞かせるおじいさんがいた。
おじいさんが現れるタイミングはいつも夕方。おじいさんは何かの仕事をしているようで、それが終わったタイミングで町の広場に現れるのだ。おじいさんが準備を始めると、どこから情報を聞きつけたのか、子供たちが集まってくる。
そして子供たちは、いつものように言うのだ。
「今日は勇者の話をするの?」
勇者の話。それは少し前、この世界で起きた『災厄』を振り払った勇者のことだった。
世界が平和になった今、勇者の物語は伝説となり、そして昔話となっている。
しかし、それも誰かが語り継がなければいつか薄れていってしまう。
それを薄れさせるわけにはいかなかった。
それを人々の記憶から消してはならなかった。
おじいさんもまた、勇者とともに戦った一員として、あの出来事を後世に語り継がなければならないと――そう思っていたからだ。
おじいさんは口を開いて、話を始めました。
「それじゃ、話を始めようか。それは、ラドーム学院というある学園から物語は始まります――」
こうして語られるのは勇者の物語。
これは運命を翻弄させられる、一人の少年の物語。
秋葉原の街並みがサブカルチャーに染まったのは、いったい何年前のことになるのだろう。
いや、正確に言えばきっと何年で表現できるような昔ではないかもしれない。
そんなことを思いながら、僕は秋葉原の街並みを見ながら、歩いていた。壁にはポスターが貼られている。最近はやっているアニメやゲームのポスターだ。少しも興味がないといえば嘘になるけれど、でも実際その作品は殆ど知らない。せいぜいキャラクターを見たことがあるかな、というくらいだ。
かくいう僕は何を求めているのかといえば、ゲームだ。
ロールプレイングゲーム。またの名前をRPGという。役割をもってプレイするゲームシステムのこと。各自に割り当てられた架空のキャラクターを演じて、時に協力し時に対立し物語を進めていく。それが、ロールプレイングゲームの醍醐味といったところだと思う。
さて。
僕が求めているゲームは世界で大人気のロールプレイングゲーム、その最新作だ。
そのゲームは独創的な世界観とバトルシステムで一躍人気になった、その続編である。もちろん前作もすでにプレイ済みであり、クリアも当然している。だからこそ、今回の第二弾に対する期待度はとてつもなく高い。
しかしながら、その人気ゆえに予約しないと発売当日に手に入れることもできない。
残念なことに予約ができていないので当日に購入することはあきらめかけていたのだが――、秋葉原駅に着いてあるチラシをもらって、それは前言撤回することとなった。
なんと、そのチラシによれば発売当日でありながら予約しなくても購入することが可能だという。そんな馬鹿げたことがあり得るのか、と何度も訊ねたが、可能だと言った。ならば信じるしかない。
……そういうわけで現在その変わった店員についているわけだが、道がどんどん暗い所になっていく。正確に言えばガード下。はっきり言って、こんなところにゲームショップなんてあったのか? なんて思ってしまうくらいだったが――すぐにその不安を拭い去ることとなった。
「ここだよ」
店員はそう言うと、中へ入るよう促した。
まあ、別にいいけれど、どうして客を先に入れるのだろう? そんなことを思いながら、僕は中へと足を踏み入れた。
店の中は所狭しに棚が置かれていて、その中にはゲームがたくさん陳列されていた。中には僕が生まれる前のゲームもたくさん陳列されていて、マニアなら垂涎もののゲームもたくさん置かれている。だのに客は一人もいなかった。
これは穴場スポットだぞ……そんなことを思いながら、棚を一つ一つ見ていく。ここまで来たならただ単にゲームを買うだけじゃなくて販売されている商品も見ていくことにしよう。ゲームを買う機会はそう何度もあるわけではないし、次に来るとしたら週末くらいしかない。学生にとって、週末は貴重な休日だから案外それすらもできないことかもしれないけれど。
「……すごいですね、このゲームの数。どうしてここって、あんまり人が来ないんですか?」
単刀直入に、気が付けば僕は質問していた。ちなみに店員さんは僕の背後に立っている状態になっている。ゲームを店ですぐに用意すると言ってくれたから、きっとその準備をしているのだろう――僕はそう思っていた。
頭に、衝撃が走った。
文字通り、衝撃が走った。
それは痛みなのか立ち眩みなのかショックなのか――よく解らなかったけれど、倒れゆく最中、店員さんが金属バットのようなものを持っているのを見て、僕はそれが最初に言った『痛み』であるのだと理解した。
バットには血がこびり付いている。きっとそれは僕を殴ったときに付着したものだ。だとすれば、今、僕の頭からは血が出ているはずだ。ああ、だから暖かいのかもしれない。納得。
いや、正確に言えば納得してはいけない。まずはこの場をどうにかしないと。携帯、スマートフォン……は無理だな。今はまともに動くことすらできない。意識が薄れつつあるのに、それを使うことはまず不可能だろう。第一、目の前にいる店員さんがそれを許してくれるだろうか? いや、まずありえないだろう。
そう考えているうちに意識が薄れていく。ああ、もう、駄目だ。なんだかんだでむなしい人生だったなあ。何も考えるでもなく、ただ普通の学生として生きてきて、きっとこの後就職もして結婚もするだろう。子供もできて、平和な家庭を築いたはずだ。……まあ、まず彼女が居ないからそんなことは出来ないのだろうけれど。
そして、次の瞬間、僕の意識は途絶えた。
_ ◇◇◇
身体を誰かが揺すってくる。
声はどこか可愛らしい感じで、少し凛としていた。誰だったかな、この声――と脳内のデータベースに聞いてみるが、そんなデータはヒットしなかった。というよりも、僕のことをフルと呼ぶ人など聞いたことがない。
「ねえ、フルってば」
さらに僕の身体を揺すってくる彼女。
うん、先ずは起きたほうがいい。これ以上揺すられると吐きそう。
そう思って、僕は目を開けた。
「あ、やっと起きた! もう、フルったら、もう遅刻する時間よ? 夜更かしでもしていたのかしら。まあ、別に遅刻しても私の知ったことではないのだけれど」
そこに立っていて頬を膨らませていたのは、美少女だった。
ブロンドのロングヘアーに赤い目、幼げな表情、なんとなく膨らみを感じる制服に見える服(こげ茶色のブレザーにスカート、黒いタイツに革靴といった感じだ)を身に着けていた。
ぼうっとしていた僕だったが、それが気に入らなかったらしい彼女は踵を返す。
「取り敢えず、急いで制服に着替えて教室に向かうこと! いいわね、私は部屋の前で待っているから!」
そう言って彼女は部屋を出て行った。
なんというか、朝から騒々しいけれど……僕にあのような知り合いって居たかな?
まあ、取り敢えず彼女の言葉を守ることにしよう。そう思って僕は身体を起こして立ち上がると、部屋を見渡した。
部屋は僕の知る自分の部屋ではなかった。床には赤いカーペットが敷かれているし、木目調の壁はどこか懐かしくもあるし高級な雰囲気も醸し出していた。
まるでホテルのような感じだけれど、窓が無いので何も言えない。これ以上はとにかく外に出て確認してみないと、解るはずもなかった。
それにしても、どうしてこのような場所に居るのだろうか? 僕はハンガーにかかっていた制服に着替えながらそんなことを考えていた。確か僕はゲームショップの店員に頭を殴られてそのまま気を失ったはずだった。
ということは、あの後、誰かが僕のことを助けてくれたというのか?
なんというか、解らないけれど。
「ねえ、フル。急いでくれない? でないと、私も遅刻するのだけれど!」
だったら君一人で行けばいいじゃないか――なんてことも言えずに、取り敢えず僕の置かれている状況は後回しすることにして、彼女の指示に従うべく、大急ぎで制服を着替えることとした。
着替えが終わり、部屋の外に出るとそこは廊下だった。まあ、窓が無い時点でなんとなく予想は出来ていたけれど、そう考えるとここがどういう構造になっているのか気になってくる。
彼女は扉の前で待っていた。何冊かのノートとペン、それにインクを持っていた。
「それは?」
「それは、って……。勉強の道具じゃない。もしかして忘れたの?」
「あ、いや、無いことはないけれど……」
机の上に置かれていた――なぜか整理整頓されていた――ノートとペン、それにインクを持ってきておいて正解だった。僕はそう思って、彼女の言葉に答える。
「なんだ、持ってきているんじゃない。心配して損したよ」
そう言って彼女は溜息を吐いた。正直言おう、そこまで言われることの問題だったのか? ノートが無くても、そこまで文句を言われる話ではないと思うのだが。
「さ、行こう。遅刻しちゃうから。遅刻したらまた先生に叱られちゃうよ?」
先生とか遅刻とか、現在の状況を呑み込めていない前に新しい状況を持ち込まないで欲しかったが、きっとそんなことを彼女に言っても無駄なのだろう――そう思うと、これからの新しい出来事だらけの未来を想像して、頭が痛くなった。
_ ◇◇◇
_ 一時間目は歴史だと、一緒に歩いていた少女は教えてくれた。
少女――といっても、歩いている道中でさりげなく名前を聞いたところによると、メアリー・ホープキンというらしい。名前から苗字に行くのは外国人のような感じもするが、単純にそうではなさそうだ。
メアリーは僕の隣の席に座り、準備を始める。僕もそれに合わせて準備をする。……ああ、そういえば教科書があるんだったか。この分厚いハードカバーの本。いったい何百ページあるというのだろうか? というか表紙には英語とも日本語ともフランス語とも、それ以外の言語ともとりづらい何かが書かれているのだけれど――これ、読めないよ? いったいどこの国の言語なのかな? まあ、それを聞きたくても、この感じからすると周りもほかの言語を話しているのだろうけれど。
そうこう考えているうちに、ドアを開けて先生がやってきた。
先生はロングヘアーの女性だった。黒い髪で、黒い目。白磁のような肌に、凛とした表情。その女性を一言でいえば、『美人』があてはまるだろう、そんな女性だった。
「では、授業を始めます」
教壇に立ち、女性は言った。
「起立」
その言葉を聞いて、生徒は立ち上がる。もちろん、僕には何を言っているのか解らない。だからほかの生徒の仕草を確認しながら行動しないといけない。面倒なことだが、致し方ないことだ。どうして僕がこういう世界に飛ばされてしまったのか解らないが、これは紛れもない異世界だ。だったら、何とか異世界で生きていくしかない。
でも、どうやって?
「礼」
頭を下げる仕草に合わせて、頭を下げる。
タイミングをうまく合わせて、頭を上げる。
「着席」
そして椅子に腰かける。
ここまで人のタイミングを窺って着席したことがあっただろうか。きっと無いと思うし、これからもないと思いたい。なぜなら、一回やるだけで相当疲れてしまうからだ。
「それでは授業を始めます。今日は偉大なる戦いについて、ですね。みなさん予習などはしているかもしれませんが、偉大なる戦いは今から二千年ほど前に起きた災厄のことで、地の底からメタモルフォーズという謎の怪物が出現したことで――」
先生と思われる女性が何かを言いながら黒板に文字を書いているが、残念なことにそれが何であるか理解できない。
はっきり言って、文字も見たことのないやつだった。仕方がないので、文字だけでも書き記しておこうとペンを使ってノートに文字を書き記しておくことにする。
しかしながら、そのペンはただのペンではなく、羽ペンだった。
インクを持ち歩く時点で気づけばよかったのだが、それはもう後の祭り。
面倒ではあるが、羽ペンを使って文章を書いていくことにしよう。
ところで、羽ペンというのはとても書きづらいということを知っているだろうか。もちろん、使ったことのある人間ならばそんなこと百も承知かもしれないが、生憎僕は一度も使ったことがない。だから『なんとなく』でしか使うことができないのだ。
「おい、アイツ見てみろよ?」
「ん。あ、もしかして……」
背後からそんなひそひそ声が聞こえる。誰を対象としているかどうか言葉では言っていないが、明らかに僕をターゲットにしているのは解る。
だが、一体全体なぜそんなことを言われなくてはいけないのだろうか? 間違っている、とまでは言わないけれど、明らかにおかしい。
気になったので、その声のするほうを向こうとした――その時だった。
「フル・ヤタクミ!!」
唐突に自分の名前が呼び出されたので、僕は思わず慌てて立ち上がった。
「この問題を答えなさい」
そう言って先生は黒板を指さす。
しかし、残念ながら文字が読めないので、何が書かれているかも解らない。
どうすればいいか――時間ばかりが過ぎていく、そう思っていた。
思わぬ助け船が出たのは、その時だった。
「ガラムドよ」
隣に座っているメアリーが、僕にそう言ったのだ。
だから、僕はそのまま答えた。
「が、ガラムドです」
それを聞いた先生は一瞬思考を停止させたように見えたが――笑みを浮かべて、頷く。
それを見て僕は静かに席に座った。
「ええ、そうですね。ガラムドは偉大なる戦いで『神』と崇められた存在です。ですが、彼女もまた、もともとは人間であると言う説もあります――」
_ ◇◇◇
_ 授業終わり。
移動教室だろうか、そそくさと移動を開始する人たちを横目に、僕はメアリーに声をかけた。
「さっきはありがとう。……もしかして僕が言葉を話せないことを知っていたのかい?」
「うん? あ、ああ……いや、何故でしょうね。私もあなたと話すときは、この言葉を話すってことにしているのよ。もちろん、この言語は現地の、この世界の言葉では無いのよ?」
「いや、まあ、それは知っているけれど……。でも助かったよ。この世界に、僕の話すことのできる言語を知っている人がいて。居なかったらどうしようかと思った」
「まあ、それもそうかもしれないね。……それについて詳しく話すのは、後にしましょう。今は、大事なことがあるから。私たちも教室を移動しないと」
「次の授業は専門なのかい?」
「そうだね。私たちのクラスは錬金術、だよ。アルケミークラス。教科書は持っているかな?」
教科書。きっとこの分厚い本のことを指すのだろう。
そう思って僕はこくりと頷いた。
「なら問題なし。それじゃ、急いで向かおうか」
そして僕たちは教室へと向かおうとした。
その時、どこかから視線を感じた。その視線は冷たく、監視されているようなものだった。
僕は即座にそちらを向いたが――当然ながら、そこには誰も居なかった。
「フル、どうしたの?」
メアリーが訊ねる。
「いや、何でもないよ」
気のせいだったのかもしれない。僕はそう思って、再びメアリーとともに教室へと向かうことにした。
_ そのころ、どこかの場所にて。
水晶玉を見る、巫女装束のような恰好をした女がいた。
女は不気味な笑みを浮かべながら、つぶやく。
「ついに来たようね……。長かった、ここまで長かったわ。テーラの弟子、リシュミアの予言が、叶うときが。まさかこんなに長くなるとは、私も予想できなかったけれど」
水晶玉から視線を移し、女は目を瞑る。
「お呼びでしょうか」
すぐに一人の男がやってきた。
女は目を瞑ったまま、言った。
「彼に伝えなさい。『予言の勇者』がやってきた、とね。そしてできることなら生きたまま捕獲すること。不可能ならば……殺しても構わない」
「かしこまりました」
それだけを言って、男の気配は消えた。
そして、女もまたその空間から姿を消した。
メアリーの後ろをついていくように、ぼくは歩いていく。それが周りから見てみれば「何をしているんだ?」ってことになるのだけれど、何せ何も知らないし解らないのだ。これくらいばかりは許してもらいたいものだ。
「着いたよ、フル」
メアリーはまたも僕の話すことの出来る言語で語りかける。
そこは教室だった。当然と言えば当然だろう。だって今から錬金術の授業を受けるのだから。
しかし、それはそれとして。
「読めない……」
当然ながら教室の扉についているプレート、それに書かれている文字も読めるわけがなかった。唯一、数字だけは僕の知る言語と同じだったようで、数字の1だけは何とか読めることが出来た。
それをメアリーは察したのか、肩を竦める。
「ああ、そういえばそうだった。これは『ALCHEMY-1』教室、という意味だよ。名前の通り、錬金術クラス、その第一学年ということ。ここは専門の授業でよく使う教室だから覚えておいたほうがいいよ」
「ありがとう」
困惑していたが、やはり自然とその言葉が出てくる。
「どういたしまして。さ、中に入りましょう? もう、すぐに授業は始まってしまうから」
そう言って、彼女は中に入っていく。それを見て、慌てて僕も教室内へと入っていった。
教室に入ると、僕とメアリーは隣に座った。
「次は錬成学の授業ね。フルはさっきの感じからだと文字が読めないようだから、大体のことは言ってくれれば翻訳してあげるわ。授業後も私がばっちりサポートしてあげる。こう見えても、私は頭がいいんだから」
そう言って彼女は慎ましい胸を張った。
「ありがとう、ほんとうにありがとう。ホープキンさん」
やっぱり、それでも。
自然にその言葉が出てくる。たとえそれが異世界であろうとも、何も変わらない。
しかし、メアリーはそれを聞いて首を振った。何か間違ったことを言ってしまっただろうか――そんなことを思ったのだが、
「ダメダメ! そんな他人行儀にしていちゃ! メアリーでいいよ、私たち、もう友達でしょう?」
そう言われて、僕はほっとした。いったい何を言われるのか、解らなかったからだ。
「うん……。ありがとう、メアリー」
その言葉を言うと、メアリーは満面の笑みで頷き返した。
先生が教室に入ってきたのは、ちょうどその時だった。
黒髪ショートカットの先生は、どこか男っぽく、りりしい表情をしていた。
教壇に立つと、いつものように挨拶をする。なんとなく、さすがに二度目ということもあるが、うまい具合にこなすこともできた。適応力というやつだろうか。
「今日は錬金術とは何か、ということについてお話ししましょう」
先生の言葉を即座に翻訳するメアリー。もちろん、そんなことがばれてしまっては元も子もないので、彼女が必要だと判断した部分だけ翻訳しているらしい(というのはあとで聞いた話なので、この時点では知らなかったが)。
先生は黒板に円を描き、指さした。
「錬金術に重要な要素といえば、先ず、円です。円は力のファクターを指します。そこに色々な術式を組み込ませることで、初めて『錬金術』は誕生するのです。……それでは、メアリー・ホープキンさん」
「はい」
メアリーが指されたらしく、立ち上がる。
メアリーから離れてしまっては、この世界の言語が解らない現状何も対応することができない。板書をすればいいのか、と思いつつもまだ黒板に書かれているのが円だけであればたった数秒で書き上げてしまう。
だから、メアリーが居ないと何も出来なかった。
「錬金術は無から有を作り出すことは出来ません。ある二つの法則が成り立っているためです。では、その二つの法則とは何でしょうか?」
メアリーが離れている間に、僕は基本的な、ある一つの疑問に辿り着く。
_ ――どうしてメアリーは僕のことを助けてくれるのだろうか?
_ それは単純であるが、最大の疑問だ。
「はい、質量保存の法則と、自然摂理の法則になります」
対してメアリーははきはきとした口調で答える。残念ながらメアリーは今現地語で話しているため、いったい何を答えたのかは定かではない。
先生はよどみなく答えたメアリーを見て、頷く。
「はい、正解です。この二つの法則から解ることは――」
席に座り、やった! と親指を立てるジェスチャー――サムズアップのポーズをとり、僕に笑顔を見せてきた。
僕は先ほどの疑問が解決していなかったから少々戸惑っていたけれど、何とかそれを内に隠して――親指を立てて笑顔を返した。
_ ◇◇◇
「お願いだよ、メアリー。あまり君にばかり頼っているのも申し訳ないからさ」
この学校には学生全員を収容してもまだ有り余るほどのスペースを持つ食堂がある。天井はあまりにも高く、またそこからシャンデリアが吊られていて、時折風で揺れている。少々怖いところもあったが、みな冷静に食事をとっているところを見ると慣れっこなのかもしれない。
僕とメアリーは向かい合わせになっていた。ちなみに学生の食事メニューはすべて一緒。今日のメニューはエスピシャートという魚のソテーに固いパン(その形は、どこかフランスパンをイメージさせる)、それにサラダとミルクだった。栄養を考えているのかもしれないけれど、少々質素なようにも思える。
「それで? どこから教えてほしい? 基礎から」
「そりゃあもちろん」
「うーん……フルが別の世界から来た、というのは正直信じがたいけれど。まあ、この際それはどうだっていいか! いいわよ、いろいろと教えてあげる」
メアリーの笑顔を見て、僕は頷く。これでこの世界でもなんとかなりそうだ。まずは言語を習得しない限り、相手と会話することすらできないからね。
「この世界の言語はね、けっこうあっさりとしていて単純なのよ。だから案外簡単に覚えるかもしれないわ。……フルの世界の言語がどういう仕組みだったかは解らないけれど、実際、フルの話を聞いていると若干発音とニュアンスを変えればそれで充分。あとは文法かな。文法はちょっと難しいかも。主語と述語、それから修飾語の順番になるのよ」
つまり、英語とあまり変わらないということか。しかも、単語の発音自体は日本語のそれと変わらない――と。なるほど、これは案外簡単そうかもしれない。もっと難しそうに考えていた僕が馬鹿らしくなってきた。
その後メアリーと僕は空いた昼休みの時間を利用してこの世界の言語の勉強をすることとなるのだが――それはまた、別の話。今は特にする必要も、きっと無いだろう。
それから数日が経過した。
どうやら僕が最初に目を覚ました場所は寮だったようで――しかも一人部屋だった。
はっきり言ってそれはとても有難いことだった。もしペアが居たとすれば会話に困っていたからだ。だってすぐに考えてみれば帰結することになるのだが、話すことのできない人間がペアに居れば部屋にいる間の時間がとても長く感じるはずだし、とても辛かったはずだ。
そして僕もなんとなくこの世界の言語を理解できるようになってきた。
その日の授業にて、先生――サリー先生が、こんなことを言ってきた。
「今日からフィールドワークを実施します。三人で一グループとなり、上級生を一人つける形になります。だから、合計四名で旅をするということになるかしらね」
それを聞いて学生たちは騒然とし始める。
まあ、当然のことといえば、当然かもしれない。これが仮に予告されているものならばよかったのだが、前日にすら予告が無かった。きっと先生からしてみればサプライズの一面もあったのかもしれないが、だとしても少々悪質なところがあるのも否めなかった。
「静かにしなさい。別に、フィールドワークといってもこの島――レキギ島から出ることはありません。だから安心してください。あなたたちに危険が及ばないように、配慮はしています。だから、落ち着いて」
そういわれても納得できないものもある。
「それじゃあ、班を決めましょうか。班はくじで決めるわ。同じ数字のくじの人とメンバーを組んでね」
「ええー!?」
再びブーイングの嵐が起こる。思えばもともとの僕の世界でも、仲の良いメンバーと組みたがる性質があった。そういう性質はどこの世界でも変わらないのかもしれない。
「静かにしなさい! いいから並んで、くじを引いて」
そう言ってサリー先生は予め用意していたと思われる箱を取り出した。
その箱を見て、もう学生たちは仕方がないと思ったのだろう。教壇にぞろぞろと向かっていく。それを見てメアリーも諦めたようで、小さく溜息を吐いて、そちらへと向かっていった。
_ くじを引いた結果、僕とメアリーは同じ番号だった。それは充分有難いことだった。別に、メアリーから教えてもらったから言葉が話せないというわけではない。問題は、誰も知らない空間において、顔も見たことのない人間三人と旅をするのは正直言って苦痛だった。
もともと人見知りがあるとはいえ、そうであったとしても知っている人と、できればコンビを組みたかった。
「……フル、よかったね、一緒で」
それを聞いてこくりと頷く僕。確かにその通りだった。メアリーは優秀だと自負しているしその通りだと思っている。だからこそ、同じメンバーにメアリーが居るというのはとても心強い。
さて、覚えているだろうか。
メンバーは二人ではなく、三人であるということを。
「……3番はここかい?」
それを聞いて、僕は振り返る。
そこに立っていたのは、やはり黒髪の少年だった。あどけなさが残る顔つき、柔和な笑みを浮かべていた彼は、訊ねる。
「なあ、聞かせてくれないか? 3番はここで間違いないか?」
それを聞いて、僕は――一瞬考えて、頷く。
「ああ、ここが3番だ。ちなみに彼女も同じく3番だよ」
「彼女……」
彼はメアリーのほうを一瞥して、頷く。
「よろしく頼むよ、僕の名前はルーシー。ルーシー・アドバリーだ」
そう、彼――ルーシーは僕とメアリーのほうを見て言った。
「さて、挨拶も軽く済ませたところで……次は行き先を選定するわよ! もちろん、こちらもくじで決定します」
サリー先生の言葉を聞いて、再び学生からはブーイングの嵐が起こる。
行く場所くらい自分で決めさせてくれ――とかそんなことを思っているのかもしれないが、僕から言わせてみればすべてが『異世界』で『行ったことのない場所』になるので、別にどこでもいいところだった。
「静かにしなさい!」
再び、サリー先生は場を鎮めるために大声を出した。
しん、と静まり返る教室。
サリー先生は息を吸って、話を続けた。
「いい? くじは偶然で決まるのよ、偶然は運命、そして運命は必然。運命はあなたたちがすべきことを教えてくれる……それは授業でも教えたでしょう? だから、くじが一番いいことなのよ」
そう言われて、学生たちは再び箱のほうへ向かう。
なんというか、ここの学生はどこか理解が早い。そういう印象がある。
「さあ、くじを引いてちょうだい。あ、一応言っておくけれど、さきほどのくじで番号に丸がついている人がリーダーになるから、よろしくね!」
そう聞いてそれぞれが先ほどのカードを見つめる。
メアリーとルーシーは丸がついていないようだった。ということは……。
……想像通り、僕のカードの番号には丸がついていた。
それを二人に見せて、
「どうやら、僕がリーダーのようだ」
そう言った。
メアリーとルーシーは何も言わなかったが、僕の言葉を聞いて強く頷いた。
_ くじを引いた結果、またもや3番だった。どうやら3の数字に愛されているようだ。
……そんな冗談を言えるようになったということは、どうやら僕もこの世界に馴染んできたのかもしれない。
「行き先はここに記してあるので、それを見てちょうだい」
そう言って、サリー先生は黒板に張り出してある地図を指さした。いったいいつの間にそんなものを張り出したのか解らなかったが、今は質問する必要も無いだろう。別に必要なことでもないし。
地図を見に行くために、僕はそちらへと向かう。僕が地図を見ていると、その背後にメアリーとルーシーもやってきた。
「番号は何番だい?」
ルーシーの問いに、僕はカードを見せつけることで答えた。
「3番……ええと、これかな。トライヤムチェン族の集落……」
「トライヤムチェン族といえば先住民族ね。確か世界がいつに滅ぶとか言っていたような……」
「今年だよ。ガラムド暦二〇一五年。今年のどこかに災厄が起きて、世界が滅ぶってこと。まあ、彼らの祖先がカレンダーをそこまでしか作っていなかったから、というのが理由らしいけれど、普通に考えると、二千年以上昔に、二千年分のカレンダーを作るだけでも大変だというのに、きっとそのあたりで飽きたからだと思うのだけれどね。意外と真実って、つまらないものだというのが相場だし」
よく解らないけれど、先住民族か。
何を見に行くのか解らないけれど、取り敢えずこのメンバーならば何とかやっていけそうだ。僕はなんとなく、そんなことを思うのだった。
「君たちが、トライヤムチェン族の集落に向かうメンバー、で間違いないかな?」
そう言って僕のほうに立っていたのは、青年だった。僕よりもどこか大人びた様子の青年は、見た感じ優等生っぽいオーラを放っているように見えた。あまりにもそう見えて、若干胡散臭さすら感じるレベルだった。
その青年は僕たちに向けて柔和な笑みを浮かべると、話を続けた。
「僕の名前はルイス・ディスコード。まあ、苗字で呼ぶと言い難いだろうから、名前で呼んでもらって構わないよ。君たちをトライヤムチェン族の集落まで案内する。道は険しいが、そう時間がかかる場所じゃない。もって半日程度かな。明日の朝出発して、夕方に到着する感じになる」
レキギ島の北端に位置する集落と、南端に位置する学院では相当な距離がかかるものが予想されていたが、半日で済むのならばそれはそれで問題なかった。一日以上かかるというのならば、面倒なことになると思っていたが。
「期間は二泊三日です。三日間という短い期間で何ができるのか、正直言って先生にも解りません。けれど、できる限りの経験を、知識を蓄えてきてください。そうして、成長にフィードバックしてください。それができるのであれば、先生は問題ありません」
それを聞いて頷く学生たち。
だからどうしてそこまで理解が早いのか、疑問を浮かべてしまうほどだが、今ここでは考えないほうがいいだろう。
「さあ、それじゃ、授業は終わり! 明日朝、出発するように! 準備も今のうちに進めておいてね。それじゃ、みなさん」
一拍おいて、サリー先生は言った。
「良い旅にしてきてね!」
_ ◇◇◇
_ 次の日は、とても寒かった。さすがに雪まで降っていなかったが、息を吐くととても白かった。
なぜか僕の部屋にはサイズがぴったりの外套がいくつかあったので、それを拝借していくことにした。まあ、深く考えないでおこう。異世界召喚のお約束、というやつかもしれないし。
「寒くはないかい?」
ルイスさんが僕に問いかける。外套を着ているので、何とか大丈夫です――ということを伝えると微笑んで頷いた。ただ、それだけだった。
ちなみに、まだメアリーとルーシーは来ていない。彼女たちが遅刻しているわけではなく、僕たちが早かっただけだ。
正確に言えば、早すぎた――のかもしれない。今はまだほかの班も集まっていない。
だから今はルイスさんと僕だけだ。
面識のない上級生と、僕だけが学院の前に取り残されている形となる。
正確に言えば、その表現もどこかおかしいのかもしれないけれど。
「ええと、君の名前は……」
ルイスさんは何枚かの綴じられた冊子を見ながら、言った。
どうやら僕の名前を探しているようだった。
「フルです。フル・ヤタクミ」
「フル・ヤタクミ、ね……。ああ、あった、あった。アルケミークラスで成績は平凡的。うん、まあ、別に問題はないよ。成績と実際は関係ないからね。君が実戦がどれくらい働くことができるか、それが重要なのだから」
「実戦、ですか……」
まるでこれから戦いに出向くような、そんな言い方だった。
ルイスさんはハハハと笑い声をあげて、
「まあ、そう真剣な表情をしなくていい。昔は少し魔物くらい出たかもしれないが、今は完全に平和になったからな。メタモルフォーズだったかな? 古の魔物だったと思うが、それも滅亡したし、今は平和そのものだよ」
「メタモルフォーズ……ですか?」
メタモルフォーズ。
歴史の中で聞いたことのある、異形。それは少なくとも僕が昔居た世界では見たことのない、この世界独特の生き物だと思う。思う、としているのは見たことがないからであるが、滅亡していることまでは覚えていなかった。
「メタモルフォーズって……すごい生き物なんですか」
「さあ? 確かに人間を食ったとか文明を一日で滅ぼしたとか摩訶不思議なことも教えられたけれど、あくまでも歴史上の話だからね。どこまで本当かどうか解ったものではない。まあ、そう言い切ってしまうと歴史学者の人が涙目になってしまうだろうから言わないでおくけれど」
大丈夫です。もう充分涙目になっています、たぶん。
そんなことを思っていたら、校舎のほうから二人がやってきた。
「遅れてすいません。もしかして……けっこうな時間待っていましたか?」
メアリーの言葉に、微笑むルイスさん。
「いいや、今来たばかりだよ。それにしても今日は冷えるね。二人とも、大丈夫かい? 一応半日かからないくらいで着く予定ではあるけれど、夕方になるとさらに冷えてくるし、北のほうに向かうからね」
「いえ、大丈夫です。ルーシーは?」
「僕も問題ないよ……ええ、大丈夫です」
二人の返事を聞いて頷くルイスさん。そして、踵を返して、
「それじゃ、出発しようか。ちょっと早いかもしれないけれど……トライヤムチェン族の集落にはなるべく早く着いたほうがいいだろうし!」
そして僕たちは、先住民族トライヤムチェン族の住む集落へと向かうべく、その第一歩を踏み出した。
_ まことに残念ながら、トライヤムチェン族の集落に着くまでの間は特筆する事項が無かった。せいぜい、他愛もない世間話をした程度だった。しかしながら、細かい気遣いなど、その他もろもろのいろんな所作を見ていると、やはりルイスさんは模範的で優秀な上級生だということが理解できた。正直、この世界の制度がよく解っていないけれど、少なくとも下級生は目標にするような学生であることは充分理解できた。
森を抜けて、山を越えて。
山間に佇むトライヤムチェン族の集落が見えてきたときには、日が暮れかけていた。
「何とか夕方前には着いたね……。いやあ、何とかなるものだね。最初はどうなるかと思っていたよ」
ルイスさんは額の汗を拭いて、頷く。
僕もそう思っていた。半日、とは言っていたけれど何せ僕にはこの世界の地理に関する情報が無い。だから、そこで躓いてしまって普段以上に時間がかかってしまうのではないか、そんなことを思っていたからだ。
しかし蓋を開けてみると――意外と前の世界と変わらない風土だったのが功を奏して、そういう状況に陥ることは無かった。
「さて、それじゃ集落に向かうことにしよう。到着したらその足で村長の家に向かい挨拶をする。夜にある儀式を見て、次の日にトライヤムチェン族について学び、その次の日の朝に出るという日程だ」
「解りました」
「それじゃ、先ずは村長さんの家に行くんですね?」
ルーシーとメアリーがそれぞれ言ったので、ルイスさんはそれに頷く。
「そうだ。物分かりがいいようで、僕もだいぶ助かるよ。村長の家は集落の北側にある一番屋根の大きな家だ。さあ、向かうことにしよう」
そうして僕たちはトライヤムチェン族の集落へと足を踏み入れた。
_ ◇◇◇
_ 木でできた巨大な柵に囲まれた村。
それがトライヤムチェン族の集落を見た第一印象だった。唯一解放されている門も、どこか物々しい雰囲気を放っていた。
しかし、中に入ってみると、
「お兄ちゃんたち、旅の人?」
「違いますよ、ラドーム学院から来ました。村長さんの家はどちらになりますか?」
ルイスさんが丁寧に子供に訊ねる。
子供は見た感じ、元の世界に居た子供と同じような感じに見える。
それはそれで有難かった。もし、実際に違う雰囲気だったらそれは面倒なことになるだろう――そう思っていたからだ。
「有難う。それじゃ、向かうことにしようか」
ルイスさんの言葉を聞いて、僕たちは村長の家へと向かうことにした。
_ 村長の家に着くと、家の前に立っていた男が僕たちの前に立ち塞がった。当然と言えば当然かもしれない。見知らぬ人間が村の長の家に入ろうというのだから不審に思わないほうがおかしいだろう。
「何用だ」
「ラドーム学院の研修で来ました、ルイス・ディスコードといいます」
それを聞いて男は怪訝な表情を浮かべていたのをやめて、笑みを浮かべる。
「ラドーム学院か。ならば話は聞いている。そのまま通るといい。村長は真ん前に座っているから、粗相のないように」
「有難うございます」
そして僕たちは村長の家へと入っていった。
入口についていた布を暖簾替わりに手でどけて中へ入る。中は質素なつくりだった。土の床の上にカーペットを敷いて、真ん中にはさながら囲炉裏のような感じに穴があけられて、そこにたき火がしてある。それにより一定の明かりが保たれており、村長の顔が見ることができた。
顎鬚を蓄えた老齢の男だった。『村長』といえばこういう雰囲気だろう――というイメージを美味い具合に表現した感じになる。
「遠くまでご苦労でしたのう。ささ、先ずは座りなされ」
その言葉を聞いて「失礼します」と言い、僕たちは安坐の姿勢をとる。
「さて……私たちは何を話せばいいのだったか。ええと、確か……」
「儀式、でございます。村長」
そう口出ししたのは、村長の隣に正座の姿勢をとっていた若い女性だった。若い、と言っても僕より年上だろう。質素な雰囲気だったが、その飾らない感じだけでもどこか可愛い雰囲気に見えた。
さて、村長はその女性の言葉を聞いて思い出したかのように手をたたいた。
「ああ、そうだった。儀式、と言ってもそんな仰々しいものではなくてなあ……。どこまでお伝えすればいいものか。ええと、先ずはこの世界の歴史について、簡単に説明することとしましょうか。どこまで授業で習っているのでしょう? 偉大なる戦いは知っていますか?」
それを聞いてこくりと頷くメアリー。僕も偉大なる戦いについては何となくというレベルで知っている。しかし、詳細となると答えられるかどうかは曖昧だけれど。
「まあ、そんな小難しい話をするつもりは毛頭無いので、そのつもりで。……偉大なる戦いは、今から二千年以上昔に起きた戦乱のことだ。歴史上で幾度となく我々を攻撃してきた謎のバケモノ、メタモルフォーズのプロトタイプと言われている『オリジナルフォーズ』が我々に攻撃をしてきたこと、それが始まりであると言われている」
「オリジナルフォーズ……」
またも解らない単語が出てきたぞ。
「オリジナルフォーズは強力な存在であったと伝わっておるよ。そして、そこで戦ったのは勇気ある若者たちだった。武器を手に取って、オリジナルフォーズは封印された。この世界の東に岩山で囲まれた島があるだろう。あれが、オリジナルフォーズの封印された島であると言われている。そして、その島は今スノーフォグが管理している。あそこは、祈祷師が自ら管理している非常に珍しい国家であるからね」
スノーフォグは祈祷師が管理している――ね。
それにしても、祈祷師ってなんだ? スノーフォグは地理の授業で何となく聞いたから知っているけれど。
この世界は少々面倒な世界だと、授業で習った。
あくまでも僕が知っているのは授業で習った知識の範疇になるけれど、復習も兼ねて脳内で整理することにしよう。
この世界はスノーフォグ、ハイダルク、レガドールという三つの国家で形成されている。非常に狭い世界となっている。地球みたく球体になっているのではなく、平べったい瓦のような感じになっていると予測されている。予測されている――という曖昧な表現となっているのはそこまで科学技術が発展していないためで、宇宙に人類が未だ進出出来ていないからだと言われている。
そしてそういう風に世界が形成されてしまった理由が――。
「偉大なる戦いによる被害は、世界の形成にも繋がった。昔はこの世界も球体だったと言われているが、今はプレートのような世界となっている。世界の果ては、滝のようになっているそうだよ? 水が流れているのだという。どこへ流れているのかは、未だ誰も調べたことがない。その先に深淵がある、としか解らないからだ」
「偉大なる戦いは……このトライヤムチェン族と何か関係があるのですか?」
「トライヤムチェン族は、もともと祓術師だったのだよ。神の一族、といえば聞こえがいいかもしれないが、圧倒的権力を誇っていた祈祷師と違って祓術師は何も出来なかった。力を失い何も出来なくなった祓術師は自らのテリトリーを作り、それを守ることで精いっぱいだった」
祓術師。
それは歴史の授業で聞いたことがある。ただ、あくまでも単語だけに過ぎないが。
「そもそも、祈祷師と祓術師とは何が違うのでしょうか? 正直なところ、まったく違いがあるようには見えないのですが……」
「祈祷師は政治を見る。もともとは神に祈りをささげて、神からお告げを聞くものだったのだよ。だから政治なんてかかわることではなかった。むろん、それは我々も……だが。政治は政治を知る人間にやらせてしまえばいいのだよ。けれども、それを両立したのがリュージュだった」
「リュージュ……」
「今のスノーフォグを統べる、王の名前だよ。彼女は『弾丸の雨』と『二度目の終わり(セカンド・ウォー)』を予言したのだからな。それによって、国王からの信頼が高まった。かつては、ハイダルク一国で世界を治めていたが、二度の災厄の事後処理等を命じて、同時に国王は彼女をスノーフォグの王に任命した」
さてと、と言って村長は一拍置いた。
「そろそろ儀式の始まる時間だ。準備も出来たことだろう。儀式は簡単なものだ。君たちには見ていただくだけになると思うが、一応説明だけはしておくことにしよう。これから村の中心にあった石像へと向かう。村人でそれを取り囲み、一斉に頭をさげて祈りをささげる。そうしてみんなで手を取り合って、我々の民謡を歌う。民謡、と言っても神に祈りをささげる、その代わりと言えるだろう。それを歌い、あとは宴が始まる。それで終わりだ。まあ、そのまま見ていただければいいだろう。……と言いたいところだが、」
言いたいところだが? 僕はそこが引っ掛かった。どうして急にそんなことを言い出したのか、僕にはそれが解らなかった。
「確かあなたの名前は……フル・ヤタクミだったかな?」
顎鬚を弄りながら、僕の名前を言った。
「はい……。確かに、フル・ヤタクミは僕ですが」
「そうか」
小さく溜息を吐いて、周りを見渡して、そして僕に視線を戻して、言った。
「不穏な気配が、あなたの周りに潜んでおりますぞ。努々、気を付けなされ。あと、その不穏な気配にも忠告しておきましょう。これは最後通告だ。何をしようとしているのか解らないが……その気配を隠そうとしても無駄だ、と言っておきましょう」
「不穏な気配……ですって?」
僕はそれを聞いて、いったい何を言っているのか解らなかった。正確に言えば、解りたくなかったのかもしれない。
だってそうだろう? その村長の発言が正しければ、その発言を一から十まで信じるならば――。
「それってつまり、私たちの中に裏切り者が居るということですか……?」
「まあ、君たちは学生同士だ。それも、あまり経験も深くないのだろう。だから、実際には裏切り者というよりも、別の目的があって行動していると言ったほうが正しいかもしれませんね」
「それは……」
やっぱり、聞き直しても、どういうことなのか解らなかった。
解りたくなかった、の間違いかもしれない。
だって、考えてみればわかる話。いままで行動してきた人の誰か一人が、敵だというのだから。
「でも、村長さん。その話を聞くと……もう、その気配を発している人が誰であるか解っているような言葉になりますけれど」
メアリーの言葉を聞いて村長は頷く。
「どうやらそこのお嬢さんは利口なようじゃな。うむ、まさにその通り。私には人の気配を読む力がある。祓術師だった祖先の名残、ともいえるかもしれないが、実際問題、それは使い物にはならなかった。せいぜい、息をひそめる動物を探すくらいだったからのう。だから、ここまで使い物になる機会が訪れるとは、全然想像もしていなかったよ」
「……」
ルイスさんを見ると、ずっと俯いていた。眠っている――ようには見えない。いったいどうかしたのだろうか? そう思って近づこうとしたが――。
「近づいては、なりませんぞ!!」
村長の大声を聞いて、思わず静止してしまった。
「……いったい、どういうことですか?」
「ばれているのならば、仕方あるまい」
ルイスさんはそう言って、ゆっくりと立ち上がる。
「もう無駄だぞ。たとえ何をしようとしているのか解らなくとも、その邪悪な気配を隠し通すことは出来ない」
「もともと隠すつもりなど無かったさ……。どこかのタイミングで、目的を達成させてしまおうと思っていた」
ふらり、ふらり。
身体を揺らしながら、なおルイスさんは俯いている。
もう彼は、つい先ほどまでの模範的な優等生、ルイス・ディスコードでは無くなっていた。
「予言の勇者と神の一族……そいつらを殺すために、うまいところまで運ぼうと思っていたのに、よ。時間のかからないように、事故に見せかけたほうが一番だと思っていたのに。まったく、すべてぶち壊しやがって。もう許せねえ、もう許してたまるかよ……!」
ルイスさんの背中から、何かが出現する。
それは、黒い翼だった。
ルイスさん自身を隠す、巨大で、黒い翼。それは闇の象徴であり、ルイスさんが人間ではない――別の何かであることを示すには、充分すぎる証拠だった。
「本性を現したか、それがもともとのあなた……。メタモルフォーズ……いや、この場合は、合成獣(キメラ)……?」
フッ、と鼻で笑うルイス。
ルイスの顔もまた、翼の現出に伴い変化していた。頬骨が出て、痩せこけている。全体的に顔を縦に伸ばした――とでもいえば伝わるだろうか。そういう感じだ。
「ああ、そうだよ。合成獣さ! 残念ながら、僕たちは合成獣がこれ以上のレベルのものがたくさんいるけれどねえ!! 合成獣を見て驚いただろう? 恐れ戦いただろう?」
合成獣。
もちろんそんな名前はゲームや小説の中でしか聞いたことのない代物だった。
それが今、目の前に立っている。
目の前に立って、僕たちを殺そうとしている。
ルイスは一瞥して、頷く。
「……やはり、これ以上時間をかける必要は無いね。神の一族も予言の勇者も力を持っていない。ならば、今のうちに――倒しておくべきだ!!」
翼を広げて、ルイスは走る。
目的地は、僕のいる場所。
ルイスの腕の先端を、針のように尖らせて。
危機が迫っているにも関わらず、僕はすぐに行動に示すことができなかった。
メアリーとルーシーも動けない。村長も、あまりに一瞬の行動で動くまでの時間が釣り合わない。
僕が動かなきゃ――僕が逃げなくちゃ!
そう思っている間にも、ルイスの腕が迫る――。
(もう……逃げられない!)
目を瞑り、僕はその瞬間を待つしかなかった――。
――のだが。
「……あれ?」
いつまで経っても、それがやってくることは無かった。
恐る恐る目を開けると、そこには、うっすらと緑色の壁が出来ていた。
そしてその壁に、ルイスの腕が突き刺さっていた。
「これは……!」
「何とか、間に合ったようね。みんな」
そして僕の目の前には、ある女性が立っていた。
それは僕もメアリーも、もちろんルーシーも知っている――ある人物だった。
「サリー……先生?」
そう。
サリー先生が、僕の目の前に立って、バリアを張っていた。
「サリー……サリー・クリプトン! どうして、どうしてお前がトライヤムチェン族の集落に居る! ここから学院までは半日もかかるはず! そう簡単に向かうことなんて……」
ルイスは腕を抜いて、
「いや、それよりも……。どうして、僕のことが合成獣だと解った?」
「校長が、私に伝えてくれたのよ。あなたのことを、ね……」
_ ◇◇◇
_ フルたちが旅立ってすぐ、サリー・クリプトンはある人物に呼び出されて学院の中を歩いていた。
静かな学院を見て、とても不気味に思いながらも、それは彼女にとってどうでもいいことではあった。現在、一学年の全生徒がレキギ島の各地に研修に向かっているためである。だからこそ、今は誰が侵入してきても解りやすい。
そもそも。
このラドーム学院という場所は西と南を断崖絶壁に、北と東を雪山に囲まれている場所に位置している。そもそもどうしてこのような場所に学院が置かれているのかは別にして、ラドーム学院が全寮制となっているのはそれが理由だと言われている。
そのため、ラドーム学院に入るには港町のクルシアート近くから延びる廃坑を通らないといけない。廃坑、と語っているが正確に言えばそれは廃坑ではなくそのように模した洞窟となっている。
ただ単に山道を切り開かなかった理由は、侵入者を防ぐためである。
ラドーム学院は錬金術だけではなく、魔術、化学等様々な分野の学生を育成している。そういうこともあって先生も超一流の魔術師や錬金術師などその分野のエキスパートを揃えている。
当然、そのエキスパートを狙う敵が居てもおかしくない。別に学院はラドーム学院だけではなく、様々な場所に置かれているのだから。
ラドーム学院に入るとスカウトを受けることは禁止されている。理由は『そのようなもので学生への教育が滞ってはならない』という為である。それが原因かどうかは解らないが、ラドーム学院に所属するエキスパートはどれも高給取りであることもまた、事実だ。
閑話休題。
ラドーム学院の通路を抜けて、図書室へと入るサリー。
図書室にあるメタモルフォーズがモチーフになっている石像に触れて、つぶやく。
「サリー・クリプトンです。ただいま到着いたしました」
その言葉を聞くと、石像がそれを合言葉だと認識していたかのように、競り上がっていく。
石像が競り上がると、その中に螺旋階段が出来ていた。
完全に競り上がったのを確認して、螺旋階段を下りていく。暗くなっているので、道中明かりをつけないといけないのだが――そんな必要は無かった。
なぜなら彼女の歩幅に合わせて、ゆっくりと炎がついていくためである。魔術なのか錬金術なのか、それとも別の学問なのか、どういうメカニズムでそれが動いているのか解らないが、とはいえ彼女がわざわざ錬金術で炎をつける必要がない、ということはとても便利なことなのだ。
螺旋階段を下りると、そこには扉があった。木でできた質素な扉だ。しかし彼女はその扉の向こうに何があるかを知っている。誰が待ち構えているかを知っている。だからこそ、これまで以上に緊張していたのだ。
数回ノックをして、彼女は息を吸った。
気持ちを落ち着けて、彼女は言った。
「失礼いたします」
そして、彼女は扉を開けて中に入っていった。
部屋の中は豪華な内装になっていた。壁はすべて赤い煉瓦で構成されており、天井にはシャンデリアがつりさげられている。さらに部屋自体の構造が二階建てとなっており、二階には壁を埋め尽くすほどの本が本棚に敷き詰められていた。
その中心、大きな机に向かって椅子に腰かけている一人の男が居た。
黒い帽子を被った、顎鬚を蓄えた老齢の男性だった。老眼になっているのか、書物を見ているとき用と思われる老眼鏡を装着して、書物を読んでいた。
サリーが入ってきたのを見て、男性は顔をあげてサリーを見る。
「サリー・クリプトンです。ご用件は何でしょうか、校長」
「まあ、そこで立っていないでここまで来なさい。話せる内容も話せないぞ」
そう言われたので、サリーはその通りに従った。
彼こそがラドーム学院の校長であり、設立当時からその職に就任している、ラドーム・イスティリアだった。
ラドームはサリーが机の前に立ったのを確認して、立ち上がる。
「まあ、そこに椅子があるから、適当に使って腰かけなさい。話はそれなりに長くなる。とはいえ急を要する事態になっていることもまた事実。だから君を呼んだのじゃよ。君ならば、何かと役に立つと思っていたのでね」
「そう思っていただけて、とても嬉しいです」
サリーは椅子を取り出して、机から少し位置を離した場所に置いた。
ラドームはそれを確認して、右手を差し出す。座ってもよい、という合図だ。
それを確認したサリーは「失礼します」と言って腰かけた。
「さて、私が君を呼んだことについて説明する前に、一つ聞いておきたいことがある」
「なんでしょうか?」
「君のクラスに……フル・ヤタクミという学生はいるか?」
フル・ヤタクミ。確か居たような気がする。
そう思ってサリーは頷いた。
「居る、か。ならば良い。聞いた話によれば、フルたちのグループはトライヤムチェン族という原住民の儀式を見に行く、だったな?」
「ええ、そうですが……それがどうか致しましたか?」
「実はアルケミークラスには、怪しい動きがあるのだよ……。私も独自に監視の目を広げていたのだが、予想外だった。まさか今回の研修に行く上級生の中にそのような人間がいるとは」
「ちょっと待ってください! それってつまり、反社会的組織に所属している人間が、このラドーム学院に居るということですか……?!」
「だから、それを言っている。一応言っておくが、可能性ではない。これは確定事項だ。すでに証拠も掴んでいる。彼奴……ルイス・ディスコードは人間ではない。彼奴は合成獣だ。ASLにより開発された、『十三人の忌み子』の一人だよ」
十三人の忌み子。
ASL――シュラス錬金術研究所が生み出した、負の遺産の一つである。
人間は人間の根源、その遺伝子を解明することで人間の未来を切り開くことができると考えた。そう考えた先端に居たのが、シュラス錬金術研究所の顧問であるミライド博士だった。
ミライド博士は最初こそその研究をしていたのだが、徐々に人間と組み合わせることのできる動物の遺伝子を調べて、それにより新たな神秘を生み出すことができる――今、科学者がその話を聞けば卒倒するだろう、そんな研究に足を踏み入れることとなった。
それにより選ばれた十三人の忌み子は、それぞれ別の種族の遺伝子を組み込まれ――合成獣となった。
「あれはとても問題になりましたね……。我々ラドーム学院の学生にも被害者が居て、社会的問題になったのを覚えています。しかし、十三人の忌み子はすでに保護されているはずでは?」
「そうだった。そうだったのだよ。十三人の忌み子のうち七名が死亡、三名が保護され、うまく合成獣から人間へと戻ることができた。……だが、残りの三人はどうなったと思う? 君は知っているかね?」
「ええ……。確か、『行方不明』になった、と……」
「それは『表向きの話』だ」
「え……?」
それを聞いたサリーは顔を強張らせた。
「実は残りの三名は、ある人間が引き取ると言い出した。シュラス錬金術研究所の解体も彼女が実施すると言い出した。私もそうだが、世界のすべてが彼女にノーとは言えなかった。そしてそれは秘密裡にされて、真相を闇の中に隠すことにした。……誰だか解るかね? その人間が」
「まさか……スノーフォグの王、リュージュ……ですか?」
こくり、とラドームは頷いた。
「私は昔からリュージュを見てきた。だからこそ、だからこそ解るのだよ。アイツは危ない存在だ、と。いつか世界を滅ぼしかねない。いや、正確に言えば自分の力を過信しすぎて、自分そのものを滅ぼしてしまう可能性のほうが高かった。だから私は幾度となくアイツにそのようなことは止めるべきだ、と言った」
「リュージュは……なんと答えたのですか?」
「ああ、未だに覚えておるよ。アイツは、子供のような無邪気な笑顔で、こう言った」
――ラドーム。あなたも解っていないようだから言っておくけれど、一度きりの人生を楽しまないと、後悔するわよ。私は、欲望のままに生きているのだから。
それを聞いたサリーは何も言えなかった。
ラドームは深い溜息を吐いて、話を続ける。
「今思えば、あの時に止めておけばよかったのだよ。例え私の命を懸けてでも。だが、それは出来なかった。それだけは許されなかった。私の古い友人との約束だよ……。それが、私がリュージュを、命を懸けてでも止めるという最悪の手段に至らせないで済んでいる」
「……そんなことが……。しかし、校長。そのこととルイス・ディスコードに何か関係が?」
「だから言っただろう。ルイスは十三人の忌み子の一人。そして、リュージュが保護した人間のうちの一人なのだぞ。そして放っておけば確実に、フルたちに牙を剥くはずだ」
「それはマズイですが……しかしやはり気になります。どうしてフルたちを狙うのですか? 正直な話、フルたちを狙う理由が全然理解できないのですが。納得できる理由を説明願えますでしょうか?」
「うむ、出来ることならあまり口外したく無かったのだが……緊急事態だ。致し方あるまい。実は――」
そしてラドームはサリー先生に、フルの正体を明らかにした。
それを聞いたサリー先生は絶句して、何も言えなかった。
「まさか、そんな……」
「そんなこと、斯様な平和な世の中では想像出来ないだろう? もっと言うならば、必要ない存在だと言ってもいいかもしれないな」
「確かに……そうかもしれませんが、しかし、そうなると、いずれこの世界に……」
「ああ。何らかの災厄がやってくる可能性はある。そして、その日はもう、そう遠くない」
ラドームの言葉を聞いて、サリー先生は自分が何をすればいいのか――考える。
結論を考え付くまでに、そう時間はかからなかった。
「では、私はフルたちを助けるためにトライヤムチェン族の集落に向かいます」
「うむ。そうしてくれ。ルイス・ディスコードがどれほどの実力かは解らない。学校の実力ではまずまずの成績だが……『十三人の忌み子』の一人であればその成績は嘘の成績かもしれない。だから、実力は――」
「未知数、ですね」
こくり、とラドームは頷いた。
_ ◇◇◇
ルイスは、サリー先生という予想外の相手が登場したにもかかわらず、その反応は至って冷静なものだった。
まるでこのような事態になることを予測していたかのように。
「……どうやら、予測していたようね? 邪魔が入ることを」
「当然だ。邪魔が入らないと思うわけがあるまい。むしろ、邪魔が入るという前提で進めていたのだから」
そう言ってルイスはあるものを取り出した。
それは卵だった。掌に乗るほどの大きさであるそれを握りしめて、ルイスはサリー先生のほうへとそれを投げた。
「マズイ!」
サリー先生は慌ててそれをバリアで守ろうとしたが――間に合わず、まともにその卵を受けてしまった。
「「サリー先生!!」」
僕たちは三人、同時にサリー先生の名前を叫んだ。
サリー先生は倒れることは無かったが、小さくうめき声をあげていた。
何か口を開けて言っているようだったが、それはフルたちに聞こえることは無かった。
「まさか……あれは『マジック・エッグ』!?」
メアリーの言葉を聞いて、フルはそちらを向いた。
「知っているのか、メアリー!?」
「ええ、あれは錬金術師にとって簡単に術式や物体を封じ込めることができる代物なのよ。だからあれを使うと、魔法をたとえ使えなかったとしても使うことができる……」
「さすがは神の一族。そういう技術については一家言あるようだ」
ルイスの言葉に首を傾げるメアリー。
そういえば幾度となく神の一族と誰の代名詞か解らない言葉を言っていたけれど、誰の代名詞なんだ?
「あなた……どうして知っているのよ」
「知っている? ああ、別にいいじゃないか。その情報の出どころくらい。君に言ったところで何も変わらないけれど、だからこそいう必要は無い。だから僕は言わない。代わりに、サリー先生にしてあげた魔法の説明をしてあげるよ」
そう言ってルイスは鼻で笑った。
「サリー先生にかけた魔法は『ダークネス』。名前を聞けば解るかもしれないけれど、五感を封じ込める魔法のことだよ。残念だったねえ! 突然やってきた先生は救世主になるかと思っていただろうに、五感を封じる魔法でいとも簡単に無効化されてしまうのだから! アハハハハハハ!」
ルイスは高笑いする。
確かに、僕たちの置かれた状況は最悪の一言で説明できる。それほどにひどい有様だった。
メアリーとルーシーの実力を僕は知らないけれど、一年生ということを考えるとそこまで強力な錬金術は使えないだろう。僕は言わずもがな、サリー先生が一番の実力者だったのに目と口を潰されてしまってはもう何も出来ない――。
(フル、聞こえるかしら?)
それを聞いて、思わず僕は耳を疑った。
だってその声はサリー先生の声だったのだから。サリー先生は、正確に言えば、脳内に声を伝達させていた。テレパシー、とでも言えばいいだろうか。
僕は思わず声を出してしまいそうだったが、すんでのところで抑える。だって、それがばれてしまえば気付かれてしまうからだ。五感を封じ込めたにも関わらず、テレパシーで疎通ができると解れば、もしかしたらそのままサリー先生を殺してしまうかもしれない。
(先生、大丈夫ですか?)
だから僕も脳内に声を出すことで、それにこたえようとした。果たしてそれでテレパシーの使用方法として合っているのか解らないけれど、とにかく今は必死にサリー先生の言葉に答えようと思ったからだ。
(ええ、大丈夫よ。……と言っても、やっぱりあのルイスの言った通り、五感は全部封じられちゃったけれどね)
封じられちゃった、って随分軽い説明になるんだな。そう思ったけれど、それは言わないでおいた。
「さて……どうしてくれようかなあ? あとは、無力化しているに等しい三人だけだし、どうとでもなるよね」
「おぬし、ここがどこだか忘れているようだな?」
すっかり誰も言っていないけれど、発言に暫く参加してこなかった村長が口を開いた。
「部外者は黙っていてもらおうか。それとも、死にたいのか?」
「この村でそんなことをしている時点で、この村の長である私は部外者ではないと思うがね?」
「屁理屈を」
「さて、どうかな?」
そう言って、村長は手を合わせる。
「……まさか」
それを見たルイスの目が丸くなる。
「先住民族は魔法や錬金術など使えないと思っていたか? だとすればそれは大きな間違いだよ。……食らえ!」
そして、手を放すと――村長の両手から、炎が放たれる。
距離にしてほぼゼロ距離。避けようにも防御しようにも、時間があまりにも足りなかった。
そしてルイスはその炎をモロに受けた。ルイスの周りが白い煙に包まれて、いったいどうなったか解らなくなる。しかしその場は見守るしかない。そこで動いて煙の中に入ってしまうと敵の思う壺だ。
だから僕もメアリーも、もちろんルーシーもほかの人も、その煙が晴れるのを待つしかなかった。
(……まだ反応があるわ)
いち早くそれに気づいたのはサリー先生だった。
(サリー先生、五感が封じられている今、どうして解るのですか?)
(五感を封じられたとしても、感じることは出来る……。超音波と同じ仕組みかしらね)
超音波、ですか。
まあ、それは別にいいのだけれど。超音波で跳ね返ることで、位置を把握するシステムなら前の世界でもイルカが使っているとかで聞いたことはある。だから理解できないことではないし、理解したくないわけではない。
「……気を付けろ、メアリー、ルーシー。もしかしたらまだ……生きているかもしれないぞ」
「ほう。気付いていたか、まだ生きているということに」
その声を聴いて、冷や汗をかいた。
同時に、いつ攻撃が来ていいように構えをとる。
煙が晴れていくにつれて、ルイスの状況が見えてくる。
ルイスは翼を使って、炎を防御していた。翼に傷こそ負っているものの、まだ戦える様子だった。
「残念だったな、村長……。どうやらあの魔法で私を倒すことができると思っていたようだが、それは間違いだ」
「倒せるものではないと思っていたが……まさかこれほどまでとは」
「ここでは舞台が狭い。戦いの場を移すことにしようか、予言の勇者よ」
「なんだと?」
唐突にそう言われて、耳を疑った。
急に場所を移動しようなどと、そんなことを言っているということは、余裕がまだ残っているということだろう。だとすればかなり厄介だ。
村長はもう疲弊してしまっているし、ルーシーとメアリーもどこまで戦えるか解ったものではない。となると、あとは……。
(フル、あなたにお願いがあります)
「?」
突然サリー先生がそんなことを言い出したので、僕は首を傾げた。
(なんでしょうか?)
(どうやら未だ気配は感じとれるようです。……ですが残念なことに、通常の状態では超音波が何かに干渉してしまって届きません。要するに位置が把握できないのです。ですが、先ほどの状態ならば干渉は無かった……。言いたいことが、解りますね?)
いいえ、全然わかりません。
(……つまりですね、気を引いてほしいのです。攻撃をする。それにより相手が防御する。すると干渉が外れるので位置を把握することができる。それを狙って攻撃をする。……相手が超音波で位置を把握することを知らなくて助かりました。もし知っていたらこの戦法が通用しませんからね)
(ですが、武器は?)
(出発前に渡した爆弾があるでしょう? 本来は動物を脅かす目的に渡していますが……きっとそれを使えばヤツの集中が途切れるはず)
「……成る程」
僕は考えた。それは確か全員で持っているから、合わせて十五個の火薬玉――爆弾がある。それを使えば少なくとも気を削ぐことは出来るだろう。そしてその隙を狙ってサリー先生が攻撃をする。――完璧な作戦だった。
僕はメアリーとルーシーを集めて、耳打ちした。
教えることは手短に、先ほどの作戦について。
「ええ? そんなことができるわけが――」
「解ったわ、フル。サリー先生に信頼されているのだから、しっかりやらないとね」
ルーシーとメアリーの反応は対照的だった。
だが、この状況なら普通はルーシーの反応が一般人的反応だと思う。メアリーの反応のほうが頼もしいといえばそうなのだが、一般人的反応かといえばそうではない。
「それじゃ、行くよ。作戦開始は、アイツが広場へと到着した瞬間。チャンスは限られている。だから、真剣に挑まないとこっちがやられる。いいね?」
こくり、と最初に頷いたのはメアリー。
それに合わせて、ゆっくりと頷いたのはルーシーだった。
「それじゃ、幸運を(グッドラック)」
そうして作戦決行の舞台へと、僕たちは進む。
この作戦が無事に終わることを祈って、僕たちは広場へと向かうため、村長の家の外へと一歩足を前に踏み出した。
_ 広場に到着すると、すでにルイスがスタンバイしていた。
「遅かったな。命乞いは済ませたか?」
サリー先生もすでに外に到着している。いつ狙ってもいいように錬金術を行使する準備をしているのだろう。
「……どんな作戦を実行するのか知らないが、いまさら命乞いをしても無駄だということは理解しているだろうな?」
「当たり前だろう。だから、僕たちはお前の前に立っているのだから」
それを聞いたルイスは鼻で笑った。
「……フン。その態度がどこまで保てるか見物だな」
そう言ったのを合図に、僕たちは――三つに分かれた。
「なんだと? いったい何を……」
そしてそれぞれの位置に到着して、火薬玉を投げつけた。
火薬玉はルイスの身体に衝突し、破裂する。火薬玉はあくまでも驚かす程度しか威力がないため、殺傷能力は殆ど無い。
しかしそれを防御するために翼を使った。
それがルイスの運の尽きだった。
(見えた!)
それがサリー先生のテレパシーで聞こえた言葉だった。
そしてサリー先生は的確に、ルイスの居る方向を向いて、両手を向けた。
刹那、ルイスの頭上に浮かび上がった雷雲から雷が撃ち落とされ、見事にそれに命中した。
「がああああああ!!??」
ルイスに効果は抜群だったようだ。ルイスはもがき苦しみながら、その身体を燃やしていく。
しかしながら、同時に彼が立っていた石像にも火が燃え移っていた。
「……くく、まさか斯様な手段で倒されることになるとは思いもしなかったぞ。お前たちの弱い戦法がどこまで通用するのか……見物だな。まあ、あの兄妹に出会えば、お前たちの表情もすぐに苦悶のそれに代わるのだろうが……」
「兄妹?」
「十三人の忌み子の中でも最強と言われた兄妹であり、『リバイバル・プロジェクト』の中核を担っていた……とも言われている兄妹。そうだな、名前だけでも教えてやろう」
燃えている身体ではあったが、それでもルイスは話を続けていた。
倒れつつも、その言葉を口にした。
「その名前は……イルファ……。覚えておくんだな、お前たちを絶望に叩き込む存在の名前だ。ハハハ、ハハ、ハハッハハハッハハハ!!」
そして、もうそれ以上、ルイスは何も言わなくなった。
_ ◇◇◇
サリー先生は村長に頭を下げる。
あれから。
ダークネスをかけられて五感を封じられていたサリー先生を救ったのは、トライヤムチェン族の村長だった。村長は儀式を台無しにされてしまったことを怒らなかった。怒るのではないかとちょっと覚悟していたが、いざされないとなると逆に怖くなってしまう。
「それと、少年たちよ。儀式が台無しになってしまったということ、決して悪いと思わなくていい」
「え……?」
「君たちは悪くないのだよ。儀式はまたやろうと思えばいつでもできる。昨日は乱入者が居たから出来なかったが……また条件さえ一致すればいつでもできるからね」
そう言って村長は柔和な笑みを浮かべた。
それを聞いた僕は内心ほっとしていた。何を言われるか解らなかったし、代償を求められてしまうとそれこそ何も出来ないと思っていたからだ。
「それと、予言の勇者だというのならば、これだけは覚えておいておきたまえ」
村長は僕にあるものを差し出した。
受け取って、そのものを見る。
それは小さな鍵だった。
「これは……?」
「それは我がトライヤムチェン族に伝わる秘宝の中にあった、鍵だ。いったい何の鍵か解らないが、それとともにある言い伝えが伝わっているのだよ。『予言の勇者が現れた時にそれを渡すように』と……。それがどういう意味を果たすかは解らないが、受け取ってくれたまえ。きっと、何か役立つときが来るはずだ」
「……解りました」
そして、僕たちはトライヤムチェン族の集落を後にする。
行きはルイス含め四人だったが、帰りはサリー先生に連れられて。
急いで今回の事態を報告する必要があることと、僕たちを保護しないといけないことが重なって、大急ぎで帰らなくてはならない――それがサリー先生の言葉だった。
そう言われてしまえば、僕たちはそれに従うしかない。
そう思うしか無かった。
「……それにしても」
ルイスに、トライヤムチェン族の村長が僕に対して言っていた言葉。
予言の勇者。
僕は、この世界では僕が思っている以上に重要なキャラクターなのかもしれない。
そういう思いを抱きつつ、僕はラドーム学院へと向かう帰路に着くのだった。
僕たちが学校へ戻るまでの道のりは、簡単に説明することは出来ない。
なんというか、あの体験は実際に体験してみないと、きっと共感することが出来ないだろうと思ったからだ。
「……わたし、初めて転送魔法を使って移動したわ。すごいんですね、先生!」
メアリーが興奮しながら話しているように、僕たちは転送魔法を使って学院まで移動することが出来た。
緑の光に包まれて、目を開けた先にはいつもの教室が広がっていた――という算段だ。
「転送魔法を使うのは、まだまだあなたたちに難しいことだとは思うけれど、そう悲観することは無いわよ。これは努力を積めば、簡単に習得できる魔法の一つなのだから」
「へえ……」
メアリーは目をキラキラさせながら、サリー先生を見つめていた。
「まったく、メアリーの魔法オタクには目を見張るものがあるよ」
「あら? でも私は錬金術が好きなのよ。魔法が好きなのはただ単に錬金術に近いものを感じているから。錬金術はバリエーションが正直言って少ないからね。魔法も一緒に使うことが出来ればとても便利ではあるのだけれど……なかなかそうもいかないのよね」
「ダブルスタンダードを持つ人間は、そう多くありませんからね」
サリー先生の言葉を聞いて、僕は頷いた。
ダブルスタンダード。
二重標準、と言えばいいだろうか。簡単に言えば魔法も錬金術も一流のレベルまで鍛え上げる人間のことを言う。はっきり言って鍛え上げることだけならばそう難しいことではないのだが、しかしながら錬金術も魔法も使いこなせる欲張りな人間になることは簡単ではない。
「錬金術も魔法も、似たような学問であることには変わりありません。しかしながら、だからといって誰も魔法も錬金術も使えるのかといえば、そうではありません。むしろ、それができる人間のほうが一握り……それは一種の才能とも言えますから」
「才能、ですか……」
僕はサリー先生の言葉に、そう続けた。
「……サリー先生、私たちは今からどこへ向かうんですか?」
そうだった。
僕たちは教室に到着してから、休むことなくある場所へ向かって歩いていた。
残念なことに僕たちはその目的地がどこであるかを知らない。知っているのはサリー先生だけだった。だからといって、サリー先生のことを信用できないわけではない。むしろ信頼しているといってもいい。
先ほどの戦いで、サリー先生は僕たちを守ってくれた。
それだけで僕はサリー先生を信頼することの理由たるものと言えた。
「着いたわ」
そこにあったのは石像だった。
図書室に入ったときには、本でも読むのかと冗談を言いそうになったが、真剣に歩くみんなの表情を見ているとそうも言えなかった。そう冗談を言える雰囲気ではなかった、と言ってもいいだろう。
石像に触れるサリー先生は、小さくつぶやいた。
「フル・ヤタクミ、メアリー・ホープキン、ルーシー・アドバリーの三名をお連れしました」
そう言ったと同時に、石像がゆっくりと競り上がっていった。
「うわあ……」
こんな仕掛けは見たことが無かった。
そしてそれはメアリー、ルーシーも同じだったようだ。
メアリーは手で口を押えていたが、ルーシーはぽかんと口を開けて呆然としていた。
自分たちの良く知る空間にこのような大仕掛けがあるとは思っても居なかったのだろう。
「……さあ、下りましょう。この先にあなたたちを待つ人が居ます」
石像の下には階段があった。延々と地下へ続いていく階段。
それを見て僕はどこか不気味な様子に思えたけれど――しかし僕たちは先に進むしかなかった。
その先に何があるのか、知らなかったけれど、僕たちに退路なんて残されていなかった。
_ ◇◇◇
_ 階段を下まで降りると、そこには木の扉があった。
ノックをして中に入ると、そこは大きな部屋が広がっていた。図書室の地下にこのような空間があるとは知らなかったので、僕は心の中で驚いていた。
「フル・ヤタクミだな」
そこに居たのは――老齢の男性だった。
それを見たメアリーとルーシーはすぐに頭を下げる。
「校長先生……。ということは、まさかここは」
「はっはっは、そう緊張せずとも良い。ここは私の部屋だ。それにしてもみな、よく頑張ってくれた。サリー先生から話は聞いておるよ。ルイス・ディスコードという脅威を退けることが出来た、と」
退けた、というよりもあれは殺した――ほうが近いかもしれないけれど、とは言わないでおいた。
「まあ、そんなことはどうでもよい。私としては、敵が現れた時にいち早く守らなければならなかったのに、何も出来なかった……。私はそれが悔しくて仕方がなかった。どうか、今ここで謝罪させてくれ。ほんとうに申し訳なかった」
誰も、返す言葉が見つからなかった。
校長自らが僕たちに頭を下げていれば、言葉が見つからないと思うのは当然のことだった。
しかし、
「ヤタクミ」
その静寂を、僕の名前を呼ぶことで、校長自らが破った。
「何でしょうか」
僕は名前を呼ばれたので、それにこたえる。
「君は、なぜルイス・ディスコードに襲われることとなったのか知りたくはないか」
それを聞いて一番驚いたのはサリー先生だった。
「校長、それはつまり……!」
サリー先生がこれ以上何かを言う前に、校長が自らの手でそれを制した。
「もう隠し通せないだろう、ここまで来て。いずれにせよ、私は隠すつもりなど無かったがね。もっと早く、本人たちに伝えてあげるべきだと思っていた。……後悔はしないね? 例え、君たちが知る真実が、残酷なものであったとしても、それを最後まで聞く覚悟は出来ているかな?」
「当然です」
そう答えたのは、僕でもルーシーでもなく、メアリーだった。
「ほう……」
校長は顎鬚を弄りながら、笑みを浮かべる。
続いて、ルーシーがはっきりと大きく頷く。
最後に僕が――しっかりと校長の目を見て、
「お願いします、校長先生。僕たちに……いいえ、僕に教えてください。なぜ、ルイス・ディスコードは僕たちを襲ったのか、その理由について」
「いいだろう。しかし、これから話すことはそれなりに長くなる。サリー先生、椅子を彼らに渡したまえ、私も立ちながら長話はしたくない。だから私も椅子に座らせてもらうことにするよ」
そう言って校長は木製の椅子に腰かける。リクライニング付きのゆったりとした椅子だ。安楽椅子の一種と言ってもいいかもしれないが、揺れる機能がついていないから、正確には安楽椅子とは言わないのかもしれないけれど。
サリー先生がどこかから椅子を持ってきたのを見て、僕たちは頭を下げた。ありがとうございます、という感謝の気持ちを伝えることは、どんなことよりもシンプルであり、どんなことよりも大事だ。
「……それじゃ、話を始めよう。そしてその前に、一つの結論を述べることにしよう。フル・ヤタクミ。君は……予言の勇者だよ。何百年も前から語られていて、それが覆されたことのない『伝説の予言』とも言われているテーラの予言から来ているものだがね。君の目的は、テーラの予言によればただ一つ。いずれやってくると言われる世界の破滅から、世界を、人々を、救う。いわゆる君は……言い方を変えよう、英雄なのだよ」
_ 校長が言った長い話を要約すると、こういうことだ。
ガラムド暦元年に、偉大なる戦いが起こる。偉大なる戦いでは、オリジナルフォーズが世界を破滅へと導いた。正確に言えばそれは未遂に終わり、神ガラムドがそれを封じ込めたと言われている。
ガラムドが神と呼ばれているのは、これが一つの大きな原因であると言われている。ほかにもその時代に人々を平和へと導いた『平和の象徴』としても語られているらしいが、それは今語るべきことではないので、割愛する。
ガラムドの子供は、二人生まれた。その二人がそれぞれ祈祷師と祓術師という二つの職業に就くことになった。もともとはどのような役職を作るか考えたガラムドが悩んだ末の結果であり、世界にあるあらゆる役職の上に立つ存在であると認識させるために躍起になっていたとも言われている。
祈祷師は神の言葉を代行する存在なのだという。そう考えると、成る程、祈祷師の初代は神を母親に持つのだから、まさに神の代行人という立ち位置に立っていても何らおかしくは無いのだろう。
祈祷師は力をつける一方で、祓術師は力を失っていく。
その象徴的な出来事がリュージュの二大予言だと言われている。今はスノーフォグの王となっているリュージュが予言した二つの事件。そのどれもが実際に起きて、多数の死者を生み出した。しかしながら、リュージュの予言によりそれによる被害者が少なく済んだとも言われており、のちにリュージュは一つの国を手に入れるほど信頼されるようになった。
リュージュの躍進とともにほかの祈祷師も高い地位に着くようになる。そのころからさらに祈祷師と祓術師の格差は生まれ、軋轢も酷くなってきたという。
「はっきり言って、あれはひどいものだったよ。私は祈祷師という地位に立っていたからこそ、あれを客観的に見ることは出来なかった。だが、助けることは出来なかった。助けることで私もその地位に転落するのではないかと思ったからだ。今思えば、恥ずかしいことなのだがね」
校長の話はさらに現在へと時系列を近づけていく。
祈祷師の一人、テーラはある予言を世界に発表した。
「それは世界を破滅へと導く予言だった。あれが発表された当時はほんとうに酷いものだったよ。だって考えてみれば解る話だ。世界が破滅していく予言だと? そんなもの誰が信じる。誰も信じない。それが当然であり、当たり前のことだったよ」
確かに、世界が破滅するなんて予言はそう簡単に信じられないだろう。仮にそれを聞いていた立場だったとしても、そう鵜呑みにできる話ではない。先ずは詐欺師を言うだろう。え? 誰のことを、だって? そんなこと、決まっているだろ、その予言をした人物を、だ。
「そうだ。その通りだ。テーラは詐欺師扱いされたよ。祈祷師の地位を下げるつもりか、と祈祷師も批判していた。だが、私は彼の予言を信じていた。ほんとうに起きるのではないか、と思っていたのだよ」
「どうして、そう思うのですか?」
メアリーの問いに、校長はしっかりとした口調で言った。
「私も見たからだ。――世界が滅びる、その日を」
嘘を吐いているようには見えなかった。
それどころか、はっきりとしている口調は、自信の象徴に見えた。
「その夢は今もはっきりと覚えているよ。業火に燃やされたハイダルク城、泣き惑う人々、そして区々を破壊し、我が物顔で闊歩するのは、見たことのない巨大なバケモノだった」
「バケモノ……メタモルフォーズのことですか?」
「知っているのかね?」
「ええ……。トライヤムチェン族の集落で、村長から聞きました」
「そうか」
校長はそれしか言わなかった。
「……予言を信じる人間は、別に私だけではなかった。しかしテーラを批判する人間からすれば、それは少数派に過ぎなかった。だからこそ、だからこそ……テーラは悩まされたのだろう。それを発表してよかったのかどうか、悩んだことだろう。けれども、世界の危機を予言したのならば、それは紛れもなく、人間に対する警鐘を鳴らしたことに等しい。だからこそ、人々はそれに気づきたくなかったのだろう。だが、それをテーラははっきりと人間に告げた。『四百年後、世界は滅びる』と」
四百年。
その時間はあまりにも長く、そして何が起きてもおかしくない時間だった。
その時間ののち、世界が滅びる――突拍子もないその予言を信じるほうがおかしな話かもしれないが、仮にそれが正しいものであるとすれば、四百年前にその予言をすることは、やはり祈祷師の力を確固たるものとするに相応しいものだったのだろうか。
「……テーラは耐えきれなかったのだろう。その翌年、死んだよ。海に落ちた。そして、テーラは遺言を残していた。そこにはこう書かれていた」
その予言は間違いではないが、一つ人間にとっての『希望』が残されていることもまた事実である――と。
「希望?」
「そう。それこそが……勇者の存在だ。三つの武器を使い、それぞれの術に長けた三人組。正確に言えばそのうち一人が勇者で、残りの二人は勇者に率いられた存在であると言われているがね。……まあ、それも眉唾物とも言われている。なにせ実際の遺言が残されていないのだ。だから、当初は……今もそうかもしれないが、テーラの弟子が自らの地位を上げるために死んだ師匠を利用した、なんてことも言われた」
「そんな酷いことを……」
「祈祷師はほかの人間に比べれば圧倒的に高い地位を手に入れていたが、それと同時に妬む人間もやっぱり多かった。神の血を引き継ぐといってもそれは二千年も昔の話。そんなもの、とっくに途絶えていてもおかしくない。だのにどうして祈祷師は未だにその地位を確固たるものとしているのか? とね」
二千年も自分の祖先が確定している、と考えれば凄いことだとは思うけれど、やはりそういう考えにはなかなか至らないらしい。
「まあ、テーラの予言がどこまでほんとうだったのかは解らない。ただ、これだけは言えるのだよ。テーラの予言があった年……それは、今年から四百年前のことだ。すなわち、テーラの予言が本当であれば、今年に世界は破滅へと向かっていく。そしてそれを守るべく勇者がこの世界にやってくる」
「それが……僕だと?」
馬鹿馬鹿しい。
そんなことがほんとうに有り得るのか?
いや、まあ、異世界に召喚――その時点で何となく普通ではないと思っていたけれど、まさかここまで普通じゃないなんて。あまりにも出来すぎている。まるで最初からこう進むようにレールが敷かれていたかのようだ。
まあ、そんなことはどうでもいい。
問題は、それが本当かということについて。
予言の勇者――それが僕であるならば、僕は世界を救う英雄になるということだ。
「……一つだけ、質問があります」
「言ってみたまえ」
「どうして、僕を予言の勇者だと断定するのですか。断定するからには、それなりの証拠があると思うのですが」
それを聞いてメアリーとルーシーは頷く。やはり彼女たちもそのあたりについて疑問に思っていたらしい。しかし相手は校長だ。そう簡単に質問できる事項ではなかったのだろう。
しかし、僕は当事者だ。どんな質問でもする権利があり、ある程度の解答を得る権利がある。だから僕はズバリ質問した。どうして――僕が予言の勇者だと断定出来たのか、そのことについて。
「予言の勇者は左利きだと言われている」
深い溜息を吐いたのち、校長はそう言った。
左利き。
またの名をサウスポー。
確かに僕は左利きだ。サウスポーだ。だが、それがどうしたというのだろうか? 左利きは珍しいことなのかもしれないが、生まれる確率はそう珍しくないはずだった。
いや、もしかしたらそれは僕がもともと生まれた世界だけの事象であって、この世界では違うのかもしれないけれど。
「左利きは神の一族だけが得ることのできる、実に特殊なものだよ。一般人が左利きにしようとしても、なぜか左利きにすることは出来ない。もちろん、フル、君が一族の一人である可能性も十分有り得たが、そんな人間が生まれたという情報もない。となると……」
予言の勇者しか、その可能性は有り得ない――ということか。
僕は校長の話を聞いて、そんなことを思った。
「……まあ、理解できないのも解る。急にこんなことを言われて困惑することも致し方無いだろう。だが、だからこそ、理解してもらいたい。君が世界に齎すものは、君が思っている以上に凄いことだということを」
_ ◇◇◇
_ 寮は地下にあるため、空が見えない。
だが、今日は特別に上級生の居る寮の空き部屋を使ってもいい――先生たちにとってもそちらのほうが狙われたとき対応しやすいのだという――とのことで、僕たち三人は同じ部屋で寝泊まりをすることになった。
「それにしても、上級生の部屋が空いているからと言って、三人を一つの部屋に押し込めるのはどうかと思うけれどね」
ルーシーの言葉ももっともだった。実際、この部屋は僕が寝泊まりしていた部屋と比べれば広い。だが、それも限度がある。二人くらいなら何とかなるだろうが、三人となれば話は別だ。やはり三人ならばもう少し広い部屋か、せめて二部屋にしてほしかった。
「まあ、でも、ルーシー。贅沢は言えないわよ。せっかく先生が私たちを守ってくれて、そのために特別措置としてこの部屋を使っていいとなったんだから。ね、楽しみましょう? 辛気臭いとなんでもやっていられなくなるから」
そういうものだろうか。
正直、僕はまだ気持ちの整理がついていなかった。
校長から言われたこの世界に召喚された真実。それを成し遂げるために、僕はどうすればいいのだろうか?
いや、そもそも。
僕はほんとうに予言の勇者なのか?
断定しているだけで、ほんとうはただの人間なのではないか?
もしそうであるならば、きっと肩透かしだと言われるに違いない。そんなことは言われたくない。たとえ、『あなたたちが勝手に勇者だと崇めたのでしょう』と僕が否定したとしても。人間はどの時代だって、祭り上げるだけ祭り上げて、実際違ったらあとはポイ捨て。昔そう崇めていたかもしれないが――なんてことでお茶を濁す。そういうものだ。
「ねえ、フル」
メアリーが僕のそばに寄ったのは、そんな時だった。
僕は一人でベランダから月を眺めていた。この世界の月は、なぜか知らないけれど二つある。一つはもともとの世界にあったような、とても見覚えのあるそれだが、もう一つは――少し平べったく見える。けれどもこの世界の人間はそれも『月』なのだという。あれも衛星――星なのだろうか? きっとそう質問しても、それをほんとうの意味で答えてくれる人間がどれほどいるだろうか。そんなことを考えていた。
それは現実逃避に過ぎない。
僕が校長から『予言の勇者』と言われた――紛れもない事実から目を背けるために、必死に考え付いたことに過ぎない。
「あなたが来ること……正確に言えば、あなたが別の世界からやってきたということ、実は私は知っていたの」
「え?」
それは予想外だった。
というかここにきて新事実が判明しすぎだ。
「なんとなく予想はつくと思うのだけれど……実は私はもともと祈祷師の子供だったのよ。祈祷師の子供、というだけで箔が付くものなのかもしれないけれど、私は母親の顔を見る前に――捨てられた。いや、それは言い過ぎかもしれないわね。正確に言えば、ほんとうの母親の顔を知らないのよ。知っているのは、私を育ててくれた叔父さんと叔母さん……もちろん、その二人は血のつながりなんて一切ないのよ。けれど、捨てられていた私を、ここまで育ててくれた――」
「顔も知らないのならば、なぜ君は母親が祈祷師だと知っているんだい?」
僕はその話を聞いていればきっと自然に浮かんでくるだろう疑問を、メアリーにぶつけた。
メアリーもその質問は想定済みだったのだろう。すぐに頷くと、ゆっくりと澱みなく答えていく。
「私がこの学校に入学する一年前、突然父が私を訪ねてきた。当然叔父さんと叔母さんは驚いたわ。十数年前に私を捨てておいて、突然やってきたのだから。けれど、父は詫びた。そして、私をずっと引き取っていてほしいと言ってお金を渡した。それは、私の養育費としては将来分も加味して充分すぎるほどだった、そう言っていたわ」
「メアリーの父はお金持ちだった、ということか?」
「解らない……。けれど、その時に父は話してくれた。私の母は祈祷師なのだ、と」
「さすがに、自分の子供を捨てた理由は教えちゃくれなかったわけか」
僕はそこまで言って、自分の口を手で覆う。言っていいことと悪いことがある。今のは確実に後者――悪いことに属する。メアリーが今の言葉を聞いて烈火のごとく怒ったとしても、僕は何も言えない。それほどのことを、僕は自然と口に出したのだから。
しかし、メアリーはそれを聞いて一笑に付した。
「そうだよね……。やっぱりフルもそう思うよね。安心して、昔の私もそんなことを思って訊ねたわ。けれど、答えてくれなかった。当たり前といえば当たり前かも知れない。自分の娘に、娘を捨てた理由を訊ねられて答えられるわけがない。それは今思えば、当たり前のことだったのよ」
果たして、それはほんとうにそうだったのだろうか。
今となってはメアリーの父親にそれを聞く機会など到底残されてはいないわけだが、とはいえ、メアリーの父親がそれを隠していたのには、きっと何らかの理由がある――僕はそう思わずにはいられなかった。
「ところで、メアリー。それと僕がこの世界にやってくることを知っていたこと。それはどう繋がっていくのかな?」
「あ……。ごめんなさい、実は夢の中でね、神様を見たのよ」
「神様……って、ガラムドのことかい?」
僕の言葉に、こくり、と頷くメアリー。
「夢の中で、神様は私に言ったのよ。予言の勇者を手助けしろ、って」
神様直々の言葉とは、参ったな。
そんなに世界を破滅させたくないのなら、神様が自ら手を下せばいいのに。
そんなことは、口が裂けても言えないと思うけれど。
「だから私はフルがやってきた瞬間、ピンときたわ。あ、予言の勇者がやってきたの、って」
「けれど君は初日、僕を起こしてきたよね? まるで僕がずっとこの世界に住んでいたかのような扱いをしていた。それは、僕がこの世界にやってくることを知っていて、あえて演技をしていた……そういうことなのかい?」
核心を突く言葉だったのか、メアリーは俯いてしまった。
「……メアリー、もし気分を害してしまったのならば、それは申し訳ない。けれど、僕は知りたいんだ。もしそうならば、うんと頷いてくれないか」
そして、メアリーはゆっくりと――ゆっくりと頷いた。
「なあ、そろそろ眠らないか? 明日に響くぜ。明日の夕方にはみんな帰ってくるんだろ? ……正直僕だってこんな雰囲気壊したくなかったけれど、言いたいことだけは言わせてもらうよ。これで睡眠不足になって授業中に眠ってもらっては困るからね」
いいタイミングで、ほんとうにいいタイミングでルーシーが入ってきた。
僕はそれを聞いて、微笑む。
「これをバッドタイミングだと思うなら、君の目は節穴だぜ? 今は超絶好のチャンスだった。いい機会だよ。話もうまい具合に切れたし。……さて、それじゃ寝ることにしようか、メアリー」
「そうね」
メアリーは短く言うと、僕よりも先に部屋の中へ入ろうとした。
「……それにしてもメアリー」
「うん?」
メアリーは振り返る。
僕はメアリーのほうを向かないまま、二つの月を見て、言った。
「今日は、月がほんとうに綺麗だね」
「そうね、ほんとうに。いつもなら、こんなに明るくならないのに。それじゃ、私はもう中に入って寝る準備をするから。フルも早く寝てね」
「了解」
そう言って頷いて、僕もメアリーの後を追うように、部屋の中へと入っていった。
ほんとうに月が綺麗な、夜だった。
こんな夜は僕のいた世界でもあまり見かけなかったかもしれない――そう思って、名残惜しく、僕はベランダの扉を閉めた。
_ ◇◇◇
_ 二日後。
二泊三日と言われた研修も終わり、普通ならばもう戻ってきていてもおかしくないはずだった。
しかし、誰も戻ってくることは無かった。
「……誰も来ないね」
ルーシーは言った。その言葉に僕は頷く。
確かにその通りだと思う。ほんとうにどこへ行ったのだろうか? まったく理解できなかった。
「……みなさん、おはようございます」
サリー先生が入ってきて、いつもと様子がおかしいことに気付く。
サリー先生はこの事実について気付いているということなのだろうか?
「学生全員、どこへ消えてしまったのか……あなたたちはそれについて聞きたいのでしょう」
サリー先生は唐突に核心を突いた発言をした。
確かにそれは聞きたかった。どうしてこんなことになってしまったのか――理解できなかったそのことを、もし知っているというならば教えてほしかった。
「……きっと、気付かれたのでしょう。この世界を滅ぼしたいと願う存在が、この世界を救うと言われている勇者が呼び出されたということに」
「勇者が呼び出されたこと……そんなこと、解るんですか?」
「それは、はっきり言って私が言いたいわ。けれど、そうなのでしょう。だって学生は戻ってきていない。予言の勇者が復活したことは、私たちしか知り得ないはず。けれどこんなことになってしまった。……原因は一つしか考えられませんよ」
それを聞いて、僕は、僕がその原因を作ってしまったのだと思い、深く後悔した。
はっきり言って呼び出された側である僕が迷惑を被っているわけだが、この世界の人間にはそんなことどうでもよいことだ。人間は誰も、自分さえ良ければいいと思っているのだから。
「そして、校長にこの事実をお話ししました。すると校長はこう言いました」
「ハイダルク城に保護してもらう。そのために、君たちにはフィールドワークをしてもらうのだよ」
サリー先生の言葉をさえぎるように、誰かの声が聞こえた。
その声がしたほうを向くと、扉のそばに校長先生が立っていた。
「校長! どうしてここに……」
「先生を通した発言を聞いてもらうよりも、君たちに対して私の発言を直接話したほうがいいと思ったのだよ。突然の方向転換で、ほんとうに申し訳ない。ほんとうならば、私の手で君たちを守りたいものだが……それにも限度があることもまた事実だ。それについては、申し訳ないと思っている」
「いえ、別に……」
「だが、学生を狙った後は、君たちを狙うはずだ。学生を吟味して、予言の勇者ではないと判別しているだろうからな。正確に言えば、予言の勇者かどうか選別していると言ってもいいだろうが……その細かい話についてはどうでもいいだろう。学生のことについては、私が全力で助け出す。それが、私の役目であり責務だからだ」
校長先生はそう言って、大きく頷く。
それに続いてサリー先生も大きく頷いた後、僕たちのほうに向きなおした。
「そういうことです。私たちがあなたたちを守ることが出来ないのはほんとうに残念であり心苦しいことではありますが……いつか必ず、あなたたちが戻ってこられるような学院にします。それが私たち先生の役割です」
つまり恒久的ではなく、一時的な措置。
サリー先生はそう言っていた。
ならばそう難しいことではないのだろうか? 実際、ハイダルク城までどれくらいの距離があるのか判明していない現状、途方もない未来について予想しているだけに過ぎないけれど。
「私の古い友人がハイダルク城……ああ、今あそこは『リーガル城』と呼ぶのだったか。つい古い名前で呼んでしまうな。まあ、それについてはどうだっていい。そこに古い友人が居て、そこに匿ってもらうことにした。どれくらい時間がかかるかは解らないが……君たちに危機が迫らないように、我々も頑張るよ」
「ということは……」
メアリーは何かを察したらしい。目を細めてサリー先生に問いかける。
「サリー先生、校長先生。私たちは……この世界を救うために、旅に出ろ……ということなのですか?」
サリー先生も、校長先生も、その言葉について明確な解答を示すことは無かった。
ただ狼狽えるような表情を、仕草を、雰囲気を見せるばかりだった。
_ ◇◇◇
_ 次の日は、とても寒かった。
ベッドから起き上がりたくなかった。
昨日のような部屋ではなくて、僕のためにもともと用意されていた部屋だった。
ベッドのかけ毛布は今の僕にとってとても重たく、起き上がるのを拒むようだった。
そして僕自身も、起き上がることを拒んでいた。
ノックが聞こえたのは、そんな時だった。
「フル、入ってもいい?」
そう言ったのは、メアリーだった。
僕は何も答えなかった。答えたくなかった。答えられなかった。きっと恥ずかしい解答しかメアリーに提示することが出来なかったからだ。
するとメアリーは勝手に中に入ってきて、ベッドの上に腰かけた。
僕はベッドの中に引きこもり、メアリーはベッドの上から僕に問いかける。
「……ねえ、フル」
「何だい」
「……世界を救うとか、勇者とか、そういうこと私はあまり解らないけれど」
そう前置きして、メアリーは言った。
「そういうこと、私は素晴らしいと思うな。自分の役割がある、ということを言えばいいのかな? まあ、誰も役割が無いことは無いと思うけれど、あなたの役割はとても素晴らしいことだと思うのよ」
「……解らないくせに、何を言っているんだよ」
「解らないからこそ、よ。あなたのことは解らない。けれど、それは同時に逆のことでも言えるでしょう? 私のことを、あなたは解らない。そしてあなたのことを、私は解らない」
「そうなのかな……」
けれど、突然勇者だと言われて動揺しないほうがおかしい。
そして学生が消えた原因が――僕かもしれないと言われて、悲観しないほうがおかしいのだから。
おかしくない。おかしくない。
僕は普通だ。正常だ。
これこそが正常であり、そう考えないほうが異常なのだから。
「ほんとうに、そうなのかな」
メアリーは、さらに僕に疑問を投げかける。
「仮にあなたがそう思っていたとしても、それは間違っていることだと思うよ。きっとあなたはそれが普通だと認識しているのかもしれないけれど、私から見ればそれは異常だと思う。そもそも、誰もが見て『普通』なんてそう簡単に見つからないことだよ。だからこそ、あなたが勇者として選ばれて呼び出されたことも、私たちがあなたについていくということも、きっと最初から決まっていたのよ」
メアリーは、優しい。
彼女は巻き込まれた側であるというのに、どうして彼女はそこまで僕に親身にしてくれるのだろうか。
そんな彼女の優しさが――とても嬉しかった。
「取り敢えず、外に出ているからね。準備はもうできているからさ。あなたも準備が出来たら、いつもの教室に来てね。私とルーシーは、いつまでもあなたのことを待っているから」
そう言って、メアリーは部屋を出ていった。
_ ◇◇◇
_ 僕が教室の扉を開けたのは、それから三十分後のことになる。
扉を開けたその中には、ルーシーとメアリーが大きな荷物を持って席に座っていた。
「おはよう」
僕はただ、その一言だけを告げて、いつも通り席に腰かける。
「おはよう、フル」
「フル、おはよう」
二人はそれぞれ僕に挨拶をかける。三十分も待ったことについて何も言わなかった。
「……」
そして、沈黙が教室を包み込んだ。
誰も話したがらないし、どことなく暗い雰囲気だ。やはりみんな、怖いのだ。誰もかれも、怖い。この先どうなってしまうのか、ということについて――考えるのは当然のことだろう。
「おはようございます」
サリー先生が教室に入ってきたのはそれから五分後のことだった。
僕たちはいつものように挨拶を先生にする。
サリー先生もまたいつものように教壇に立つと、僕たちを見渡して頷く。
「どうやら全員集まっているようね。それじゃあ、今後の予定を話すわね」
そう言って、紙を広げるサリー先生。
その紙を見ながらサリー先生は話を続ける。
「リーガル城があるハイダルク本土へ向かうには、やはり船となります。本来であれば転送魔法を使ってもよかったのですが、正直なところ私の力では港までが限界です。ヤタクミは知らないかもしれませんが、港からは本土への定期船が出ています。本土まではそれを利用し、そのあとは陸路となります。まあ、そう遠くは無いでしょう。校長先生曰く、途中の町までは使いを出すと言っていましたので」
「使い、ですか」
それにしてもそんなことをできる、校長先生の古い友人とはいったい誰なのか。まさか、国王とかそれくらい高い地位の人間じゃないだろうね?
「解りましたか?」
サリー先生は一人一人の表情を見つめながら、そう言った。
「はい」
やはりどこか表情が暗い。仕方ないといえば仕方ないのかもしれないが。
「転送の魔法陣はすでに完成してあります。まずはそこまでみなさんを案内しますね」
そう言って、サリー先生は教室を出ていく。
僕たちは名残惜しく、教室を後にした。
_ 魔法陣は校庭に描かれていた。
緑色の光が淡く滲み出ているそれは、どうやらもう魔法が発動しかけているのだという。
「それでは、これに乗れば自動的に――。あとは私の『鍵』によって発動しますが」
そう聞いて、僕たちは魔法陣に乗る。
「サリー先生……」
僕はサリー先生に問いかける。
ほんとうに幸せになるのか、と。
ほんとうにこの先、平和な世界がやってくるのか、と。
言おうとしても、その質問が、その言葉が出てこない。
それを理解してくれたのか、サリー先生は頷く。
「大丈夫ですよ、フル・ヤタクミ。これが今生の別れになるわけではないのですから。すぐあなたたちが戻ることのできるようにしてあげます。ですから、そんな悲しそうな表情をしないでください。いいですね?」
「は、はい!」
その言葉に、僕はとても勇気づけられた。
サリー先生の言葉は、そういう言葉の常套句を並べただけかもしれないけれど、それを聞いてなぜかとても安心した。
そしてそれを見て――サリー先生も察したのか、その最後の『鍵』を口にした。
目を瞑り、両手を合わせる。
そのポーズはどこか、神への祈りを捧げているような――そんな感じにも見えた。
「我、命ずる。かの者が、無事に辿り着くことを――!」
そして、僕たちの視界は淡い緑に包まれた。
_ ◇◇◇
_ 船の上から見る海は、とても穏やかだった。
ゆっくりと小さくなっていく学院、そしてレキギ島を見て僕は小さく溜息を吐いた。
レキギ島とハイダルク本土を結ぶ定期船。僕たちはそれに乗って、ハイダルク本土の港町アリューシャへと向かっていた。
「船、乗ったこと無いんだよな。フルはあるかい?」
甲板に立って海を眺めていた僕に、ルーシーは問いかける。
「そうだね。僕がもともと居た世界では、船は世界中にあって、そしていろいろな航路があるからね。あとは空を飛ぶ船もあるよ」
「空を飛ぶ船、だって? そんなものがあるのか?」
ルーシーは身を乗り出して僕に訊ねる。余程空を飛ぶ船のことが衝撃だったらしい。
「まあ、その名前は飛行機というのだけれど、あれは快適だよ。けれど、船よりも大きくて船よりも早く進む。だからとても素晴らしいものなんだよ」
「へえ、それは一度ぜひ乗ってみたいものだな」
そんな二人の会話が流れていく、ちょうどそんな時だった。
_ ――唐突に、船が二つに割れた。
瞬間、僕は何が起きたのか理解できなかった。
そしてそれを部分的に理解できるようになったのはそれから少しして――正確に言えば、海に落ちたタイミングでのことだった。
「がはっ!! ……な、何で急に船が!」
「解らないよ! ええと、メアリー! メアリーは無事か!」
「ここにいるわ!」
メアリーはルーシーの後ろに居た。ほかの乗客も船員も何とか泳いでいる。どうやら無事らしい。
「けれど、ここからどうすれば……!」
まさに絶体絶命。
どうすればいいのか、すぐに冷静な判断が出来なかった。
逆にそれが命取りとなった。
目の前に出現したのは――その船を二つに割った元凶だった。
巨大な海の獣。
しかしその表情は、人間に近い――人間そのものと言ってもよかった。
牙を出して、目を血走らせ、僕たちを睨みつけている。
こんな獣が、この世界に居るのか。
そんな説明は、歴史の授業では無かったはずだぞ!
そう叫びたくても、今は無駄だし、もう遅い。
「……フル、ルーシー、潜って!!」
メアリーの言葉を聞いて、僕は言葉通りに潜る。
刹那、海を切り裂くエネルギー弾が撃ち放たれた。
その衝撃をモロに食らった僕は――気づけば視界が黒に染まっていた。
_ 目を覚ますと、そこは砂浜だった。
白い砂浜、青い海。僕の居た世界だったら、素晴らしい風景の一つだろう。
けれど、今は絶望的なそれとなっている。
僕はぎらつく太陽で目を覚ました。
太陽がとても暑い。どうやらこの世界は、寒暖の差がとても激しいようだった。
「う、うーん……フル?」
メアリーが目を覚ました。どうやらメアリーも無事のようだった。ルーシーはまだ目を覚まさないので、待機することにした。
メアリーは起き上がると、砂だらけになっている衣服から砂を払った。……そもそも、水に濡れているうえで砂がついているので、その程度でとれるわけがないのだが。それを言ったとしても、きっと彼女はそれをやめることは無いだろう。女の子というのは、そういうものと案外相場が決まっているのだから。
ルーシーもそのあと目を覚まして、僕は二人の無事を確認した。無事、と言えば少々仰々しい話になるけれど、まあ、それは表現の問題ということで。
そして、僕は、二人に問いかけるように――こう言った。
「――ここは、どこだ?」
その疑問は、少なくとも今の状況では最大といえるものに違いなかった。
海に打ち上げられて、少し休憩したのち、僕たちは探索を開始した。
まずはここがどこであるか、ということについて。
「……駄目ね。地図を見ても、ここがどこだか見当もつかない。かといって歩いていては不味いことになりそうね。有耶無耶に歩いても解決するとは到底思えない」
そう言ってメアリーは砂浜の向こうを見つめた。
砂浜の向こうは鬱蒼と生い茂った森が広がっており、そう簡単に進めるものではない。
「……ここを通れば、どこへ向かうのかしら?」
「正直な話、あまり無作為にいかないほうがいいと思うよ。……でも、だからといって、動かないわけにもいかない。いったいどうすればいいものか……」
ルーシーは手を組んで考えた。
けれど、それよりも早く――何かがやってくる音が聞こえた。
「静かに。何か聞こえる」
メアリーの言葉を聞いて、僕は耳をひそめる。
何かがこちらに近づいてくる。
かっぽ、かっぽとコップを鳴らしているようなそんな音。
けれど、それは正確に言えば――。
「やあやあ、やっと森から出ることが出来た。まったく、この馬はかなり面倒な馬であることだ……」
森から出てきたのは、馬車だった。
それもそれなりに立派な。
「……まさか馬車が森の中から出てくるなんて」
「もしや……君たちはラドーム学院からやってきた子供たちかい?」
それを聞いて、僕たちは目を丸くした。どうしてそんなことが解るのか、はっきりと言えなかったからだ。
いや、それ以上に。
その人は、信じられる人間なのか? 突然やってきて、僕たちがどこからやってきたのかが解っている。そんな人間をすぐに信じられるだろうか? はっきり言って、そんなこと不可能だ。
「……乗りなされ。扉の鍵は開いている。それに、中には誰も載っていない」
「……ほんとうですか?」
「安心しろ。取って食うわけではないし、そもそも私はラドームの古い友人だ」
ラドーム……それってつまり、校長先生の?
「だったら、信頼できるかも?」
「そうかもしれないけれど……」
メアリーを筆頭に、ひそひそ声で話し出した。そうしている理由は単純明快。聞こえないようにしているためだ。聞こえてしまえば、すべてが無駄になってしまうのだから。
それを察したのか、馬車の老人は頷く。
「まあ、疑うことも仕方ないだろう。疑うこともまた、意識としては大事なことだからな。けれど、人を信じることも時に大事だぞ」
「……どうする? フル」
ここでルーシーが僕に話題を振った。何で、ここで話題を振るんだよ、もっと考えてから僕に手渡してくれよ、もっと何かあっただろ。
……そんなことを考えても無駄だと思った僕は、あきらめた。小さく溜息を吐いて、踏ん切りをつけるしかなかった。
「そうだね。ここでずっと話をしていても無駄だ。だったら、従うしかない。遠慮なく、馬車に乗せてもらうことにしよう。正直、どこに向かうのか解らないけれど」
「そう焦ることは無いぞ、若人。私がやってきた場所は、妖精の住む村として有名な場所だよ。名前はエルファスという。そこへ向かえば、きっと君たちの身体も休まるだろう」
_ 結局。
僕たちは馬車に乗っていた。
馬車に揺られて、森の中を進む。木の枝が入ってくることがあるのではないか、ってことを考えていたのだけれど、はっきり言ってそれは杞憂だった。そんなことを考えても無駄だった、ということだ。
「馬車に乗ることが出来るとは、思わなかったよ」
「この世界で馬車を持っている人間ってとても少ないからね……。私たちも初めてだよ」
僕の言葉に答えたのはメアリーだった。
メアリーの言葉を聞いて頷く。そうなのか、この世界で馬車を持っている人間の数はそう多くない、と。正直もっと居るのではないか、と思ったけれど、どうやらまた別の考えらしい。
「それにしても、馬車に揺られるのって、とても気持ちいいのね……」
メアリーは座っていながら、伸びをした。
確かにメアリーの表情はどこか気持ちよさそうだし、僕も気持ちよかった。こんなに馬車の揺られが気持ちいいものだとは知らなかったからだ。
「……エルファスまではどれくらいですか?」
「なあに、あと一時間は軽くかかるだろう。それまではゆっくりとしていても何ら問題は無い。なんなら眠っていても構わないよ。着いたら起こしてあげよう」
眠り。
そう聞くと、途端に眠くなってくる。
なぜだろう。まあ、解らないことなのだろうけれど。長い間海水に浸かっていたから、体力が知らないうちに消費されていたのかもしれない。だったらあの時の気絶しているときに少しでも回復していればよかったのだけれど、人間というのは少々面倒な生き物だ。
そして、気付けば僕たちは夢の世界へと旅立っていった――。
_ ◇◇◇
_ 次に僕が覚えているのは、老人がカーテンを開けたタイミングでのことだった。
「そろそろ、エルファスの市内へと入っていくぞ」
それを聞いて僕は目を開ける。どうやら随分と長い間眠っていたように見えるけれど、ようやく着いたという言葉を信じるとまだ一時間程度しか眠れていないのだろう。何というか、すごく長い間眠っていたように見えるけれど、きっとそれは違うのだろう。
メアリー、ルーシーも目を覚まして大きな欠伸をした。
「まさかこんなに眠りやすい環境とはね……。馬車、恐るべし……」
どうやらメアリーは馬車に屈してしまったらしい。まあ、言いたいことは解る。そして仕方ないと思うことも事実だ。
市内へと入る大きな門――それを馬車の中から見て、とても幻想的な雰囲気が感じられた。石煉瓦を積み上げたことでできている壁よりも大きな巨木が見えているけれど、きっとあれが妖精の住む樹なのだろうか?
市内へと入っていくと、その雰囲気はがらりと変わっていく。
石煉瓦でできた質素なつくりの家、それに広い道を歩いていく人々。そしてその光景に映りこんでいる女性は、どこか露出度が高いように見える。一例をあげれば背中をぱっくりと開けたドレスを着ていることだろうか。どうしてあんな恰好を平気でできるのか、解ったものではないけれど。
「ここは西門の前なので、娼館が多いのじゃよ」
そう言って老人は笑う。
娼館――ねえ。ゲームの中でしか聞かないと思っていたよ、そんな言葉。
「なあ、娼館って何だ、フル?」
ルーシーはその言葉の意味を理解していないらしく、無垢にも僕に訊ねる。
いや、言おうと思えばすぐに教えることは出来るけれど――お前の隣には少女が居るんだぞ? しかもお前と同じ年頃の、だ。まあ、その意味は僕にもそのまま通るのだけれど。
大きな木――町の中心にあるそれの下には、一つの家があった。ほかの家と同じく石煉瓦で形成されているのだが、その幻想的な雰囲気に、思わず目を奪われた。
「ここがこの町の長老の家だよ」
馬車を止めて、老人はそう言った。
「……行こう、フル」
そう言ったのはメアリーだった。
確かに何も知らないでやってきた場所において、そのまま従っていくのはどうかと思う。緊張感もないし、皆を信じてもいつか裏切られる可能性を常に考慮しておく必要がある。
しかしながら、メアリーの言葉を聞いて――僕は小さく頷いた。
「そうだね。先ずは向かってみないと何も始まらない。きっとこの町の人はいい人だと思うから」
そう言ったのは、正直嘘だった。
ほんとうは不安ばかりだった。けれど、彼女の言葉に押されて、僕はそういうしかなかった。
_ ◇◇◇
「こちらこそ……よろしくお願いします」
今、僕たちは町長と面を向かいあって話している。
町長は椅子に腰かけて、ずっと笑みを浮かべている。それが若干気持ち悪く感じたけれど、あくまでもそれは僕が思っただけのこと。もしかしたらメアリーとルーシーはそう思っていないかもしれない。だから、僕は何も考えず、そのまま話を聞いていた。
「まあまあ、堅苦しくならずに、楽にしなされ」
その言葉を聞いて、僕たちはそれに従う。
その様子を見届けて、町長は小さく溜息を吐いた。
「……あなたたちはラドーム学院の学生だろう? どうして、このような場所にきているのか解らないが……」
まず自分たちの身分を話されて、驚いた。
なぜ知っているのだろう。こちらから話しているわけでもないのに。
「……ああ、すまない。実はラドームから聞いているのだよ。この町は、ラドームが昔住んでいた場所でね。私も昔からよく話を聞いていた。だから仲が良いのだよ」
そう言って、町長は背を向けている電話機を指さした。
電話機。それはこの世界にやってきて、一番驚いたことだ。この世界の文明は、もともと僕が居た世界に割り当てれば、産業革命以前になるだろう。船も蒸気船ではなかったし、そもそも蒸気で船を動かすことは、ほぼ出来ないかもしれない――そんなことを語っていた。
しかしながら、この世界には電話機がある。産業革命よりも前には、電話機は発明されていない。もちろん電話機が生まれたのは、僕のいた世界では産業革命以後となる。にもかかわらず、どうしてこの世界には電話機があるのか? 謎は深まるばかりだったから、取り敢えず暫く残置させておいた疑問の一つではあったのだけれど。
「……まあ、その電話で知ったのだよ。もしかしたら船がながされてエルファスのほうまで来ているかもしれない。もしそうなっていたら、助けてやってほしい。保護してほしい、とな……。さて、君たちがここに来たということは、つまり、ハイダルク城へと向かうことになるのかな?」
ほんとうに何でも知っている。この世界の有識人は、脳内ですべて繋がっているのか?
そんな冗談を言えるくらいには、僕は気になっていたけれど、でも、余裕を感じていたこともまた事実だった。
こくり、と頷いてそれにこたえると、町長は小さく頷いた。
「成る程。ならば、序でに……そう、ほんとうに序でのことになるのだが、一つ頼まれごとをしてくれないだろうか?」
「頼まれごと、ですか?」
「そう。頼まれごと、だよ。なに、そう難しい話ではない。ただ、一つ、あることをしてほしいだけなのだよ」
「あること、って……何ですか?」
フルの言葉に、町長は頷いて神妙な顔で話し始めた。
「……妖精をこの町に取り戻してほしい」
町長はそう言って、木を見る。合わせて僕もそれを見てみた。
確かに木はどこか元気がないように見える。
「……少し前までは、元気だったのだよ。この木は。けれど、それがつい最近、急に元気を失ってしまったのだよ。……なぜかは解らない。だが、敢えて言えることがある。それは、町の中から妖精が居なくなった、ということなのだよ」
妖精が居なくなった。
そもそも妖精を見たことがない僕にとって、それは簡単に納得できることではなかった。けれど、町長の話し方――トーンからして、それは重要なことであるということは、すぐに理解できた。
「妖精の住む町にとって、妖精が居なくなったことは大変なことなのだよ。そして、妖精が住む場所は別にある。だが、そう近くは無いし、この町に住んでいる人間がそう簡単に行けることは無い。難しいとでも言えばいいだろうか。平坦な道ではないものでね、かなり険しい道のりになるのだよ」
「だから私たちに?」
「ああ。こうお願いするのは心苦しいと思っているがね」
町長がそう思うのも当然だろう。急にやってきた人間に、この町のために働いてくれと言い出すのだから。冒険者ならともかく、まだ僕たちは学生だ。そう簡単にそのクエストを受けるわけにもいかなかった。
「……まあ、そう簡単にお願いして、了承してもらうとは思っていない。今日はゆっくりと休んでみてはいかがかね? この町で一番の宿屋の部屋を確保している。そこで一晩休んで、また次の日に結論を見出してはくれないだろうか? 短い期間で大変申し訳ないと思っているが……」
「……」
確かに、すぐに結論を出せるはずがなかった。
だから僕たちはひとまず町長の意見に了承して――一日の猶予をもらうこととしたのだった。
_ ◇◇◇
_ 僕たちは町の中を歩いていた。
なぜそんなことをしているのかといえば、一日の猶予をもらったことで、ちょっと時間が空いてしまったことが原因となる。ほんとうならば急ぎでリーガル城に向かわないといけないのかもしれないけれど、結局ここを解決しない限り心残りになるという判断で、僕たちはエルファスの町を歩いているということになる。
「……それにしても、ほんとうに古い建造物ばかりが並んでいるなあ。歴史がいっぱいになっている、というか」
ルーシーの発言を聞いて、僕も心の中で云々と頷いていた。
この町は人が多い。けれど、それは蓄積した歴史の上で成り立っているということ、それが十分に理解できる。そのような建造物を見て、僕はこの世界にきて何となく嬉しく思うのだった。こういう、もともとの世界ではまず見るのが難しいものを簡単に見ることが、きっと異世界の醍醐味なのだろう。そう、あくまでも勝手に思っているだけになるけれど。
「なあ、そこのあんた!」
その声を聴いて、僕は振り返った。
そこに立っていたのは、一人の少女だった。黒のロングヘアーで、フリルのついたネグリジェを着用している。
「……フル、知っているの?」
「そんなわけないだろ。僕ははじめてこの町に来たんだぞ?」
「そう……よね」
メアリーはそう自分に言い聞かせるように言って、頷いた。
対して、少女の話は続く。
「お願い、私を助けてほしいの」
「助けて……ほしい?」
「実は私は……」
「ミシェラ、なにしているのよ!」
それを聞いて、再び踵を返す。正確に言えば、僕は前を向いただけ、ということなのだが。
そこに立っているのは女の子だった。
まあ、それくらい見ればすぐに解ることだから割愛すべきことだと思うのだけれど、僕たちからしてみればそれくらいの基礎知識はとっても重要なことだった。
「カーラ。邪魔しないで。今私はここに居る旅人と話をしているのよ――」
「その旅人は町長と話をしている、とても大事なお客さんよ。あなたのような低俗な人間の話なんて聞かせてあげることは出来ない」
低俗な人間、と出たか。
確かにミシェラと呼ばれた少女の容姿は、カーラという少女に比べれば雲泥の差だ。
「低俗な人間、ねえ! 元はと言えば、私とあなたは同じ親から生まれているじゃないか。だのに、どうしてここまで変わってしまったのかねえ? あなたが媚を売ったからか、それとも身体を売ったのか? だったら私と変わらない、低俗な人間に変わりないじゃないか」
「……何を根拠にそんなことを言っているのかしら?」
カーラは笑みを浮かべていたが、その表情はどこか冷たい。冷たさを張り付けたようなそんな表情を見ていて、僕はそら恐ろしく思えた。
「何で怒っているのかな? もしかして、それが本当だった、とか? 私は、言っておくけれど、こういう可能性があるんじゃないの、と示唆しただけに過ぎないよ。当たり前だけど、そんな証拠なんて一切持っているわけでもないし。だってあなたは町長の秘書で、私はしがない娼婦なんだから、さ」
「貴様……さっきから言わせておけば!」
らちが明かない、そう思って僕は二人の中に割り入ろうとした――その時だった。
先に退いたのはミシェラのほうだった。
踵を返し、笑みを浮かべ、ミシェラはつぶやく。
「……そこのオニーサン、あとで『メリーテイスト』という色宿に来てみなさい。話はそれから幾らでもしてあげるわ。もちろん、それ以外のことも……ね」
そう言ってミシェラはウインクをして、立ち去って行った。
それを見てカーラは深い溜息を吐く。
「大丈夫でしたか? まったく……あの子には困ったものです。昔はああいうものではなかったのですが……いつしかああなってしまった」
「ああなってしまった……?」
くすり、と笑みを浮かべたカーラはそのまま僕たちに頭を下げる。
「ああ、挨拶が遅れてしまいましたね。私の名前はカーラと言います。以後、お見知りおきを。町長からあなたたちに町の案内をするように言われました。小さい町ではありますが、ぜひ楽しんでいってくださいね!」
そうして僕たちはカーラに町を案内してもらうこととなった。
_ 楽しい時間はあっという間に過ぎ、僕たちは宿屋で休憩していた。宿は僕とメアリーとルーシー、それぞれ一人ずつの部屋が確保されていた。
随分凄い対応だな、と僕は思いながらベッドに横たわり、天井を見つめていた。
メアリーはこの町についてメモを取っていた。勉強をこういうところでもするというのは、彼女らしい。
ルーシーは既に眠りについているのだろうか。先ほど部屋に行ってノックしても反応が無かった。だから、そうなのだろう――僕はそんなことを思っていた。
そこで僕はふと、ある言葉を思い出す。
昼に語っていた、ミシェラという女の子の発言。
「メリーテイスト……か」
僕は鞄から地図を取り出して、メリーテイストという色宿を探すことにした。
メリーテイストはすぐに見つかった。宿屋からもそう遠くない。
あの子の発言が少々気になる――そう思った僕は、部屋を抜け出して、夜の街へと繰り出した。
_ ◇◇◇
_ 夜のエルファスは昼のそれとはまったく違う状態だった。
正確に言えば、全体的に酒臭い。結局その理由は火を見るよりも明らかなのだが、それを気にすることなく町を歩いていた。
一言ルーシーに何か言っておくべきだったか――出発前に僕はそんなことを思ったけれど、何か面倒なことになりそうなので言わないでおいた。ひとまずは、あのミシェラが言っていた発言が妙に引っ掛かる。それをどうにか解明するために――僕は歩いていた。
メリーテイストという色宿に到着したのはそれから十分後のことだった。
そしてメリーテイストの前には、一人の少女が僕を待ち構えていた。
ミシェラ――彼女だった。
「待ちくたびれたわ、アナタ。まさかこんな時間にならないとやってこないなんて」
「……一緒に居るメンバーが眠りにつくか、あるいはそれに近いタイミングじゃないとやってこられないものでね。それくらい何となく解るだろう?」
言い訳に近い言葉を話して、僕は何とか許しを請おうと願う。
「ふうん……。まあ、いいけれど。取り敢えず、入ってよ。あ、言っておくけれど、お金はかからないよ」
「そうなら、安心できる」
「ま、別に大した話じゃないけれどさ、聞いてほしい話もあるってわけ。オーナーには、アナタは私の友人として通すから。アナタ、名前は?」
「フル……ヤタクミ」
「フル・ヤタクミ……ね。うん、ちょっと変わった名前だけれど、気に入った。さあ、中に入って」
そう言ってミシェラは中に入っていく。
ほんとうに僕がこの中に入っていいのかと思うが――しかし情報を得られるのであればどうだってかまわない。そう思って、僕は色宿の中へと入っていった。
_ 色宿とは名前の通り娼館と宿を兼ねている空間のことを言う。のちに知ったのだが、エルファスの町を支える産業の一つが色宿と言われているくらい、この町には色宿、そして娼館が多い。
色宿『メリーテイスト』の扉を開けると、甘ったるい香りが鼻腔を擽った。
「よう、ミシェラ。どうしたんだ?」
ミシェラは現れた眼鏡をかけた男に訊ねられて、目を細める。
「別に。ちょっと古い友人と出会ったから外で話していただけ。寒いから、部屋で話すの。いいでしょう? 別に客も来ていないし。もちろん客が来たら対応するから」
「それくらい当たり前だ。……解った、それじゃ、部屋に案内しろ。言っておくが、」
「なに?」
強い目線で、男を見つめる。
男は何か言いたかったようだが――言葉に詰まって、何も言い出せない。
少し間をおいて、男は頷くと、
「解った。お前さんには稼いでもらっているからな。少し時間をやるよ。ただし、その時間を過ぎて、客がやってきたら、その時は対応してもらうからな」
「ありがとうございます」
そう言って、二階へと続く階段を昇っていくミシェラ。
それを僕は追いかけていくしかなかった。
たとえこの先に何が待ち受けていようとも、ひとまずは――従うしかない。
彼女の部屋に入ると、白を基調とした部屋が出迎えてくれた。
大きな屋根付きのベッドに腰かけて、彼女は深い溜息を吐いた。
「……座りなよ」
隣をポンポンと叩くミシェラ。正気か? と僕は思ったけれど、普通に考えてみると彼女はそういう職業だから隣に男を座らせることには何の抵抗もないのだろう――そう思って、僕は彼女の隣に座った。
ミシェラは呟く。
「今日は来てくれてありがとうね。まさかほんとうに来てくれるとは思わなかったからさ」
「……いや、ちょっと気になったからね。それにしても、いったいどういうこと?」
「どういうこと、って?」
「君の言葉が少し気になっただけだよ。どうして、ただの旅人としか言っていなかった僕たちに、話したいことがあったのか? もしかして何か隠しているのではないか、って」
「……そうよ」
予想以上に早く、彼女は口を開いた。
そしてミシェラは俯きながら、言った。
「私、旅がしたいの」
「……旅?」
何を言い出すのかと思っていたが、その発言を聞いて思わず目が点になった。
しかし、ミシェラの話は続く。
「この世界は広い。けれど、私たち姉妹に立ち塞がったものは、重く、深く、それでいて残酷だった。私の姉、カーラのことは知っているでしょう? 何せ、今日の昼に出会ったのだから」
「……ああ、もちろん知っているよ。ただ、あそこで諍いがあった程度にしか理解していないけれどね」
「それで充分。それで問題ないよ。先入観さえなければいいのだから」
そう言い出して、ミシェラは彼女の思い出を話し始めた。
それは深い思い出であり、残酷な思い出だった。
正直言って、彼女がその年齢でそれを受け止めるには、あまりにも残酷すぎる。
ただし、それは部外者、あるいは経験したことの無い人間が語ることの出来るものになるのだろうけれど。
_ ◇◇◇
_ 十年前、私たちはスノーフォグのとある村に暮らしていた。
スノーフォグというのは、この国のように治安が良いわけではない。正確に言えば、治安が一定なわけではない。治安はその場所によってバラバラで良いところもあれば悪いところもあった。ハイダルクはそれが無くてすべて均等になっているけれど、スノーフォグにとってはそれが常識だった。
スノーフォグの村、そこで私たち姉妹と家族は暮らしていた。父親はスノーフォグの兵士で、母親は村で私たち姉妹を育ててくれた。父は城を守る兵士だったから、そう簡単に家に帰ってくることは無かった。けれど、城の安全を守っているということは常日頃聞いていたから、私はお父さんのことを尊敬していた。
私たちの日常が一変したのは、八年前にあった科学実験が原因よ。
科学実験――そういえば聞こえがいいかもしれないけれど、実際に言えば悪魔の実験だった。錬金術、魔術、化学……一応いろいろな学問があると思うけれど、あんな学問は未だに見たことがない。
阿鼻叫喚、悲鳴が合唱のように響き渡り。
私たちの住む村は――壊滅した。
そしてなぜか私たちだけ、生き残った。
父が帰ってきていた、偶然で最悪のタイミングでのことだった。
_ ◇◇◇
淡々と語られる過去を聞いて、僕は何も言えなかった。
正確に言えば、相槌を打てるようなそんな余裕も無かった。
「……そのあと、私たちは施設に送られた。強制的に、ね。その施設こそ、私たちの村を滅ぼした科学者が居る施設だった」
「……だったら、それを国に訴えなかったのか? 非人道的実験を実施しているなんてことを国に知られたら、それこそその組織は終わってしまうだろ?」
「国ぐるみでやっているのに?」
「……え?」
「あくまでもこれは私の推察だけれど、あの村の非人道的実験は確実に国があったからこそできたことだと思う。そして今もその組織が活動しているのかどうかは知らないけれど……私は許せなかった」
「組織は、何をしてきたんだ?」
「メタモルフォーズは人間の進化の形である」
「え?」
彼女の言葉に、僕は首を傾げた。
「その組織に居た科学者がしつこいほどに言っていた言葉よ。洗脳するつもりだったのか知らないけれど、それに近いものだったことは覚えている。ただ……その言葉の意味はまったく理解できなかったけれど」
「メタモルフォーズは人間の進化性、ってことは何かされたのか?」
「……血液の採集、それだけだったかしら。あとは『適性が良くない』というばかりで何もしなかったけれど。それだけは運が良かったのかもしれない」
月の光が、窓を通して入ってくる。
ミシェラの横顔が、月に照らされて――とても綺麗だった。
しかしながら、それに対して語られる物語は酷く残酷なものだった。
「それで、君たちは逃げ出した……ということなのか?」
こくり、とミシェラは頷く。
「……私たちは逃げ出した。あの施設で実験をされることがとても怖かったから。それに、見てしまったのよ」
「見た、とは?」
ミシェラに問いかける。彼女自体が話しているとはいえ、内容自体は彼女の心的外傷――トラウマに近いものだ。だから慎重に話しかけなければ、情報を得ることは出来ない。
けれども、彼女は強かった。
はっきりと、自分の言葉で考えて、そして話していた。
「人が苦しんで――『翼』が生える瞬間よ」
翼。
それは人間には有り得ない部位のことだった。
そして明らかに人間とは違う部位であることを――彼女だけではなく、人間誰しもがそれを理解することが出来るだろう。
「苦しみながら、もがきながら、けれども科学者は笑っていた。そういう感情を抱く被験者を見て、笑っていたのよ。そして――翼が生えた。その衝撃で被験者は気を失っていた。けれども、科学者は喜んでいた。それこそが科学の進歩、その第一歩だって……」
人間を、進化させる?
それが科学の進化、その第一歩?
正直、彼女の言っていることは突拍子もないことだった。それに間違いはないのだけれど、その話を聞いていて、怒りが芽生えてくることもまた事実だった。
人間の遺伝子を、自分の好き勝手に組み替えて実験を行う。
そんなもの、許されるはずがない。
許されるわけが無かった。
「……逃げた後、どうして君たち姉妹は分かれることになったんだ? 一緒に住むことは不可能だったわけか?」
「私たちは逃げて、船を使って、バイタスという港町に辿り着いた。生まれてスノーフォグを出たことが無かったから、私たちはすぐに立ち止まってしまった。これからどうすればいいのか、途方もない旅をいつまでも続けるわけにはいかない……そう思っていた」
一旦、彼女は言葉を区切る。
「けれど、そこで私たちにほぼ同時に二つの出会いがあった。一つは、偶然旅行に出ていたエルファスの町長、そしてもう一つはスノーフォグに興行のため向かっていたメリーテイストのオーナー。二人はそれぞれ『一人』しか保護することは出来ない、と伝えていた」
「……それで分かれることになったのか」
「はっきり言って、雲泥の差よ。どちらに着くか、は。当時であっても、私たち二人は町長に保護してもらうことが一番であると考えていた。だから二人とも、必死に頼み込んで、私たち二人とも保護してもらうか、あるいはエルファスで仕事の都合をつけてもらえるかどうか、そういうことを頼んでみよう……そういう話をしていたのよ」
ミシェラは自らの身体を抱くように、両手を逆側にそれぞれ伸ばした。
「けれど、裏切った。姉さんは裏切ったのよ」
姉さん――とは昼に出会ったカーラのことだろう。僕は適当に相槌を打って、彼女の話の続きを聞き出す。
「その日、姉さんは『私を町長の保護下にしてほしい。そういう話し合いで決まった』と言い出した。私は呆れてなにも言えなかった。それと同時に私は実感したわ。私は姉さんに捨てられたのだと。妹のことなど、姉さんには必要ないのだって」
「……そして、ミシェラ、君は?」
「その場から逃げ出して、すぐにメリーテイストのオーナーに声をかけた。話し合いで私がメリーテイストに向かうことになったので、よろしくお願いします……ってね」
ニヒルな笑みを浮かべ、僕のほうを向いたミシェラ。
その表情は、どこか悲しそうだった。
「……でも、それと旅に出たい。二つのことは導かれないと思うのだけれど?」
「一言いえば復讐、けれど広い目的で言えば世界を見てみたかった、ということかな」
「世界を見てみたかった?」
「私はずっとスノーフォグ、それとこのエルファスしか見たことが無かった。それ以外の情報と言えば客が英雄譚のように話す物語ばかり。飽き飽きしていたところだったのよ、正直言って、ね」
彼女の言い分も、なんとなくであるが、理解できた。
つまり、百聞は一見に如かず。一度聞いたことを、見てみたいということだった。
「でも……女の子一人で旅に出る、というのは……」
「あら? これでも私、回復魔法を使うことが出来るのよ? ……きっと、これはあの研究所で身につけさせられたモノなのかもしれないけれどね。ちなみに姉さんは守護霊術だったかな。いずれにせよ、あの場所で身に着いたものが役に立つことは無い、そう思っていたことは紛れもない事実だけれど」
回復魔法を身につけさせられた?
それはつまり、まったく何も無かった人間に魔法や守護霊術のような――一つの才能を人工的に備えさせた、ということだろうか。もしそうであるならば、それは凄いということには間違いないだろう。ただし、勝手に身に着けさせた――というのであれば、話は別になるだろうが。
「それを使えることは、はっきり言ってこの町じゃ出来ないことよ。けれど、旅をするのならば話は別。回復魔法を使う魔術師なんて、あんまり居ないでしょう? ねえ、私を……あなたたちの仲間にしてくれないかしら。きっと、足手まといにはならないし、させない。後悔もさせないつもりだから」
ミシェラは復讐がしたいと言った。
けれど、その発言は出来る限り通したくない発言だった。
復讐は復讐しか生み出さない。それはどこかの誰かが言っていたような気がした。その発言通りであるならば、ミシェラが復讐をすることを止めたほうがいいと思ったからだ。
けれど、それをそのまま伝えても逆上されるだけだろうし、彼女が諦めてくれるとは思えない。僕たちじゃなくても別の旅人を捕まえてでも、最悪一人でも復讐の旅に向かうはずだ。
けれども、それを言える立場は僕にはない。
僕はこの世界にきてまだ日が浅い。そんな僕が、彼女に『復讐なんてやめたほうがいい』なんて言っても問題ないのだろうか? きっと、受け入れてもらえるはずがない。
「……まあ、これを言ってもきっと君には関係ないと言われるかもしれないけれどね。でも、もし受け入れてくれるのならば、私も旅の仲間に入れてほしい」
僕は彼女の強い眼差しに、ただ頷くしか無かった。
彼女の意志はとても強いものだった。
だから、僕が断ったとしても、きっと彼女は一人で旅に出る。
そうしたとき、仮に――モンスターの攻撃で死んでしまったら、それこそ後味が悪い。
だから僕は、その言葉に頷いた。
それは話を聞いてしまった責任かもしれないけれど、きっとメアリーたちはそう言ったとしても信用してくれないだろうなあ。『お人よし』の一言で済ませてしまうかもしれない。まあ、それで済ませてくれるのであれば、とっても嬉しい話ではあるけれど。
_ ◇◇◇
帰ってきて、次の日の朝。メアリーは想像通りの言葉を口にした。
予想していた通りと言えばその通りではあるのだけれど、いざ言われると申し訳ない気分になる。いや、昨日の時点ではしっかり彼女の話を伝えて、メンバーに入れたいという意向をはっきりと伝えるつもりだったのだけれど、どうもメアリーと話すとうまく自分の意見が反映されないことが多々ある。それはメアリーがうまくメンバーのかじ取りをしているということでもあるのだけれど。
ルーシーは頭を掻いて、メアリーの後に続ける。
「あのな、フル? 君がどういう考えをもって行動しているのか、あんまり考えたことは無いけれどさ、だとしてもこれはどうかと思うぜ? メンバーを入れること、まあそれについては百歩譲って認めるとしても、それをせめてこちらに一回話をしてくれることくらい考えてもらっても良かったんじゃないか?」
「それは……確かに申し訳ないと思っている」
「まあ、いいわ」
メアリーは深い溜息を吐いて、僕のほうを改めて見つめてきた。
「フルが決めたんだもの。そして今はフルがリーダー。私たちのメンバーは、トライヤムチェン族の集落へ向かった時からずっと変わらないと思っていたけれど……、それでも、フルが認めたのならば、私たちも認めましょう」
一蓮托生、という言葉がある。
確か、善悪に限らず仲間として行動や運命を共にする――そんな意味だったと思う。
メアリーの世界にそんな言葉があるとは思えないけれど、それは即ち、一蓮托生ということなのだろう。
ルーシーもメアリーの反応を見て、頷く。
「メアリーが良いというならば、僕も構わないよ。それに、回復魔法を使うことが出来るのだろう? だったら、今後の旅に打って付けじゃないか。まあ、そんな危険な旅になるかどうかは未だ解らないけれどね」
「メアリー、ルーシー、有難う……」
僕は、無茶なことを認めてくれたメアリーとルーシーに頭を下げた。
仲間という言葉がとても嬉しかった。
仲間という言葉がとても有難かった。
「……ところで、エルファスの町長に頼まれた件、忘れていないでしょうね?」
「それももう決定しているよ。頼まれたからには、行動するしかない。僕はそう思っている」
「つまり、やるってことね……。まあ、そういうと思っていたわ、フルのことだから」
「確かに、メアリーの言った通りのことになったね。まあ、それはそれで全然構わないけれど」
頷いて、ルーシーも僕のほうを見た。
それに答えるように、僕も――はっきりと頷いた。
_ そうして、僕たちは了承した。
ただし、一つの条件を付加して。
「……ミシェラも連れていく、ということですか?」
その条件に一番反応したのは紛れもない、カーラだった。
その言葉に僕は頷く。少し遅れてミシェラも頷いた。
「ミシェラ。確かカーラの妹だったか。何故、そのようなことを望むのか、私に聞かせてくれないか?」
町長の言葉を聞いて、彼女は小さく頷いた。
そしてミシェラは、昨晩僕に言ったことを、そのまま告げた。さすがに一言一句一緒とまでは行かなかったけれど、彼女は、彼女の言葉でそのことを告げた。
ミシェラの言葉を聞いたのち、町長は頷く。
「……そうか。君はずっとそういう思いを抱いていたのだな。済まなかったな、気付けなくて。まったく、大人として恥ずかしいよ。こんなことにも気付けなかったのだから」
「町長。そのようなことは……」
「カーラ、君にはこの四人のサポートをしてもらいたい」
町長は踵を返し、カーラにそう言った。
「私が……ですか?」
「不服かね?」
町長の言葉に、首を横に振るカーラ。
「いえ、そのようなことはございません」
「ならば問題なかろう。生憎、場所は解らない。しかしカーラ、君なら道案内が出来るはずだ。本来であるならば、私が出向きたいところではあるのだが、私は町長だ。この町を離れるわけにはいかない」
「ですが……」
カーラは何処か嫌悪を抱いているような、そんな表情をしていた。正確に言えばそれはただ困っていただけに見える。まあ、普通に考えれば致し方ないことかもしれない。
自分の妹が旅に出ると言うのだから。普通の神経を持っていれば、心配するのは当然のことだと言えるだろう。
しかし、それを制したのは町長だった。
「カーラ、言いたいことは解るが、少し彼女のことも考えてみてはどうかね?」
「しかし、町長!」
町長は首を横に振った。
それを見て、彼女は今ここに自分の味方がいないことを思い知ったのか、口を噤んだ。
「……君が心配することも解る。だが、それまでにしないか。君がずっと心配性だと、ミシェラはずっと一人になりたくてもなることはできない。いや、言い方を変えよう。ミシェラは独り立ちすることが出来ないよ」
「……そんな、いや、まさか……。町長、あなたまでいったい何を……」
「君の言う言葉と、私の言う言葉では相容れないこともあるかもしれない。はっきり言って、それは当然のことだ。人間は一人一人違った生き方をしていて、一人一人違った考えを持っているのだから」
どうやら、町長は未だきちんとした考えを筋として持っているようだった。そしてそれは僕たちの考えにとっても、とても有難いことだった。
カーラは深い溜息を吐いて、ミシェラに問いかける。
「ミシェラ、あなたがどういう道を歩むかは解らないけれど……、そのことについて、何も後悔していないのよね?」
「少なくとも、今は。そしてこの選択を永遠に後悔しないようにするのは、今からの努力次第になると思うよ」
「そう……」
ミシェラの決意はとても強いものだということ、それを彼女は再認識して、大きく頷いた。
「うん。だったら、お姉ちゃん止めないよ。あなたの行きたい道に進みなさい。けれど、あなたの家族は、ここでいつまでも待っているから。そのことだけは忘れないでいて」
「……解った。ありがとう、姉さん」
「さて、話はまとまったようだな」
町長の話を聞いて、ミシェラとカーラは頷いた。
「カーラ、場所は知っているね? 家の前に馬車を置いているから、それを使ってエルフの住む里へと向かうのだ。場所は御者に伝えてあるから、その通りに行けばいい」
「解りました」
カーラは頷き、頭を下げると、僕たちに向かいなおして、言った。
「それでは、向かいましょう。エルフたちの住む、隠れ里へ」
_ ◇◇◇
_ どこかの場所。
暗い部屋に、一人の科学者が跪いていた。
その先に居るのは、一人の人間――いや、それを人間と言っていいのだろうか? 解らないが、どちらにせよそれが正しいかどうかも、もう科学者は解らなかった。
「して、報告を受けようか」
声を聴いて、科学者は首を垂れたまま話を続ける。
「はい。トライヤムチェン族の集落に向かったルイス・ディスコードですが、失敗に終わったようです。現に、予言の勇者はエルファスに辿り着いたものかと……」
「エルファス、ねえ……。あそこは確か妖精の木があった場所よね?」
「ええ。ですが現状エルフは住んでいません。エルフが住んでいない妖精の村など、ただの村と変わりありませんよ」
「……ふうん。そう、あの子たち、あの場所に居るの。ということは、あの武器も手に入れられる可能性があるわけね」
「いかがなさいますか?」
次に、違った男の声が聞こえた。
その声は科学者のそれと比べると明らかに幼い。まだ学生かそれに近い年齢の声に聞こえた。
「……まだあなたが出る幕では無いでしょう。今は私にお任せください」
また別の声が聞こえた。
「あなたもいいけれど……あなたは村のほうに向かってもらいましょうか。あそこには確か『手に入れるべき』モノがあったと記憶しているし……。まあ、ほんとうは必要ないのだけれど、私以外の誰かが持っていると厄介なのよねー。あの苗木は」
つまらなそうに。
手に入れた玩具が自分の好みに合わなかったかのような、そんな子供のような表情を浮かべているように感じられた。
しかし、科学者には顔が見えないから、それがほんとうにそういう表情をしているのかどうかというのは解らないのだが。
しかし再び、明らかにつまらなそうな溜息を吐いて、それは言った。
「苗木の回収と、目撃者の抹消。その二つを目的として、出撃して頂戴。目標はエルファス。座標は……まあ、言わないでも解るわよね? 大きな木を目印にしていけば、そう長い距離では無いから」
「了解いたしました」
頭を下げて、声が一つ消えた。
「それじゃ、僕は今回要らないってことか。あー、暇になるなあ。ねえねえ、もっと遣り甲斐のある仕事はくれないかなあ? さすがにここで演習ばかりやっていくのも飽き飽きするよ。ロマもそう言っているしさー」
「ならば、あなたにはもう一つの任務を授けましょうか。……うふふ、私に付いてきなさい」
「付いていって、どうするつもりさ? 護衛でもするつもり?」
科学者にとって高尚な地位に立っているそれと話すときは、敬語を外すことなどできやしない。
しかしながら、彼の前に立っている二人は対等な地位――というよりも、男がそれに対してフランクすぎる態度で話していた。それは男が敬語を嫌っている以上に、精神的に未だ子供だと言えるところが多いからだった。
(だが、それが問題だ……)
精神的に子供と言える――それは即ち、扱いづらいということを意味していた。
子供は大人以上に、欲望に忠実に生きる。それは即ち、自分がやりたくなければたとえ上司からの命令でもやらないことが殆どだということだ。さすがに、彼の目の前に立っている男はそんな我儘を通すほどではないが、問題は、もう一つのほうだった。
「私はこれから暫し外出する。あれの研究を進めておくように。私が戻ってくるまでに、何らかの良い結果が得られることを、期待しているぞ」
そう言って、それは立ち上がると、気配を消した。
そして男もそれを追うように、姿を消した。
一人取り残された科学者はようやく顔をあげると、自らの額に触れた。額には汗がじんわりと滲んでいた。
それほどに、その存在は科学者にとって恐ろしい存在だった。何か間違った発言をしてしまえば、自分の命を消される。そういう存在だった。
「……早く、『あれ』を完成させねば。あのお方の機嫌が、悪くなる前に」
そう言って踵を返すと、科学者は部屋を後にした。
エルフの隠れ里に向かうまで、そう時間はかからなかった。
距離にして――と説明するのは難しいので、時間で説明するとおよそ二十分程度。話をしていると気付けばもう到着していた――そんなくらいの時間だった。
とはいえ話なんてそんなこともあまり盛り上がらなかった。自己紹介をして、ぎこちない会話をした程度。
エルフの隠れ里に着いて、最初に異変に気付いたのはルーシーだった。
「……なんか臭くないか?」
鼻を抓みながら、ルーシーは言った。
彼の言う通り、鼻が曲がりそうな酷い匂いがした。正確に言えば、血の匂い。
ガリ、ボリ、ボリ――。
次いで、何かを噛み砕くような音が聞こえた。随分と節操とマナーのなっていないやつだ、そんなことを思っていた。
しかし、森の影に隠れていたのは――そんなことが言えるようなモノでは無かった。
それはまさに異形と呼べるような存在だった。普通、ドラゴンか何かだったら、顔は一つしかない。それは生き物それぞれが持つルールのようなものであって、たいていそのルールを守っていない生き物はいない。
しかし、それは顔が幾つもあった。
それだけで元来生きている生き物とは違う存在であることが理解できる。
そして、それは巨大すぎた。森に隠れている程度、とはいえ数メートルはある。僕たちの身体と比べればその大きさは一目瞭然、太刀打ちしようにもできるはずがなかった。
そして、その異形はあるものを食べていた。
それは小さな人のように見えた。
なぜそう言えるかというと、足らしきものが異形の口から見えたからだ。そして、同時に地面を見ると、薄く輝いている羽らしきものも見える。
――それは、紛れもなく、エルフだった。
「嘘……だろ? まさか、エルフを食べているというのか……!」
ミシェラの言葉を聞いて、僕も現実を再認識する。
エルフ。またの名を妖精。空を華麗に舞い、自然物の精霊とも言われている神秘的な生物。
それが今、異形によって見るも無残な姿になっている。
「い、いや……」
見ると、メアリーが今にも大声を上げようとしている。
怖いと思っているのは、仕方がない。
しかし、今大声を出されてしまうとあの異形に気付かれてしまう。
それは出来る限り避けたい。
だから、僕はメアリーにそっとささやいた。
「気持ちを抑えて。叫びたい気持ちも解るけれど、今気付かれたら一巻の終わりだ」
「……そうね、ありがとう、フル。もしあなたが言ってくれなかったら、私は叫んでいたかもしれない」
メアリーはどうやら我に返ったようだ。
さて、ここからスタートライン。
対策をしっかりと考えていかねばならない。どのようにしてあの異形を対処していくか。
「おそらくあの異形が居るからこそ、エルフたちはエルファスに向かうことが出来ないのだろう……。ここはもともとエルフが住む場所だ。エルフたちにとっては生まれ故郷と言ってもいい。その場所が破壊されようとしているのならば、ここを脱出するわけにもいかないだろう」
『その通りです、若人たちよ』
カーラの言葉の直後、僕の頭に声が響いた。
どうやらそれは僕以外の人にも同様の症状が起きているようで、
「誰……?」
メアリーがその言葉について、訊ねた。
その言葉に呼び出されたかのように、目の前に小人が姿を現した。
そう、飛んでいた。
羽をはやし、僕たちに比べると六割程度の身長になっているそれは、耳が斜め上の方向に尖っており――。
「もしかして――エルフ?」
そう。
そこに富んでいたのは、エルフそのものだった。
緑の髪をしたエルフは頷くと、
『いかにも。私はエルフです。あなた方人間が森の精や妖精と呼んでいる存在、それが私たちになります』
「……しかし、エルフと呼ぶのもどこかこそばゆい。それは君たちの種族名なのだろう? 君たちにも個を識別するための何か……そう、例えば、名前とか、無いのか?」
ルーシーの問いに、首を傾げるエルフ。
『残念ながら、私たちエルフには名前がありません。すべて職業で認識されるためです。ですので、名前は――』
「解ったわ。じゃあ、呼びやすい名前を付けましょう。今からあなたはミント。いいわね?」
ミシェラはそう言って、ミントのほうを指さした。
ミントはその言葉を聞いて暫く首を傾げていたが、少しして頷いて、笑みを浮かべた。
『ミント……ミント。ええ、いいですね。良い名前です。解りました。では、私のことはミントとお呼びください』
「ミントさん。それじゃ早速質問するけれど」
メアリーはそう前置きして、質問を開始した。
「エルファスにある大樹はどうして枯れてしまったのかしら? あれはあなたたちエルフが管理しているものだと聞いたのだけれど」
『……そうですね。確かにその通りです。本当ならば私が向かわねばならないのですが……あのバケモノにエルフを食べられてしまい、今、エルフは私しかいません。だから、ここを離れることが出来ない。それが現状です』
「エルフが……一人しかいない?」
それを聞いて僕は冷や汗をかいた。まさかここまでエルフの状況が酷くなっているとは知らなかったからだ。
『そう悲観することはありませんよ』
僕の表情を見てからか、ミントはそう僕に声をかけてくれた。
慰めの言葉になるのかもしれないけれど、しかし、実際どうするというのだろうか。そんな言葉を投げかけても、エルフは復活することなんてないと思うけれど。
『あなたはエルフを何か勘違いしているかもしれませんが……、エルフは自然から生まれる精霊です。ですから時間さえ置けば幾らでも生まれるのです。……もちろん、管理限界はあるので、その人数を超えることはありませんが。しかしながら、あの異形が生まれた瞬間にエルフを食べてしまうものですから、溜まることはありません。私はどうにかして結界を張って、見つからないようにしていますが……。あの異形の頭が良くなくてよかった、というのが正直な感想になりますね』
「アイツを倒す方法というのは、無いのですか?」
僕はミントに訊ねてみる。もっとも、すぐに見つかるものではないと思っているが――。
『無いことは無いですが……。しかし、それを使いこなせるかどうかは解りませんよ?』
そう言って、ミントは僕の周りを一周する。
「あの……どうしましたか?」
『いや……うん。行けますね。ちょっとやってみましょう。物は試しです。あなたに魔法の技術、そのすべてを授けます』
魔法。
でも、僕が学んでいたのは錬金術だったと思うけれど……。
しかしミントは問答無用で、僕の前に移動すると、目を瞑った。
そして誰にも聞こえないような小さな声で、詠唱を開始した。
目と鼻の間の距離しか離れていないというのに、ミントの声はとても小さくて、聞こえなかった。
きっと、この声がミントのほんとうの声なのだろう。
「……うっ」
同時に、頭が痛くなる。
まるで大量のデータを思い切り脳内に直接書き込まれているような、そんな感覚。
有無を言わさずたくさんのデータが流し込まれていく。
それは魔法の原理、そして技術。
初心者である僕が、魔法を使いこなすには十分すぎるそれを、僕はミントの詠唱により思い切り流し込まれた。
頭痛がする。大量のデータを一気に、短時間で流し込まれた。処理しきれない、と言えばうそになるが――きっとそういう感覚なのだろう。
『……終わりました』
「これが……これが魔法だと?」
「ええ。しかし、その大きすぎる情報は、いずれあなたを滅ぼすでしょう。それだけは、理解していただきたいものですね……」
ミントは何か言ったけれど、囁く様な声だったので、僕たちにまで届かなかった。
「それでは、これであのバケモノと……!」
『ちょっと待ってください。まだ、まだ足りません』
「?」
『まだ使えるモノがある、ということです』
そう言ってミントはどこかへと向かった。少し動いて、立ち止まる。そうして僕たちのほうを一瞥して、また動き出した。
どうやら、ついてこい、と言っているようにも見えた。
「……どうやらまだ隠している何かがあるようだな」
ミシェラの言葉を聞いて、僕は頷いた。
「向かおう、ミントの動く方向へ……」
そして、馬車もまたゆっくりとそちらの方向へと向かった。
_ ◇◇◇
_ ミントが居た場所は、巨大な木の室の中だった。
「……カーラさん、ミシェラ。ここで待っていてくれませんか?」
「どうして?」
「いや、何か……何となくだけれど、僕たち三人だけに用事があるような気がするんだ。あのミントとかいうエルフは」
ルーシーはそう言って、馬車から降りた。
僕も、なんとなくそのような予感はしていた。
そして、それはメアリーも同じだった。
「あら? ルーシーもそう思っていたの? 奇遇ね、実は私も、なのよ。けれど、どうしてそういう感覚をしているのか解らないけれどね……。もしかしたら、ミントさんがそういう感覚を無意識に流しているのかもしれないわね?」
僕たちは、三人それぞれの言葉を聞いて――そして同時に頷く。
「解ったわ。それじゃ、私たちはここで待っています」
「何かあったら、すぐに私たちを呼びなさいよ」
カーラ、ミシェラはそれぞれ僕たちにエールを送る。
それを聞いて、僕たちは頷いて――木の室の中へと入っていった。
木の室の中には、小さな部屋があった。
そしてそこには、三つの武器が並んでいた。
「……これは?」
『これは、ガラムド様から渡された武器です。それぞれシルフェの剣、シルフェの杖、シルフェの弓……。聖なる力が宿っていて、絶大な力を誇ると言われています。この平和な時代に必要かどうか解りませんでしたが……、今ならば必要である。そう思うのですよ』
そう、ミントが言った瞬間――。
剣を見ると、それがほのかに緑色の光を放ったような気がした。
「?」
そして――剣がゆっくりと動き出す。ひとりでに、勝手に。
『まさか……剣が持ち主に呼応している、というのですか……!』
シルフェの剣はそれに頷くように、突き刺された地面から抜け出すと、自動的に僕の左手、その手元に柄が――まるでそこを掴め、と言っているかのように――移動した。
そして僕は、その、シルフェの剣を――しっかりと掴んだ。
同じ現象は、ルーシー、それにメアリーにも起こった。
お互い、無意識に見ていたのだろうけれど、ワンテンポ遅れて、ルーシーには弓が、メアリーには杖が自動的に装備できる場所まで、武器が移動してきた。
「これって……どういうこと?」
「解らない……。けれど、これで、戦える気がする……」
僕はその剣から感じる力が、とても強いものだと――感じた。
ミントは目を丸くしていて、とても驚いている様子だった。
『……まさか、このようなことが起きるなんて。ええ、ええ、これなら、これなら戦うことが出来るでしょう。剣、杖、弓、それはそれぞれあなたたちの基礎エネルギーを底上げすることで、普通の武器を装備するよりも何倍のパワーを出すことが出来ます。それならば、あなたたちもあのバケモノを倒すことが……きっと!』
その剣をもって思った感想は一つ。
その剣を持ったことにより、力があふれ出してきた。正確に言えば、その剣から力があふれ出ている、と言ってもいい。その剣を構えた時から、その剣に秘められた力が僕に流れ込んでいる――と言えば解るだろうか。
そして、その感覚を感じているのは、僕だけではないようだった。ルーシーは弓を、メアリーは杖を見つめながら、その力に驚いているようだった。
「……行ける」
僕はぽつり、そうつぶやいた。それはその力から出た自信の表れかもしれなかったが、現にそれほどの力を持っていたのだ。
そして僕たちは、木の室を飛び出していく。
目的はいつだって単純明快だ。
妖精を乱暴に食べているあのバケモノを倒す、そのために。
「「了解!」」
僕とルーシーは同時に頷いて、それぞれ行動を開始する。
「ねえ、こいつは一体どういうことなの?」
ミシェラがメアリーに質問する。
「ミシェラは回復魔法が得意だったわよね。だから、みんなのサポートをして。バリアを作ると言っても、それでどれほど軽減されるか解らない……。だから、ダメージを受けた時素早く回復をする。それがあなたの役目よ」
「……解った!」
ミシェラが物分かりの良い人で良かった。僕は心からそう思っていた。
そして、僕たちは攻撃を開始する。
メアリーが念じると、同時に僕たちの周りに球状のバリアが出現する。バリア、と言ってもこちらから攻撃することが出来る非常に曖昧な境界を持つものだったが、しかしながら、一番に彼女が驚いたのは――。
「嘘……。魔法陣も無しに、バリアを使えるだなんて……!」
魔法陣。
この世界の魔法は、円というファクターをもとにしていくつかの図形を組み合わせた陣――魔法陣を作り上げ、それにエネルギーを送り込むことで初めて魔法として成立する。
しかしながら、今メアリーが発動させたそれは魔法ではあるものの、そのいくつかの工程をすっ飛ばしたものとなっていた。
「凄い……」
ミシェラ、それにカーラは驚いていた。
当然だろう。きっと、これはこの世界でも珍しい存在なのだ。魔法陣を使わずに魔法を放つという、その行為自体が。
「これで……終わりだ!」
そして。
僕はバケモノの頭に――剣を突き刺した。
「がるる、がるうううううううううう……!」
同時に、苦痛にも似た表情を浮かべながらバケモノは雄叫びを上げる。
なんというか、とてもやりにくい。
表情が人間に似ているからだ。こんな敵と戦ったことなど(そもそも僕の居た世界では、『戦う』ということ自体がゲームの世界であることが殆どなのだが)無いので、とてもやりにくい。感情をそのまま、倒すという方向に倒しづらいとでも言えばいいだろうか。
「ここから……決める!」
そして、僕は素早く魔法陣を描き――剣で強引に切り開いたその先へ炎をぶつけた。
_ ◇◇◇
_ そのころ。
ラドーム学院の校長室では、ラドームが大量の書類と格闘していた。
そんな庶務をしているところで、彼は何か――不穏な気配に気付いた。
「隠れていないで出てきたらどうだね」
一言、隠れている相手にぶっきらぼうに言うラドーム。
「……さすがは、ラドームね」
ぽつり、どこかから声が聞こえた。
そして本棚のある部分がぐにゃり、と歪み――そこにぽっかりと小さな穴が出来た。穴から誰かが出てくるまで、そう間隔は空かなかった。
純白の、いわゆる普通の着物を身に着けて、赤い袴、ポニーテールに近い髪形で烏帽子を被っていた女性は小さな水晶を手に持っていた。
さらにもう一人、彼女の護衛――というポジションだろうか、がやってきた。
赤いシャツ、赤く燃え上がるような髪、ニヒルな笑みを浮かべたそれは、すぐに人間ではない別の何かだと理解できた。
「合成獣を連れてくるとは、ほんとうに趣味が悪い人間だな。リュージュよ」
その言葉を聞いて、笑みを浮かべるリュージュ。
「スノーフォグで争った以来かしら、ラドーム?」
「……そうだったかね? できる限り、貴様との記憶は忘れてしまいたかったので、もう覚えていないのだよ。まあ、まるで少女のような容姿をしおって。いったい、どういうマヤカシを使っているのか」
「あら。興味がわいてきた? けれど、教えてあげないわ。これは私が使ってこそ、生えるものだからね」
「フン」
ラドームは鼻を鳴らして、庶務を再開した。とはいえ完全にリュージュを無視することなど出来ない。突然彼女がラドームを燃やす炎魔法を放ってきても何らおかしくない、彼女はそういう存在なのだ。だから、意識はあくまでもリュージュに集中させつつも、処理しなくてはならない庶務を片付け始めていた。
「我々は、神の一族。だから、折衝はいけない。折衝も、殺生も。別にジョークを言っているつもりではないけれど、それについては間違いないわよね?」
「ああ、そうだな。神の一族どうしで殺しあったら、ガラムド様が何を言い出すか解ったものではない」
ラドームは庶務を進めながら、あくまでもリュージュに視線を移すことなく、言った。
「そう。だからここで、取引と行かないかしら?」
ぴたり、と庶務を進めていた手を止めるラドーム。
「取引?」
「そうよ」
リュージュはニヒルな笑みを浮かべながら、ソファに腰かけた。
「……予言の勇者を、こちらに受け渡してもらえるかしら?」
はあ、と溜息を吐き立ち上がるラドーム。
彼はこういう状況を予想していなかったわけではない。
予言の勇者が現れて以降、確実にそれを狙う相手が出てくることは明らかだった。
しかしここまで早く出てくるとは思わなかっただろうし、それが同じ祈祷師からのものだった――ということが彼にとってとても悲しかった。
「ねえ、聞いているかしら? 予言の勇者、それを受け渡してくれるだけでいいのよ」
「それをみすみす許せるとでも思っているのか?」
ラドームはリュージュの問いに、はっきりと答えた。
「……ハハハ、さすがはハイダルク一の頭脳と謳われたことはあるわね、ラドーム」
「いずれにせよ、私たちラドーム学院にすでに所属している学生を、お前にみすみす渡すと思っているのか?」
「ねえ、もう話すのをやめたほうがいいのでは? 政治にはまったくと言っていいほど詳しくないけれどさ……これはどうみてもずっと平行線を辿ったまま終わってしまうと思うけれど?」
そう言ったのは、炎のように燃える髪を持った少年だった。
「……そうね。面倒なことはなるべく避けたかったけれど、致し方ないことかもしれない。けれど、まあ、あなたは少々考えが固すぎるのよね、ラドーム」
リュージュは立ち上がり、とてもつまらなそうな表情をして、炎の少年に命令する。
「バルト・イルファ。命令よ。この学院をできる限り破壊しなさい」
「人は燃やしても?」
「構わないわ」
それを聞いたとたん――彼の表情が醜く歪んだ。
まるで新しい玩具を与えられた子供のような、純粋な笑顔。
それをして、彼は右手を差し出した。
「……私を殺すかね」
こくり、と頷くリュージュ。
「殺して、何が生まれるというのかね。少なくとも何も生まれないと思うが」
「何? この状況においても、そのような発言をするわけ。まあ、あなたらしいといえばらしいけれど。そんなあなたにこの言葉を贈るわ、ラドーム」
リュージュは踵を返して、指を鳴らす。
「言論だけで戦争を止められるなら、世の中に兵器や魔法が流行するわけがないのよ」
そして、それを合図として――バルト・イルファの右手から炎が放射された。
校長室にある資料をすべて燃やし尽くしたバルト・イルファは笑顔でそう言った。
「あなたは学園の破壊を最優先しなさい。私はやることがあるのよ。ある人物に会って、話をつける必要がある」
「それじゃ、別行動?」
「そういうことになるわね」
バルト・イルファは頷く。
「それじゃ僕はここから、攻撃することにするよ」
笑みを浮かべたバルト・イルファは――両手から炎を放射して、T字路の左に進んでいった。
「……一応言っておくけれど、魔力を使い過ぎないでよ? あなたは、一応無尽蔵に力があるとはいえ、それは『木の実』で得られた魔力。枯渇する可能性も十分に有り得る。もし枯渇の可能性が出てきたら急いで私のもとに来なさい。いいわね?」
「解りました。まあ、それが出来るほど、楽しませてくれるかどうか解らないですけれど」
そう言って、バルト・イルファは今度こそ歩みを進めていく。
それを見送ったリュージュは溜息を吐いて、背を向ける。
バルト・イルファは『十三人の忌み子』の一人だった。そして、その中でも優秀な実力を持っていた。実験の中でも一番の成功、と科学者が認めていた。それがバルト・イルファだった。
しかしながら、副作用ともいえることがあった。それは人間だったころの記憶を一切保持していないということ。科学者によればそれは魔力を得た代償だと言っていたが、リュージュにとってはむしろ都合が良かった。
「……まさか、バルト・イルファの人格が、『兄』という人格になったとはね。それはさすがに想定外だったけれど……」
それでも結果としては問題ない。
彼女が望む方向に、計画が進むのならば、それだけで。
「さて……話をつけに行きましょうか。もちろん、それが解決するものであるとは思っていないけれど」
そう言って、リュージュは通路を進んでいく。
目的地はただ一つ。彼女が会おうと思っている、ただ一人の女性のもとへ。
_ ◇◇◇
_ 獣は弱っていた。
炎の一撃が相当効いているようで、獣はふらつきながら、それでも何とか倒れまいとしていた。
「今よ、フル!」
メアリーの声が聞こえる。
そうだ、今こそがチャンスだ! 今なら、倒せるはず!
そうして僕は――獣の心臓に思い切りシルフェの剣を突き刺した。
獣はゆっくりと倒れていく。どうやらその一撃が急所――つまるところ、獣の心臓に命中したらしい。ようやく、というところではあるが、何とかといったほうがいいだろう。
僕とメアリー、ルーシーの三人は必死に力を合わせた。がむしゃらに戦った。そして僕たちは何とか獣を追い詰めることが出来た。
獣は力を失ったためか、その形を保てなくなっていったのか、身体が砂のような粒状に変わっていく。そしてその粒は風に舞って散っていく。
「やった……!」
僕は、シルフェの剣を持ったまま小さくつぶやいた。
「はじめて、魔物を……倒したんだ……!」
_ 再び大樹に向かうと、ミントが僕たちを出迎えてくれた。ちなみに僕たちは戦闘が終わってへとへとになっていたけれど、ミシェラの回復魔法で何とかなった。彼女の回復魔法は一回でかなりのダメージを回復することが出来る。これについてまったく副作用が無い――というのは少々恐ろしいことではあるけれど、あまり考えないほうがいいだろう。
『あなたたちのおかげで、エルフの隠れ里は救われました。エルフもこれから生まれてくることでしょう。ほんとうに……ほんとうにあなたのおかげです』
「あの……差し出がましいようですが、これでエルファスには……?」
『はい。向かうことが出来るでしょう。もとはと言えば、あの獣が居たからこそ、この楽園は破壊されようとしていたのですから。その脅威がなくなった今、我々は再びあの大樹へと向かうことが出来ます』
「それじゃ……」
カーラさんの言葉に、ミントは微笑んだ。
もともと、そのためにこの場所にやってきたのだから、当然と言える。あの町にエルフが出現しなくなったから、その原因を突き止めるためにやってきた。そして、その原因は今撃破された。そうすれば、もうあとは……。
「これでようやく、リーガル城へと向かうことが出来る、ということかな?」
ルーシーの言葉に、僕は頷く。
随分と時間がかかってしまったけれど、城で待っている人は怒っていないだろうか? そこだけが少々不安なところでもある。大急ぎで向かわないと、悪い印象を与えかねない。
「それじゃ、一先ず町長さんに報告を――」
そう言って、カーラさんが振り返った――ちょうどその時だった。
「ねえ、あれ……いったい何?」
はじめにそれに気づいたのはメアリーだった。
彼女が指さしたその先には、黒煙が空へ伸びていた。
そしてその方角は紛れもない――エルファスのほうだった。
「エルファスが危ない!」
カーラさんは大急ぎで馬車に乗り込む。
僕たちはミントに急いで一礼して、彼女を追うように馬車に乗り込んでいった。
僕たちが乗り込んだと同時に、馬車は急発進する。この際、乗り心地など二の次。エルファスから延びる黒煙の正体、それを突き止める必要があった。
そのためにも僕たちは――急いで向かわねばならなかった。
_ フルたちの乗り込んだ馬車を見送ったミントは小さく溜息を吐いて、大樹を見た。
大樹からは白い光の粒が生み出されている。それがエルフであった。
エルフの隠れ里にはこれからたくさんのエルフが生まれることになる。
そして、ミントは考えた。
勇者に与えた三つの武器と、魔法の使い方。
勇者はこれにより魔法を使うことが出来た。しかし、魔法をつかうこと自体が――ノーバウンドでできるものではない。使うためにはエネルギーが必要であるし、代償も必要だ。
だが、ミントはそれを知っていて――フルに魔法の加護をした。
それはガラムドから言われていたこと。
それはガラムドから命じられていたこと。
ミントは空に向かって、つぶやく。
「――ガラムド様、あなたは、ほんとうにこれをお望みなのですか……?」
その小さく儚い声は、当然フルたちに届くことなど無かった。
_ ◇◇◇
_ エルファスに戻ってくると、それは酷い有様だった。
最初に到着したときにあった壁は破壊されているし、石造りの区々から火が出ている。道にはたくさんの人の――衣服だけが落ちていた。
まさに奇妙な有様。
死体ならまだしも、衣服しかない。
「これはいったい……?」
「予言の勇者サマのお出ましか。意外と早かったね……」
声を聴いて、僕はそちらのほうを向いた。
そこに立っていたのは、カーキ色の衣装に身を包んだ女性だった。髪はショートカットで、りりしい顔立ちは女優か何かと言われても信じることが出来るほどのプロポーションだった。
そして、その右手には町長の姿があった。
「町長!」
カーラさんは思わず馬車から飛び出そうとした。
「ダメ! 今出ると、敵の思う壺になる!」
それを制したのはメアリーだった。
それを聞いて、カーラさんは何とか外に出るのを思いとどまった。
「ボクの名前はラシッド。それにしてもまさか、『番外(アウター・ナンバー)』に出会えるとは思いもしなかった。……ま、そこまでの排除は求められていないから、別にいいけれど」
「アウター・ナンバー……?」
「十三人の忌み子、という言葉があってね。それに入りきれなかった人のことを言うのだよ。彼女たちはそれから逃げ出した。だから『番号から落とされた』。まあ、その忌み子も、もうイルファ兄妹しか残っていないわけだが」
「何を言っている!」
「君たちにはいずれ、偉大なる歴史の大見出しを観測する、観測者になってもらう。まあ、そう時間は無いからそれを食い止めることはまず無理なのだろうけれど。言っておくけれど、この町の人たちはみんな『溶かした』から。あとはこの町長だけ。けれど、この人は殺さないから安心して。この人にはこの町で起きた惨状を世界に伝えてもらわなくっちゃ! そして、魔法科学組織『シグナル』の名前も、ね」
そう言ってラシッドは無造作に町長を地面に投げ捨てた。
「町長!」
「ダメ! 今は出てはいけない!」
「ハハハ……。年下に宥められているようでは、感情がうまくコントロール出来ていないね? まあ、別にいいけれど。あーあ、取り敢えずやることは終わったし、ボクはこれで帰るよ」
そう言ってラシッドはウインクする。
「じゃあねっ!」
そしてラシッドの身体は――まるで空気に溶け込んだかのように、消えた。
_ ◇◇◇
_ 次の日。
僕たちは町長の家で目を覚ました。
「……よく眠れたようだね」
町長の声を聴いて、僕はすぐに頷けなかった。町長からしてみれば、自分の町が何者かによって壊滅してしまったのだから、そう眠れるわけがない。
「気にする必要は無い。君たちはやるべきことをやってくれた。それはカーラとミシェラから聞いているよ。……むしろ、それを考えるのは君たちではない。私たち、エルファスの人間のほうだ。そして、君たちは前に進まねばならない」
そこに立っていたのは、兵士だった。銀色の、輝いた鎧に身を包んだ白髪交じりの男だった。男は僕の顔を見ると、柔和な笑みを浮かべて言った。
「やっと出会えた。私の名前は、ハイダルク国軍兵士長のゴードン・グラムと言います。エルファスの被害調査に出向いたら、まさか予言の勇者様ご一行に出会えるとは思いもしませんでした」
「……ハイダルク国軍?」
つまり、この人は軍人――ということか。
ゴードンさんは話を続ける。
「この町がなぜこのような事態に陥ってしまったのか、先ず調査を進める必要も有りますが……、予言の勇者様、あなたがここに居ることも驚きました。船が転覆してしまった、ということは聞いていましたが……」
「やはりあの船は、転覆してしまったのですか?」
こくり、と頷くゴードンさん。
「……ですが、安心してください。船員は全員無事です。港町バイタスに流れ着きましたから。ですが、あなたたちが見つからなかった。だからみんな心配していたのです。予言の勇者様は、どこへ消えてしまったのか……ということを城中皆言っていたのですよ」
「心配をかけてしまって、すいません」
僕は頭を下げる。
ゴードンさんは「いえいえ」と言って、話を続けた。
「むしろ、私たちのほうが見つけることが出来ず申し訳なく思っています。ほんとうに、ここで見つかったのは偶然だと思います。……さあ、ここは我々に任せて、あなたたちは城へ向かってください」
_ 荷物をまとめて、外へ出た。
息が白く、とても寒い。
そういえば、もうこの世界にきて――二か月が経過した。この世界の季節は、どうやら元の世界の季節とあまり変わりがない。というか、変わらない。春夏秋冬、しっかりと季節が色づいている。
まるでこの世界は元の世界と同じような……そんな感じすら浮かんでくる。
けれど、そうだとしてもこの世界の歴史のことを考えると、元の世界と合致しない。だからこそ、異世界という感じがしないから僕にとってはとても有難いことなのだけれど。
ふと大樹を見ると、周りがきらきらと輝いていた。
エルフたちが僕たちのことを、見送っているように見えた。
馬車に乗り込み、僕は目を瞑る。未だ疲れているのか、とても眠かった。
「――僕はどうやってこの世界に来たのだろう?」
そんな、誰にも聞こえないくらいの小さな声で呟いて、僕はそのまま眠りに落ちた。
_ ◇◇◇
ラドーム学院は崩落しつつあった。様々な場所から火が出て、先生や学生が対処しているが、それでもバルト・イルファにはかなわなかった。
そしてサリーもまた、学院と学生を救うべく通路を走っていたのだが――それを遮ったのが、リュージュだった。
「……まさか、これをあなたが行ったことだというの? スノーフォグの王である、あなたが」
「正確に言えば、命令しただけね。私は直接手を下していない。交渉決裂してしまったから、致し方ないことになるけれど」
「校長は……」
「ラドームなら殺したわ」
淡々とした口調でリュージュは言った。
「まさか……そんな」
「嘘はついていないわよ。もちろん。アイツは交渉しようとしなかった。だから、殺した。そしてこの学院も、私が来たという証拠を残さないように消えてもらう。そういう運命なのよ」
「……あの予言を、実現させるつもりだというの?」
あの予言――それは即ち、テーラの予言だった。
「予言の勇者……あの忌まわしき存在を消し去らないと、私の野望が実現できない。それはあなただってそうでしょう?」
それを聞いて、眉を顰めるサリー。
「……何を言っているのか、さっぱり解らないのだけれど。私があの予言と何か関係が?」
「無いとは言わせないわよ。……もはや知る人も殆ど居ないけれどね、クリプトンという独特な苗字、そしてテーラの苗字を知る人間は殆ど居ない。……サリー・クリプトン。テーラ・クリプトンの子孫であり、その遺志を継ぐ者。テーラの予言を阻止するべく活動していた。そしてあなたはテーラが編み出した『禁断の魔術』を継承していた」
それを聞いてサリーは両手を上げた。
「……まさかそこまで知っていたとはね。さすがは祈祷師サマ、ってことかしら? それで? そこまで私のことを調べ上げて、何が欲しいの?」
「当然、『禁断の魔術』、その方法を」
それを聞いて、サリーは鼻で笑った。
当然それを見て苛立たないリュージュでは無かった。リュージュは一歩前に踏み出して、サリーの表情を見つめた。
「禁断の魔術……その方法、知らないとは言わせないわよ」
「禁断の魔術はどうして『禁断』と言われているのか、それを理解してから話したほうがいいと思うけれど? まさか祈祷師サマのくせにそこまで知らない、なんてことは……無いわよね?」
サリーはリュージュに対抗するように、そう言い返した。
「……人命を蘇生させる魔法、よね」
こくり、とリュージュは頷く。
「そう。そして、面白いことにその魔法は人間以外にも適用される。それは封印された、伝説のメタモルフォーズにだって……」
「やはり、それが目的なのね」
サリーの目線が冷たく突き刺さる。
しかし、そんなことリュージュには関係なかった。
「……オリジナルフォーズを復活させれば、世界を滅ぼすことだって、世界を管理することだって簡単にできる。だって、そうでしょう?」
「世界を滅ぼすことで……、何を生み出すというの? 何も生み出さない。それは無駄なことでしょう?」
「世界を滅ぼすことは簡単だ。その魔法を使ってオリジナルフォーズさえ復活させればいいのだから。そして、世界を滅ぼした後は新しい世界を生み出す。これぞ、テーラの予言を実現させたといえるのではないかしら?」
それを聞いて、サリーは溜息を吐く。
サリーは持っていた杖をリュージュに向けて、
「話し合いで解決するとは到底思えなかったけれど……、まさかこんな結末になるとはね」
「私を脅しても無駄よ。禁断の魔術が書かれた魔導書は、私の先祖によって封印されたのだから」
「封印……テーラめ、まさかそのようなことをしていたとは……!」
リュージュは深い溜息を吐いたのち、指を弾いた。
それと同時に、彼女の隣にバルト・イルファが出現した。
「やっほー。リュージュ様、いったい何をすればいいの?」
「この魔術師を殺しなさい。ああ、一応言っておくけれど手練れよ。そう簡単に倒せるものじゃない」
「なんか弱そうだけれど?」
「ルイスを殺したのは、この魔術師よ。そう言えば、あなたも少しは働く気になるかしら?」
それを聞いて、バルト・イルファは笑みを浮かべる。
今まで興味を抱かなかったのが、その事実を聞いて興味を持ったらしい。
「成る程ね……。ルイスを殺したのは、お前だったのか。だったらちょっとは興味を持ったかな」
そう言って、バルト・イルファは手から炎を出した。出した炎は何かの形に形成されていき、最終的にそれは剣の形となった。
炎の剣を構えて、バルト・イルファは言った。
「さて――どうなるか、試してみようかな。せめて僕を楽しませておくれよ?」
「そう余裕を言っているのも、今のうちかもしれないわよ?」
そうして、バルト・イルファとサリーの戦闘が始まった。
_ ◇◇◇
_ 気が付けば、僕は白い空間の中に居た。
そしてそこには一筋の川が流れていた。
そこに流れていたものは、記憶。
森の獅子との戦闘。
船が爆発して海に放り出されたこと。
トライヤムチェン族の集落での戦闘。
ラドーム学院での日常。
ゲーム屋での出来事。
色んなことが、記憶の川を遡ると見えてくる。自分でも『こんなことがあったのか』と思うくらいだ。
記憶の川は、さらに遡ることが出来る。
これから青春を送ると思われた高校時代。
何事もなく、一言でいえば真っ白な中学時代。
小学時代は何も知らずにひたすら騒いでいた。
幼稚園のころなんてもっとそうだった――と思う。
「……意外と覚えているものなんだな」
僕はそんなことを独り言ちった。
幼稚園に入園する前の自分は、自分で言うことではないけれど、とても可愛らしい。
しかし、そこで唐突に記憶の川は涸れていた。
「……あれ?」
おかしい。
そんなところで記憶の川が涸れるはずが無かった。
だって、そこからさらに遡って――『生まれる』という記憶が残っているはず。
けれど、記憶の川はここで終わっている。
自分は母親から生まれた、という『記録』は当然残っている。
けれど、『記憶』が残っていない。
「いったい、どういうことなんだろう……」
『フル…………!』
そこで、声が聞こえた。
記憶とは別の場所からの呼びかけだった。
_ 身体がゆすぶられて、僕はそこで目を覚ました。
「フル、フル! 起きて!」
「え……何……?」
見ると、メアリーが僕の身体を揺すって起こしてくれたのだと気付いた。
「もうすぐ城に着くよ。城に着いたら王様に謁見するから、きちんと眠気を覚ましておいてね」
「……ああ、解ったよ」
僕は目をこすりながら、馬車から外を見る。
どうやらもうリーガル城下に入っているようで、多種多様の店が軒先を並べ、人があふれていた。リーガル城は円形に形成されており、外殻に城下町が構成されている。内殻にある城と外殻にある城下町の間は堀があり、それを超えるために二つの橋が架けられている。しかしその橋も夜間になると閉められる――これはメアリーから聞いた基礎知識であって、僕はそれ以上のことは知らないのだけれど。
「フルは、リーガル城に来たことがないの?」
ミシェラの問いに僕は言葉を返す。
「そう言うからにはミシェラは来たことがあるのか?」
「城下町には数回ね。娼館は出張サービスもやっているから。さすがに城が近い場所だと警備も厳しいからあまり出来ないけれど、入口そばとかだと案外客が多いのよね」
溜息を吐いて、ミシェラは外を眺めた。
どうやら彼女にも彼女なりの思い出があるようだった。
橋を渡り、大きな門がゆっくりと開かれていく。
僕たちは、馬車に乗ったままリーガル城へと入っていった。
_ ◇◇◇
_ 燃えていくラドーム学院を眺めながら、リュージュは歩いていた。
「……まさか簡単に逃げられてしまうとはね」
「擬態魔法を使うなんて、やっぱりテーラの子孫なだけはあるよね。いや、もしくは学校の先生だったから?」
バルト・イルファは両手を頭の後ろに回して組み、笑いながらそう言った。
「あなたがさっさと倒さなかったからよ」
「だって逃げるんだもん。素早い、と言ったほうが正しいかな? まさかあそこまで逃げ足が速いとは思いもしなかったし」
「……まあ、それは確かね。もしかしたら最初から逃げる目的だったのかも」
「これからどうするの? だって、魔導書を探さないといけないんでしょ?」
「……それもそうねえ。確かに探さないといけないのだけれど、場所の見当がつかないと無理だし……。一先ず戻ることにするわ。あなたは?」
「僕も戻るよ。だってもう面白いことは無くなってしまったし」
そうね、とリュージュは言って右手を天に掲げた。
そしてリュージュたち二人の周りに自動的に円が描かれて、それが緑色の光を放つ。
それが消えたと同時に、リュージュたちの姿も――消えた。
リーガル城。
ハイダルクの首都にある城であり、その城下町のことを言う。
そして僕たちはゴードンさんに連れられて、王の間、その入り口へとたどり着いた。
階段を上った先にあったその入り口の両脇には兵士が立っていて、それぞれ守っているようだった。しかしながら彼らはゴードンさんよりも階級が低いためか、ゴードンさんを見かけるや否や敬礼をした。
「ここが王の間です。どうか、粗相のないように」
そう言って、ゴードンさんは立ち止まる。
どうやら、僕たちだけで王の間に入れ――ということらしい。
「……」
そして、僕たちはゆっくりと王の間へと、足を踏み入れていった。
扉の中は広々とした空間だった。松明の光で明るくなっているとはいえ、あまり日が入らないためか若干暗い部屋になっている。そして、王の頭上にあるステンドグラスから殆どの光が入っているようだった。ステンドグラスには林檎を抱えた女性が描かれていて――。
「フル・ヤタクミ、ルーシー・アドバリー、メアリー・ホープキン……か」
「はい」
王様の前では、その一言しかいうことが出来なかった。
王様は思ったよりも若々しかった。僕と見た目が変わらないくらい、年齢が同じなのではないかと――そう思ってしまうほどだった。
「そう固くしなくてもよい。楽にしたまえ。ラドームから話は聞いているよ。なんでもフル、おぬしが『予言の勇者』である、と……」
王様の隣には、禿げ頭の大臣と思われる人間が居た。
若い国王の補佐――とでも言えばいいだろうか。国王の表情を窺いながら、僕たちを監視するように睨みつけている。
「陛下。いかがなさいますか? 予言の勇者一行をハイダルクで保護する、ということになるのでしたら……」
「むろん、そのつもりだよ。しかしどこが空いていたかな。城下町の宿屋では、正直警護が完全に確保しづらい。となれば、やはり城の部屋になるか……」
「しかし城の部屋は埋まっているのでは? 兵士たちの居る寮ならば、空いているかもしれませんが」
「そこで良いだろう。何かあったとき、すぐに兵士たちが対応できる」
国王と大臣の短い会話を経て、国王は改めて僕たちのほうを向いた。
「……おっと、放置して済まなかったな。場所も決まったことだ。先ずは君たちを部屋に案内しよう。そして、明るいうちにこの町を案内させよう。案内は、ゴードンに任せることにするか」
云々と頷いて、国王は言った。
_ ゴードンさんに連れられて、僕たちは部屋に到着した。場所は国王が言っていた通り、兵士たちの宿舎の中にあり、すれ違う兵士たちに毎回敬礼されるというのは、少々こそばゆい気分にもなった。
部屋は二つ。男女でちょうど二人ずつになっているので、男女で分かれるほうが賢明だった。そして荷物を置いて、少し休憩してから僕たちは町へ繰り出すことになった。
城と町を結ぶ橋を、今度は歩いて渡り、城下町へと到着した。
「リーガル城の城下町は東西南北、四つのエリアに分かれている。商業、娯楽、住居、自然の分割になっていて、大抵そのエリア分割で成り立っている。ここは商業エリア。だから店も人も多い。住居エリアや自然エリアに行けば、もっと人は少なくなるし静かになる。……まあ、そんなことはどうでもいいことではあるが」
「どうしてそうエリアを分割したのでしょうか?」
ゴードンの説明に、最初に質問を入れたのはメアリーだった。
ゴードンは顎に手を当てて首を傾げ、
「ううむ、それはあまり解らないのだよ。何せ随分と昔からこのルールが適用されているものだからね。しかし、これによって税率を決定することが出来るようになったから、もしかしたら国民のことよりも国政のことを思って計画されたものなのかもしれないな」
成る程。
確かにそれならばエリアごとに政治体制を変えていけば簡単に政治を行うことが出来る。頭のいいやり方だったかもしれない。けれど、それはきっと僕の居た元の世界では当然できることではないと思うけれど。
それにしても、この道はとても広かった。馬車が通っても全然邪魔にならないほどだったことを考慮すればそれは当然のことだったし、そもそもこの道自体が城から入口までずっと真っ直ぐな道なので特別な道だということは理解できることだし、それによってこのような広さが維持されているのだと思うと納得できる。
「この町は美味しいモノが集まっている、グルメな町とも言われている。どうだい? 何か食べてみる、というのは。今は食べ歩きがこの町のトレンドになっているんだ」
ゴードンさんはそう言って、僕たちに提案した。
ちょうど僕たちもお腹が空いていたところだった――そう考えていた僕たちに、イエス以外の解答は有り得なかった。
_ それにしてもこの世界での食べ物って、どうして元の世界のそれと変わらないのだろうか。
今僕が食べているのは焼きそば。名前こそ違っているが、味はほぼ変わらない。さすがにレシピまでは教えてくれなかったが、キャベツにベーコンに、味付けにはソースを使っているはずだ。……もしかして異世界でも焼きそばがブームなのか?
そんなバカな、というセルフツッコミを入れて、僕は考えるのをやめた。
ちなみにこの道はとてもきれいだ。きれい、というのはゴミが落ちていない――ということである。けっこう目につく距離にゴミ箱が設置されているためだ。しかし、ゴミ箱が設置されているだけで人がゴミを捨てるかと言われるとそうではない。『ゴミ箱があるからゴミを拾おう』という価値観が確立されていない限り、そんなことは出来ない。
「よう、兄ちゃん! アピアルはどうだい? 新鮮でとってもおいしいぜ。それに食べると元気になる」
焼きそばを食べていた僕にそう声をかけてきたのは、青果店――元の世界で言うところの『八百屋』のような場所に居た人だった。ねじり鉢巻きをつけて、僕に何かを見せつけている。それがアピアルというものなのだろう。しかしながら、それはどう見ても林檎の類にしか見えないのだけれど。
「アピアルはこの世界にとって、知恵の木の実と同じ形状をしているから、ということでとても重宝されているね。滋養強壮にいいというからねえ、アピアルは」
ゴードンさんはそう言って僕たちに補足した。
この世界では林檎が重宝されている、ということか。確か前の世界でも林檎は滋養強壮にいいって言われていたし、この辺りは共通認識なのかもしれない。異世界と元の世界で共通認識とは何事か、という話になるけれど。
「アピアル、先ずは一個食べてみないかい? 新鮮で、とっても美味しいからさあ!」
そう言って店主は僕にアピアルを差し出す。そこまで言ってくるというのなら、やっぱり味に自信があるのだろう。そう思って、僕はアピアルを手に取った――その時だった。
右のほうから、声が聞こえた。
最初は微かなものだったけれど、徐々にこちらに近づいてきているのか、その声のトーンが大きくなってきている。
「どいた、どいたーッ!」
セミロングの金髪の少女だった。
着古した黒を基調とした服装は、露出度がそれなりにある。へそ出しルック、とでも言えばいいだろうか。そういう感じ。そんな彼女は、とても足が速かった。
「おっと、ごめんよ!」
僕たちにぶつかりそうになったのを、彼女はそう言ってうまい具合に避けた。
「大丈夫だったかい。まったく、アレは盗賊だよ。ああいう風に何かを盗んでは質屋に売りつける。残念ながら、あれも一つのビジネスとして成り立ってしまっているのが実情だ。我々も何とかせねばならないのだがね……」
じゃあ、何とかしてくださいよ。さっきの、普通に考えれば警察的役割たるあなたが何とかしないといけませんよね?
そんなことを思いながら僕はふと手を見つめる。
……無い。
さっきまで手に持っていたはずの、林檎が無い!
「ああ、もしかしてさっきの嬢ちゃんが奪っていったか? だとすれば災難だな。アイツは腕利きの盗賊として有名だよ。名前はなんと言ったかな……」
「レイナだ」
「レイナ」
「そう。彼女の住処は一切判明しないものでね。我々が探索してもうまく掻い潜るのだよ。味方であれば頼もしい存在ではあるが、如何せん彼女は盗賊だ。市民に迷惑をかけている以上、我々は彼女をとらえ、罰せねばならない」
「盗賊というのは、この町にたくさんいるものなのですか?」
メアリーの問いに、ゴードンさんは首を横に振る。
「いいや、そういうものではない。むしろ少ないと言ってもいいだろう。しかしながら、あのレイナという小娘は盗賊の中でも名が知れている。しかしながら、まだ住処の場所も掴めない。気付けば居る……そして雲のように消えてしまう……。そういう存在だと言われているのだよ、彼女は」
「だとすれば厄介だな……、あれ?」
そこで僕は、ある違和感に気付いた。
鞄に入れていたはずの、あるものが無かった。
それは鍵だった。トライヤムチェン族の長老からもらった、大事な鍵だった。
「……鍵が無い」
「鍵? 鍵ってまさか……」
一言だけメアリーたちに言うと、勘のいいメアリーはすぐに理解したようだった。青ざめた表情で、僕に告げる。
「うん。……トライヤムチェン族の長老にもらった、あの鍵が無い。どうやら盗まれてしまったみたいだ……」
「それは大事な鍵なのか?」
ゴードンさんの問いに、僕は頷いた。
小さく溜息を吐いて、ゴードンさんは踵を返した。
「まず町を訪れるときにそれについて説明したほうが良かったな……。いや、それについてはもう後の祭りではあるが、致し方ない。先ずは、それを解決する必要があるだろう」
「隊長、どうなさいましたか、このような場所で!」
ようやくレイナを追いかけていたであろう兵士が息絶え絶えにやってきた。
ゴードンさんは溜息を吐いたのち、
「どうした、ではない。ここに居る旅人も鍵やアピアルを盗まれたようだ。だから、私もレイナ逮捕に協力する。言え、やつは何を盗んだ?」
そうして兵士は頷くと、レイナが盗んだものを言った。
それは、銀時計だった。
「銀時計……だと? それは、国家直属兵士の証ではないか! なぜ、そんなことを盗まれてしまったのか? なぜだ!」
「はっ、恥ずかしいことではありますが、兵士が一瞬目を離したすきに……」
「馬鹿な。超人だというのか、あのレイナという盗人は!?」
ゴードンさんがそんなことを言ったが、きっとそんなことは無いのだろう。
紛れもない超人など、居るはずがない。きっと何らかのカラクリがあるはずだ。例えば、そう……。
「ゴードンさん。そのレイナという盗人は、魔術師だったのではないですか?」
……僕がその結論について述べる前に、メアリーが先に到達してしまっていたようだ。というかメアリーも同じ結論にたどり着いていたというのか。まあ、別に問題ないけれど。
メアリーの話は続く。
「魔術師ならば、すべて説明がつきますよ。そのレイナという盗人は転移魔法と変化魔法を使い分けているのです。だからこそ、誰も見つけることが出来なかった」
「馬鹿な……。魔術師ならば、魔法を使うまでの間にインターバルがあるはずだ。詠唱や、円を描くこと。それについては、どう説明すると?」
ゴードンさんの意見ももっともだった。
魔法を使う上で必要なこと――詠唱とファクター、その二つをどのように処理すれば、瞬間的に魔法を行使できるのか、それがゴードンさんの疑問点だった。
それについてメアリーは顎に手を当てて、
「たぶん、これは良そうですけれど……、きっと、省略することが可能だったのではないでしょうか? 『コードシート』を使えば、少なくともファクターについては解決します。そして詠唱についても……技術があれば省略は可能です。少なくとも一言二言は必要になると思いますが……」
コードシート。
また新単語が出てきたが、まあ、名前からしておそらくコードをプリントした紙のことを言うのだろう。コード、とは魔法や錬金術などを実行するときに円をファクターとして描きあげる特殊な図形のことを言う。普段はそのコードを実行時に描くものだが、それでは描いている間の時間がもったいない。
そういう理由で生み出されたのがコードシートだ。コードシートは使いたいところでそれを使うことで、あとは詠唱すれば術が発動するらしい。――まあ、それはあとでメアリーから聞いた話なのだけれど。
「成る程。コードシートですか。ははあ、私はあまり魔法には詳しくありませんが、コードシートならば聞いたことがあります。実用化出来ていませんが、それを実用化していずれは魔法を軍事転用しようと考えている研究者も少なくありませんから」
まあ、それは当然の帰結かもしれない。
今まで一部の人間しか使用できなかった魔法が、コードシートの開発によって専門の知識を必要としなくなるのであれば、それさえ持たせてしまえば一般人にだって魔法を使うことが出来るのだから、それをうまく活用するには――やはり軍事転用しかないのだろう。単調な考え方かもしれないが、一番効率のいいやり方かもしれない。
「コードシートを使っている、ということにして……。ならば、詠唱については? メアリーさん、詠唱は省略可能なのですか?」
「技術的には、可能です」
ゴードンさんの問いに、メアリーは即座に答えた。
一拍おいて、さらに彼女の話は続く。
「正確に言えば魔法において必要な詠唱のみ行えば、魔法としては発動できる、ということになります。魔法詠唱において必要なものは『承認詠唱』と『発動詠唱』のみ。普段は必要最低限のコードを描き、それの補足として詠唱を行いますが……事前に用意しておけるコードシートを使用すれば、それらは完全に無駄になります。正確に言えば、コードシートにそれを含めて描いてしまえばいいのです。そうすれば、残るのは承認詠唱と発動詠唱の二つ。それらは多くて四つの単語で構成されているので、十数秒もあれば詠唱は可能です」
「……要するに、コードシートさえあれば一分もかからずに魔法は発動できる、と?」
こくり。メアリーは頷いた。
ゴードンさんは何となく理解しているような表情を浮かべているが、残りの兵士は首を傾げているばかりで何も言わなかった。どうやら何も解らないようだった。
まあ、当然といえば当然かもしれない。魔法を使うことが出来る人間は専門の技術を身に着けないと出来ないので、ただの兵士には魔法は使えない――そんなことを授業で習うくらいなのだから、きっと彼らは魔法についての知識は、一般市民が知る程度の基礎知識しか知り得ていないのだろう。
ゴードンさんは咳払いを一つして、さらにメアリーに質問を投げかける。
「しかし、そうなると問題はどこへ居なくなってしまったか? ということになる。コードシートは消えてしまうのか?」
「もしかしたら複合魔法を発動しているのかもしれません。別に、一つの魔法陣から一つの魔法が生まれるわけではなく、一つのフローにそって複数の魔法を発動させることが出来ます。ですから、転移魔法や変化魔法を行使したあとに、コードシート自体を焼却する魔法を使えば……」
「証拠が残らない、ということか。なんてこった、なぜ今までこんなことに気付かなかったのだ……。気付いてさえいれば、簡単なロジックであるというのに」
確かに、気付いてさえしまえば簡単なロジックだ。
けれど、簡単なロジックは気付いたからこそ言える言葉であり、気付くまではいったいどうやって行使したのか解らない。即ち超人しか出来ないことではないか? ということを案外勝手に思い込んでしまうものだ。
しかし、それにしてもメアリーはどうして自分の専門以外の知識も持っているのだろうか? 授業で習った――ということでもなさそうだし、はっきり言って、錬金術と魔法は基本が一緒であるとはいえ、その仕組みの殆どはまったく異なるもののはずだ。だとすれば、メアリーが仕組みを理解できているというのは、やはり誰かから教わった――ということになるのだろうか。
「兎角、問題は一つ解決した、ということだ」
ゴードンさんは兵士に向き直り、そう言った。
確かに、これによってレイナが実施した方法は解決した。
しかし、問題はまだある。たとえレイナの移動方法が解決したとしても、レイナの根城自体は判明していないからだ。
「結論は見えています。……次にレイナが何を狙うか、予測を立てるしかありません。あるいは、レイナがどこで盗品を売りつけているか」
「はっきり言ってそれが解れば苦労しない。アイツが品を売りつけているのは裏町のどこか、ということしか判明していない。もし解るとすれば……」
「裏町の情報通、」
塞ぎ込んだかと思われた道に、活路を与えたのはミシェラだった。
「情報通?」
ゴードンさんは首を傾げて、ミシェラの目を見つめる。
「裏町には情報通が居るはずだよ。名前は誰にも明かしていないから、その姿しか判明していないけれど……」
「情報通なら聞いたことはある。どこに居るのかは解らないが、よく裏路地の喫茶店に居るという情報はあるな。ただ、アイツは我々のような存在を嫌っている。……どうすればいいものか」
「それ、僕たちに任せてくれませんか?」
僕はとっさにそう言った。
鍵を盗まれたし、ほかにも盗まれたものがあるという。
だったら、それを取り戻さないといけない。それが僕たちにしか出来ないというのであれば、なおさら。
「……それは君たちには出来ないよ。もともと追っていたのは、私たち国だ。国で何とかしないといけない問題を、君たち冒険者に任せるわけには……」
「しかし、兵士を嫌っているのも事実ですよね? その情報通というのは」
ゴードンさんは何も言い返せなかった。
決してゴードンさんを言葉攻めにしたかったわけではない。むしろゴードンさんを助けたくて、僕はこう言った。
きっとメアリーとルーシーが口を開いても、こう言ったに違いない。現にメアリーとルーシーの表情を見ると、彼らもまた頷いていたからだ。
それを見たゴードンさんは溜息を吐いて、僕たち三人の顔をじっと見つめて、
「……解った。そこまで言うのであれば、君たちに任せよう。オイ、その情報通が居るという噂の喫茶店はどこだ?」
「カルフィアストリートの脇にある喫茶店です。確か名前はテーブルノマスです」
「テーブルノマス、だそうだ。申し訳ない、よろしく頼む」
ゴードンさんは頭を下げて、僕たちに言った。
「いいえ、大丈夫ですよ。僕たちも物を盗まれました。いわば被害者です。それを取り戻さないと、僕たちは先に進めませんから」
「解った。……それでは君たちにすべてを託そう。テーブルノマスへと向かう行き方は兵士から教えてもらうことにして、何かあったら詰所へ向かってくれ。この紙切れを渡してくれれば、きっと詰所の兵士からこちらに連絡があるはずだ」
_ テーブルノマスという喫茶店はすぐに見つかった。
客も入っていない、見た様子では寂れているお店だったが、外から見るとひとりの男性がコーヒーを飲んでいた。
「……もしかしてアレが?」
「かもしれない。だってこのような場所に一人、よ? はっきり言って怪しいと言ってもおかしくない。何か秘密があるからこそ、ここに居るのよ。きっと」
メアリーの後押しを見て、僕たちは喫茶店の中へ足を踏み入れた。
カウンターの向こうにはマスターと思われる男性がコーヒーカップを磨いていたが、客が入ったことに対する挨拶など無く、ただ自分の行っている行為に集中しているようだった。はっきり言って、そんなことは客商売が成り立っているのかどうか疑問だが、まあ、そんなことは客である僕たちが考える必要も無いだろう。
情報通と思われる、一人の男性の前に立って、僕は言った。
「……お前が情報通か」
情報通と思われる男性はそれを聞いて僕を一瞥して、すぐにコーヒーを啜る。
「だとすれば、どうする?」
「情報を買いたい。それも早急に」
「……どのレベルの情報かによるが。先ずは、何の情報が欲しいのか、それを教えてもらおうか」
「レイナという盗人の住処、そこを教えてもらおう」
「……レイナ、か」
それを聞いた情報通は目を細めて、窓の外を眺めた。
暫し時間をおいて、情報通は溜息を吐いた。
「十万ドムでどうだ?」
十万ドム。
確か出発前にサリー先生から戴いたお金の全額が四十万ドムだったから、四分の一ということになる。
正直、それほどの価値があるとは思えない情報かもしれないが、あの鍵を取り返すためにはその情報が必要だった。
だから、僕は頷いた。
「……思い切りのいい人間は嫌いじゃないぜ。じゃあ、前金で支払ってもらおうか」
そう言って情報通は右手を差し出す。
次いで、僕は麻袋から十枚の金貨を取り出してそれを情報通に差し出した。
情報通はしっかりと一枚一枚丁寧に数えて、頷く。
「よし、きちんと十枚確認したぞ。……それじゃ、お望みの情報を教えようじゃないか。しかし、残念なことに、あのレイナの居住地は誰にも解らない」
「ちょっとあなた、それって……!」
それは裏切りと言ってもいい。
メアリーが前のめりに彼に問い質そうとする気持ちも解る。
だが、情報通はそれを右手で制すと、
「ただ、レイナは毎日手に入れたものを裏道にある特定の質屋へと向かって換金している。そこはレイナをひいきにしているらしいからな。なんでも、レイナが盗賊稼業をする理由がその質屋にあるとも言われているが……、おっと、それは余談だったな。いずれにせよ、その質屋に行けば、確実にレイナに会えると思うぞ。まあ、そのあとはお前たち次第だがな」
_ レイナが行くという質屋は、そう遠くない距離にあった。
「ほんとうにあの情報通は、正しい情報を教えてくれたのでしょうね?」
メアリーは強い口調でそう言ったが、そんなことは正直言って誰にも解らない。解らないからこそ、実際に行って確かめるしかない。
裏路地はたくさんの店が軒を連ねている表通りとは違って暗い雰囲気に包まれていた。店も疎らだし、その開いている店も正直まともな店ばかりとは言い難い。まあ、だから裏路地と言われているのかもしれないけれど。表通りにはない店ばかりが並んでいるからといって、それが万人に受けるものであればさっさと表通りに移転するのが普通だろうし。
「……なあ、フル。それにしてもこのようなところに店なんてあるのか? 人も通っていないし、どちらかというと、ただの抜け道のような感じにしか見えないけれど……」
「そうかもしれないが、進むしかないだろ? 十万ドムの情報だぞ。はっきり言って安くない。それをどうにかして稼がないといけないことも考慮しても、先ずはこの情報を有用に使わないといけない。それが誤っている情報であったとしても、だ」
暫く歩いていくと、明かりが目に入った。この路地はとても暗くなっているためか、このような時間でも明かりをつけているのだろう。
「……もしかして」
小さく出ている看板には、『何でも買います 質屋シルディア』と書いてあった。
「これがあの情報通が言った……?」
「そうかもしれないな」
そうして、僕たちはその質屋へと入っていった。
_ ◇◇◇
_ 質屋の中にはどこで手に入れたのか解らないモノがたくさん広がっていた。
そして、カウンターの向こうにはローブに身を包んだ白髪の女性が椅子に腰かけて、笑みを浮かべていた。
「いらっしゃい。……おや、見ない顔だね。売りに来たのかい、買いに来たのかい」
「人を探しているのだけれど。名前はレイナ」
「……レイナなら今日はまだ来ていないよ。だから、そう遠くない時間にやってくるのではないかな。……それにしても、彼女に会いたいとかどういうことかね? それに、別にここはそういう施設ではないし。まあ、彼女に会いたいということは大方予想がつくが」
どうやら彼女にモノを盗まれた人間がここまで到達することは、よくあるらしい。
「でも、彼女と交渉してモノを奪い返そう、というのであればソイツは筋違いだ。我々の世界では、奪ってしまえば同時に権利も奪える。即ち、奪ってしまえばそれはその奪った人間のモノになるわけだよ」
「そんなことが……!」
「有り得るわけがない。または、通用するはずがない。そう言いたいのだろう? でも、それは表の世界のルール。これは、裏の世界のルールだよ。それは別にへんなことではないし、むしろ裏の世界からすれば表の世界のルールがおかしい、ってものさ」
「そんな……!」
メアリーは思わず絶句した。
対してミシェラは何となく予想がついていたからか、何も反応しなかった。
彼女もどちらかといえば、娼婦という裏の世界に近い人間として過ごしてきたからか、そういうことも知っていたのかもしれない。
「……ただし、権利を譲渡することはたった一つだけできる。……モノを買えばいいのだよ」
「何ですって……」
「この世は金だ。金さえあればそんな些細な問題はあっという間に解決することが出来るよ。だから……どうだい? 金を払ってみる、というのは」
そんなバカな。
奪われて、それを取り返そうとしたら、金を払え――だって? そんな理不尽な話があってたまるか。そんなことを思わず口走りそうになったが、何とかそれを呑み込んで、
「……じゃあ、仮に、お金を払うとしましょう」
僕がどうするか齷齪しているとき、メアリーが一歩前に出て言った。
その言葉を聞いてメアリー以外の僕たちは、驚きを隠せなかった。対して、メアリーは自信満々な表情を浮かべて、さらに話を続けた。
「そうすれば本当に返してくれるのかしら?」
「あたりまえだ。この世は金だからな。それに対する代価さえ払えば、どんなものでも売ってやろうじゃないか。それで商売が成立するからな」
「言ったわね」
メアリーがなぜか珍しく、もう一歩前に進んで言った。
「……あ、ああ。言ったとも。だが、君たちのような学生に、そのような大金が払えるのかね? 払えるのであれば、どんなものでも売ってあげようではないか!」
メアリーはその言葉を切るように、カウンターにあるものを置いた。
それは、小さな紙切れだった。
そこには数字が書かれている。その数字は、とても大きな数字となっている。
「……な、何だ。この数字は……?」
あまりの大きさに、商人も呆れ返ってしまっていた。要は、それほどの巨額だった。
メアリーの話は続く。
「もしそれでも足りないというのであれば、まだ何枚か同じ金額が書かれたそれはあるわ。だから、幾らでも言うがいい」
「……あんた、あんた、何者だよ! どうして、どうしてそんな大量の金額を持っているんだ? 富豪か王族じゃないと手に入らないほどの巨額じゃないか!」
「私はただの学生よ」
商人の言葉をそう一蹴するメアリー。
「けれど、学生の本気は、幾らでも大きい。あなたが思っている以上に、ね。さあ、これでレイナからあの鍵とアピアル、それに銀時計を回収することは可能よね?」
「ふうん、なんだか面白いことになっているじゃないか」
背後から声が聞こえた。
その方向を振り向くと――そこに立っているのは、先ほど僕から鍵と林檎を奪い取った、レイナだった。レイナが笑みを浮かべて、そこに立っていたのだ。
「まさか、リムに自ら交渉をする人間が居るとは思いもしなかった」
レイナはそう言って、ゆっくりと僕たちのほうへと歩いていく。
それは興味を抱いているようにも見えたし、恐怖を抱いているようにも見えた。
レイナは僕の前に立って、呟く。
「……何が目的だ?」
「何が目的? そんなこと、言わなくても解っているだろう。鍵を返せ。それは大切なモノだ。あと、アピアルと銀時計も返すんだ。そして、もし可能ならば、出来る限り、奪ったモノをもとの人間に返せ」
「……欲張りだねえ。そんなこと、簡単に出来るわけがないじゃないか」
レイナはニヒルな笑みを浮かべる。
そんなこと予想は出来ていた。
だけれど、関係ない。
たとえそんなことを言われようとも――やらないといけないことがあるのは紛れもない事実だ。
「出来るわけがない……かもしれない。けれど、やらないといけないんだ。だって、僕は予言の勇者と言われているのだから。予言の通りならば、世界を救わないといけない」
「世界を救うぅ? そんなこと、出来ると思っているの!」
レイナは両手を広げて、口の端を吊り上げる。
「治安維持、という大義名分を掲げて私たちのような下位身分の存在を抹消しようとしていた、現政権のことを知っているかい?」
現政権。
即ち、現在も王として君臨している人間、ということになる。
「……現政権が、そんなことを言っているというの?」
「そうだよ。まあ、大臣がそれを止めていると言っているが、その大臣が止めている理由も、きっとろくでもない理由に違いない。おそらく、我々を必要悪として、庶民にとって最下層の存在を敢えて見せつけることで、それになりたくないと思わせることもあるのだろう。……まあ、どこまでほんとうかどうかは、あくまでも噂の段階だが」
噂の段階でここまで断言できるということは、それなりの理由があるのだろうか。
「でもそれはあなたの事情でしょう」
しかし、それを一刀両断したのはメアリーの言葉だった。
「何が言いたいの?」
「何度でも言ってあげるわ。それはあなたの事情。あなたの考え。それを他人に押し付けることは、はっきり言って間違っている」
「……あなた、態度と考えが間違っているように見えるのだけれど?」
レイナは怒っているように見える。
マズイ。このままだとモノを返してもらえなくなる! どうにかしてメアリーとレイナの口論を止めて、謝罪しないと、何も進まないし、これ以上話が拗れかねない。それだけは防がねば。
「まあまあ、そのあたりで……」
「それじゃ、私から一つ提案しましょうか」
レイナの言葉に、僕たちは目を丸くした。
いったいどのような提案を言われるのだろうか。まったく予想出来なかったからだ。
「私は昔からあるものを探している。それを見つけるためには、どのような手段だって問わない。その証拠というか、その秘密というか、その手がかりを見つけたかった」
「……それは?」
「知恵の木、という木だよ。すべてが金に輝く、伝説の木。その木には、『知恵の木の実』という木の実が生っている、とも言われている。けれど、その木を見つけた人間は誰も居ない。だから、それを見つけたい。そうすれば、私も世界に名を遺すことが出来る」
知恵の木。
知恵の木の実がどういうものであるかは知らないが、それが生るものということはもっとすごいものに違いない。
「知恵の木の実……伝説上に言われている、エネルギーの塊。それが生っているということは、エネルギーをさらに蓄えた、その源……ということよね? 知恵の木の実ですら伝説上と言われているのに」
こくり。レイナは頷く。
「話が解るようで何より。知恵の木は歴史書にも殆ど記述がないと言われているほど、観測者も少ない。だからこそ、探したいのよ。その『知恵の木』を見つけることが出来れば、私は先人よりも先に進むことが出来る……!」
「話を戻しましょうか」
メアリーは唐突に話のハンドルを切った。
「あなたの提案を、簡潔にまとめてもらいましょうか? つまり、『知恵の木』を探したい――と」
「知恵の木を探したい。それは確かにそう、そして、それを求めるためにはいずれリーガル城を出ていく必要がある。広い世界を知る必要がある、というわけよ」
レイナは壁をたたいて、さらに話を続ける。――正確に言えば、壁をたたいた段階で質屋の店主がぎょろりとレイナのほうを睨みつけたが、レイナはそれを無視していた。どうやら、日常茶飯事のようだった。
「そしてあなたたちは世界を旅している。だって予言の勇者、なのでしょう? ということは世界を救うために、世界を旅している。ということは、『知恵の木』の情報が手に入る可能性が高い……というわけよ。そこで、提案に戻る」
レイナは人差し指を立てて、メアリーに向けて言った。
「私を、あなたたちのメンバーに入れてよ。決して、悪い話ではないと思う……からさ」
_ はっきり言って、レイナのその発言を一言で示すとなれば、『自分勝手』の一言で収まると思う。だって、誰の意見も聞くことなく、対立していた人間と唐突に同盟を組もう、等と言い出すのだから。
そんなこと、普通の人間だったらどうやってオーケイを出すことが出来るのか?
きっと僕だったらオーケイを出さないかもしれないけれど――。
「ほんとうに、それを聞いたらモノを返してくれるというのね?」
そう答えたのはメアリーだった。
「ああ、それは嘘を吐かないよ。私は嘘を吐かないことを信条にしているからね。それに、君たちこそ信じてくれているだろうね? もし、君たちがやだというのならば、私もこれを返すことに関しては否定的になるけれど」
「……おい、メアリー。ほんとうにいいのか?」
「何が?」
僕はメアリーに問いかける。
けれどメアリーは何も思っていない様子で、きょとんとした表情を浮かべて首を傾げた。
きっとあまり気にしていないことなのだろう。
「……取り敢えず、交渉成立ということで。じゃあ、私はモノを返してあげる。だから、あなたたちのメンバーとともに旅をする、ってことでいいよね」
そう言ってレイナは僕に近づくと、あるものを差し出した。
それは僕から奪ったとみられる鍵とアピアルだった。
「……まだ足りないぞ」
「ああ。そうだったわね。ええと……」
そうしてレイナはもう一つ、ほとんど忘れ去られていたかのような扱いだった銀時計を差し出した。
「これで一先ず解決……か? まあ、いろいろと語るべきポイントはあるけれど」
ルーシーの言葉に僕は頷く。確かに、このような結末でゴードンさんたちが納得してくれるかどうか、それが一番のポイントだと思う。
まあ、取り敢えず、決まってしまったことは仕方ない――そう思うと、僕は目を瞑った。
_ ◇◇◇
_ 結局、ゴードンさんは僕たちに対して怒ることはしなかった。
レイナに対しても、彼女がそう言ったのならば仕方がないとして、お咎めなしとなった。それが果たして今後どれだけの結果を生み出すのかは解らないけれど、一先ず僕たちはゆっくりと休むことにした。
「それにしても、旅はこれで終わりなのか……?」
みんなが集まったところで、開口一番そう言ったのはルーシーだった。
「少なくとも、これで終わりでしょうね。世界の終わり、と言われていてもどのように世界が終わるかも解らないし、そうなればこのまま待機するだけじゃないかしら。大人がどうにかしてくれる、というか子供がどう転ぼうとも大人はそれを咎めるだけだから」
ルーシーの問いに、現実的な解答を示すメアリー。
しかしながら、お互いの言葉はまったく間違って等いなかった。
しかしながら、それをそのまま認めるわけにもいかない。それは僕も思っていた。
「まあ、それについては明日考えることにしようよ」
僕はそう言った。
あくまでもその場を逃げるため――ではない。
お互いに考えるための時間を設けるべく、そう言っただけに過ぎない。
けれど、それがほんとうにどこまで出来るかは解らないけれど、とにかく、今の僕たちにとっては時間が必要だった。
そしてそれについて否定する意見が無く、僕のその意見はそのまま受け入れられることになった。
そうして、食事を終えて――僕たちはそれぞれに用意された部屋に入り、そして気が付けば僕たちは深い眠りについた。
_ その夜。
僕は夜空を見つめながら、記憶の川を遡っていた。
中学時代、小学時代、幼稚園――記憶の川はそこまで遡っても、鮮明に思い浮かべることが出来る。
しかし、やはりというか、予想通り、同じところで記憶の川はぷっつりと涸れていた。
「……どうして?」
僕は誰にも聞こえないほど小さい声で、ぽつりとつぶやいた。
「どうして……これ以上、僕の記憶は遡れないんだ?」
僕のつぶやきは誰にも聞こえない。そして、その質問は誰にもこたえることは出来ない。
そう思って――そう結論付けて――僕は無理やり目を瞑ってどうにかして眠ろうと布団に深く潜っていった。
_ ◇◇◇
_ 次の日の朝は、轟音で目を覚ました。耳を劈く程の轟音は、それを聞いた僕たち全員が一斉に起き上がった程だった。
「なんだ、今の音は!」
起き上がると、僕は窓のほうを見る。
窓の向こうには城壁が広がっており、そのあたりから黒煙が上がっていた。
「みなさん! 大変です!」
ゴードンさんがノックもせずに入ってきたのは、ちょうどその時だった。
「何があったんですか?」
ほかの部屋に居たメアリーも、どうやらその轟音に気付いたらしい。目を覚まして、ネグリジェ姿のままゴードンさんに問いかける。
ゴードンさんは息を乱したままだったが、そのまま答えた。
「はい。実は、北のほうから大量のバケモノが空を飛んできているのです。目標はおそらく……いや、確実に、このリーガル城を狙っているものとみられます」
「バケモノ……もしかして!」
「ええ、おそらく、メタモルフォーズ、でしょうね」
ゴードンさんの言葉に僕とメアリーは意識合わせする。
対して、何も知らないゴードンさんは首を傾げる。
「メタモルフォーズ……とは?」
「説明している時間は有りません、残念ながら。取り敢えず、外へ向かいましょう。フル、ルーシー、ちょっと着替えてくるからあなたたちも着替えて。大急ぎで向かいましょう!」
メアリーはそう早口で捲し立てて、そのまま部屋へ戻っていった。
僕たちが着替え終わるまで二分、メアリーがその後遅れて三十秒後に到着。最終的に二分三十秒余りの時間を要して、僕たちは外へと向かうことになった。
外へ向かうまでは迷路のように入り組んだ通路を通ることとなるので、ゴードンさんを先頭にして僕たちは進むこととなった。
道中行き交う人たちは、どこか忙しない。毎回、僕たちに敬礼をしてくるので僕たちもそれに倣って返すのだけれど、外に近づくにつれてそれも億劫になるのか、立ち止まることなく一礼のみして立ち去る人も出てくる。
「どうやら、想像以上に大事になってきているようですね。兵士が無礼を働いているかもしれませんが、お許しください」
「いえ……。忙しいようでしたら、仕方ありません。別に、これが悪いことでもありませんから」
言ったのはメアリーだった。メアリーはこういうときでも落ち着いている。いや、むしろこれが彼女の取柄なのかもしれない。
外に出ると、すぐに爆音が僕たちの耳に届いた。
「……さっきの轟音はこれが原因か」
僕は呟く。状況判断して、それを呟いた。
爆音の正体は城壁の上に設置されている砲台だ。確か魔術で動く砲台となっているので、砲台の下には魔法陣が描かれており、その魔法陣には自動で作動できるようなプログラムが組み込まれているのだという。
魔術は古き良きスタイルで、いちいち魔法陣を描くスタイルもあれば、一つのシンプルなフローであればルーティンワークを実行するプログラムを魔法陣に組み込むことで自動的に魔術を打ち込むことが出来る、いかにも現代チックな魔術のスタイルもある。
……まあ、なんだかよく解らないけれど、プログラムに関しては案外簡単な構文らしいので、学生でも作ることが出来るのだという。というか、ラドーム学院でも魔術のプログラミングの授業は設けられている。たしかカリキュラムにそんなことが書いてあった気がする。……それだけは、受けてみたい。
「問題は、あのメタモルフォーズ……だったか。あれに攻撃が命中しても、うまくいかないということだ」
「うまくいかない? それってつまり、どういうことですか」
「簡単なことだよ。命中してもダメージを受けているように見えないのだ。……あれほどの数が、一匹も倒せないままリーガル城の区々にやってきたら、すべてがおしまいだ。少なくとも、町に住む人々が犠牲になることは避けられない。だが、それを避けなくてはならない。どうにかして、あれを駆除する必要がある」
命中しても、ダメージを受けていない?
仮にそれが事実だとすれば、確かに非常に厄介なことである。即ち、今の僕たちの腕ではメタモルフォーズの大群を倒すことは出来ないということを意味しているのだから。
しかし、そうとすればどうすればいいのか……。
「ヤタクミ、どうやら助けが欲しいようですね」
声を聴いて、僕は振り返った。
そこに立っていたのは――サリー先生だった。
「サリー先生? どうして、ここに。ラドーム学院に居たはずじゃ……」
「再会の余韻に浸りたいところだけれど、それは一旦おいておきましょうか。問題は目の前に広がっている、あのメタモルフォーズの大群。攻撃が通らないということですが……、もしかしたら、可能性はなくなったわけではないかもしれませんよ」
そう言って、サリー先生はあるものを取り出した。
それは望遠鏡のようだった。そしてそれを通して、サリー先生はメタモルフォーズの大群を見つめる。
「……もう一発、砲台を使用してもらえますか?」
サリー先生の言葉を聞いて、ゴードンさんは頷いた。
「それに関しては問題ないが……、しかしメタモルフォーズにはそれが効かないのだろう? だとすれば使う意味が無いように思えるが……」
「いいえ、今こそ使うべきです。おねがいします!」
「……解った。おい、もう一度魔術を行使しろ!」
ゴードンさんの言葉を聞いて、砲台のそばにいた兵士が慌ただしく準備を始めた。
_ それから兵士が準備を終えるまで数瞬とかからなかった。ほんとうにあっという間に、「終わりました!」と言ってゴードンさんに向けて敬礼した。
それを確認したゴードンさんは頷いて、サリー先生に訊ねる。
「……よろしいのですね?」
「ええ。一つ、確認したい事があります。そのためにも、もう一度攻撃をしてもらうほかありません」
「了解しました。……おい、攻撃を開始しろ!」
即座に敬礼して、兵士は魔術を行使する。そして、数瞬の間をおいて、砲弾が撃ち放たれた。
砲弾――というのは説明としては間違いかもしれない。なぜならばその砲台から放たれたものはどちらかといえばレーザーに近いものだったからだ。レーザー、といえば科学技術の結晶に見えるかもしれないけれど、それはどうなのだろうか。案外、この世界の科学技術は発展しているのかもしれない。
「……やはり、そうだったのね」
双眼鏡でメタモルフォーズを見つめていたサリー先生は、そう言って僕たちのほうを向いた。
「……サリー先生、いったい何を見つけたというのですか?」
「一言、簡単に結論を述べましょうか」
サリー先生は歌うように言って、ゴードンさんの前に立った。
ゴードンさんは、彼のほうを睨みつけるサリー先生を見て、たじろいでしまう。
「な、何か解ったのであれば、教えていただきたいのですが……」
「あのメタモルフォーズはすべてまやかしよ。本物はどこか別に居る」
「何……だと?」
空に浮かぶ――こちらにやってくるメタモルフォーズの大群を指さして、
「なぜ私があなたたちにもう一度砲弾を撃ってほしい、と言ったかというと、これを確認したかったから。メタモルフォーズに命中したと思われるそれは、案の定命中したように見せかけただけだった。雲のようになっていた、とでも言えばいいでしょう」
「メタモルフォーズを操っている敵、ではなく……あれだけの量のメタモルフォーズが『居る』と見せかけた、ということですか?」
こくり。サリー先生は頷いた。
「成る程……。となると、それらを操っている敵を倒せば、あのメタモルフォーズの大群も消える、ということですね?」
「そうなるでしょう。……そして、その人間の見立てもすでについています」
「それは……いったい!」
ゴードンさんは鬼気迫る勢いでサリー先生に問いかけた。
「それは……」
指さしたその先には、一人の少女が立っていた。
そこに立っていたのは――ミシェラだった。
「……サリー先生、あなたはいったい何を……」
メアリーは疑問を投げかける。
しかし、それよりも早くサリー先生がミシェラのほうへと歩き出す。ミシェラはずっとサリー先生のほうを向いて、表情を変えることは無かった。
そしてミシェラとサリー先生が対面する。
「言いなさい。あなたは何が目的で、このようなことを?」
サリー先生の言葉に、ミシェラは答えない。
暫しの間、沈黙が場を包み込んだ。当たり前だが、このような間でもメタモルフォーズの大群は城へ向かって邁進し続けている。
沈黙を破ったのは、ミシェラのほうだった。
ニヒルな笑みを浮かべて、ミシェラは深い溜息を吐いた。
「……あーあ、まさかこんなにも早く判明してしまうなんてね。それにしても、あなたから出てくるそのオーラ、ただの学校の先生には見えないけれど」
「そんなことは今関係ないでしょう? 結果として、あなたはメタモルフォーズの大群を操っている……ということで間違いないのかしら」
「だとしたら、どうする?」
ミシェラはそういうと――消えた。
「消えた!?」
「いや、違う……。ここよ!」
しかし、サリー先生だけがその姿を捉えていた。
サリー先生の拳が、確かにミシェラの姿を捉えていたのだった。
「……くっ。まさか、人間風情に……!」
「人間だから、何だというの? そう簡単に倒せると思ったら、大間違いよ」
「貴様を逮捕する」
次いで、ゴードンさんがミシェラに近づいた。
「逮捕? そんなことは出来ないわ。するならば、それよりも早く――」
ミシェラはどこからか取り出したナイフを、自らの首に当てる。同時にミシェラはサリー先生の手から離れ、僕たちに見せつけるようにナイフに力をかけた。
「貴様、まさか――!」
サリー先生とゴードンさんがナイフを奪おうと、ミシェラのほうへ走っていく。
「フル・ヤタクミ。あなたはどういう未来を歩もうが、もう結論は見えている。この世界を救うなんてことはムリ。メタモルフォーズが世界を覆いつくす、その日は、そう遠くない!」
彼女は笑顔でそう言った。
その笑顔はとても臆病で、恐怖で、狡猾だった。
「……何を言っても、無駄だ。人間はメタモルフォーズには屈しない」
「そう言っていられるのも今のうちよ」
そうして、ゴードンさんがミシェラの前に立ったタイミングで――ミシェラは首を切り裂いたのか、彼女が横に倒れた。
なぜそれが断定出来なかったかと言えば、ゴードンさんが前に立っていて、その瞬間を見ることが出来なかったからだ。
もし、それを見ていたらきっと僕たちの心に何らかの傷を植え付けていたかもしれない。
ごとり、と何かが床に落ちる音――きっとその対象は、『首』だったのだろう――を聞いて、僕たちはゆっくりとそちらに近づく。
しかし、それをしようとしたタイミングで、サリー先生が僕たちの前に立ち塞がった。
「見ないほうがいい」
その言葉を口にしただけで、あとは何も言わなかった。
けれど僕たちも、不思議とそれ以上何も語ろうとはしなかった。
_ ◇◇◇
_ そのあとの話を簡単に。
ミシェラが殺されたことによって、メタモルフォーズの大群は消え去った。やはりサリー先生の予想通り、ただの幻影だったらしい。もし彼女が死んでも消えなかったらそれはそれで厄介だったが。
ミシェラの遺体は秘密裡に処理されることとなり、そのまま淀み無くエルファスに居るカーラさんの元へ届けられることとなった。『処理』と言ってもあくまでも火葬や土葬の段階まで進めたわけではなく、必要最低限の処置をしたまでのことだという。
カーラさんがどのような心境でその事実を聞いたのか――出来れば考えたくない。
その日の夜は酷く眠れなかった。
目の前で首を斬られた人間を見たから?
それとも仲間が裏切ったから?
……いいや、何故だろうか。
どうして眠れなくなってしまったのか――それについては理解できなかった。理解したくなかった、と言えば間違いではないのかもしれないけれど、きっとそれは、いろんな感情がごちゃ混ぜになってしまった、その結果なのかもしれない。
「……フル、眠れないの?」
外を見つめていたら、隣から声が聞こえた。
その声はメアリーだった。そちらを向くと、メアリーも隣のベランダから空を眺めているようだった。ああ、そうだった。説明を省いていたかもしれないけれど、今日も男女別の部屋だ。別に何も起きないけれど、何か起きたら……という配慮なのだろう。
「そうだね、ちょっと今日はいろいろあったから……」
「そうだよね。仕方ない、なんて一言では片付けられないくらい、今日はいろいろとあったよ。……まさか彼女が敵なんて、知るはずがないのだから」
メアリーの言葉ももっともだった。もしあの状況で敵だと解るのならば、それは予知のレベルに近い。
でも、そんな理不尽ともいえることであったとしても、僕は自分が許せなかった。
どうしてこのような結末を、防ぐことが出来なかったのか――ということについて。
「難しく考えないほうがいいよ」
そう言って、深く溜息を吐いたのはメアリーだった。
さらにメアリーの話は続く。
「普通に考えても解る話じゃないよ。だって、あなたは悪くないのよ。私だって、ルーシーだってそう。みんな悪くないの。あなただけが悪いわけじゃない。誰も悪くないのよ」
「うん……ありがとうメアリー。なんだか少しだけ、頑張れる気がするよ」
メアリーはいつも勇気をくれる。僕を励ましてくれる。とっても優しい。
メアリーが居るから、僕は頑張れる気がする。
そう思ってメアリーと別れると、僕はそのままベッドに潜り込んだ。
やっぱり眠れなかったけれど、メアリーと話したからか、少しだけ眠れるような気がした。
_ ◇◇◇
リュージュは水晶玉を見つめながら、彼女の向こう側に膝をついている科学者に告げた。
「はっ。リーガル城へと向かわせたメタモルフォーズが不完全だったようで……」
「だから言ったじゃない。自分で精神をコントロールできないようならば、ココロをメタモルフォーズに植え付けるのではない、と。メタモルフォーズはただの木偶。けれど優秀なメタモルフォーズにはココロを植え付けて自分で物事を考えさせる」
「僕のように?」
リュージュの隣にバルト・イルファが近づいた。
バルト・イルファはリュージュが腰かける椅子に体重を乗せて、
「……まあ、ココロって不完全で不確かなもの、というくらいだからね。それがほんとうに正しいか正しくないか、なんて科学者のミナサンにも難しいことじゃない?」
「……それをメタモルフォーズであるあなたが言うのかしら?」
リュージュは溜息を吐いて、再び科学者を見遣る。
「はてさて、今回の失敗について、どう言い訳をするつもりかしら」
「メタモルフォーズにはその種を広げていくための手段があることをご存知でしょうか」
逆に質問されたリュージュは一度バルト・イルファのほうを見て、考える。
数瞬の時間をおいて科学者を見ると、
「感染、だったかしら。空気感染ではなくて、経口感染だったと記憶しているけれど」
「ええ。そしてメタモルフォーズに感染する人間には特徴があると考えています。しかしながらまだその条件ははっきりとしておらず、未確定となっているのですが……」
「それがどうかしたのかしら? 明らかに言い訳とは繋がらないように見えるけれど」
「いいえ、これは言い訳ではありません。一つのプランの説明をしています。メタモルフォーズを失ってばかりでは、こちらもすぐに戦力の増強が出来ませんから。先ずは、あと一日お待ちいただけませんか。そうして、ある一定の結果を生み出すことが出来るはずです」
「……ほんとうに?」
科学者は何も言わなかった。
それを見たリュージュのほうが先に折れた。
「……解ったわ。あと一日だけ時間を与えましょう。しかし、それでいい結果が得られなければ……その時は、覚えておくことね」
小さく首を垂れたまま、科学者は何も言わなかった。
リュージュは椅子から立ち上がると、バルト・イルファとともに部屋を出ていった。
次の日の朝。
目を覚ました僕たちは町へ向かうこととなった。理由は特にないけれど、しいて言うならばレイナが町へ向かいたいと言い出したことが原因だった。
「……どうして町へ向かおうとしたんだい?」
「だって、もうあんたたちはこの町を出ていくだろう?」
振り返り、レイナは言った。
「だったらこの町でやり残したことをすべて終わらせてしまったほうがいいんじゃないかしら? それとも、まだ戻れる可能性を残しておいたほうがいいとでも?」
可能性。
やり残したこと。
まるでもうここには戻りたくない――レイナはそんなことを言っているようだった。
きっと気のせいなのかもしれないけれど……まあ、あまり考えないでおいた。
それはそれとして。
僕たちは町を歩いていた。今居るのは商業店が多く立ち並ぶエリア。ここに居る理由は、彼女がずっと生業としていた盗賊稼業で『世話になった』人たちに挨拶に回るためだという。
「というか、世話になった、って……単純に今までモノを盗んだ人たち、じゃないの?」
「君たちはそういう風に解釈してしまうのかもしれないけれど、私は少なくともそのように解釈していないよ。実際、私はずっとこの町と生きてきた。この町の人たちと、常に切磋琢磨しながら活動してきたんだから」
「それが犯罪行為だったとしても、そう胸を張って言えることかね?」
その声は、ゴードンさんの声だった。
ゴードンさんは路地から姿を見せて、僕たちの前に立っていた。
「……何か用かしら?」
「別に君を捕まえるつもりなど無いよ。……ただ、君が居なくなると少し寂しくなるな、というだけだ」
「もっと私に暴れてほしい、ってことか?」
「そういうことではない。君はずっと私たち兵士たちを悩ませていた。しかし、この平和な世界では君のような盗賊に手を拱いている状況こそが、平和の象徴そのものだったのかもしれないな……。ただ、それを言いたかっただけだ」
「褒められているのか貶されているのか解らないが……、まあ、受け取っておくよ。もう二度とあんたと追いかけっこすることも無くなるだろうし」
「それが『足を洗った』という意味での話であれば、こちらも両手をたたいて歓迎したかったところだが……。やっぱり盗賊稼業は続けるつもりかい?」
「どうだろうねえ。やっぱりこういうメンバーに入った以上は出来ないかもしれないよ。ほら、だって、迷惑をかけることになるだろう? 迷惑をかけてしまったら、私が求めるものも手に入らなくなる。まさに、ギブアンドテイクというやつだ」
「……よく解らんが、お前らしいといえば、らしいものだ」
鼻で笑うゴードンさん。
それを見たレイナはどこか恥ずかしそうな表情を浮かべて、すたすたと歩いていった。
「結局変わらないか……。まあ、仕方ないといえば仕方ないかもしれないが。いずれにせよ、この町が若干静かになることは間違いないだろうよ」
ゴードンさんの言葉を聞いて、首を傾げるメアリー。
「それじゃ……あんまりこの町って犯罪とか起きないんですか?」
「起きないよ。この町の平和ぶりを見てみれば解る話だろう? この町はいつも平和だ。だが、平和はいつまでも続くものではない。むしろ平和以外の時間に比べれば限りなくゼロに近いくらい短いものだ。そんな中、この町で唯一の犯罪者と言えば……レイナだった」
「レイナが……唯一?」
確かにこの町はのほほんとした雰囲気を醸し出していて、どちらかといえば平和一色としか言いようがないくらいの雰囲気に包まれているのだけれど、まさかそこまで平和だとは思わなかった。
ゴードンさんの話はなおも続く。
「だからこそ、誰も彼女を捕まえようとはしなかった。なんでだと思う?」
「……エンターテイメントを、市民が求めていたから?」
即座に答えたのは、やはりメアリーだった。
「その通り。エンターテイメントがこの町には不足していた。だからといって、盗賊にエンターテイメントを求めるのは如何なものかと思うが……。しかし、市民は我々と彼女の大捕り物、正確に言えば捕まえていないから捕り物にはならないのだが……、それを楽しんでいた。現にこの町がひどい有様だったなら、もっと我々は本気で活動している」
平和だからこそ出来る、やり取り。
僕はそう思った。だってこの世界が少しでも平和じゃなかったら出来ないことだと思ったから。
「……彼女についての昔話はこれで終わりだ。お前たちについていく、と言ったときは正直驚いたが、彼女には彼女なりの引き際を考えていたのだろう。だとすれば、それを我々が止めるのは野暮というもの。せめて最後まで見送ってやりたいものだよ」
「ですが、僕たちはここに来た理由は……」
「それは、もう君たちも知っていることではないのかな? 確かに君たちはこの城へやってきた。そしてその理由はラドーム学院では安全が保たれないと思ったためだ。しかし、リーガル城まで敵の侵攻を許してしまった現状、我々でも君たちを守ることは出来ないと判断した。それと同時に――『平和』は終わったのだと、王は判断されたそうだ」
「それってつまり……」
僕の言葉に、ゴードンさんは目を細めて頷いた。
「申し訳ない。君たちをここで守ることは、出来ない。これからは君たち自身の力で、何とか頑張っていただきたい。これを言うのは、ほんとうに申し訳ないことではあるのだが……。これも王の命令なのだ。我々はこの城を守るために仕えている。この城を守るために、もっと我々も頑張らなくてはならない」
ゴードンさんはレイナを見つめて、そう言った。
ゴードンさんたちは、兵士としてこの町の平和を維持すべく日々活動している。しかしながら、平和が続く昨今ではそれもマンネリ化しているのだろう。
そこで、今起きている平和からの転換を、どうにか防がなくてはならない。
「……まあ、それがどうなっていくかは解らないけれどね。我々が平和を、未来に託していかないといけない。そういうことは義務だ。我々が争いの絶えない世界を、未来の君たちに託してはいけないのだよ」
「ゴードンさん……」
僕、メアリー、ルーシーが合わせてゴードンさんに声をかけた。
その時だった。
時計塔の鐘が鳴った。
リーガル城城下町のシンボルである、時計塔の鐘が鳴った。
銃を落とした音を聞いて、僕たちはゴードンさんのほうを向いた。
ゴードンさんは何か気持ち悪そうな表情を浮かべていた。
「……ゴードンさん、大丈夫ですか?」
「近づくな」
近づこうとしたメアリーを強い語気で退こうとするゴードンさん。
背後で異変を感じ取ったレイナも踵を返していた。
「おい!」
レイナは走って、ゴードンさんのほうへと走り出す。
その間にもゴードンさんは跪く。見る見るうちに、恰好が変わっていく。正確に言えば、彼の身体の内から何かが変形しているような感覚だ。暴れている、と言ってもいいだろう。
ゴードンさんの身体が変化していく。
僕たちはとても恐ろしくて、一歩もそこから動けなかった。
そして、ゴードンさんの背中から――巨大な白い翼が現出する。
ミシェラの言葉が僕の頭の中をこだまする。
_ ――メタモルフォーズは人間とは明らかに異なる部位、翼部の現出により判断する。
_ その通り、ゴードンさんの身体には巨大な白い翼が生み出されていた。白い翼、といえば天使のそれを想像するが、その翼は羽で出来ていて柔らかいイメージがあるのに対し、ゴードンさんのそれは筋肉質でゴツゴツとした感じだった。それだけで、奇妙な雰囲気を放つのには十分すぎた。
「メタモルフォーズ……!」
「はは……。どうやら、あの少女の血を浴びてしまったことが原因だったのか」
ゴードンさんは未だ意識があった。未だ自分の言葉を話すだけの意識は持ち合わせているようだった。
「聞いたことがあります。メタモルフォーズは人間のそれと大きく異なるポイントがある、と。それが翼である……」
「そんな……。つまり、ゴードンさんは……」
ゴードンさんの翼の現出により、周りの住民も慌て始める。当然だろう、今まで国を守ってきた兵士が倒れこみ、その兵士から人間とは明らかに違うパーツ――翼が生えてきたのを目の当たりにすれば、驚かないわけがない。
「フル・ヤタクミ……私はもう、『人間』ではないのだろう……?」
僕に問いかけたゴードンさん。
その質問の答えは、紛れもなくイエスだ。だから、僕は首を縦に振る。
「だったら私を殺してくれ……。頼むよ……」
ゴードンさんと僕たちの周りに兵士がやってくる。兵士はメタモルフォーズの状態変化を初めて見たからだろう。その状況に狼狽えて何も出来ない兵士も居た。
それは僕たちも同じだった。
ただ、動けなかった。
レイナも同じだった。レイナはゴードンさんの前に立って、涙を流していた。
「……何で、何でこいつがこんな目に合わないといけないんだよ」
レイナは悔しそうに、そう言った。
僕たちも、兵士のみんなも、その言葉に答えることは出来なかった。
「何で、何でなんだよ……」
「殺せ」
兵士の真ん中に立っている、いかにも階級が一つ上の女性は言った。どうやらゴードンさんとは顔見知りなのか、ゴードンさんがそちらを向いて笑みを浮かべる。
「まさか、お前に殺されることになるとは、な。数奇な運命とは、このことを言うのだろうか」
「さて、どうでしょうか? ……いずれにせよ、チェックしなかった我々のミスでもあると言えます。まさか、あのバケモノにこのような結果で感染が認められるとは……」
そう言って、女性は銃を構える。
「これは特殊な銃です。この弾丸が命中すると、眠るように死に至ります。痛みを感じることはありません。まったく、平和ボケした人間が考える兵器とは思いませんか?」
「貴様は昔から御託を述べるのが多かったな。さっさと殺してくれないか。さっきから身体を組み替えているのか知らないが、とても痛くてね。話をすることすらままならない。……まあ、人を襲う前に死ぬことは未だいい結果なのかもしれないがね」
「ええ、私もそう思っていますよ」
そう言って、女性は銃の水準を彼の心臓に合わせた。
「……レイナ、すまなかったな」
「……何を言っているんだよ。こんな結末、認めねえぞ……」
「ははは。まあ、仕方ない結末だった。……カミサマが試練を与えたと思えばいい。……フル・ヤタクミ、レイナを頼むぞ。彼女を再び盗賊稼業に戻すことは、俺が許さない」
「……解った」
僕は、その一言しか答えることが出来なかった。
そして、女性は銃の引き金を――ゆっくりと引いた。
_ ◇◇◇
_ 出発の朝。
僕たちは王様の部屋に再び立っていた。出発について、王に話すためだ。
「……君たちを守ることが満足に出来ず、申し訳ない。本来であれば我々がずっと守っていけるようであればいいのだが、この国は、いいや……この世界は予想以上に平和が脅かされているようだ」
「だから、僕が予言の勇者として行動していかないといけないのでしょう。……大丈夫です。王様、ありがとうございました」
僕は頭を下げる。それから数瞬の時をおいて、メアリーとルーシーも頭を下げた。
「次に向かうとしたら……スノーフォグになるかな。あのメタモルフォーズの大群がやってきた方角も、確かその方角であったと聞く。もしかしたら、あの国でメタモルフォーズが開発されたのかもしれない」
「スノーフォグ……」
スノーフォグ。
聞いたことがある。祈祷師であるリュージュが治める国。だが、情報自体はそれしか持っていないので、いったいどのような国家なのか全くもって予想がつかない。
「本当に、お世話になりました」
そうして僕たちはもう一度頭を下げると、踵を返し、王様の部屋を後にした。
_ 城門の脇には、サリー先生が立っていた。
「聞いたわよ。スノーフォグへ向かうのですって?」
「……ええ。スノーフォグからあのメタモルフォーズの大群がやってきたらしいので……。もっとも、あの大群は幻影だったわけですけれど、あの方角に何かあったのは間違いないのではないか、と考えられています」
「だったら、私も何か物をあげましょう」
そう言ってサリー先生はポシェットに入っていた小さな林檎を僕に差し出した。
「これって……」
「『知恵の木の実』、よ。効果は……まあ、実際に使ってみれば解ることでしょう。ただし、使い過ぎに注意してね」
「……はい」
サリー先生の言葉に頷く。
「それじゃ、これから世界を救うだろうあなたたちにこんな言葉を贈るのは間違いかもしれないけれど……」
サリー先生は笑みを浮かべて、僕たちに語った。
「――良い旅にしてね」
「はい! ありがとうございます!」
_ ――そうして僕たちは、サリー先生と別れ、一路スノーフォグへと向かった。
_ ◇◇◇
_ リーガル城、王の間。
国王が一人で何かを待ち構えていた。普通ならば兵士か大臣か、そのいずれかが王の間に滞在していることが殆どなのだが、今は国王自らが退去させている。
今からやってくる相手は、それほどに秘密裡なのだ。
コツ。
足音を聞いて、国王は目を開ける。
「……少々、遅かったのではないのかね?」
その声を聴いて、相手は口角をあげる。
「私にもいろいろとやることがあるのよ、ハイダルク国王」
そこに立っていたのは――スノーフォグの国王、リュージュだった。
リュージュは水晶玉を見つめながら、
「一応、私が言った通りに物事を進めてくれたようね。予言の勇者を上手い具合に追い払ってくれて。しかもスノーフォグへ誘導までしてくれた。ほんとうに感謝しているわ」
そう。
ハイダルク国王がフルたちをスノーフォグへと誘導させたのは、リュージュのシナリオがあったからだった。
それだけではない。リュージュが提出したシナリオにはメタモルフォーズの大群が襲撃してくることや、それを追い払うこともすべて書かれていた。
要するに、今まであったことはただの八百長だった――ということになる。
「……お前は何を企んでいる? 貴様はいったい……」
「それを話す前に、私からひとつ提案しましょうか。そもそも、私はその提案をするためにここにやってきたのだから」
リュージュはハイダルク国王の目を見て、言った。
「あなたが『捕獲』したメタモルフォーズ……きっとそれはここで研究をしていくのでしょうけれど、それを渡してもらえないかしら?」
「……やはり、あのメタモルフォーズから『感染』したものだったのか」
溜息を吐くハイダルク国王を見て、笑みを浮かべるリュージュ。
「ええ、そうよ。そうだったのよ。メタモルフォーズは感染する。いや、正確に言えば、メタモルフォーズの血液により、覚醒した。そういう表現が案外正しいかもしれないわね」
「覚醒した? まるで、メタモルフォーズが――」
「メタモルフォーズは人間の進化の可能性、その一つよ」
リュージュははっきりと言い切った。
メタモルフォーズは人間の進化の可能性、であると。
「……人間の、進化の可能性……? あのバケモノが、か?」
「バケモノ。確かにあなたはそう思うかもしれないわね。それは間違った解釈ではない。むしろ正しい解釈かもしれないわ。けれど、いつかきっとこれが正しいと言える時代がやってくる。これは予言ではない、確定事項よ」
「確定事項……か。しかし、予言の勇者を泳がしておくとは、お前らしくもないが。もし、メタモルフォーズをそこまで使おうと考えているのならば、予言の勇者は一番の邪魔者なのではないかね?」
「邪魔ね。はっきり言って」
リュージュはそう言い放った。
しかし、踵を返して、
「しかしながら、それよりも今は私のシナリオ通りに進んでいること。それについて考える必要があるのよ。予言の勇者をまだ殺すべきではない。私はそう考えているからね」
「……もうお前に言い返す言葉もない。何代前から、ハイダルクとスノーフォグは関係を築いているのか、覚えていないだろうからな」
「そうね。そして私はずっとこの地位に君臨し続けている。言わせてもらうけれど、祈祷師はずっと若々しい身体を保つことが出来るのよ? さすがに不老不死、とまではいかないけれど、普通の人間と比べればその差は歴然。祈祷師というのはね、選ばれし人間なのよ。まあ、すでにガラムドの血を引き継いでいる時点で、普通の人間とは違うことはお解りいただいていると思うけれど?」
深い溜息を吐いて、ハイダルク国王は目を瞑る。
「……メタモルフォーズに関しては引き渡そう。船で構わないかね? それとも連れ帰るか?」
「連れ帰るわ。感謝するわ、ハイダルク国王」
そう言って再び踵を返すと、ハイダルク国王に一歩近づく。
「場所は?」
「案内しよう」
ハイダルク国王は立ち上がると、リュージュを追い抜いていく。そして部屋の出口の前で立ち止まり、振り返る。
「こちらだ」
そうして、ハイダルク国王とリュージュは部屋を後にした。
僕たちは馬車を乗り継ぎ、ハイダルク最北端の港町、バイタスへ到着した。
エルファスやリーガル城の城下町と比べるとその喧騒は少なく、静かな、ゆったりとした雰囲気が流れていた。
もう夕方になっていたので、スノーフォグへの船は既に終了していた。もともと急ぐ旅ではないと考えていたので、無理に急ぐことなく明日の朝スノーフォグへ向かうことで僕たちの意見は集結することとなった。
今回僕たちが泊まることとなった宿は埠頭近くの小綺麗な宿。下宿と酒場を兼ねている、人気のあるお店だ。二人部屋が二つも空いているとは考えていなかったが、意外にもスムーズにとることが出来た。
一階のレストランで僕たちは夕食をとることになった。
「はい、今日のメニュー」
そう言って女性――女性にしては屈強な身体だし、顎鬚も生えているが、それについてはあまり言及しないほうがいいだろう――は四人分のおかずとライス、スープをお盆に乗せて持ってきた。
おかずは鳥の丸焼きにソースをかけたようなシンプルな料理となっている。周りには野菜が盛り付けられている。なかなかシンプルな盛り付けとなっているけれど、とても美味しそうだ。
「いただきます」
両手を合わせて、頭を下げる。
どうやらそういう形式的なものは異世界でも特に変わらないようだった。それはそれで嬉しいし、むしろ好都合であった。
そうしてフォークを手に取ると、鶏肉のスライスを刺し、それを口に入れた。
すぐに口の中に塩気が広がる。その塩気はライスを進ませるにはちょうどいい味付け。ずっと今日馬車を乗り継いできて、とても疲れている僕たちにとってはちょうどいい塩気と言ってもいいだろう。汗をかいていて、塩分を欲しているというのもあるだろうけれど。
「美味しい……!」
「そう言ってくれると、作った甲斐があるというものだよ。はい、これサービス」
そう言って女性はもう一つお皿を持ってきた。
そのお皿には刺身が乗っていた。
「刺身……。こんな量の刺身をサービスで、いいんですか?」
訊ねたのはメアリーだった。
女性は首を振って、
「ああ、ああ。いいんだよ。そんな畏まらなくて。うちはそんな固い雰囲気じゃなくていい。アットホームな雰囲気を目指しているからね。だから普段通り話してくれればいいし、これはあんたたちがとっても美味しそうに食事をしていたから、それについての礼と思ってくれればいいよ」
そうして女性は厨房のほうへと向かっていった。
刺身の内容を改めて確認すると、色とりどりの魚の切り身が入っていて、とても美味しそうだった。
刺身と言えば、醤油だ。しかし、疑問となるのはここが異世界であるということ。ならばこの世界では醤油の代わりに何をつけるのだろうか……。
そんなことを考えていたら、メアリーが小皿に黒い液体を注いだ。テーブルの脇に置かれていた小瓶から注いだものだった。
小瓶にはこう書かれたシールが貼られていた。
マキヤソース。
この世界の人間はこれを使っているのか――僕はそう思って、メアリーからマキヤソース入りの小瓶を受け取った。マキヤソースを小皿に注いで、今度はルーシーに手渡す。
小皿に満たされた黒い液体。それは何も言われなければ醤油のそれと等しかった。
箸を手に取って、刺身をとる。そうしてマキヤソースにつける。すると脂が浮いた。けっこう脂が乗っている魚なのかもしれない。
そして僕はそれを口に入れた。
「……美味い」
やっぱり、それは僕が知っている醤油そのものだった。やっぱり、醤油の生産技術は異世界でも共通なのだろうか。
そして僕たちは、夕食へと戻っていく。
そのどれもが美味しく、とても満足できるものだった。
そして、夕食後。僕たちは部屋へと戻るべく、廊下を歩いていた。
「ところでスノーフォグとメタモルフォーズって、何か関連性があるのかな?」
ルーシーがふいに問いかけた。
「今のところ関連性は無いと思うけれど……しいて言うならば、祈祷師が国王をつとめていることかしら。祈祷師はガラムドの子孫だし、何か詳しいことを知っているのかもしれない」
「祈祷師……か」
「まあ、難しいことを考えるのはよしましょう」
言ったのはレイナだった。
「どうせスノーフォグには明日向かうのでしょう? だったら、難しいことは考えないで、また明日考えたほうがいいじゃない。私はいつもそういう感じで生きてきたし」
……難しいこと、か。
そう言われてみると、今日はとても疲れていた。
僕は大きな欠伸をして、そう思った。
「それじゃ、詳しいことはスノーフォグに向かう船の中で考えることにしましょう。それでもまだ遅くないから」
メアリーの提案を受け入れて、僕たちは眠りにつくことにした。
そう結論付けたところで、ちょうど僕たちの部屋――右側が女性陣で、左側が男性陣の部屋に到着した。
向かい合って、僕たちは言った。
「それじゃ、おやすみ」
「おやすみ、また明日」
そうして僕たちは、それぞれの部屋へと入っていった。
僕は深夜、熱さで目を覚ました。
目を開けると、カーテンの向こうが赤く照っていた。
……もう朝か?
しかし、朝の光にしてはとても赤すぎる。それに、まだルーシーは寝息を立てている。
ならば、何だというのか?
カーテンを開けた僕の目に広がったのは――燃え盛るバイタスの区々だった。
「ルーシー、起きろ! 大変だ、町が燃えている!」
僕はそれを見て、大急ぎで、慌ててルーシーを起こした。
ルーシーは当然すぐに起きることは無かったけれど、強引に何度も揺り起こした。
ルーシーが起きたのはそれから数十秒後のこと。とても気分が悪そうに見えたが、そんなことはどうだっていい。あとで謝罪すればどうとでもなる。
問題は現状の把握。そして、どうすればいいかという解決策の考察だ。
「……ううん、どうしたんだよ。フル、そんなに慌てて」
「慌てている場合なんだよ! いいから、急いで目を覚ましてくれ。話はそれからだ!」
何度も叩き起こして、ようやくルーシーは起き上がった。そして少しして、窓から見える光景を見て――目を丸くした。
「おい、これっていったいどういうことだよ……!」
「だから言っただろう!! この状況、いったいどういうことか……取り敢えず、メアリーとレイナだ。彼女たちが無事かどうか、確認しないと!」
そうして僕たちは大急ぎで着替えると、メアリーたちが居る向かいの部屋へと向かった。
向かいの部屋の扉をノックして、扉を開ける。緊急事態だったので乱暴になってしまったが、この際仕方がない。
扉を開けるとそこに広がっていたのは――炎だった。
「……また、少しだけ遅かったね」
一人の男が溜息を吐いて、僕にそう言った。
メアリーとレイナの姿は無く、代わりに一人の男が立っている状態になっていた。
「メアリーと……レイナは?」
「それを君に伝えるメリットがあるとでも?」
「メリット、だと……!」
一歩踏み出したのはルーシーだった。
ルーシーはそのままその男に向かって走り出すのではないかと一瞬考えたが、彼もかれなりに考えているのだろう、その場で立ち止まった。
炎のように燃える髪を持つ男だった。赤いシャツに赤いズボン、それを際立たせる白いネクタイを着用した男は大人びた格好こそしているが、その表情は僕と同じかそれよりも若いように見える。
男は笑みを浮かべる。
「君が……予言の勇者だね。ああ、何で知っているのか、ということは言わないでいいから。僕には僕なりの情報網があるということだよ。それについては語ることはしなくていいよね」
「さっきからべらべらと……。いいから、メアリーを、レイナを、返せ!」
僕は男に対して、剣を向ける。
しかし男はそれでも表情を変えることは無かった。
「それは噂のシルフェの剣、だね。けれど、それで勝てると思っているのかな? 解っていないようだから教えておくけれど、僕はこの町を火の海にしたのだよ。それだけで僕の実力は理解してくれるかな? あと、こちらには人質が居る。それだけで、それを聞いただけで、君たちにとって相当不利な状況であることは充分理解できると思うのだけれど?」
それは彼の言う通りだった。
僕は未だ数日程しか魔法、剣戟の技術を持たない。それだけでも圧倒的不利な状況だというのに、この町を火の海にするほどの魔法を放っておいて、未だ余裕を見せているということは、実力を隠しているということだ。あれほどの魔法を放っておいて、未だ?
そう考えると、僕は前に出ることが出来なかった。
「そうそう。それが最善の選択だよね。そんな君にはリワード(ごほうび)をあげないとね。僕たちが所属している組織、その名前は魔法科学組織『シグナル』。リーガルを襲った彼女は、しょせんシグナルの一端にもかなわない。そりゃ、命令こそはしているけれどね、彼女もまた、シグナルの手足に過ぎなかったのさ」
そして、男は窓に足をかける。
忘れ物をしたかのように振り返って、男は言った。
「ああ、そうだった。忘れていたよ。僕の名前はバルト・イルファ。見た目とこの町を灯の海にしたことで理解できると思うけれど……炎の魔法を使う魔術師さ。また会った時には、成長を期待しているよ、予言の勇者君」
そして、今度こそバルト・イルファは外に飛び出していった。
どんな魔法を使ったのか――バルト・イルファの姿はすぐに見えなくなってしまった。
_ ◇◇◇
バルト・イルファは自らの魔法で燃え盛る町を駈けながらつぶやく。
「軈て、彼はこの世界を救うことだろう。……それが彼にとって最善の選択であるかどうかは、定かでないが」
たん! と跳躍して、五階建てほどの高い建物から飛び降りる。
地上に到着するも、魔法で衝撃を少なくしたためか、特に彼にダメージは見られない。
「……いずれにせよ、彼が望んだことだ。今度の世界がどうなるか、楽しみにしているよ。フル・ヤタクミ」
その笑顔はとても楽しそうだった。
まるでこれから起きるシナリオを、すべて理解しているかのように。
大陸から東に位置する一つの島。
その島は名前もないただの島として知られている。周囲を岩山で囲まれており、島に上陸するためには唯一の港を使う必要があるのだが、その港自体はシュラス錬金術研究所が管理しているため、一般人が使用することは許されない。
その港から岩山の内部へと続く唯一の道を二人の少年少女が歩いていた。
「この島に来ることは初めてかい?」
炎のような赤い髪の青年――バルト・イルファは言った。
隣に歩いているのは、制服に身を包んだ少女だった。
目つきが鋭く、どこか他人を寄せ付けない何かがある。どこか男のような顔立ちにも見えるが、彼女は紛れもなく、少女であった。
「……そうね。この島に来るのは初めてかしら。場所と名前くらいは知っていたけれど、それにしてもどうしてわざわざ私を連れてきたのかしら?」
「それは簡単だ。君もきっとリュージュ様に認められた、ということなのだろう。まあ、それがどこまでほんとうであるかは定かではないがね」
「相変わらず、あなたは回りくどい言い回しが好きなのね、バルト・イルファ」
「そうかな? まあ、でもそうかもしれないね……。それは妹にもよく言われるよ」
「ロマちゃんは繊細だからねえ。私によく言ってくるよ、お兄様はいつも言葉が長くて実際の結論に比べると何倍も違ってしまうのです、と」
後半、少女は少し声色を変えて言った。その『ロマ』という少女に合わせて話したのだろう。
「……頼むから、そのロマの真似は止めてくれないか? 正直、君があまりにも似過ぎていて逆に恐ろしい。襲いたくなりそうだ」
「やめてほしいわよ、別にあんたに襲ってもらいたくてこんな真似をしたわけじゃないのだから。冗談よ、冗談。……まったく、どうしてそういうことが理解できないのかしらね? いつ嫌われてもおかしくないわよ? そのシスコンっぷりは」
「シスコンではなくて、彼女のことをずっと想っている、と言ってほしいものだね」
バルト・イルファはそう言って少し早歩きをした。
「それが強すぎるからシスコンと思われるのでしょうが……。まあ、それはどうでもいいか。本人同士が解決することではあるし。けれど、見ていてこそばゆいのよね、あなたたちのやり取り」
「そりゃ、僕たちは長い間同じ場所で育ってきたからね」
バルト・イルファは踵を返し、少女に向き直る。
少女はそれを聞いて溜息を吐き、
「『十三人の忌み子』、かしら」
「そうだ。あれはとても素晴らしいものだと記憶しているよ。メタモルフォーズは人間の進化の可能性、と言われていて、確かに僕たちも現に人間とは違う新たな可能性を見出すことが出来た。ただ、それはまだ不完全だ。もっと頑張らなくてはならない」
「オリジナルフォーズの力を体内に補充しているうちでは、まだ不可能だということね?」
こくり、とバルト・イルファは頷く。
「その通り。オリジナルフォーズの力を、今僕たちメタモルフォーズは加護の一種として体内に補充している。しかしながら、それも無限ではない。いつかは回復するために、その力を補充する必要がある。そして、それがある場所が――」
歩き始めた先には、クレーターが広がっていた。
否、正確に言えばそこはクレーターではない。クレーターは隕石の衝突跡などと言ったものだが、それは隕石などが衝突したことによりできたものではない。
本来ならばその下にはマグマがぐつぐつと煮えたぎっている場所。
即ちそこは火口だった。この島は休火山となっているため、それほど活発な火山活動が行われているわけではなく、学者の予想によれば数千年は火山活動が活発になることは無い、と言われているほどだった。
そして、その休火山の火口にはマグマの代わりに、あるものが眠りについていた。
「これがオリジナルフォーズ……」
少女はその姿を見て圧巻させられた。その火口に眠りについていたのは、大きな獣だった。巨体、と言ってもいいその獣は地面に半分埋まっている形になっていた。そしてその脇には黄金の葉を持つ大樹が生えている。
「あれが、知恵の木、だったかしら。知恵の木の実が生るという唯一の木」
「正確には僕たちの拠点、その地下にもこれの若芽から得られたものがあるから、二つだけれどね。まあ、天然ものの知恵の木、というものであればここにあるのが唯一と言えるだろう」
「それで?」
少女はバルト・イルファを見つめて、笑みを浮かべる。
「それで……とは? いったい何が言いたいのかな、クラリス?」
少女――クラリスの笑みを見て、首を傾げるバルト・イルファ。
「だから、言っているじゃない。あなたが何をしたいのか、何をするためにここにやってきたのか。それを聞きたいのよ、私は」
「簡単だよ。オリジナルフォーズを復活させる」
簡単に述べられた言葉だったが、それはそう簡単に実現できるものではないことを、クラリスも理解していた。
だからこそ、バルト・イルファもそれを理解していた。簡単に出来る話ではないから、それでもバルト・イルファはこの地にやってきた。
それは命じられたから?
いや、違う。
自分の意志でここに来た。
自分で、目的があって、ここにやってきた。
バルト・イルファは頷くと、クラリスに一歩近づいた。
「オリジナルフォーズを復活させる……ですって? それは、あのお方の命令かしら」
「いいや、違うよ。これは僕が自らで考えたことだ。考えた結果の結論だ」
それを聞いて鼻で笑うクラリス。
「あのお方がなんと言うかしら」
「もしかしたら殺されるかもしれないな。いや、あるいは復活させたことをほめてくれるかもしれない。いずれにせよ、あのお方の目的にはオリジナルフォーズの復活も含められているはずだからな」
バルト・イルファはそう言って、オリジナルフォーズを見つめた。
オリジナルフォーズは今もなお目を瞑っている。それだけを見れば、ただ自分の根城で眠っているようにしか見えない。
いや、実際に眠っているだけだった。オリジナルフォーズはただ眠っているだけに過ぎない。けれど、そうであったとしても、実際には薄膜におおわれており、その傍まで近づくことは出来ない。
「……その障壁が、ガラムドの作り上げたものなのだろう?」
こくり、とバルト・イルファは頷く。
「なんだ、研究しているじゃないか、クラリス」
「そりゃ一応念のため、ね。私だって何も知らないでずっとあなたと共に行動しているわけではないから。……それにしても、そう簡単に出来る話ではないでしょう?」
踵を返し、クラリスはバルト・イルファに問いかける。
その目線は氷のように冷たく、バルト・イルファの心を見透かそうとしているようにも見える。
それを見たバルト・イルファは、一笑に付し、
「……やはり、君には何も嘘を吐くことは出来ない。……いや、正確に言えば嘘を吐いているわけでもないのだが、それに近しいものだと思っても過言ではないだろう」
「やはり、何か裏があるのね」
バルト・イルファは一歩近づき、彼女の顎に手を添える。
そしてくい、と顔を上げさせる。強制的にバルト・イルファとクラリスの目線が一致した状態になり、彼は言う。
「どうせ、君が得た情報は筒抜けになるのだろう? だったら、別に伝える必要も無かろう。僕は裏表なんて何も持ち合わせてはいない。すべてはあのお方のため、だ」
「ふうん……。だったらどうしてこのようなわざとらしいことをするのかしら」
「これは忠告だよ、クラリス」
バルト・イルファはクラリスの言葉を遮って、強い口調で告げた。
そして彼女を睨みつけたまま、話を続ける。
「君がどう思っているかは知らないが、これまでも、そしてこれからも、僕は僕のやり方でやらせてもらう。これはあのお方にも了承を得ている。だから君が不審に感じていたとしても、それを止めることは許されない。理解できるだろう? つまり、僕の行動は、あのお方の考えと直結するということを」
「……解ったわ。私も少し言い過ぎた。だから、この態勢を止めてもらえないかしら? 別にあなたのことを疑っているわけではないのよ。それだけは理解してもらいたいことね」
それを聞いたバルト・イルファは彼女の意見を受け入れて、彼女の顎から手を放す。
そそくさと移動して、様子を見るクラリス。
バルト・イルファはそれを見て、ばつの悪そうな表情を浮かべて小さく舌打ちした。
「……ところで、オリジナルフォーズはほんとうに復活できそうなのかしら?」
「どういうことだ?」
「噂によれば、ガラムドの張った結界を破壊するにはある魔法が必要であると聞いたことがあるのだけれど。しかもその魔法はあまりにも強力過ぎて封印されているとか」
「ああ、その通りだ。しかし……一つだけ間違いがある」
人差し指を立てて、バルト・イルファは言った。
その言葉に対し首を傾げるクラリス。
「間違い……だと?」
「つまり、君の理解している『噂』には間違いがある、ということだ。別に君が間違って理解しているとは考えていない。つまり、噂にも間違ったものが流布していることがある。伝言ゲームみたいなものだ。伝言を続けていくうちに、人の記憶はそう完全なものではないから……どこか抜け落ちたり、変わってしまったりすることもある。クラリス、君の聞いた噂話は、そういう『変わってしまった』ところがあるのだ、ということだよ」
「だから、その変わってしまったところはどこだ、と聞いている」
「魔法は封印されている。ここまでは正しい事実だ。……しかし、事実としてはここからが違うことになる。その魔法はとある魔導書として封印されている。魔導書は知っているだろう?」
「あの旧世代的魔法の教科書のことか?」
こくり、と頷くバルト・イルファ。
「ああ、そうだ。あの魔導書だよ。まあ、魔導書については殆ど残されていない。確かに君の言った通り、もう古い文献に成り下がっている。けれど、昔にあるから『古い』という考えは、少々お門違いになり果てている……ということだ」
「封印されたから……古いものに、結果としてなっている、ということか……」
「ご名答。そうしてその魔導書はガラムド本人の手によって封印されたらしい。だから、どこにあるのかは誰にもわからないのだというよ」
「……ならば、それこそ手詰まりではないのか?」
その言葉に笑みを浮かべるバルト・イルファ。
もうその流れに呆れてしまったのか、小さく溜息を吐いてオリジナルフォーズの眠る火口を見つめるクラリス。
そうしてクラリスは火口からオリジナルフォーズを見つめた。
「……手詰まりだとすれば、やはり我々にはどうしようもないのではないか? その魔導書が見つかるのならばまた話は別だと思うが」
「見つかるよ、魔導書は」
それを聞いてクラリスは踵を返す。
「あてがあるのか? その魔導書がある場所が」
「無いわけではないけれど、きっと僕たちが行っても無駄だろうね。正確に言えば、予言の勇者サマじゃないと無理かもしれない」
「ガラムドが、このような事態を予測していて、勇者の手に渡るようにしていた……と?」
「可能性は充分に有り得る」
「面倒なことをして……!」
「面倒なこと、というのは仕方ないことだ。物事が簡単にすべて上手くいってしまったら意味がないだろう? だからこそ、それこそ楽しいんだよ。障害があればあるほど、燃える! それが男というものだ」
はあ、と深い溜息を吐いてクラリスはバルト・イルファを指さした。
「あなたはそう思っているかもしれないけれど、私は女ですから。あと、あなたが思っている以上に私だって強いのですよ?」
それを聞いて頭を掻くバルト・イルファ。
どうやらいつもこのようなやり取りをしているようだった。
バルト・イルファは少し頭をリフレッシュさせたのか、オリジナルフォーズを見つめたまま舌打ちをする。
「……このままだと何も解決策が浮かばない。だったら、もうここには用がない。きっと彼らが魔導書を回収してくれると思うのだが」
「彼ら、って……予言の勇者のこと?」
「それ以外に誰が居るというのだ。予言の勇者は、きっと、いや、確実に魔導書を手に入れるはずだ。そこからどうやってあの魔法を使わせるか……それが問題だ」
「詳しいねえ、バルト・イルファ。まるで、これから起きる出来事をすべて理解しているようだ」
確かに。
バルト・イルファの発言を先ほどから聞いているだけだと、すべてこれからのことを理解しているようにしか聞こえない。つまり、的を射た発言ばかりだということになる。
しかし、未来を予言することなど『祈祷師』以外に出来ることではない。
祈祷師の素質があるのは、この世界ではガラムドの血筋を持つ人間だけとなっている。そして、その血筋を持つ人間は厳正に管理されていて、バルト・イルファのような管理から零れた存在が出てくることは有り得ない。それこそ、祈祷師の中でも上位に立つ人間が故意にそのような行動をしなければ、の話になるが。
問題として提起すべき議題でないことはクラリスも重々理解しているのだが、しかし彼女の中でバルト・イルファの発言はどこか引っ掛かるものが多かった。
とはいえ、バルト・イルファの発言の真偽を確かめる術など無い。可能性だけを考慮するならば祈祷師に直接話を聞くことが残されているが、そもそも彼女の地位では祈祷師と謁見することは不可能に近い。それに対して、祈祷師に気に入られているバルト・イルファのほうが出会いやすい。
「……まあ、それについては一旦おいておきましょう。あなたの発言がほんとうであるか、それともただの出任せなのか、は」
「自己完結かい? 君らしくないなあ。まあ、僕の発言の真偽を確かめる術が見当たらなかったから、仕方なく受け入れた……というオチだろうけれど。どちらにせよ、僕の発言は本当だよ。僕が保証する。これは確証をもって行動しているのだから」
そうしてバルト・イルファは歩き始める。
クラリスもまた、ここでやることなど無いと結論付け、バルト・イルファの後を追った。
_ ◇◇◇
場所は変わり、バイタスの港に仮設された宿泊所にて。
フルの隣で眠っているルーシーは、彼に問いかけた。それは彼がまだ眠りについていないからだという予測と、周りの人間がすべて眠っているから二人きりで話をするなら今の内だと思ったからだ。
フルは背中を向けたまま、何も答えない。
もしかして眠ってしまったのかな――ルーシーはそう思って、布団に深く潜る。
「ごめんね、フル。もし眠っていたのならば、申し訳ない。これは僕のただの独り言だからさ。つまらなかったら聞いてもらわなくて構わない。けれど、これからのことに重要だと思うんだ。もし、起きているならば、話だけでも聞いてもらいたい」
そう長ったらしい前口上を終えて、ルーシーは話を続けた。
「メアリーはどうして攫われてしまったのだろうか? 僕はずっと気になっていたんだ。そうして、僕はずっと考えていた。どうしてメアリーが攫われないといけないのか。普通に考えてみると、予言の勇者と言われているフル、君が狙われるべきだろう? 戦力を削ぐという可能性もあったかもしれない。メアリーを攫うことでフルの動揺を狙ったため? ……いいや、どれもちょっと詰まるところがある。要するに、それが確たる理由ではないと思うんだ」
フルは起きていた。
そしてルーシーの話を聞いていた。
だからこそ、ルーシーの言葉から、彼なりの構想を考え直すことが出来た。確かにルーシーの言う通り、メアリーが狙われた理由がいまいちわからなかったのだ。
そうして、ルーシーは言葉を投げかける。
「フル。覚えているかい? ――メアリーは祈祷師の子供だ」
それを聞いて、彼は思い出す。
ラドーム学院での夜。彼女から語られた、フルを助けているその理由。その中で彼女はそう言っていた。自分は祈祷師の子供である、と。
「何で僕がそれを知っているのか、ってことに繋がるかもしれないけれど――実はあの時、僕も少しだけ聞こえていたんだ。だから、知っている。そして、メアリーが祈祷師の子供であるということを、あのバルト・イルファも知っていたならば――」
メアリーを攫ったことに、一応の理由として説明がつく。
フルはそう思って、心の中で頷いた。
ルーシーは大きく欠伸をして、さらに布団に潜っていく。
「……まあ、それがどこまで本当かは解らないけれどね。いずれにせよ、あのバルト・イルファがどこへ向かったかは定かではない。……けれど、僕たちは前に進まないといけない。それは君が予言の勇者だから。そして世界に危機が徐々に迫ってきている、その予兆があるから。……まあ、明日メアリーが泊まっていた部屋を見てみないと何も言えないけれどね」
おやすみ、フル。
そう彼は言って、以降ルーシーは何も言わなくなった。
フルもルーシーの言葉に従って、深い眠りへ落ちていった。
次の日。
僕とルーシーは燃えてしまって殆ど跡形も残っていないバイタスの町を歩いていた。
理由は単純明快。メアリーが攫われてしまい、その相手がどこの誰なのか、その手がかりをつかむためだった。
「バルト・イルファ、という名前しか今の僕たちには情報が無い現状、少しでもあの部屋に情報が残されていればいいのだけれどね……」
「どうなのだろうね……。あのバルト・イルファという男、実際どういう感じかは掴めない感じだったけれど、ぼろを出すようには見えないしなあ……」
それは僕も思っていた。
だからといって、探さない理由にはならない。
少しでもメアリーの手がかりを探さないといけなかった。
「……けれど、あれほど探したのに見つからなかったんだよ、フル。その意味が理解できるかい?」
「じゃあ、簡単に諦めてしまうのかよ、ルーシー。君はそういう薄情な人間だったのか」
「そこまでは言っていないだろう? ……まあ、いい。殺伐とした状況はあまり長続きさせないほうがいい。とにかく、メアリーの手がかりを見つけること。それを『実行する』ことは大事だ。そうは思わないか?」
「……そうだな。ここで言い争っている場合ではないし」
ようやくルーシーも納得してくれたようだった。
それにしても、昨日の火事は相当酷いものだったように見える。
建物の殆どは崩壊している。煉瓦造りの建物が数少ないためか、殆ど燃え尽きてしまっていた。また、煉瓦の壁で屋根が木材となっている家も多いようで、その場合は屋根だけが燃えてしまっていて俯瞰図のような感じになってしまっている。
瓦礫に向かって膝を折り、泣き叫ぶ人も居た。
僕はその人のことを、ただ一瞥するだけだった。
宿屋に掲げられていた看板を見つけて、その場所が宿屋だった場所だと理解できた。
宿屋だった場所は瓦礫と化していて、もはやその姿を為していない。
足を踏み入れる。瓦礫をかき分けて、どうにかメアリーの寝ていた部屋だった場所まで向かう。
「想像以上だったな……。これだったら、メアリーの手がかりどころかメアリーが眠っていた部屋すら判明しないんじゃないか?」
ルーシーの言葉はもっともだった。確かにこの瓦礫の中からメアリーが居た部屋だったものを探すのは難しい。簡単にクリアすることではない。
瓦礫をかき分けて、出来る限りメアリーの手がかりを探していく。一言で言えば簡単なことかもしれないけれど、けれどそれはただ無駄なことを続けて時間を消費しているだけに過ぎなかった。
しかし、僕たちはあきらめなかった。
僕たちがメアリーの部屋にあったと思われる書物を見つけるまで、そう時間はかからなかった。
書物の脇にはご丁寧にシルフェの杖も放置されている。シルフェの杖はバルト・イルファにとって不必要と判断されたのだろう。そのまま残置されているということは、即ちそういうことになる。
書物は『ガラムド暦書』と呼ばれるものだった。この世界の歴史を事細かに記した書物であり、宿屋には必ず部屋に一つは置かれている。ビジネスホテルに置かれている聖書のようなものだと思えばいい。
それにはあるものが挟まっていた。
「なんだ、これは……?」
拾い上げて、そのページを開く。
そのページはメタモルフォーズに関する記述のページだった。
そして挟まっているものは、小さなバッジだった。金色に輝くバッジはこちらの言語で三つの文字が刻まれていた。
その文字を、一つ一つ、僕は読み上げていく。
「ASL……?」
_ ◇◇◇
_ 船が運航したのは、その日の午後だった。
徐々に小さくなっていくバイタスの町を眺めながら、僕はメアリーの部屋で拾ったバッジを眺める。
「ASL……といえば、あれしか思いつかないよ、フル」
「あれ?」
「シュラス錬金術研究所。スノーフォグが誇る、世界最高峰の錬金術研究所だ」
シュラス錬金術研究所。
確かに、錬金術の授業で習ったことがある。錬金術の研究に重きを置いているスノーフォグは、専門の研究施設を保持しているのだという。その研究施設の名前が、シュラス錬金術研究所だと。シュラス、とは錬金術師としても有名な高尚な学者の名前であり、その名前からとっているのだという。
「その研究施設が仮にバルト・イルファを生み出したのならば……問題と言えば問題かもしれない。だって、未だ『十三人の忌み子』の開発を続けている、ということになるのだから。それをさせないように国が管轄しているはずなのに……」
「その国が、それを許可した……ということになるのか?」
僕はルーシーに問いかける。
けれどその質問はルーシーが答えられるような、そんな簡単な質問ではなかった。
「……ごめん。ルーシーが答えられるような問題じゃなかった。けれど、たぶん、そんなところまで来ているのだと思う。このままだと世界は――」
ほんとうに、おかしな世界だと思う。
メタモルフォーズは大量破壊を可能とする、生物兵器だ。それを生み出して、それを復活させてその先に何を見出しているのだろうか? 最終的に、メタモルフォーズを生み出さないと倒すことの出来ない敵など居ない。むしろ、メタモルフォーズさえ居なければこの世界は充分平和を保っている。
にもかかわらず、メタモルフォーズが誕生する。
それによって、平和が破壊される。
「……だから、僕はこの世界に、」
勇者として、召喚されたのか。
そう思うと、いや、そうとしか思えなかった。
そんなことを考えていたところで、僕の肌に何か冷たいものが当たる。
それが雪だと気付くまで、そう時間はかからなかった。
「雪……」
そういえば、僕たちが今から向かう国の名前は、スノーフォグだった。
雪が入る国名、それは、その国がそれほど寒い国であることを象徴するようにも思えた。
そして外を眺めていくと、霧がかった向こうにうっすらと島が見えてきて、その島の高いところに明かりが併せて見えてきた。きっと灯台だろう。このような状態でも安全に航海が出来るように対策されているのだ。そう考えると、この世界の航海技術もそれなりに発展しているように思える。
そうして、僕たちを乗せた船はスノーフォグ最南端の港町――ラルースへと到着した。
_ 碇が下され、埠頭へと橋がかかる。
そうして僕たちは船を下りる。町には雪が降り積もっていて、とても寒かった。こんなときのために外套を用意しておいてよかった――そう僕は思ったと同時に、メアリーが心配になった。彼女は外套を持っていない。正確に言えば、外套を持つこともなく攫われてしまった。場所がどういう場所だか定かになっていないが、もしそれなりに寒いところであれば、早く彼女を救出する必要があった。
ルーシーから聞いたスノーフォグの基礎知識を、脳内でまとめることも兼ねて簡単に説明することにしよう。
スノーフォグはもうすでに理解している通り、とても寒い国だ。国土自体北方に位置している国であるため、最南端であるこの町を皮切りに海に氷が張っている場所が多い。そのため、砕氷船を通して氷を壊していかないと、僕たちが乗ってきた船のように安全に航海することが出来ない。
「さて、問題は……」
「ここからシュラス錬金術研究所へ、どうやって向かうか、だね……」
そう。
シュラス錬金術研究所はスノーフォグのどこか、としか解っていない。だからどこかがはっきりしない限り、国内を縦横無尽に駆け巡る、ローラー作戦めいたものも考えてもいるが、はっきり言ってそれはあまりにも時間がかかりすぎる。それに、スノーフォグの全体的な面積はハイダルクのそれとほぼ同等であるため、そう簡単に駆け巡ることは出来ない。それに、この世界最大の離島もあるくらいだし。そんなところに、船を持っていない僕たちがどうやって行けばいいのか? それも問題だった。
「ただ、僕たちには唯一の手がかりがある」
一本指を立てて、僕は言った。
「どういうこと?」
「どういうことだ?」
ルーシーとレイナが同時にそう言った。
「ミシェラとカーラが言っていたことを、僕は覚えている。十三人の忌み子のこと、そして、彼女たちがもともと住んでいた場所のこと」
それは僕があの夜一人で聞いたことだった。
結局ミシェラは敵だったわけだけれど、あの発言自体の裏付けはカーラとエルファスの村長からとれている。だから滅んだ村の記憶はスノーフォグの人々に刻まれているはずだ。
「そうか……。その情報が真実ならば、まだ可能性は有るかな」
ルーシーの言葉に僕は頷いた。
「だとしても、問題はまだあるぞ。その『滅んだ村』だっけ? それを知っている人間がどれくらいいるか、だ。その十三人の忌み子とかよく知らねーけれど、結局それが組織によってもみ消されていたらそれまでじゃねーの?」
「それはそうかもしれない。けれど、そうだとしてもまずは聞き込みから入るしかないだろうね。滅んだ村はどこにあるのか、そしてこの町で拠点を確保することもね」
_ ラルースという港町について整理しよう。
ラルースは町の南部に埠頭がある大きな港町だ。町の中に灯台があるくらいだから、相当規模は大きいものと思える。絶えず積荷が船に載せられていくところを見ると、経済は運搬や商人で回っているようだった。
それに、どこか子供が多い。さっきも子供とすれ違ったけれど、その量は大人の倍以上に見える。もしかしたら航海に出てしまって殆ど大人は居なくなってしまっているのだろうか? だとすれば、ここはいわゆる子供の町と言っても過言ではないかもしれない。
僕の提言により、宿屋を探すことになった。宿屋は埠頭のすぐそばにあったので、そう慌てることもなかった。
中に入ると、カウンターへと向かう。カウンターに居たのは、予想通り子供だった。
「いらっしゃいませ、宿泊ですか? 休憩ですか?」
「宿泊で。女性が居るので、二部屋とりたいんですけど」
「余裕ですよー、空き部屋は幾らでもあるのである程度の希望は聞くことが出来ますけれど、何かありますか? 角部屋とか、日差しが入る部屋がいいとか」
不動産じゃあるまいし。
「えーと……いや、取り敢えずどこでもいいです。しいて言うなら二部屋は隣同士で」
「了解です。それじゃ、二階の二号室と一号室の鍵、お渡ししておきますね」
そう言って、カウンターに居る子供は鍵を二つ手渡す。
そのタイミングで僕は一つ質問した。
「そうだ。一つ質問したいのだけれど。……この近くで、何らかの要因で滅んでしまった村のことを知らないか?」
「滅んでしまった村、ですか? ……いや、あまり聞いたことがないですね。すいません。私、この町から出たことが無いので。もしかしたら商人さんに聞けば何か解るかもしれませんよ。だって、商人さんはスノーフォグの至る所からやってきて、ここから船に乗って世界各地へ向かうので」
「成る程、いい情報を聞いた。有難う」
一礼して、僕たちはさっそく休憩と今後の方針を考えるべく、部屋へと向かった。
_ ◇◇◇
_ 休憩がてら僕たちは宿屋の一階にあった喫茶店に居た。僕とルーシーはアイスコーヒー、レイナはそれに追加してミルクプリンパフェを注文していた。それにしてもこの世界にもプリンとかコーヒーってあるんだな……。
「それで。これからどうするんだい?」
ミルクプリンを一口頬張って、レイナは僕たちに質問した。
「とにかく、先ずは宿屋の人から聞いた通り、商人に話を聞く」
「けれど、そう簡単に商人から話を聞くことが出来るとは思えないけれどね」
「……というと?」
「商人はけっこう疑心暗鬼になっている人間が多い、ってことさ。軍に助けてもらうことはせずに、わざわざフリーの傭兵を雇って警護させるほどにね。それでも、その傭兵も十分に信用はしていないけれど」
「……軍を、国を信頼していないということか?」
「スノーフォグはどうかはわからないけれど、少なくともハイダルクではそうだったよ。だから手を拱いていることも多かったのではないかな。同じ商人どうしならば競争原理が働いていたとしても同盟を組みたがるけれどね。国が介入して来たら競争原理が働かず、自分たちの思うようにいかない、と思っているんじゃないかな。まあ、私は商人じゃないから、そこまで確証をつかめた発言は言えないけれど」
疑心暗鬼。
もしレイナの発言がスノーフォグでも適用されるものであるとすれば、かなり厄介なことになる。
商人たちの心をつかむ必要がある。
レイナの発言は、僕たちのこれからの方向性を位置づけるに等しいものだった。
_ ◇◇◇
_ ラルースの北東に位置する商業区。
そこは軍の庇護も通らない、自警団が町を警護している非常に特殊な場所だった。
南門にいる兵士に通行許可を求めたけれど、武器を持っている人間は入ることを許さないということで、門前払いさせられてしまった。
門前にある四阿にて僕たちは休憩しながら、どうするべきか考える。
「どうする? 武器を没収させられてでも入る場所ではないと思うのだが?」
「でも、情報を得たいのは事実でしょう? だとすれば、何か策があるはずなのだけれど……」
「そこで一つ、提案があるのだけれど」
そういったのはレイナだった。
レイナはチラシを一枚持っている。どうやら先ほどの南門でもらったものらしいのだが……。
「それで? そこにはいったい何が記載されているのかな?」
「ここにはこう書かれている。今度商業区が隊商を出すらしいんだよ。そんで、それはどうやらエノシアスタという町まで向かうらしいよ。エノシアスタは世界でも有数の巨大都市だ。ロストテクノロジーじみた旧時代の遺物をこれでもかと使った結果、魔術や錬金術とは違う『科学』が発展した町として有名になった町……といえば、さすがのフルやルーシーも知っているだろう?」
正直知らなかったが、レイナが説明してくれたおかげで大体は把握することができた。
そもそも。
この時代を現代と呼ぶならば、偉大なる戦い以前の世界は『旧時代』と呼ぶ時代だった。そこでは今のような魔術や錬金術が発展していることはなく、科学技術の陰に隠れていたのだという。弾丸の雨も、旧時代のロストテクノロジーであったミサイルが何らかの理由で誤発射したことが原因だと言われている。
今でこそ寂れているが、スノーフォグは世界一の技術立国だった。スノーフォグの王がそれを好むかららしいのだが、それはいまだにこの世界で科学技術が後退していかない要因になったともいえる。
「……その町は研究施設が多いらしいし、もしかしたらシュラス錬金術研究所の情報も得られると思うのだけれど、どうかな?」
科学技術が発展している町ならば、確かにレイナの考えは正しいかもしれない。
シュラス錬金術研究所が相当の秘密主義であったとしても、噂のような感じでその研究所について知っている人はきっといるだろうし、情報を得る可能性はそっちのほうが高い。
だったらそこへ向かったほうがいい。
僕はそう思って、レイナの言葉にこたえるように――強くうなずいた。
_ 南門。
僕は兵士にそのように言った。言った、といっても簡単なことだ。ただ、隊商の警備をしたいといえばいいだけのこと。
そういうことで僕たちは商業区の一番奥にある管制塔へと向かうことになった。
管制塔を囲むように家屋が軒を連ねており、それが商業区の長の家であった。
「……して、君たちがその警護を行いたいと立候補した者か?」
「はい」
目の前に立っている、大きな男が商業区の長だった。
大きな、というのは何も身長だけではない。肥満体ということで、横に大きいことだってある。まあ、そんなこと口が裂けても言えるわけがない。もし言ってしまったら、その瞬間牢屋に叩き込まれることだろう。
「しかし、子供三人が、ねえ……。できるのか? 武器も弓と剣とダガー……。どこか心もとない気がするのだが」
「それについてはご安心ください。僕たちはラドーム学院に在籍していた学生です。現在はいろいろな理由がありまして旅をしているのですが……きっと商業区長様が求められている人材であると理解しています」
ルーシーはそう言いながらも、恭しい笑みを浮かべている。
僕とレイナもそれに同調するようにうなずいて、笑みを浮かべた。
「求める人材……ですか。まあ、いいでしょう。実際、人材は多ければ多いほうがいい。現に今、とても人材は少ない。どうしてかわかりますか? あのメタモルフォーズという謎の獣がスノーフォグから出発したと噂されているからなのですよ」
淡々とした口調で話しているが、その口調にはどこか怒りが込められているように見えた。
商業区長の話は続く。
「それによって我々の商売は衰退の一途を辿っています。何故か解りますか? メタモルフォーズがやってくる国の商品など買いたくないなど言っているのですよ。はっきり言って言いがかりにも程がある、眉唾物の言葉ではあるのですが……。しかし、その言葉は案外強く効く。その意味がお解りですか?」
人の噂も七十五日、とは言うが裏を返せば七十五日間もその噂は継続するということになる。つまり今はその七十五日の間、ということになる。
噂が流れている間は、たとえ本人がそれを払拭しようと躍起になってもなかなか回復出来ないものである。
そしてそんなことは、商業区長も解り切っていたことだった。
だからこそ、敢えてその噂を大急ぎで払拭せねばならなかった。
商業は信頼が一番の交渉材料と言われている。たとえ品質の高いものを販売しようとしても、信頼が無ければそれを販売することは難しい。それどころか在庫が減るかどうかも怪しい。しかし、信頼さえあれば若干品質が低いものであったとしても、『信頼』が交渉材料として上乗せされて、販売が成立する。
「……まあ、そんなことはどうでもいい。問題はその影響が国内にも出ている、ということなのですよ。国内でもメタモルフォーズに関する不安を感じる意見はとても多い。そして我々のような人間を護衛してもらうために、たとえば用心棒のような存在もなかなか見つからないのですよ。メタモルフォーズに対処できるかどうか解らないということでね……」
「それであれば、僕たちは幾度かメタモルフォーズと戦ってきています」
それを聞いて、商業区長の目つきが変わった。
ほう、と頬杖をついて首を傾げる。
「ということはメタモルフォーズに対する策も幾つか持ち合わせている、ということでよろしいのですか? ならばこちらとしても願ったりかなったりではありますが……」
「ええ、そのような認識で構いません」
僕の言葉に商業区長は大きく頷いた。
どうやら交渉はいい方向に動いていったようだ。
こうして僕たちは無事――エノシアスタへの隊商、その護衛に合格するのだった。
_ ◇◇◇
終了後、街並みを歩いているとルーシーがそんなことを言ってきた。
別に僕としてはいつもと同じように話していたつもりだったのだけれど――いや、それは訂正しよう。ちょっとは緊張していた――どうやらルーシーにはそれがどっしりと構えていた、という風に見えていたらしい。まあ、内面性と外面性は必ずしも一致しないからそれは案外普通なことかもしれないけれど。
「確かに、かなり落ち着いているように見えたよ。やっぱりフルをメインに据えていてよかった」
そう言ったのはレイナだった。レイナはそれを提案した張本人だったわけだけれど――、いざ始まってしまうと、案外話すことが出来ないものだ。というよりもレイナが話すよりも先に僕が話してしまって話の流れを作ってしまったのが一因かもしれない。
さて。
そうと決まれば出発日までの時間つぶしだ。出発日は明後日と決まっているので二日ほど、どこかで時間を潰さないといけない。宿はとっているから宿に戻ってもいいのだけれど、もう少しここで情報収集してもいいような気がするが……。
「というかここまで来たらエノシアスタに行ってから情報収集したほうがいいんじゃないか? それともここで情報を少しでも仕入れておく? それはそれで構わないと思うけれど」
「うーん、そうなんだよな。ここで有益な情報が手に入ったとしても、一度請け負った仕事はやっぱり最後までやらないといけないのは当然の責務だ。だから出来ることなら情報はここで仕入れないほうがいいかな、とは思うけれど――」
「おい、てめえ! ぶつかっただろ!」
僕たちの話を遮るように、昼間の状態には似つかわしくない男の大声が聞こえた。
そちらを向くと、酒瓶を持ったいかにも酔っぱらっています、という感じの男が立っていた。
男から少し離れた位置には大きな銃を背負った女性が背を向けて立っている
「……、」
女性は答えない。
男はさらに話を続ける。
「おい、聞いているのかよ! お前、さっきぶつかっただろ、って言っているんだよ!」
男はゆっくりと近づいて、銃に触れた。
その時だった。
踵を返し、男の手を取り、そのままその手を地面に落とし込んだ。男のほうが図体が大きかったにも関わらず、男は地面にその身体をつける形になった。
男はなぜそんなことになってしまったのか解らず、呆気にとられていた。
「……汚い手で私の銃に触れるな」
「……メタモルフォーズを倒せば偉いのかよ、掃除屋、っていう職業はよお!」
男は言葉を投げつけるが、女性は表情を一つ変えることなく立ち上がると、そのままもともと歩いていた方向へ歩いていった。
「……なあ、今聞いたか?」
ルーシーは僕に語り掛ける。
ああ、聞いたよ。
気になるワードが、幾つか登場していた。
メタモルフォーズを倒す、掃除屋。
もしかしたら彼女ならばメタモルフォーズに関する情報を幾つか掴んでいるかもしれない。そう思って僕たちは彼女の後を追いかけた。
_ ◇◇◇
_ 路地に入ったところで、彼女は踵を返し――唐突に僕に銃口を向けた。
「……あんたたち、さっきから私のことをつけていたようだけれど、いったい何が目的? そういうプロにしてははっきり言って素人のような素振りだったし……」
「ちょっと待ってくれ。別にあんたを狙っているわけじゃない。まあ、つけていたことは事実だけど……。ちょっと聞きたい事があるんだ」
僕は必死に訂正した。
追いかけていたことは事実だけれど、先ずは彼女が僕たちについていいイメージを抱かせないといけない。正確に言えば敵意を消す、という感じかな。
「聞きたい事?」
警戒を解いてくれることはさすがにすぐにはしてくれなかったけれど、銃だけは僕の前から外してくれた。
しかしながらまだ目線は鋭い。ここはどうにかして警戒をもう少し解いてもらえるようにしないといけないのだけれど、そう簡単にうまくいくとは限らない。情報が手に入らない可能性もあるので、慎重に行動しなくてはいけない。
「……ああ。実は、メタモルフォーズに関する情報を知りたい」
「メタモルフォーズに関する情報……ねえ。そんなもの、聞いてどうするつもりだ? もしかしてお前たちも掃除屋か? 一端の掃除屋だったら同業者から何もなしで情報を得るなんてそんな暴挙簡単に出来ないと思うが」
「違う。そうではない。僕たちは掃除屋でも何でもないよ。けれど、情報は得たい。だから、出来れば情報を知っている人間を探していたのだけれど――」
「だから、言っているだろう?」
そう言って少女は僕に右手を差し出した。
その意味が解らなくて暫く彼女の右手を見つめていたのだが、
「まったく、何を意味しているのか言わないと解らないのか? あんまり言いたくないが、これだから何も知らない子供は……。見た感じ、それなりにいいところを出ているように見える。そうだろう? この世界でいい学校と言えば……、そうだな、ラドーム学院か。あそこの出ならば少なくとも常識くらいは知っているだろうが、しかしそれはあくまでも『表』の世界の常識。私たち掃除屋に代表されるような裏の世界の常識なんてまったく仕入れていないだろう? だから、そんな常識外……埒外なことが言える。それに私は腹を立てているのだよ。敢えて言おう、表の人間が必要以上に裏に干渉するな。これは警告だ。こう警告してくれる人間は居ないぞ」
「……じゃあ、解った。何をすれば情報を提供してくれる? まずはそこから始めようじゃないか」
「……そもそも、そこが問題だよね」
そう言って少女は僕の顔を指さす。
「対価を払わないとダメと言ったからと言って、対価さえ払えば問題ないというわけではない。私が知っているメタモルフォーズに関する情報は、長年の『掃除屋』としての経験から得たものが殆ど。それを教えるとは即ち私の掃除屋の経験そのものを伝えるということに等しいのよ。それの意味が理解できる?」
「……そうかもしれないけれど、こっちだって切羽詰まっているのよ」
そう言ったのはレイナだった。
レイナはどこか強い発言をすることが多い。というよりも発言がおのずと強くなってしまう、という感じだろうか。いずれにせよ、僕やルーシーのように強く言うことが出来ないタイミングでも言うことが出来るから、とてもそれについては有難いのだが。
しかして、こうもはっきり言われてしまうと当然相手の心情もどう行くか完全に二択になってしまう。
「……切羽詰まっている? どういうことよ」
首を傾げ、目を丸くする少女。
もしかしたら少しだけ話を聞いてくれるのではないか――僕はそんなことを思った。
そしてその『チャンス』を有効活用すべきだと思っていたのは、僕だけではなかった。
「私たちはメタモルフォーズを倒す必要がある。ね、そうでしょう? フル」
「あ、えーと、うん。そうだ」
唐突に会話の矛先を向けられてちょっと動揺してしまったが、ここでチャンスを逃がしてしまうとなかなか次のチャンスはやってこないだろう。
そう思うと、不思議と声は落ち着いてきた。
「僕たちはメタモルフォーズがどこからやってきたのか、それを探している。それが世界を破壊してしまう可能性があるから」
「まるで予言に示されていた勇者サマみたいな言い回しだな。……ほんとうに世界を救おうと考えているのか? あんたみたいな、学生風情が?」
「世界を救えるかどうかは解らない。けれど……メタモルフォーズはかつて世界の危機へと導いた存在だろう? ならば倒すのは当然だし、それがなぜ生まれてしまったのか突き止めなくちゃいけない。そのためにも……」
「ああ、いい。解った」
そこまで言ったところで少女は手を振った。
何か言っちゃまずいことを言ってしまったか――?
僕はそんなことを思ったが、少女は頷いて笑みを浮かべた。
「解った、解ったよ。けれど、あんたたち大馬鹿者だよ。どこへ向かいたいと思っているのか、解っているのか? メタモルフォーズの巣へ向かうと言っているんだぞ? そして、そこに進んでいく存在なんて居るわけがない。確かにこの世界はメタモルフォーズによって幾度か滅ぼされかけている。それは世界の歴史書にも示されている、殆どの人間が知る一般常識と言ってもいい。だが、その力は圧倒的すぎる。人間には到底倒すことが出来ない存在だったんだよ」
「解っている。解っているよ。……だが、どうにかしないといけない。そうしないと……助けられる人間も助けることが出来ないから」
それを聞いたからか知らないが、少女は小さく舌打ちをして踵を返す。
「……やっぱり、駄目か?」
僕は首を傾げ、少しだけ儚い様子で言った。恐る恐る、と言ったほうが正しいかもしれない。
しかし少女は踵を返すと、さらに話を続ける。
「違う。……さっき、私は言ったよな。タダで情報を得ようなんてことは出来ない。だから、それなりのものを提供してもらう必要がある、ということだ」
「交渉成立、ということか?」
「そう思ってもらって構わないよ。ただし、その『それなりのもの』はこの町一番の店でのディナーだ。はっきり言って、それなりに金は弾むぞ?」
「それで貴重な情報が得られるならば安いものだ。有難う、恩に着るよ。ええと、名前は……」
「リメリアだ。勘違いするなよ。お前たちにおける状況が私の琴線に触れた、というわけではない。それだけは理解してもらうぞ」
そう言ってリメリアは再び踵を返すと、歩いていった。
僕たちもそれを追いかけていくように、リメリアの後を追った。
_ ◇◇◇
_ 目を覚ますと、そこは暗い部屋だった。
壁に松明がつけられていて、それが唯一の明かりとなっている。いったい自分がどういう状況に置かれているのか立ち上がろうとして、そこで自分の足首と手首が重たいことに気付いた。
少し遅れてジャラリ、という鎖の音が聞こえたことで、私の両手首と両足首が鎖によって動きを制限されていることを理解した。
「ここはいったい……」
そう私がつぶやいたところで、私の目の前にある扉が大きく開かれた。
「目を覚ましたようだね、お姫様」
その声を聴いて、私はそちらを向いた。
そこに立っていたのは燃えるような赤い髪の男――バルト・イルファだった。
バルト・イルファは笑みを浮かべて、こちらに一歩近づいた。
「怒りを抱いているようだけれど、ちょっとこちらに怒りを抱くのもどうかと思うよ。僕は主から命じられてやっているわけだからね。下請け、とでもいえばいいかな? とはいえ、君がそう思うのもわかるけれどね」
「……何が目的なの?」
私は一歩下がる。すぐに壁にぶつかってしまい、もうこれ以上後退することができない――その事実を受け入れざるを得なかった。
バルト・イルファはさらに一歩近づくと、私の腕を手に取って、強引に部屋から連れ出そうとする。
「君に真実を伝えるためだよ、お姫様」
そう言うだけだった。
私はそれ以上何も言うことなく――そのまま引きずられるようにどこかへと向かうのだった。
_ 通路は薄暗かった。手枷と足枷を外してもらうことはできたけれど、だからと言って逃げ出せるような状況でもなかった。場所がわからない、ということもあるし、できることならこの場所の情報を少しでも手に入れたい――そう思っていたからだ。
通路の先に見える明かりは、ようやく見えた明かりだというのにどこか悲しそうに見えた。正直言ってあの先にあるものがはっきりと見えてこない。
そうして私はバルト・イルファを先頭にして、通路の先を抜けた。
通路の先に広がっていたのは巨大な空間だった。壁の殆どは透明になっていて、壁の向こうの空間に何があるか見ることができる。
そこにあったのは、巨大な獣だった。それがどんな動物であるかはっきりと解らなかったけれど、ただ一つ、これだけははっきりと言えた。――それは、どの動物とも違う肉体で、様々な動物の顔がいろいろな場所についていたということ。
「これは……」
「オリジナルフォーズ、といえば解るかな? いや、正確に言えばオリジナルフォーズの肉塊から生み出された別のメタモルフォーズといってもいいだろう。どちらかといえば、そちらのほうが正確かもしれないがね」
「メタモルフォーズ……。こんなにも大きな、メタモルフォーズが」
エルフの隠れ里で初めて見つけたそれよりも大きなメタモルフォーズが、目の前にいた。ただしそれは目覚めているわけではなく、ほのかに緑色の液体に浮かんでいて目を瞑っていた。それだけ見れば眠っているように見えるけれど……。
「そうだ。君の思っている通り、あれは眠っている。眠っているけれど、起きている。どういえばいいかな。二元性を保っている、といえばいいか」
「オリジナルフォーズを使って、世界をどうするつもり?」
「オリジナルフォーズ。あれはまだ目覚めることはないよ。それは主の計画にとっては非常に残念なことではあるがね。目覚める手順は解っているというのに、それになかなか手を出すことができない。現実は非情だねえ」
「オリジナルフォーズを目覚めさせることができない……? けれど、あなたたちが使っているメタモルフォーズは」
「あれは模倣だよ」
バルト・イルファはそう言葉を投げ捨てた。
水槽を眺めて、バルト・イルファは遠いところを見つめるかのように、目を細めた。
「そう、模倣だ。オリジナルフォーズから抽出したサンプルを用いて、同じ構造の物体を作り上げる。そうすることでかつてのメタモルフォーズと同じようなものが生み出されていく、というわけだ。とはいえ、かつての時代で世界を滅ぼそうとしていたあのメタモルフォーズと比べれば力のスケールは圧倒的に小さいものとなってしまうがね。やはり模倣はそれなりの力しか使うことができない、ということだ」
「酷い言い様だね。……バルト・イルファ、君はいつも科学者のことを考えない。研究している人間にとってみればそれが精一杯の成果だということを、君も彼女も考えないのだ」
その声を聴いて、バルト・イルファは踵を返した。
そこにいたのは白髪頭の男だった。白衣を着て眼鏡をかけていたが、その様子はどこか落ち着いている様子に見える。しかしながら、その男の様子はどこか不思議と落ち着きのないようにも見えた。
「ドクター……。相変わらずあなたはまたこのような場所に居るのですか」
「別にいいではないのかい? ……きひひ、私としてはいつまでも研究の場に立っていられることはとても素晴らしいことだといえるけれどねえ」
そう言ってドクターとよばれた男は私に近づく。一歩、さらに一歩。最終的に小走りになった形で私の目の前に立った。
目の前にいる様子では、ドクターは小奇麗な男だった。こんなところにいなければそれなりに活躍できるのではないか――とは思ったけれど、それも彼の思って進んだ道の結果なのだろうか。
ドクターは私の表情を確認するように見つめると、頷いて笑みを浮かべる。
「……いつまで長々と見つめているつもりだ、ドクター。何か思うことでもあったか?」
「いひひ。いいや、何でもないよ。あのお方の子供を目の当たりにできるとは思いもしなかったからねえ。研究は続けていくものだ」
「当たり前だろう。……彼女はピースだ。それでいてスペアでもある。王の器を受け継ぐには必要な存在だ……。お前たち科学者は常々そう言っていただろう?」
「まあ、間違いではないさ」
ドクターはくい、と眼鏡を上げる仕草をして、
「けれどその認識のままでいくといつかダメージを受けることになると思うよ? 残念ながら、まだ当分王はあのままでいくだろう。結果はどうなるか解らないけれど、過程としては素晴らしいくらい順調に進んでいる。計画はあと少しで終わりを迎える。いや、正確には今から始まり……ということになるのかな。いずれにせよ楽しみであることには間違いない」
「別にそこまで言わなくてもいいだろう? ……さてと、話が過ぎた。これから僕は彼女をある場所に連れて行かないといけないからね。これで失礼するよ」
バルト・イルファはそうして強引にドクターとの会話を打ち切って、私の手を取った。
ドクターは小さく舌打ちをして、
「強引に連れていくのは、女の子に嫌われるよ? そう、例えば君の妹のような子にも……」
「妹のことは関係ないだろう? 君こそ、そんな適当なことを言って、僕に何かされる可能性は考慮していなかったのか」
バルト・イルファとドクターは仲が悪いのだろうか。いや、こういう文句を言い合える仲は意外と悪いものではない、と聞いたことがあるし、そんなことはないのかも知れない。
ドクターはこれ以上何も言えないと思ったのか、諦めて手を振った。
けれど、その様子はまだ諦めていないようにも見える。どちらかといえば、そっちのほうが大きいかもしれない。……ドクター、要注意人物に入れておこう。
「それじゃ、向かうことにしようか」
踵を返し、バルト・イルファはそう言った。
いったい私をどこへ連れていくつもりなのだろう。
バルト・イルファに問いかけたかったが、そうすることもできなかった。
バルト・イルファと私の戦力差は圧倒的なものであるとすでに理解している。バイタスの街を彼一人で焼き尽くしたことからもはっきりしている。ならば、無碍に戦いを挑むようなことはしない。
おそらくフルとルーシー、それにレイナが私を探しているはずだ。しかし出来ることなら、彼らが来る前にここから脱出しておきたい。彼らがどういうルートを辿るのか、そもそもここはどこなのかすらはっきりとしていないけれど、できる限り情報を盗んでおいてから脱出しておきたい。
そんなことを考えながら、私とバルト・イルファはまたひたすらと長い通路を歩いていた。
長い通路を抜けた向こうに広がっていたのは、いろいろな機械がある空間だった。機械はたくさんのガラスがついていて、その小さな箱には一つ一つ今まで通った場所が透けて見えるようになっている。
「……その反応だと見たことがないようだね、これはモニターというものだ。そして、私たちが今捜査しているものはコンピュータ。これを使ってあれの維持とこの場所の管理をしている。まあ、実際のところこれほどの技術は外部に流出なんてさせないから、別にこれを知ったところで何の意味も無いのだけれどね」
「あなたは……?」
「はじめまして、メアリー……で良かったかな? 私の名前はシュラス・アルモア。シュラス錬金術研究所の所長であり、現在もこの『リバイバル・プロジェクト』の主任を務めている人間だ。これからきっと長い付き合いになるだろうから、よろしく頼むよ」
そう言ってシュラスは私に手を差し伸べた。
しかし私はそれに応えることなく――シュラスを睨み付ける。
シュラスはそれを見て舌打ちをするなり、私の脛を蹴り上げた。
「痛っ……!」
「お前は黙って話を聞いていればいい。いうことさえ聞いていればいいんだよ」
先ほどの丁寧な口調とは違うシュラスの言葉。きっとこちらのほうが普段の口調なのだろう。シュラスは私を蔑むように見下ろした。
バルト・イルファは私を見つめることなく、シュラスのほうをただ見つめていた。仲介することも話をすることもなく、ただ傍観していた。
「……まあ、取り敢えずこれ以上私の手を煩わせるな。いろいろと面倒なことになるのは解っているだろう?」
「お言葉ですが、シュラス博士。彼女はおそらく自らの立ち位置を理解していないものかと思われますが……」
「『十三人の忌み子』の末路である貴様が、何を知っていると?」
それを聞いて眉を顰めるバルト・イルファ。
どうやら彼にとってその言葉は耳あたりの良いものではないようだった。
「……所詮、お前も主には逆らえない従順な犬に変わりない。それを理解することだな」
そう言ってシュラスは立ち去っていく。
結局あのシュラスという男は何がしたかったのだろうか――私にはさっぱり解らなかったけれど、バルト・イルファはそんな私を無視するようにさらに引っ張り上げていく。
「バルト・イルファ、あなたはいったい私をどこに連れて行こうとしているの?」
「そう焦ることもないだろう? すぐ終わることだ。それに、立場を弁えたほうがいいぞ。君は今、捕虜の立場に居るのだから」
「……貴様がメアリー・ホープキンか。神の子であり、王の器の継承者でもある人間」
その言葉を聞いて、私は前を向いた。
そこに立っているのは、麻の服を着た男性だった。頭部がすっぽりと隠れる帽子を被って、暑さを遮っているように見える。
「……私の名前はアドハム。スノーフォグ国軍大佐を務めている。以後、お見知りおきを……。と言っても、貴様はどう足掻いても最終的に私の名前を覚えざるを得なくなるがね」
「スノーフォグの……国軍大佐、ですって? この研究施設は国の施設……!」
それを聞いたアドハムは何も答えることなく、小さく舌打ちした。
「王の器と相性は、ほんとうにあっているのだろうな?」
「当然でしょう。だって、彼女は王の子ですよ?」
「王の子、とはいっても彼女は情報を何一つ知らないのだろう? はっきり言って、その状態ではただの一般人と変わりないではないか。だったらまずその知識を植え付ける必要があるのでは?」
「器との相性、知識とは関連性はありませんよ。器と相性さえ良ければ問題ありません」
背後から近づいたのはシュラスではない、また別の研究者だった。
「フランツ……」
「おや、僕のことは呼び捨てか。僕も嫌われたものだね。十三人の忌み子を育てたのは紛れもない僕なのに?」
溜息を吐いた科学者はまだ若い科学者のようだった。シルバーブロンドのさらりと透き通るような髪をしていた。
「フランツ。君からも何とか言ってくれないかね、この実験結果について」
そう言ってアドハムはバルト・イルファを指さした。
バルト・イルファはそれを見てにらみつけるようにアドハムを見たが、アドハムは当然それに屈することなど無かった。
「……さて、フランツ。私は忙しいものでね、さっさとエノシアスタに向かわねばならない。まったく、あの女王にも困ったものだ」
「女王、ですか。……まあ、あの人は我儘ですからね、致し方ありませんよ」
「その発言、女王に聞かれたら貴様とてただでは済まないのではないかね?」
「そうなればきっと『あれ』が許しませんよ」
そう言って、フランツは背後に浮かんでいる何かを指さした。
それはメタモルフォーズだった。まだ眠りについているようだったが、先ほど見たそれとはさらにサイズが違う。それに周りにある液体を取り込みながら、若干ジェル状になっているようにも見える。
「……確かに、そうだな。貴様がまだここにいるのもそれが要因だ。せいぜい、やることを果たしてくれ給えよ」
そう言って、アドハムは部屋から出て行った。
「アドハムはいつもああいう性格で、ほんとうに困ります。まあ、彼がここに居るからこそ、こういう研究が出来るわけですが。それも合法的に」
そう言ってフランツは溜息を吐くと、改めて私のほうを見つめて、笑みを浮かべた。
「君がメアリー・ホープキンだね? いや、まさかこんなにも早く君に出会えるとは思わなかったけれど、生憎王の器の時間が限られていてね。次の器を用意する必要が出てきたのだよ。申し訳ないねえ、君は冒険をしているようだったけれど、強引にこのような場所に連れてきてしまってね。残念ながら、少しだけお話をさせてもらうよ。なに、そんな難しい話じゃない。ちょっとしたヒヤリングみたいなものだ」
そう言ってフランツは話を始めた。
バルト・イルファはさりげなく話が始まるタイミングを見計らって、少しずつ私のそばから姿を消した。
_ ◇◇◇
_ 夜。
ラルース一のレストランに僕たちとリメリアは居た。六人掛けのテーブルで、片方にリメリアのみが座っており、もう片方に僕たち三人が座っている形になる。ラルース一のレストランとはいえ、銃器の持ち込みを禁止しているわけではない。
盛り付けられている料理を一言で述べるならば、肉料理が中心となっている。魚、鳥、肉……いろいろな種類の肉を使った料理がテーブルに所狭しに並べられている。
そしてそれをがっついているリメリアと、ただ茫然と眺めている僕たち。
光景だけ俯瞰で眺めると、意味が解らない状況であることは間違いないと思う。
「……あら、どうしたの? 別に、奢ってくれとは言ったけれど、全部とまでは言っていないわよ。さすがに食べきれないだろうしね。だから、あなたたちも食べてよ。……まあ、そんな言葉を言える立場でないことは重々承知しているけれどさ」
「それよりだな、情報はきちんと提供してくれるのだろうね?」
ルーシーが僕も気になっていたことを代弁して、話してくれた。
対してリメリアは豚肉のようなもの(おそらくハムか何かだろうか?)を豪快に口で引きちぎり、噛みながら笑みを浮かべる。
「当たり前だろ。掃除屋は嘘を吐かないものさ。ほら、それよりも食べないと冷めてしまうよ。それとも、冷めた料理が好きというのならばそれもそれで止めないけれど」
「あ、ああ……。そうだな。取り敢えず、頂くことにしよう」
本来は僕たちが支払うお金で注文しているので、リメリアの言う通り僕たちが普通に食べていい食事になるから、『頂く』なんて表現は少々変なことになるのだけれど、実際問題、それは間違った話ではないということになる。
そういうわけで、僕たちもまた食事に取り掛かるのだった。というか、それしか選択肢が残されちゃいなかった。
食事について特筆すべき事項は無いと思う。だって、実際に食事シーンをつらつらと説明する必要もないだろう? しいて言うなら、肉料理まみれというのもバランスが悪い食事だということを再確認出来た、ってことくらいかな。リメリアは野菜が嫌いなようで、殆ど肉料理しか注文しなかった。だから僕は我慢できなくなって(のちに聞いたがルーシーとレイナもそう思っていたようだった)、サラダを注文した。そのときリメリアはサラダも食べるのか、と言わんばかりの悲しげな表情を浮かべていたけれど、そんなことはどうだっていい。というか、嫌いならば食べなければいいだけの話だ。僕は肉料理ばかりだとなかなか舌がリセットされないから注文しているだけだから。
そんなことはさておき。
料理を食べ終えたところでリメリアはメニューを取り出した。あれだけ食べられない量を注文したというのに、また何か注文するつもりなのだろうか? というか、まだ君が注文したものすべて食べ終わっていないのだけれど!
そう僕が考えていたら、どうやらその視線に気付いたらしく、
「……何よ。デザートを食べようとしていただけじゃない」
デザートまで所望するというのか。
これは情報がそれなりのものじゃないと納得しないぞ。今日だけで懐がどれほど軽くなったと思っているのか。
「私が情報を持っていない、とかそんなこと思っているのならば安心しろ。きっちり私が持っている情報を提供してやるよ。無論、それがどこまで君たちにとって有益な情報であるかは、いざ話してみないと解らないことではあるがね」
「確かにそれもそうだが……。だからといって、それを理解していない僕たちでもない。掃除屋は実際の一般人以外で知っているような情報を仕入れているのだろう? 例えば……メタモルフォーズの住処、とか」
「……そこまで理解しているなら、話は早いじゃない。あ、バニラアイスパフェ一つ」
いつの間に店員を呼んでいたんだ。
そんなツッコミを入れようとしたが、それよりも早く注文を終えてしまったので何も言えなかった。情報が有益であるかそうでないかは、僕たちの情報分別能力にかかっている。
_ パフェがやってくるまで五分、それから食べ終わるまで十分。合計十五分をさらに待機していた僕たちは、さすがに大量の肉料理を平らげていて、リメリアがパフェを食べ終わるまで待機していた。なぜそのまま待機しているかというと、逃げられる可能性を考慮していたからだ。逃げられてしまったら、このお金も無駄になる。……少々豪勢な食事をした、と割り切ってしまえばいい話かもしれないけれど。
パフェをすべて食べ終わり、食後にサービスでやってきたホットコーヒーを啜るリメリアは、溜息を吐いて目を瞑った。
そして少しして目を開けると、リメリアは大きく頷いた。
「……それじゃ、少々時間はかかってしまったけれど、食事をおごってもらうのが約束だったからね。私もその約束を果たさないと」
紙ナプキンで口の周りを拭いて、リメリアは話を始めた。
「先ず、メタモルフォーズの住処について簡単に説明しようか。メタモルフォーズの住処、と言うけれど実はうまい特徴は見当たらないんだ。大抵場所は見つかっているけれど、……ああ、でも一つだけあったかな。その特徴、当たり前かもしれないけれど、人が少ない場所に住処はあるんだよ。それは当たり前だよね。メタモルフォーズは人間の敵だ。人間が逃げるか、メタモルフォーズを撃退するか、はたまたメタモルフォーズに返り討ちにあってやられてしまうか……そのいずれかだから」
「メタモルフォーズは、人間の進化形……それについて聞いたことは?」
ルーシーはこの前、リーガル城であった出来事について質問する。
リメリアは知った風な様子で答える。
「あれならば、スノーフォグならば常識だよ。逆に、ハイダルクではそれは知られていなかったのか? ……もしかして、ハイダルクだとメタモルフォーズが出現すること自体も少なかったのか?」
「そうかもしれないわね。メタモルフォーズはハイダルクでは殆ど発見されていない。この間の城へやってきたメタモルフォーズが初めて、なのかもしれない」
正確に言えば、それよりも前に僕とルーシー、それにメアリーがエルフの隠れ里で出会ったのが最初になるけれど……それは言わないでおこう。
「スノーフォグでは、恐らくメタモルフォーズにおける知識がある程度常識化しているかもしれないね。実際、スノーフォグはメタモルフォーズをどう倒せばいいか、ということについては私たち掃除屋や軍に投げっぱなしになっているところも多いのも事実だけれど。……大抵の一般市民は軍に頼るし、軍が嫌いな人間は私たちのような掃除屋に頼む。そういうものだよ」
「掃除屋はたいていフリーで働くものなのか?」
それを聞いて頷くリメリア。
「そういうものよ。あなたたちは掃除屋のことをどう思っているのか定かでは無いけれど……、掃除屋は世界から良い風に思われていない。それが現実。それが真実。だからこそ、私たちももう少しその地位を上げていかねばならないと考えてはいるのだけれどね」
「考えている……ですか?」
「まあ、それについては語る必要も無いでしょう。あなたたちが知りたいのは、もっと直接的な情報だと思うから」
そう言って、リメリアはコーヒーを飲みほした。
「メタモルフォーズの巣。私たち掃除屋はその情報を知っている。一番ここから近い巣はエノシアスタから南方に行ったところ。どうしてあのような場所にあるのか、と思うくらい人の里に近い場所にある。……まあ、私たち掃除屋にとってみれば拠点を作りやすいから有り難いといえば有り難いのだけれど」
_ それから、得られた情報はいろいろとあったけれど、最大の情報はやはりエノシアスタの南方に巨大な巣がある――ということだった。実際に、それ以外にも情報は得られている。たとえば、メタモルフォーズは基本的に『属性』があるため、その属性に弱い攻撃を与えないとなかなかダメージが通らないということや、しかしそのような属性があったとしても近距離からの爆撃はそれなりにダメージが通るということや、大抵は戦闘に関することだったが、メタモルフォーズに関するどのような情報でも欲していた僕たちにとって、それは有り難いことだった。
「……これくらいの情報で何とかなる、かなあ」
リメリアと別れた僕たちは宿屋にて休憩していた。部屋は二つとっているのだけれど、そのうちの僕とルーシーが眠る部屋にてレイナも集まっているという形になっている。
「それにしても、情報はそれなりにあったよね。まあ、豪勢な食事を食べてしまった、ということもあるけれど、かなり満足感は得られたのではなくて?」
レイナの言葉に頷くルーシー。
そして僕もその意見に賛成だった。満足感が得られた、ということよりもここまで簡単に情報が得られたということ。そしてその情報の一つが、明後日向かうエノシアスタに関する情報であるということがとても僕たちにとって有益な情報だった。
「それにしても、エノシアスタ……ね。行ったことの無い場所だからちょっと気になるけれど、いったいどのような場所なのかしらね?」
「機械都市、ということは聞いたことがあるけれど、どこまで機械じみているのだろうね? 僕も教科書でしか見たことは無いのだけれど……」
機械都市エノシアスタ。
教科書ではよく見たことのある、その都市の名前。旧時代にあった文明をうまく組み合わせることでこの世界では珍しい機械仕掛けの町を作り上げたのだという。そのため、世界各地から観光客が訪れている、スノーフォグ随一の観光地なのだという。
「確かにそんな場所ならば、ビジネスチャンスは多く存在するはずだよな……。あの商人が何をするのかは解らないけれど」
ルーシーの疑問も解らないではなかった。
ただ僕たちはまだ子供だ。そういうことに関してまだ解らないことが多い。解らないことが多いからこそ、知りたいと思うことも多い。
それについてはきっと、経験と時間が解決してくれるはずだろう。僕はそう思っていた。
「……まあ、明後日からはエノシアスタへ向かうことになる。どういう場所でどういうことになるかはっきり解ったものではないけれど……取り敢えず、今はゆっくり休もう。休息も大事だ。メアリーを助けることももちろん大事だけれど……」
「いや、フル。君の言っていることも解るよ。今はゆっくり休もう」
そうしてレイナは自分の部屋に戻り、早々に僕たちはベッドに潜った。
_ ◇◇◇
_ そのころ、メアリーも夜を迎えていた。
フランツからのヒヤリングは簡単なものだった。この世界の歴史について、それにスノーフォグについての基礎知識の質問がある程度で、そのようなものは頭に叩き込んでいたメアリーにとってそんな質問は楽勝だった。
しかし、どこか彼女にとって引っ掛かっていた。
なぜフランツはそのような質問をしたのだろうか?
「フランツ……。なぜあの科学者は」
思わず呟くが、けれども考えが進むわけでもない。
一先ず今の状況では、ここに居る人間が彼女をどうこうするという話にはまだ至っていない。それどころかどこか大切にされつつある状況にもなっている。
それが彼女にとって一番理解出来ないことであった。なぜ自分が大切にされる必要があるのか? それをフランツに訊ねたが、今は知らなくていいとの一点張りでまったく答えて等くれなかった。
「……今はもう、眠るしかないのかもしれないわね……」
まったく考えがまとまっていなかったが、このまま考え続けてもまとまるとは到底思えなかった彼女はそのまま横になり――そして、半ば強引に眠りにつこうとそのまま目を瞑った。
_ ◇◇◇
_ 二日後。
僕たちは旅団と一緒に機械都市エノシアスタへと向かうこととなった。
エノシアスタへ向かうにはトラックを用いる。トラックが合計四台。荷物を載せているものが三台と人を乗せるために荷台部分を改造したものが一台となっている。人員はそれほど割かれているわけではなく、僕たちを除くと十人程度しか居ない。
そもそも一台――その人を乗せるためのトラックだけ明らかに巨大だった。もともとはダンプカーだったのかもしれないが、そうだとしても改造度合が半端ない。とにかく、人を乗せるためにいろいろな改造をとことんやってのけた、という感じがする。
「それにしても、こんな若い人が俺たちの護衛についてきてくれるとはね」
僕たちの居た部屋――と言っても間仕切りが殆どされていないので、部屋という空間と言っていいかどうか微妙なところだが――そこに入ってきた兵士はそう言った。
兵士――と言ってもそれはあくまでも推測しただけに過ぎない。本人から兵士だと聞いたわけではないからだ。ただ、ほかの人間に比べて若干装備が重装備に見えた。だから、そうかな、と思っただけに過ぎない。
「あ、俺のことかな? おかしいなあ、自己紹介していなかったっけ……。あ、していなかったかもしれないな。俺の名前はシド。こういう身なりをしているが、俺も商人の端くれだ。まあ、よろしく頼むよ」
「……よろしく」
シドさんが手を差し出してきたので、僕もそれに答える。きちんと答えないと意味が無いからね。それについては今から少しでも良い関係を築いておかないとギスギスしてしまうし。
シドさんの話は続く。
「まあ、君たちの実力を否定しているわけではないけれどさ。実際にその目で見たわけじゃないから、それを否定することも間違っていると思うしね。……取り敢えず、お近づきのしるしにどうぞ」
そう言って、シドさんは僕たちにキャンディを差し出す。
それを受け取ってそのままポケットに仕舞い込んだ。
「俺はいろいろと嗜好品を取り扱っていてね。まあ、別に珍しい話じゃないと思うけれど。特にここ最近嗜好品の売り上げが増えてきた。好調、とでも言えばいいかな」
「へえ、何故ですか? やはり、メタモルフォーズに対する不安?」
「そうとも言えるし、そうとも言えないかもしれない。メタモルフォーズは不安になる材料ではあるけれど、商業としては一番いいところを持ってきてくれるからねえ。何というの? その、災害特需、ってやつ? そういうことも多いわけだよ。今から向かうところも、確か一応メタモルフォーズの攻撃を受けてしまったために一部被災しているエリアがあるわけだが、そういう場所というのはもう何もかも足りないわけだ。人はもうあまりまくっているというらしいがね」
「人は余っている……?」
「『助けたい精神』の骨頂というやつだよ。助けたいけれど、何も出すものが無い……。だから自分の身体だけでも、という人間のこと。そういう人間は確かに有難いよ。人は多ければ多いほうがいい。けれどそれはあくまでも仮定に過ぎない。実際問題、増え続けてしまえばそれは過多になってしまう。食料の供給もまともに無い、寝る場所も少ない、まともに眠ることの出来る人間すら少ないというのに、人が増え続けてしまう。そうなったら、何が生まれると思う?」
その先に何が生まれるか。
ええと、おそらくきっと……。
「答えは簡単だ。供給と需要が割に合わなくなり、食料は益々減ることだろう。おそらく、寝るところも衣服も……何もかも足りなくなる。そういう場所に売りに行くのが……俺たち商人、というわけ」
「ボランティア……無料で提供しようというつもりはない、ということですか?」
「あるわけないでしょう。だって、ビジネスチャンスの一つだよ? そんなチャンスを逃がしてまで商品を出すわけにはいかない。世界の仕組みというのは、案外そういうものだよ。まあ、君たちのような子供にはあまり解らないかもしれないが……」
「けれど、それは理屈でしょう? ボランティアとは言わずとも、せめて安く提供することだって……」
「そんなことを言ってもね、俺だって、こっちだって商売だ。飯を食うために、そして何より生きていくために働いている。物を売っているわけだよ。もちろんなるべく安くしているつもりだ。けれど、これ以上安くしてしまえば俺だって生きていけなくなる。不謹慎? 悪者? そんなことを言う人だっているさ。けれど、そんなことですべて萎縮してしまったら世界もろとも暗い雰囲気に包まれてしまうとは思わないか?」
「それは……」
それについて、僕ははっきりと答えることは出来なかった。
無料で提供すること。それは出来なくても、安くすることは出来ないのか――ということについて。
それはきっとやろうと思えば簡単に出来ることなのだと思う。けれど、それを実際にしてしまえば今度は商人が生きていけなくなってしまう。そうなってしまうと経済がうまく回らなくなり、世界的に経済が破綻してしまう。要するに、一つの災害で世界を崩壊させてはならない……そういうことなのだろう。
「……まあ、君にそれを言うことは間違っていたかもしれないな」
先に折れたのはシドさんのほうだった。
もっとも、折れたというよりは話の流れをこれ以上続けても場の空気が澱むままだと判断したためかもしれない。
「邪魔したね」
シドさんは座席から立ち上がると、そのまま扉代わりのカーテンを開けた。
「それじゃ、また後で。何もないことを祈っているよ」
「ええ、僕たちも祈っています」
そう言い交わして、シドさんはカーテンを閉めた。
_ ◇◇◇
_ そして、そのシドさんの言った通り、何も起きなかった。
早朝出発して、エノシアスタに到着した頃にはその日の夕方になっていた。ちなみに到着したときには、
「おおい! もうすぐ、エノシアスタに到着するぞ!」
そんな掛け声だけだったが、僕たち以外の人たちはみんな続々と準備をしだした。どうやらそれがここにとってはアタリマエのことらしい。
窓から外を眺める。エノシアスタの町はどういう状態になっているのか、気になったからだ。
鉄で出来た城壁、そこから生え出てきているように見える石造りのビル群。それだけ見れば、僕がもともといた世界にもあったような町に見える。
「すごいなあ……こんな町があるんだ……」
僕は思わずそんなことを呟いた。
どうやらそれはルーシーにも聞こえていたようで、
「この町はスノーフォグだけじゃなくて、世界随一の技術を備えた場所……だったかな。だからこのようになっているらしいけれどね。おかげでこの町ですべてを賄えるようになってしまったらしい。あの町での技術は全世界の技術より二世代近く進んでいるとか……。まあ、噂に過ぎないけれど。あくまでも、それは一般的に科学技術が流通していないせいかもしれないけれどね。現にあの町は、ほかの町に科学技術を流出しないからって文句も飛んでいるし」
「ふうん……。そうなのか」
まあ、魔法や錬金術が主流になっている世界で、科学技術なんて流行らないのかもしれない。ただ、便利なものが便利であると証明されれば、それは確実に流行するだろうし、おそらくそれをする準備がとても面倒だったのだろうか。あるいは、この世界の人間性――ううん、そこまで考えるとなんだか面倒なことになってきそうだ。
そんな難しいことを考えていたら、ゲートに到着していた。
ゲートは誰か人がいるわけではなく、自動ドアのようになっていた。おそらく上部にセンサーがついているのだろう。それで判別しているのかもしれない。いったい何を判別しているのか、という話だけれど。
「すごいな、このゲート。自動で判別しているのかな? 人も居ないようだし」
「ほかのところとは違う感じだよね。もしかして通行証とか持っているのかな。それで判別しているのかも」
ルーシーの問いに僕の推測を伝える。
ルーシーはそれを聞いて頷きながらも、完全に納得しているようには見えなかった。まあ、仕方ないことだと思う。実際伝えたことも僕の推測に過ぎないので、それの裏付けもしていない。だから、それが本当だろうか? もっと別の考えがあるのではないか? という考えに至るのも自明かもしれない。
暫くしてゲートが開く。ゲートが完全に開ききったタイミングを見計らって、僕たちを乗せたトラックはエノシアスタの中へと入っていった。
_ ◇◇◇
_ エノシアスタの中心地にあるホテルにて、僕たちは一旦の契約解除に至った。一週間後に再びラルースの町に戻るときに改めて契約して、また戻るスタイルになるそうだ。ちなみに契約解除した時点で一回分の契約になったということでその分のお金は支払われた。
そういうこともあり、僕たちは現在小金持ちになっているのだった。
「それにしても……機械ばかりだよなあ……」
お店で販売しているものも機械。町を動いているのも機械。町に生きている人々もどこか機械を装着しているためか機械っぽさがある。
僕の住んでいた世界でもこんな機械を使っていただろうか、と言われると微妙なところかもしれない。
「うわあ、すごいよ、フル! 見てみて!」
そう言ってルーシーはウインドーを眺めていた。
「……子供ね」
「そう言ってやるなよ、レイナ」
レイナと僕はそう言葉を交わしながら、ルーシーのもとへ向かった。
ルーシーが見ていたのは一台のコンピュータだった。デスクトップ本体とキーボード、それにモニタが配線で接続されている。電源は入れられていないので画面が表示されることは無いのだが、それでもルーシーは興味津々だった。
「何だい、フル。あれはいったい? もともと来た世界にはあのようなものはあるのか?」
ルーシーの問いに僕は小さく溜息を吐いてから答えた。
「……ああ、あったよ。あれはコンピュータと言って、いろんなことを機械の演算で実行してくれるものだったはず。人間の脳で出来ることが実行できるのだけれど、それを並行で実施するから、人間が手で計算するよりも若干早く出来たはず。まあ、それもメモリチップという人間でいうところの脳みその大きさに依存する、はずだったけれど」
「……はあ、よく解らないけれど、すごいというのは伝わったよ……。すごいなあ、エノシアスタ。魔法とも錬金術とも、別の学問とも違う何かがここにはあるよ……!」
ルーシーの目はどこか輝いているように見えた。
別に彼は科学信仰というわけではないだろう。ただ珍しいものに興味を示しているだけ、だと思う。なぜそうはっきりと言えるかというと、もともといた世界でもそういう反応を示していた人が良く居たからである。
「確かにそう思うのも仕方ないかもしれないけれど……、私は少し苦手かな。ちょっと無機質過ぎるよ、この場所は」
苦言を呈したのはレイナだった。彼女みたく、このような無機質なものばかりが並べられた場所を嫌うこともあるのかもしれない。まあ、仕方ないことといえば仕方ないと思うのだけれど。
さて、そんなことよりも。
この場所で調査する時間は一週間しかない。はっきり言ってその時間のうちにやるべきことをやる必要がある。メアリーはどこへ消えてしまったのか、そしてシュラス錬金術研究所はどこにあるのか――その場所を調べなくてはならない。
そう考えて、僕たちは情報の収集を開始した。
メアリーに関する情報を少しでも集めることが出来ればいいのだけれど。
_ とまあ、そう勢いをつけた割には何も情報が得られなかった。強いて言えばやはりあのメタモルフォーズの巣に関する情報くらいだっただろうか。興味はあるけれど、今の僕たちで向かうのは少々危険過ぎる。
というわけで結局その日はエノシアスタの観光をすることにした。もちろん、情報収集も進めているけれど、想像以上に何も出てこない。話を聞くと、殆どここに住んでいる人はこの町から外に出ないのだという。だから、あまり他人に干渉しない。それどころか一人で動くのが好きなのか、そもそも話を聞いてくれる人すら居なかった。
「なんというか、この町の人、冷たい人だらけよね。話くらい聞いてくれてもいいじゃない」
そうレイナは言ったけれど、見ず知らずの人の話を聞く余裕がある人が案外居ないのかもしれない。見たことのない人間が突然声をかけてきて、反応してくれる人はそう滅多にいないと思う。大抵は忙しいとか用事があるとか言って適当なことではぐらかす人が大半だと思うけれど、どちらにせよ情報が得られないのは確かだ。
レイナは溜息を吐いて、空を見る。
エノシアスタの中心に聳え立つグランドタワー。
高さは聞いた感じだとリーガル城の二倍以上の高さを誇り、展望台からはスノーフォグを一望出来るどころかハイダルクも見えるのだという。
「……タワーにも入ってみる?」
「タワー……か。タワーに入って観光もいいかもしれないな」
「フル、レイナ。一応言っておくけれど、目的は忘れていないよな? 今回、ここにやってきた目的、それは……」
「メアリーの情報を入手すること、だろ? それくらい知っているよ。だが、情報を入手する可能性を高めるためにはいろんな場所に入る必要がある。そのためにもこの町を観光していきながら様々な場所を巡ったほうがいい。そうは思わないか?」
ルーシーの言葉に僕は答える。はっきり言ってもっともらしい言葉を並べただけで、実際はルーシーの言った通り。ただの観光となってしまっていることは紛れもない事実だった。
しかしながら、情報が少しでも得られるならば――その可能性が秘められていることもまた事実だ。あれほどの高い建造物から外を眺めることが出来れば、何らかの情報が地形から掴むことが出来るかもしれない。
ルーシーはまだ納得しきっていないようだけれど、結局僕がもうひと押ししたことでそれが成立することになった。高い塔から少しでも情報を掴むことが出来ればいいのだけれど……。
_ ◇◇◇
_ 今日は朝から本を読んでいた。
なぜそんな自由なことができるかというと、あのフランツとやらが知識を得ることも大事だと言ってこの図書室に幽閉するよう部下に命じたかららしい。現にバルト・イルファが扉の前にある椅子に腰かけて何らかの本を読んでいるし。仕方がないので、私も何か情報を得るべく――本棚を見ていた。
けれど、本棚に入っていた本はどれも難しいばかりで、はっきり言って私が読めるようなものはこれといって無かった。
もうこのまま何も無いのかなあ、と思っていたけれど本棚の一番端にあるものを見つけた。やはりそれも表紙が掠れてしまって文字が読めなくなっているくらい古い本なのだと思うのだけれど、でもなぜかその本を開いてみたくなった。
今までのそれとは違って、表紙などから内容が掴めないからかもしれない。もしかしたらこの本にならば私が欲している情報が載っていると思ったのかもしれない。
「……これだ」
そう自分に言い聞かすように呟いて、それをもって椅子に腰かけた。
本を読み進めていく。その本は歴史書のように見えるが、メタモルフォーズの仕組みにも触れている。まさに今の私にとって一番重要な要素が詰め込まれているものだと思った。
一ページ捲る。そこには知恵の木の実のことについて、このように書かれていた。
『知恵の木の実』とは遠い昔、エデンにいたアダムとイブが蛇の誘惑に負け、食べてしまった果実のことを言う。それを食べてしまったことで、神は怒り、アダムとイブをエデンから追放してしまった。
なぜ神は怒り、アダムとイブを追放したのか?
神は『アダムとイブ』という人間が自分の地位に近づくのを恐れたのではないか?
そのように考えることもできる。
しかし、それは伝説上の産物である。
時は流れてガラムドが生まれ、そして空へ還った。
ガラムドの墓を守っていた男――ニーチェ・アドバリー、はガラムドの墓に樹が生えていることを見つけた。
その木の実は黄金に輝き、形は林檎のようだった。
その男は敬意を込めて、『知恵の木の実』と呼ぶのだった――。
私はそんなことを呟きながら読み進めていった。知恵の木の実は神ガラムドが生み出したものということで有名らしいけれど、こういう神話から裏付けされたということなのね。意外と原典を読んでみるのもなかなか面白いかも。というか、なぜこのタイミングでこれを面白いと思えたのかが面白いところではあるけれど。
まあ、それは戯言だけれど。
そんなことを言いたいがために私はこれを見ていたわけではない。さらに本を読み進めていけば、きっと私の知りたい情報が出てくることだろう。
そう思って、私はさらにその本を読み進めていった。
さらに読み進めていくとこのような記述を見つけた。偉大なる戦いのとき、ガラムドはある錬金術師に知恵の木の実を授けているのだという。そこでははっきりと知恵の木の実とは書かれていないものの、その説明文からして、その言い回しからして、私はそれが知恵の木の実であることを理解した。
しかし、知恵の木の実はその説明がいずれも事実であるとするならば、偉大なる戦い以前にも存在していたことになる。
それって何だか矛盾していないだろうか?
だって知恵の木の実が存在したのは、神が生み出したからと言われている。それがその通りであるとするならば、今の話題は完全に矛盾することとなる。どちらが正しいのだろうか? そう思ったとしても、この歴史書めいた古書にはどちらの説も記載されている。
「……だめだ。もっと何かあるはず……」
こう読み解いていくうちに、私は何かあることが気になった。
_ ――この世界は、何か裏があるのではないだろうか?
_ もしかしたら、私たちこの世界に住む人間の殆どが知らないような、重大な事実が。
この世界にはあるのかもしれない。もし、そうであるとするならば、私はそれを突き止めたい。そしてそれを、その情報の断片を少しでも得るためにはこの蔵書は役立つ可能性がある――そう考えて私は古書の読み解きを再開した。
_ ◇◇◇
_ グランドタワーの展望台に向かうにはエレベーターに乗る必要がある。正確に言えばエレベーターではなく昇降機と呼んでいたのだけれど、エレベーターの日本語訳が確かそれだったと記憶しているので、全然不思議な話ではない。
昇降機にはたくさんの人が載っていた。別に僕たちだけの話ではない。ここは連日多くの人が訪れる観光地のような場所なのだろう。そうかもしれないけれど、ここに住んでいる人もやってくるのだろうか? だって毎日のようにその姿を外から眺めているはずだから、そう何度も訪れることはないとは思うのだけれど。
それはどうでもいい。それについては僕が簡単に語るべきことではない。
飄々と。
淡々と。
黙々と。
それを僕が語る権利はないのかも知れないけれど。
昇降機を降りて、空間が広がる。目の前に広がるのは、広大な景色。ガラス張りになっているため、外の景色が一望できる。当然といえば当然かもしれないけれど、床は普通だ。壁がガラス張りとなっているだけ。僕の世界にあった、普通のタワーと同じような仕組み。
まあ、それについては予想通りだったと思う。
あと、これも予想通り。やっぱり外の景色を眺める人は居なかった。居なかった、とは言い過ぎかもしれないかな。実際には少しは見ている人も居る。けれど、実際に昇降機に乗ってきた人は展望台にあるレストランやちょっとした観光をしているだけに過ぎない。或いは楽しんでいるのは子供だけで大人は退屈そうに話をしているか本を読んでいるか……といった感じ。
正直、それだけ見ていると僕のいた世界と何ら変わりない。
「……わあ、いい景色だねえ」
レイナはそう言って、手すりに手をかけた。
確かに景色は良い。だが、広がっている景色は僕の想像通りの景色が広がっていたので、少し肩透かしを感じる。
そして、人もいない。
話を聞くこともできない。
はっきり言って、ここに来たことは失敗だったか?
「……あれ、フル、ルーシー。あれは何だ?」
レイナの言葉を聞いて、僕は踵を返した。僕だけじゃない。ルーシーもそうだ。ルーシーもその声を聴いてレイナに近づく。
レイナは僕たちが隣に立ったことを見計らって、それを指さす。
「ほら、あれ」
そこにあったのは岩山だった。ただの岩山という感じではない。粘土細工のような、ところどころ穴が開いている。
「……何だ、あれは?」
レイナが言った言葉をそのまま反芻する形で僕は言った。
「あれはメタモルフォーズの巣だよ」
声を聴いて、そちらを向く。
そこに立っていたのは眼鏡をかけたいかにもな一般市民だった。
一般市民の話は続く。
「……あれはかつてどこかの研究施設をメタモルフォーズが乗っ取った、と言われているよ。実際にどこまでほんとうなのかは解らないけれど。……この町の人間ならば常識だったと思うけれど、それを知らないところを見ると君たちは旅人かな?」
ニヒルな笑みを浮かべて、一般市民は眼鏡をくいと上げた。
僕は頷くと、一歩前に立った。
「はい。実は今日この町に来たばかりで……。機械がたくさんありますね。ほかの町とは違う。それにしても……あの巣は誰も対策しようとはしないのですか?」
「そんなことを僕に言われてもね」
肩を竦めて、話を続ける。
「ああ、でも、噂だけれど、あの巣をさっさと破壊しないのは裏の研究施設が未だ生きているからかもしれない……というのはあるよ。実際問題、あそこはメタモルフォーズの巣になっている。時たま、メタモルフォーズがここに攻めてくることもある。だが、根本的な対策には至っていない。それくらい科学技術が発展していてもおかしくないのに。だから、そういわれている。まあ、あくまでも噂の一つだから、本気で信じている人なんてそう居ないけれど」
噂。
噂、か。
人の噂も七十五日とは良く聞いたことのある話ではあるけれど、しかし存外噂というのはその日付以上に流通してしまうものだと思う。実際問題、それはよくある話だと思うし、間違っていないことだと思う。怖がることも面白がることも、興味が失せるタイミングまでずっとそのままでいると思うし、もしかしたらうまくずっと長く続けていられるかもしれない。広告的手法でも使えることだ。なぜ僕がそのようなことを知っているのかといえば、興味があることというよりも目についたものを片っ端から調べていたことがあったので、それで調べたからである。そのことの殆どは実際に役立つことは無かったけれど、まさかこのようなタイミングで、そこで調べた知識を思い出すことになるとは思いもしなかった。
知識を得ることに間違いなんて存在しない。だって、普通に考えてみて、知識を得ることで失敗した経験なんて無いからだ。それは僕が経験した、ただそれだけのことかもしれないけれど、それについては僕が保証する――なんて言ったとしてもそれはたったのこれっぽっちも認めてくれることはない。結局、ただの個人の自信なんてそのようなものだ。ただのハリボテと変わりない。
ハリボテと変わりないなら、結局そのハリボテをハリボテと思われないようにする。そういう風に思う人間だっているし、それを地で行く人間もいることもまた事実だと思う。現にこの世界に来ただけでもどれくらいの人間がそういう精神でやってきた人間が居るだろうか。数えたことも考えたこともないけれど、おそらくそれが世界の一般的な常識なのだと思う。
それが世界の普通で。
それが一般的な常識で。
僕にとってそれは普通じゃない、また何か違うことのように思えたけれど。
「でもそう思うことって間違いなんだろうな……」
「うん? 何かあった?」
「あ、いや。何でもないです。ありがとうございます」
貴重な情報を手に入れて、僕は頭を下げる。そうしてルーシーに声をかける。
「どうやら、行先はきまったようだぞ、ルーシー」
「……裏の研究施設がある、という噂のことか? まさかそれを全体的に信用するつもりなんじゃないだろうな?」
「それしか手段はないと思うよ。だって、現状の情報はそれしかない。だったら、そこに向かうしかないでしょう? 問題は、そこにどうやって向かうか、だけど……。やっぱり歩くしかないのかな」
「まあ、そうなるよな……。しかし、徒歩か。何かいい手段無いかなあ……」
僕とルーシーが頭を抱えていた、ちょうどその時だった。
「そういえば、さっき見たんだけど。この町、行商が多いよね。もしかしたら、それって使えない?」
そう言ったのはレイナだった。
行商? そんな情報、どこで入手したんだ。それにしても、その情報はほんとうに有り難い。
「行商……か。もし徒歩で行くならば、そちらのほうが問題ないといえば問題ない気はする。……なら、一度探してみる? それで良い条件の行商が見つかればいいけれど」
生憎今はそれなりの路銀を確保している。契約の時の値が若干張るものだったとしても、多少は何とかなると思う。
そう思って僕たちはタワーを降りて、行商のもとへと向かった。
_ 行商通り。
実際には何か花の名前がついた名前らしいけれど、行商の家が多いためこのような名前がニックネームのような感じでつけられて、それが正式名称のようになっているらしい。
そして通りにはその名前を裏付けるように、馬車の車庫が多く面していた。
「しかし科学技術がここまで発展しているのに、まだ馬車が混在しているんだな……。もっと、何か無かったのかな。トラックとか」
確かに。
ラルースの人間でもトラックを使用しているのに、この行商通りの人間は殆ど馬車を使用している。まあ、全員が全員使用しているわけではないけれど、それでも馬車は未だ根強い。
「多分それって、この世界が未だ馬車のほうが主流だからじゃないか? だって、主流じゃないものを使い続けるわけにもいかないだろ。実際、同じスノーフォグですらこの町しか科学技術は発展していなくて、あとは横並びってくらいだし。だから、その横並びから突出していることを見られないためにも馬車を使っているとか。あとはメインテナンスの問題じゃないかな。何かあったとき別の町でも何とかなるじゃないか。ただトラックとか、この町特有の何かだったら別の町で故障した時も何か大変なことになるんだろうし」
「そうか……。まあ、確かに間違いではないだろうなあ。ま、別に馬車になろうが馬車以外になろうが問題ないよ。問題はメタモルフォーズの巣に進んで行ってくれる行商が居るかどうか、というだけ」
僕はシニカルに微笑むと、ルーシーもその通りだと頷いた。
実際問題、トラックだろうが何だろうがそこについてはどうだっていい。問題はメタモルフォーズの巣に僕たちがこれから向かう、ということだ。
メタモルフォーズの巣はこの世界の人間が考える危険地帯の一つだ。その場所だけじゃない、そこへ向かうまでの道のりも酷いものだと思う。果たしてそこに進んで向かってくれる人がいるだろうか? そう考えたときに、大分幅が狭くなってくると思う。
まあ、それよりも――実際にやってみないと解らない。
だから僕たちは行商を確保するために、行商通りにある店に向かうのだった。
_ まあ、そう簡単にうまくいくわけもなく。
そもそも僕たちの向かう場所がメタモルフォーズの巣。そうとも知ればそこまで生きたがる稀有な存在など当然いる筈もなく、結局のところ、交渉は難航していた。
そこまでははっきり言って予想の範疇。
問題はそれよりもスピードを優先すべきことだった。メアリーがどうなっているか解らない現状、大急ぎでバルト・イルファが向かったとされるシュラス錬金術研究所へと向かわねばならない。しかしながら、僕たちにはその場所を知る術は無かった。そうとなると、別のアプローチでシュラス錬金術研究所へと向かう必要がある。
現在において、唯一の情報はメタモルフォーズの巣があるという情報のみ。そしてそこへ向かうには徒歩では少し遠すぎる(必ずしも徒歩では行けない距離ではないけれど)。そうなると、やっぱり足は必要になってくる。そういうものだと思う。そうとなれば話は早い、ということで僕が主体となって契約をする必要が出てくるわけだ。
果たして、なんの契約か――なんてことは言わなくたっていいと思う。
馬車、或いはトラック。
正確に言えば足になるものがあればいいのだけれど、この世界において足と呼べるものはそれしか無い。実際、こういうものを使うとなると契約してお金を支払えばいい。別にお金さえ支払えば子供であろうが遠い場所であろうが対応してくれる――はずだった。それが上手くいかないのは僕たちが向かいたいその目的地が原因だろう。目的地はメタモルフォーズの巣、そんなところに行きたい子供を、果たして契約するといえ連れて行ってくれるだろうか? 良心の呵責があって連れて行こうとは思わないかもしれない。そもそも、実際そのように言われて断れたのが殆どなわけだけれど。
「……しかし、フル。これからどうする? このままだと何も解決することが無いまま時間だけ過ぎてしまうことになるが」
「それくらい解っているよ。……しかし、どうすればいいか」
ルーシーに指摘されなくてもそんなことは知っていた。
問題はそれをどう解決するか。その方法が思いついていなかった。それが一番の問題だったかもしれないけれど、とにかく見える範疇の問題を一つずつ解決していかないと、何も前には進まない。
「解っている……。だから、僕たちは作戦会議をするためにここにきているんだ。何か、考え付かないか、ルーシー。まあ、最悪歩いてもいいのだけれど、そうなると数日間の食料プラス眠るところを確保する必要がある。道中に何もないのが欠点だよな……。街道って、もっと普通ユースホステルみたいなものがあるんじゃないのか?」
「え、えーと、ユースホステル?」
「あ、ごめん。こっちの話。ルーシーには関係ないよ」
今、僕たちは作戦会議と昼食を同時に済ませるため、近所のレストランに居た。しかしながら、まったく意見が出ることなく、不毛な作戦会議となってしまっているのだけれど。
僕が食べているハンバーグも残り三分の一程度。さて、どうすればいいのやら……。
「ちょっとごめんよ。さっきから聞いていたのだけれど、行商を募集しているようだね?」
それを聞いて、僕はそちらを向いた。
隣のテーブルからの声だった。隣のテーブルでは、一人の商人が同じように食事をしているようだった。
「……そうですけれど、どうかしましたか?」
「いや、盗み聞きをしてしまったようですまなかったな。ちょっとその話を聞いていたら、適役かもしれない相手を見つけたんだよ。よかったら、ちょっと話だけでもそいつに話してはくれないか?」
「……別にいいですけれど」
クールを装っているけれど、これはチャンス。
ここで契約を上手く取ることができれば、メタモルフォーズの巣まで簡単に移動することが出来る。そう考えて僕は二つ返事でその商人と思われる男性の言葉に頷いた。
「いいのか? フル。そう簡単に了承しちゃってよ」
「別に問題ないと思うけれど。だって、僕たちも必要としていたのは事実。そしてこの人が適役を見つけてきている。それなら一度会ってみないと話は解らないだろう? そこで契約可能ならばしちゃえばいい。ダメならダメでまた別の可能性を探ればいい。そうだろう? そんなことよりも今は可能性の一つを潰してしまうことが問題だと思うよ」
「それはそうかもしれないが……」
ルーシーの言葉を聞いて、商人は向かいの席に腰かけていた――正確に言えば机に突っ伏して眠っている状態ではあるのだけれど――人の身体を揺さぶる。
「おい、起きろよ。眠っている場合じゃないぞ!」
そうしているうちに、漸くその人は起きだす。それでもゆっくりとした感じでとても眠そうだったが。
「……あれ? どうかしましたか。今日は僕が仕事の無さすぎを励ましてくれる会だったでしょう。もう終わりですか、お開きですか。それともアルダさんはお仕事があると、いやあ、いいご身分ですねえ。僕はずっとお仕事がありませんから借金も返せないのに」
「そういうことじゃねえ。自分を卑屈に思うのは辞めろ、仕事にも影響するぞ。……そんなことより、ビッグニュースだ。お前に仕事が生まれるかもしれないぞ」
それを聞いてビールと思われる黄色い液体を飲み干す男の人。顔はほんのり赤く染まっているのだけれど……大丈夫だろうか。ちょっと不安になってきた。
ビール? を飲み干したところで、男の人はそれでも向かいに座っているアルダさんが何を言っているのか理解できない様子だった。
そして少しの時間を要して、目を丸くして、身を乗り上げる。
「それは……本当ですか? アルダさん。僕のテンションを上げるための、面白がるための嘘なのではありませんよね?」
「お前のその状況を見て嘘を吐くような輩が居たら、そいつは相当捻くれ者だろうよ。それとも何だ? お前は俺のことを捻くれ者だと扱っているということか?」
「いやいや! そんなことは思っていませんよ。それにしても……え? ほんとうに、この僕に依頼が?」
「だから言っているだろう。ビッグニュースだと」
先ほどの酩酊ぶりはどこに行ったのか、あっという間によれよれになっていた服の襟を正して、僕たちのテーブルへと向かった。
そうして完璧にお辞儀をしたところで、
「はじめまして。僕の名前はシュルツ。シュルツ・マークラケンといいます。しがない行商ではありますが、腕に自信はあります。まず、きちんとお時間は守ります。たとえ無茶な時間を言われようとも、問題ありません。さすがにスノーフォグからハイダルクまでを一時間、というのは無理な話ですのでお断りする可能性もあるといえばありますが」
仕事の交渉一発目でそんな話をしていいのだろうか……?
そんなことを思ったけれど、それについては今語るべき話題でもないのかも知れない。
そう思って僕は話を始める。
これからは僕のターンだ。
「はじめまして、シュルツさん。早速ですが、僕たちが行きたい場所は既に決まっています。……まあ、先ずは座っていただいて」
流石に立たせたままで話をするのはちょっと周りからの目線が痛い。
そうともなれば、さっさと先ずは座っていただいてからきちんと話をしたほうがいい。
「ありがとうございます。……それで、ほんとうに僕でいいんですか?」
「かまいませんよ。僕たちも行商を探していたので。誰も見つからなかったのですよ」
「見つからなかった……? いったいどこへ向かうつもりだったのですか?」
そこで僕は、目的地をはっきりと告げた。
「メタモルフォーズの巣へ向かおうかと」
「すいません、お断りさせていただきます」
立ち上がろうとしたシュルツさんの腕を即座につかむレイナ。
僕の背後からアルダさんが茶々を入れる。
「おいおい、どうしたんだよ、シュルツ。別に問題ないだろう、お前、仕事が欲しいって言っていたじゃないか」
「言っていましたけど、言いましたけれど! けれど、こんな大変な仕事じゃ断りたくなるのも当然じゃないですか! わざわざ死地に赴く人が居るとでも!?」
「……やっぱりだめですよね。仕方ないといえば仕方ないかもしれないですけれど……。やっぱり、私たちだけで歩いて彼女を助けないと」
「彼女を? ……ええと、君たちはわざわざメタモルフォーズの巣へ向かって死にに行くということではなくて?」
「そんな馬鹿なことを自ら進んでするはずがないでしょう」
そう冷静に発言したのはレイナだった。
まあ、当然といえば当然なのだけれど。
「……メタモルフォーズの巣に、僕たちの大切な友達が居るかもしれないんです。もしかしたら居ないかもしれないけれど、居てほしくないけれど、でも手がかりは一つしか無い。だから、僕たちはそこへ向かわないといけない。……これは、きっと、誰も行こうとは思わないことかもしれないのだけれど」
言葉が、溢れていく。
メアリーは大切な友達だ。
この世界にやってきて、初めて知り合った友達。
そんな彼女を、このような場所で見捨てては――ならない。
「……解りました」
溜息を吐いて、シュルツさんはそう言った。
「それじゃ……」
「本当は嫌なんですけれどね。あなたたちの言葉に感銘を受けましたよ。まさかそのようなことを考えている人がいるなんて。正直、この世界はメタモルフォーズに心まで蹂躙されてしまった人間ばかりかと思っていました。けれど、違うのですね。解りました、向かいましょう。そうと決まれば、時間は急いだほうがいいでしょう?」
その言葉を聞いて、僕たちは大きく頷いた。
_ ◇◇◇
_ シュルツさんとの待ち合わせ場所は南門と呼ばれる場所だった。
そこから向かうことで、メタモルフォーズの巣へと一番近付くことが出来るのだという。実際には、それにプラスして馬車やトラックが出しやすい状況にあるらしいのだけれど。
「お待たせしました」
声が聞こえて、僕たちはそちらを向いた。
そこに居たのはシュルツさんと……小さい竜だった。いや、ただの竜じゃない。その竜が馬車を引いている。
驚いている様子の僕たちを見たシュルツさんは首を傾げていたが、少ししてその正体を理解する。
「ああ、もしかして、あれですか? 竜馬車を見たことがない?」
「竜馬車……。そういう名前なのですか、これは」
「ええ。正確にはミニマムドラゴンを使うことで馬車とは違うこととしていますけれど。スピードは馬車の数倍も出ます。ですが、うまく扱わないと馬車の中がごちゃ混ぜになってしまうことから操縦が難しいといわれていますけれどね」
そう言ってシュルツさんは竜の身体をぽんぽんと叩いた。けれど、竜はすっかりシュルツさんに懐いているようで、何もすることなくただシュルツさんのほうを見つめていた。
そしてシュルツさんは後ろにある馬車を指さした。
「準備ができているようならば、後ろの馬車に乗り込んで。僕はもう出発の準備はできているから、君たちに合わせるよ」
その言葉を聞いて僕たちも大きく頷くと、そのまま後ろの馬車へと乗り込んだ。
「それじゃ、出発するよ!」
竜に乗ったシュルツさんは、優しく竜に語り掛ける。
「さあ、出発だ」
それを合図として、竜は起き上がる。竜の大きさはなかなかある。跪いていたから正確なサイズが解らなかった、ということもあるけれどこう見ると圧巻だ。
そうして竜と、連結している僕たちを乗せた馬車はゆっくりとエノシアスタの町を後にするのだった。
_ ◇◇◇
_ 竜馬車の乗り心地は事前に言われていた状態と比べると、とても心地よいものだった。もっとガタガタ揺れるものかと思っていたけれど、これなら普通の馬車と変わりないような気がする。
内装はかなり豪華な様子になっていて、椅子もふかふかになっている。このまま眠ってしまいそうだったが、それが『しまいそう』で済んでしまうのには理由があった。
理由は単純明快。どうやらあまりにも仕事が無かったためか、竜馬車の中身がシュルツさんの私物がたくさん詰められている状況だった。まあ、それでも十分広さは確保されているので別に問題が無いといえば無いのだけれど。
「……しかしまあ、やっぱり馬車を契約して正解だったね。徒歩よりかは早いスピードであることは間違いないし」
ルーシーの言葉に頷く僕。
確かにそれはその通りだった。車窓から見える景色はかなりスピードが速く流れている。確かにトラックと比べればそのスピードも大したものではないのかもしれないけれど、それでも徒歩で向かうよりかはマシだ。
「それにしても、このペースなら日が暮れないうちに到着しそうだな」
「そうだったらいいんだけどね。夜ならちょうど侵入も出来そうだし」
こくり、と僕は頷いた。
実際、もし研究施設が存在するならばその監視体制も厳重になっていることだと思う。何せ、メタモルフォーズの巣によってカモフラージュしているのだから。もしそうじゃなかったとしても太陽が出ているうちよりかは沈んでいたほうがメタモルフォーズに見つかりにくい。ならば沈んだ後の時間がどちらにせよ都合がいいということだ。
「それにしても……」
レイナは僕たちの会話の後に続いた。
うん? 何か気になることでもあっただろうか。
「この大きな武器……何だと思う?」
それは僕たちの背凭れの後ろにあるスペースに入りきらないほど大きな銃だった。ガトリングみたいにも見えるけれど、しかしその大きさはとても一人では抱えることが出来ないように見える。
いったい誰の持っている武器だろうか、なんて考えるのは野暮なことだろう。どう考えても九割九分はシュルツさんの武器だ。しかし、シュルツさんがそれくらい大きな武器を活用する時期があったのだろうか?
まあ、でも、行商はいろいろな危険を躱しながら目的地へと無事に到着することを目的としている。何も無ければいいのだけれど、何かあったときに武器が無ければ対抗出来ない。だからそのようなものがあるのだろう。多分。
「だからといって質問するわけにもいかないしなあ……」
そんな質問をしたところで護身用と答えられるのがオチだと思う。
だから僕は質問することもなく、そのままにしておいた。きっと、それを思っているのは僕だけではないと思う。三人ともそう思っているだけで、ただそれ以上議論を発展させないだけ。
そう考えるのが当然。
そう考えておくのが必然。
きっとそれ以上考えたところで袋小路に迷い込んでしまう話になってしまうことだと思うから、誰もそう言い出さないだけだと思うけれど。
斯くして。
僕たちは一つの秘密を共有したまま向かうことになる。
メタモルフォーズの巣にはいったい何が隠されているのか。
そしてメアリーは、僕たちの予想通りメタモルフォーズの巣に隠された研究施設に居るのだろうか。
そんな思いを乗せたまま、竜馬車は進んでいく。
_ ◇◇◇
朝、単刀直入にバルト・イルファが私にそう言った。
一体全体何があったのか私には解らなかったけれど、きっとそれを質問したところで答えてはくれないのだろうな。
「……怖いから睨み付けないでおくれよ。いいかい? 僕たちだってやることがある。そしてそのためにも別の拠点へと向かう必要がある、ということだ。君には場所を教えておこうか」
一歩私に近付いて、さらにバルト・イルファの話は続く。
「スノーフォグの北にあるチャール島、そこには『邪教』としてオリジナルフォーズを祀る神殿がある。そこへ向かうことになるだろう。なに、そう難しい話じゃない。そして、ここを捨てるつもりはない。ここは研究施設だからね。君をこのままこの場所に放っておくわけにもいかないということだ」
「……別にこのままでいいじゃない。どうして場所を変える必要があるのかしら?」
漸く。
漸く私はその言葉を口にすることができた。
しかし、バルト・イルファはそれにこたえることはなかった。
そしてバルト・イルファは――そのまま姿を消した。
_ それからバルト・イルファがやってきたのは、少ししてからのことだった。私が持っていた荷物をそのままバルト・イルファは持っていたので、てっきり返してくれるものかとおもったがそんなことは無く、私にここから出ろと言ってきた。
従わなければ何が起きるか解ったものではない――そう思った私は、それに従うこととした。
「少々急になってしまい申し訳ないが、今から出発する。なに、簡単だ。魔術を行使していけば一瞬で行くことができる」
「だったら急ぐ必要は無いんじゃない?」
廊下を歩きながら、私はバルト・イルファに問いかけた。
「……だから言っただろう。急になってしまったが、と。急にならざるを得ないことが起きてしまった、ということだ。それくらい少しは理解したらどうだ?」
その言葉を聞いて少々苛ついたことは確かだけれど、それを口にするほどでも無い。そう思った私はそのままバルト・イルファに従うこととした。場所が解らない以上、ここでバルト・イルファに抗ったとしても簡単に逃げることは出来ないだろう。陸続きならまだしも、ここが絶海の孤島という可能性だって十分に有り得るわけなのだから。
それに、魔術を行使して移動することもそれを考慮してのことだろう。陸路ないし海路で移動するとなると仮に目や耳を塞いだとしてもそれ以外の方法で察しがつく可能性がある。そう判断して魔術で瞬間的に移動させ、究極的に外へ出させないという結論に至ったに違いない。
結局、色々な案を脳内でぐるぐるシミュレートしてみたけれど、そのどれもが実行不可能であることを理解して、今はバルト・イルファに従うしか無い。そう考えるしか無かった。もしフルたちが今ここに向かっているとするならば、完全に行き違いになってしまうのだけれど。
「……どうかしたかな?」
ふと前を向くとバルト・イルファが踵を返して立ち止まっていた。どうやら私の様子を気にしていたらしい。バルト・イルファが私のことを? そう考えると、一笑に付してしまうこともあるけれど(そもそもバルト・イルファがそんなことをするとは考えられなかった)、しかしそれ以上のことを私は言うことはなかった。
そして、バルト・イルファもそれ以上のことを語ることなく、そのまま踵を返すと歩き始めた。
_ ◇◇◇
_ 竜馬車がメタモルフォーズの巣に到着するまで、それから半日ほど経過していた。
あまりにも乗り心地がよかったので眠りについていたけれど、
「おい、到着したぞ。……ってか、どこがゴールになるのか明確に教えてもらっていないわけだけれど」
シュルツさんの言葉を聞いて、僕たちは目を覚ました。僕たち、と説明したのは単純明快。簡単に言えばルーシーもレイナも眠っていたということだ。彼らも乗り心地が良かったから眠りについたのだろう――そうに違いない。
そんな根拠もない机上の空論を考えながら、僕は窓から外を眺めた。
見ると景色は想像通りの岩山が広がっており、見るからに何か出てきてもおかしくなかった。
「……なあ、どうしたんだ? 今からどこへ向かうのか教えてくれてもいいと思うのだけれど。メタモルフォーズの巣といってもきちんとした場所は判明していないわけであるし」
「あ、ああ。そうだったっけ。まあ、そんなに遠くない場所だったはず。……確か粘土細工のような無機質な塔があったはずだけれど」
「その塔だったら、そこにあるよ?」
シュルツさんが後ろを指さす。
すると確かに、その通りだった。目と鼻の先の距離に粘土細工のような塔があった。
塔の根元は岩山になっており、洞窟が広がっているように見える。そしてその洞窟は――。
「メタモルフォーズが見張っている、と……」
「まあ、明らかに怪しいわな。けれど、あれを掻い潜っていけるほど戦力はこちらにないぞ」
言ったのはルーシーだった。
それについても首肯。
「……首肯するのはかまわないけれど、フル、何かアイデアでもあるのかい? 無いのならば、あまり無策で飛び込むわけにもいかないと思うけれど」
「それくらい解っているさ」
状況は把握している。
そして、どうすべきかも理解している。
けれど、それをどう対処すべきか――一番具体的で、一番重要なポイントが浮かんでこない。由々しき事態ではあるけれど、事態の緊急性を知っているけれど、けれどそれが浮かび上がってこない。
「……聞かせてもらったけれど、君たちは友達を探しているのだろう?」
シュルツさんの声を聴いたのは、ちょうどその時だった。
顔を上げると、シュルツさんは笑みを浮かべていた。
「はっきり言って、君たちは昔の僕と同じだ。未来に希望を見ていたころの僕と同じだ。そして、彼女を失う前の僕と――」
そうして。
シュルツさんは竜馬車に入っていたモノを手に取った。
それはガトリングだった。――けれど、正確に言えば銃の要素もあり、槍の要素も見えた。遠距離型武器と近距離型武器のいいとこ取り、とでもいえばいいだろうか。いずれにせよ、その武器が今まで見たことのないタイプであることは容易に理解できたことなのだけれど。
「今ここで諦めたら何もかも終わってしまうぞ、少年」
ガトリングから延びるネックストラップを首にかけて、頷く。
そうして、シュルツさんはスイッチを入れた。
――そんなかっこいいことを言ってみたけれど、結局僕にはこれしか選択肢が無かった。
結局、僕にはこれしか無いんだ。
自分に言い聞かせて、気持ちを落ち着かせる。
僕もかつては彼らみたいに旅をしていた――けれど、それは失敗してしまった。彼女を失ってしまってから、僕はずっと悲観に暮れていた。彼女のために、将来を考えようと思っていた。その矢先だったのに。
それを変えてしまったのは、メタモルフォーズだった。
「……結局、お前たちが何もかも変えてしまった」
ぽつり。
ほんとうに誰にも聞こえないくらいの小さな声で、僕は呟いた。
メタモルフォーズ。
どこからか、いつからか、何度人間が駆除しても姿を見せるその存在は、この世界が人間に与えた試練と言っていた人もいた。
でも僕はそんなものくだらないと思っていた。
試練だというのならば、こんな辛い試練僕は受けるなど一言も言っちゃいない。
神様は非常に残酷だ。
残酷で、非情で、絶望しか与えない。
そんな神様は、信じる価値など無い。
僕はずっと、そう思っていた。
逃げ続けていたばかりの僕に、もう一度メタモルフォーズを倒すチャンスを与えてくれた。
それはきっと神様と、あの少年たちに感謝しなければならないだろう。
僕はあのとき死んだ人間だ。いや、死ぬべき人間だった。
けれど生き残った。今もしぶとく生きていた。
そして、僕の目の前には昔の僕と同じように――今を生きている少年たちがいた。
ならばその少年たちのために、最後の命を使うのも悪くない。
そう思って、僕はその銃の引き金をゆっくりと引いた。
_ ◇◇◇
_ シュルツさんが撃った弾丸は、メタモルフォーズに命中した。
でも、それだけだった。
その弾丸一発だけでメタモルフォーズの勢いが止まるはずはなく、メタモルフォーズはなおも動きを止めない。
このままだとシュルツさんは――!
「シュルツさん――!」
「いいんだ、君たちは前に進め! まだ失いたくないものが、あるというのならば!」
そうして。
シュルツさんは――僕たちの目の前で、メタモルフォーズの足に踏みつぶされる。
呆気なかった。
一瞬だった。
それを冷静に見ることの出来た僕たちは――もしかしたら、異端だったのかもしれない。
僕たちは、前に歩み続けないといけない。
「……フル。行こう」
そして、最後のひと押しを、ルーシーが言ってくれた。
ほんとうに呆気なく、ほんとうに悲しい気持ちもあった。
けれど、僕たちは前に進むしかなかった。
メアリーを助けるために、前に進むしかなかった。
_ ◇◇◇
_ 私は魔方陣の中にいた。
魔方陣は私がラドーム学院から出発したときと同じもの。つまり転移魔方陣、ということ。転移するためにも魔法が必要というのは厄介な世の中ではある。もうちょっとうまくできる方法は無いものかな。ほら、例えば、スノーフォグには科学一辺倒の都市があるくらいだし、その都市が何か開発していることは無いのだろうか。……まあ、無いのだろうね。もしそれが開発されていたとしても、それはきっとスノーフォグにしか流通しないだろうし、秘密裡にリリースされているだろう。
「……準備もできたところだし、もういつでも君を別の場所に飛ばすことができる。ほんとうはあのお方に会わせてからのほうがいいと思うのだけれどね……。まあ、あのお方も暇じゃない。だからここでいったん、先に君には移動してもらうという話だ。まあ、いずれ会えることだろう。君とあのお方は、そういう運命にある」
長ったらしい言葉だったけれど、うまく実感が沸かないのは事実。だって『あのお方』というのが誰だか解らないし、そもそもの話をすれば、私はその人のことを知る必要もない。運命とか信じていない、というところもポイントだけれどね。
それはそれとして。
この魔方陣にされるがままになっているわけだけれど、私だって少しはどうやって脱出すべきかを考えている。けれど、はっきり言ってこのままではフルたちとの合流は愚か脱出するのも難しいと考えている。だって、ここがスノーフォグなのか、ハイダルクなのか、はたまたレガドールなのか解らない、まったく未知の場所に居るのだから。せめてそれだけでも解ればまだ対策も立てられそうなものだけれど、しかしそれはバルト・イルファが許してくれるとは思えない。窓も無ければ図書室にも場所を示す蔵書も無かった。そうとなれば、この場所を教えてくれる手がかりなんて一つも無いわけで。
「失礼します」
魔方陣の部屋に私とバルト・イルファ以外の人間が入ってきたのはその時だった。扉は閉まっていたはずだったけれど、ノックをすることなく入ってきた。
ふつうはノックくらいするんじゃないかな、とかそんなことを思っていたけれど、
「……ノックをするのが常識だと習わなかったかな?」
その気持ちはバルト・イルファも同様に抱いていたようで、入ってきた男にそう問いかけた。
しかし男は軽く頭を下げただけで、話を続けた。
「申し訳ありません。しかし、しかしながら……侵入者が入った模様でして」
「侵入者、だと? ふむ、しかし入口にはメタモルフォーズが居たはずでは?」
「メタモルフォーズは侵入者のうち一名を捕食しています。ですが、残りの二名が……」
「もしかして、フルとルーシーが!?」
私のその言葉を聞いてバルト・イルファは静かに舌打ちをする。まさか私もこんなに早くフルたちがやってくるとは思っていなかったけれど、それはバルト・イルファも同じだったようで、
「急いで転移をさせる。……今、ここで君を彼に引き渡すわけにはいかない。こうなったら意地でも君を大急ぎで転移させる」
そう言ってバルト・イルファは目を瞑った。
刹那、私の視界が徐々に緑色に染まっていく。
バルト・イルファはそこまでして私とフルを再会させたくないのだろうか。でも、どうして? なぜ? そんな疑問が頭を過るけれど、けっして今の状態がいいことではない。それは火を見るよりも明らかだ。
「そうして、世界は消えていく。粛清へと歩みを止めない。それが一番だ。ベストだといってもいい」
「あなたはいったい……何のためにこんなことをするつもり?」
私は、最後にバルト・イルファに問いかけた。
バルト・イルファは笑みを浮かべて――言った。
「僕をこんな運命に仕立て上げた、神様の作ったレールを破壊するため、かな」
その言葉を最後に――私の意識は途絶えた。
_ ◇◇◇
_ 僕たちは施設の中に入っていた。
施設、と言ったのは簡単なこと。洞窟の入り口かと思っていたのだけれど、いざ中に入ってみたら広がったのは鉄板で出来た壁だった。いくら何でも鉄板が自然で出来たとは考えられない。ということは、この壁は人工の壁だということに、容易に説明が出来る。
問題はこの場所の全容だ。扉が開いていたから何とか中に入ることが出来たものの、あの塔も含めて岩山全体がこの施設であるとするならば、攻略するのは難しいかもしれない。
しかし、メアリーを救うためだ。どうこう言っていられる場合ではない。
「……メアリーを助けるためには、もうなりふり構っていられないんだ……!」
目の前で、シュルツさんを失った。
彼のためにも僕たちはメアリーを助けなくてはならない。必ず。
「しかし、フル。こんな広い場所を簡単に探すことなんて出来ないと思うのだけれど?」
「それはそうだけれど……。でも地図とか無いしなあ」
これがロールプレイングゲームとかならば、きっとどこかに地図が落ちているか、セレクトボタンとビーボタンを同時押しすると地図が表示されるはず。けれどここは現実。異世界ではあるけれど、現実ということには変わりない。
そういうことだから、現物の地図を探す必要があるということだ。
しかし、はっきり言ってこのような場所に地図がご丁寧に置いてあるとは思えない。となるとやはり自分の方向感覚を頼りに闇雲に進むしかない――そういうことになる。
「……とにかく、ルーシー。このままいくべきだとは思わないか?」
だから僕は、ルーシーにそう言った。
別にルーシーだけに言ったわけじゃない。確かにルーシーの名前しか言っていないけれど、レイナもその発言を聞いて同じように頷いていた。
とはいえ、この状態が好転するものではなかった。
この場所の構造が判明しない以上、何かあったときに逃げることが出来ない。あるいは作戦を立てるときに厄介なことになる――それが面倒なことだった。
その時だった。
ドシン。
何かが響く音が聞こえた。
「……なあ、フル」
「ああ、ルーシー」
聞こえたのは僕だけじゃなかったらしい。ルーシーもそう言ったので、僕は頷く。
そしてそれはレイナも一緒だった。
いったい、何の足音だったのだろうか? ……ここでなぜ僕が足音と明言したかというと、すぐにその影が見えたからだ。
「……なあ、あれ」
あれはどう見ても人間の影ではない。
もっと違う、大きな、獣……?
ずしん。びちゃり。
先ほどの足音に追加して、何か濡れているような音も聞こえる。
獣は濡れている……?
「いや、違う。獣じゃない……! あれはまさか……!」
「いひひ。そうさ、その通りだよ。あれはメタモルフォーズさ」
そこに居たのは、白髪頭の眼鏡をかけた男だった。不敵な笑みを浮かべていた男は、どこか不気味に見える。
「お前は何者だ……?」
「僕かい。僕の名前は……そうだねえ、自分の名前をそう何度も言うことは無いから、覚えてもらう必要も無いよ。ドクターとでも言ってくれればいいんじゃないかな。いひひ、でも会う機会はもう無いと思うけれどね」
そう言ってドクターと言った男は眼鏡をくい、と上げて、
「なぜなら君たちは僕の開発したメタモルフォーズに蹂躙されるのだから!!」
刹那、ドクターの背後には巨大な獣が登場した。
その獣は今まで僕たちが見てきたメタモルフォーズ――厳密に言えば、エルフの隠れ里で出会ったそれと同じような感じだったけれど――とほぼ同じ容姿をしていたけれど、その身体自体はゼリー状になっていた。プルプル振動している、とでも言えばいいだろうか。
「……まさか、それもメタモルフォーズだというのか……?」
「どうやら、メタモルフォーズがどういうものであるのか、君たちはまだ理解していないようだけれど。メタモルフォーズはどのような容姿でも問題ないんだよ。もともとのメタモルフォーズ……オリジナルフォーズからの遺伝子を取り込んでいれば。そして、そこから改良されていれば」
「オリジナルフォーズ……」
ということは、彼ら研究者はオリジナルフォーズの遺伝子をどこかで所有していて、それを自由勝手に研究・開発をすることによってメタモルフォーズを生み出している――ということになる。
「研究のためだけに……人々を不安に陥れている、ということか!」
「研究。そうだよ、メタモルフォーズは人間の進化性、その一つとして挙げられている。そして僕もそのように考えている、ということ。それによって何が生み出されるのかはあまり明確に考えていない科学者も大半だけれど……、けれどそんなことよりも、僕は人間の進化の可能性以上のことを考えている。それはきっと君たちに話しても解らないことだと思うけれどね。君たちがここに居る時点で、ただの社会科見学、ということにはならないだろうから。いひひ! それにしても、勇者という職業は面倒なことだねえ。自ら、危険なところに首を突っ込むのだから。少しは休憩したいとか、面倒だとか、考えたことは無いのかい? ……まあ、僕の言葉は戯言だから、別に気にすることもしないのかもしれないけれど」
そうして、ドクターと呼ばれた男は僕たちに向かってこう言い放った。
「さあ、このメタモルフォーズに勝てるかな?」
ドクターがそう言った刹那、メタモルフォーズは動き始める。どうやら僕たちを明確な敵と認識しているらしい。厄介なことだった。せめてその研究者も敵と認知していればよかったのだけれど、分別は良かったほうだった。
「感心している場合じゃないぞ、フル。どうするんだ、これから!!」
問題は山積みだった。
メタモルフォーズに追われている状況をどうにかしなくちゃいけない。
しかも今はメアリーが居ない……。つまり、僕とルーシー、それにレイナで何とかあのメタモルフォーズを退けないといけないわけだ。
「何を勘違いしているか知らないが……、このメタモルフォーズはただのメタモルフォーズではない! 行け!」
そう言った直後、メタモルフォーズは通路を覆い隠すほどの水を放出した。
ドクターは別の通路に逃げてしまったためか水を浴びることはなく、そのまま僕たちはメタモルフォーズから放たれた水をもろにかぶってしまった。
水は若干粘度があったが、無臭だった。簡単に言えば、砂糖水のような感じだった。
「げほっ、ごほっ……。いったいこれは何だっていうんだ……!」
そしてそれを見計らったかのように、ドクターは笑みを浮かべ、
「管理者権限で以下の命令を実行する! 命令コード001、対象はお前の水を被った三名!」
そう叫んだ。
ドクターの言葉を聞いて、それに反応するかのようにメタモルフォーズの頭部にあった赤い球体が光りだす。
「貴様、いったい何をした!」
「命令コード001は殺しの命令だよ、この場所の秘密を知ってもらっては困るのでね。まだ僕はここでいろいろと研究をしたいからねえ、いひひ!」
「そんな自分勝手なことを……!」
「ああ、そんなことを言っている場合かな? 君たち、別に気にしているのかそれともその身体を神に捧げるつもりなのかは知らないけれど……、どちらにせよ君たちには勝ち目が無いよ。一応言っておくけれど、このメタモルフォーズは水を操作することが出来る。君たちの体内に含まれている構成要素、その八割が水分と言われているのは周知の事実であると思うけれど……、それを操作されてしまったら、どうなるだろうねえ?」
ぞっとした。
背中に悪寒が走る――とはまさにこのことを言うのだろう。いずれにせよ、このままでは大変なことになる。先ずはそれをどうにかしないといけない。ああ、メアリーを探さないといけないのに、こんな厄介なことに巻き込まれてしまうなんて!
そこで僕はふと、何かに気付いた。
もしかして――ここの研究員は僕たちが入ってくることを最初から察知していた?
だとすれば話は早い。僕たちが予めそこから入ってくるように仕組んでおいて、そこにメタモルフォーズを待機させる。そういうことで確実に僕たちを排除する狙いがあったとすれば?
「すべてあの研究者の掌に踊らされている、とすれば……」
それは非常に厄介であり、かつ非常に面倒なことだった。
しかし、どうすればいいのか……。
「何してんだ、フル!」
そこで僕は我に返る。
メタモルフォーズが走り出したのだ。それを見ていて何も動じなかった僕を見ておかしいと思ったのだろう。ルーシーがすぐに声をかけて、肩を揺すった。
そして目の前に迫るメタモルフォーズを見て、踵を返した。
先ずは逃げて時間を稼ぐ必要がある。
そう思って僕たちは大急ぎで走り出した。
_ ◇◇◇
_ バルト・イルファはモニタを見ていた。
そこに映し出されたのは、フルとルーシー、それにレイナが逃げている姿だった。
「……それにしても、あの時と比べると若干メンバーが増えているね。何の意味があるのか解らないけれど……、まあ、彼にも彼なりの考えがあるのかもしれないね。あの時も、確か結局それによって一つの結末を迎えたわけだし」
「どうするつもりかな? バルト・イルファ」
彼の背後には、フランツが立っていた。
声を聴いて、振り返るバルト・イルファ。
「……おや、フランツ。研究は休憩中かい?」
「侵入者と聞いて、安心して研究が出来るわけがないでしょう? しかもそれが予言の勇者というのであれば猶更です」
溜息を吐いて、モニタを見るフランツ。
フランツはモニタに映るフルとルーシーを見て、首を傾げる。
「それにしても、勇者は意外と若いのですね。ほんとうに、メアリーと変わらないくらい。簡単にメタモルフォーズどころか大人に殺されてしまいそうな子供ですけれど。ほんとうにこの子供が予言の勇者なのですかね?」
「気になるようであれば検証すればいいさ」
バルト・イルファは歌うように答えた。
「検証? そんなこと出来るとでもお思いですか。ただでさえ資金が枯渇してきそうであるというのに、そんなこと出来るわけがないでしょう。お上からの指示もまだ到達していないというのに……」
「結局、オリジナルフォーズそのものを起こすしかないわけだろ? 今までわざわざあの島に何度も遺伝子を手に入れるために肉片を回収してきたけれど、それにも限界がある。というかその処置自体暫定処置だった。暫定、というからには終わりが必ずある。そして、その後の対応が、オリジナルフォーズの覚醒……ということだ。そうだろう?」
フランツは苦虫を噛み潰したような顔をしてバルト・イルファを睨みつけた。
「君が何を知っているというのですか。所詮ただの研究結果の一つに過ぎないあなたが? 知ったような口で物事を語るのはやめたほうがいいですよ」
「果たして、そうかな。結構的を射ている発言だとは思うけれど」
「そう言っていられるのは外野の人間であると相場が決まっているのだよ。……いや、細かい話ではあるが、君は外野の人間は無いけれど、内野の詳しい事情を君は知らない。そういう人間がどうこう言おうとしたって、何も変わらないのが事実だし真実なのだよ」
「……そう回りくどい話をしても、結局意味は無いと思うけれどね?」
「意味があるか無いか、ではないよ」
フランツは頷いて、モニタに背を向ける。
「どこへ向かうつもりだ?」
「どこへ、と言ってもね。研究はまだ終わっていない。いや、そう簡単に終わっちゃいけないものだからね。先ずはそれをどうにかする必要がある。お上もそう言っているからね」
「だが、お上が言っていることってそう簡単にクリアできるものでもないだろう?」
フランツは出口に向かって歩きながら、笑みを浮かべた。
そして何も答えないまま、外へ出ていった。
バルト・イルファは溜息を吐いて、モニタに視線を移す。
「……結局、この世界をそう簡単に変えることなんて出来ない、ってことなんだろうな……」
バルト・イルファの呟きは、誰にも聞こえることなく、自然に消えていった。
_ ◇◇◇
_ 僕たちは何とか右や左に角を曲がり、少しずつ距離を稼いでいった。
そうしてようやくある場所へ逃げ込むことが出来た。
第四倉庫と書かれた名板を見て、僕は何か隠れられないか――と考えた。
しかし、その考えはすぐに捨てることになった。
「フル。やっぱり、あのメタモルフォーズは倒すしかないんじゃないか?」
ルーシーの言葉を聞いて、僕はその言葉を受け入れなくてはいけないと思った。
やはり、あのメタモルフォーズを倒さないといけないのか。しかし、どうやって? あのメタモルフォーズは全体的にゼリー状で、とてもじゃないが斬撃が通る相手とは思えない。となると剣や弓での攻撃は不可能と言ってもいいだろう。
では、魔法なら?
しかしながら僕たちは今までメアリーに助けられっぱなしである事実を考えると、それも難しい話だった。それに僕もルーシーも高度な魔法を知らない。だって予言の勇者という肩書きこそあるけれど、僕たちはただの学生だ。学生に出来る魔法なんてたかが知れている。
となると、このままでは手詰まりだ。
ならどうすればいいだろうか……。
一先ず、倒すとするならば使えそうなものはフルで活用していったほうがいい。そう考えて僕たちは倉庫の中を探してみるのだが、
「ねえ、フル。これっていったい何かな?」
ルーシーがあるものを指さした。
それを見て僕は首を傾げる。
そこにあったのはモーターがつけられた大きな機械だった。そしてその機械の隣には燃料が入っているとみられるドラム缶が多く置かれている。
「……これは発電機のようだね。きっともともとはどこかで電気を作っているのだろうけれど、緊急時のために置いているのだろうね。こういう施設だから電気が無いとやっていけないのだと思うよ。それに、これは……?」
燃料の入っているドラム缶から少し離して、幾つかの薬品が入っているドラム缶を見つける。
それにはラベルが貼られており、やはりここが何らかの研究施設であることを改めて認識することとなる。
「これは……水酸化ナトリウム? ということは……」
僕は学校で習った知識を思い出す。確か水酸化ナトリウムと電気……何か法則性があったはず。なんだ、思いだせ。思い出すんだ……!
そして、思い出した。
「これだ……!」
そして、ルーシーとレイナにそれを告げる。
「これなら、あのメタモルフォーズを倒すことが出来るかもしれない!」
「成る程……。でも、無茶じゃないか!? そんなこと、実際に出来るかどうか……」
「出来るかどうかを考えるんじゃない。出来ると思って考えないといけない。この作戦なら絶対にあのメタモルフォーズを倒すことが出来る。だから、何とか頑張るしかない」
「けどこのドラム缶をどうやってあそこまで!?」
「あら、ルーシー。何か忘れていないかしら」
そう言ったのはレイナだった。レイナはあるものをひらひらと僕たちに見せつけるように持っている。
それを見たルーシーは目を丸くして、「あ!」と何かを思い出したかのように驚いた。
「そうか、それを使えば確かに……!」
ルーシーも作戦を理解してくれたのを見て、僕は大きく頷いた。
「さあ、時間が無い。あとは作戦を実行するだけだ。急いであいつを倒して、メアリーを探さないと!」
その言葉にルーシーとレイナは大きく頷いた。
_ メタモルフォーズが倉庫の中に入ってきた。迷う様子もなく一目散に入ってきたところを見ると、やはり水による探索機能はまだ生きている、そして嘘ではないということになる。それにしても、ほんとうに厄介な機能だと思う。そのような機能を付けるということは、相手を確実に死に追いやるということも考えられているのだろう。
それはさておき。
「いいか。レイナ。チャンスはおそらく一回きりだ。これを逃すとメタモルフォーズを倒すことは出来ないだろう。……まあ、別にここだけがタイミングを逃すとマズイところかと言われると、そうでもないのだけれど」
「解っているわよ。それに、そちらもきちんとタイミングを守ってよね? 私がうまくいったとしても、ダメになる可能性があるのだから……」
それくらい、百も承知だった。
だからこそどうすればいいとかそういうことを考えていて、最終的に僕が入口で監視することになった――そういうわけだ。ただし、それは入口にある荷物の上に居る、ということになるので、正確にそうであるかは言えないかもしれないけれど。
「今だ、レイナ!」
そうして、メタモルフォーズがあるポイントに到着した。
レイナはその瞬間、ある薬剤が入ったドラム缶に転移魔方陣が描かれた紙を貼付した。
その転移先は――メタモルフォーズの頭上。
そしてドラム缶は重力に従うままに、床に落ちていき、メタモルフォーズに命中した。
いや、正確に言えばメタモルフォーズから少し外れた位置であったが、むしろそちらのほうが、都合が良かった。
薬剤を取り込んだメタモルフォーズだったが、それが何を意味しているのかメタモルフォーズ自身も理解していないようだった。
「ルーシー、今だ。スイッチを押せ!」
今度はルーシーにスイッチを押すよう言う。
そのスイッチとは――発電機のスイッチだった。
そしてルーシーは大きく頷くと、彼の手元にあった発電機のスイッチを入れた。
一瞬だった。
床に置いてあった端子から電気が放出され、メタモルフォーズに電気が流れる。
もし、メタモルフォーズの主成分がただの水であれば、ただ水に電気が流れるだけで終わってしまうだろう。
ただし、メタモルフォーズにある薬剤が溶け込んでいるとしたら?
水酸化ナトリウム。
水に溶かし、電気を流すことによって電気分解をすることが可能になる薬剤のことだ。水は水素と酸素に分解される、電気分解という現象。それは、大規模な電気を生み出すことの出来る発電機と、大量の水酸化ナトリウムが溶けたメタモルフォーズが加わることで急激な電気分解が可能となった、ということだ。
メタモルフォーズは苦しみながら、雄叫びをあげながら、徐々にその身体を小さくさせていく。
メタモルフォーズは相当大きい質量であったが、その全体が水素と酸素に分解されるまで、そう時間はかからなかった。
そして、最終的にメタモルフォーズの頭部にあった赤い球のみが残されて――地面に落下し、四散した。
「……倒した?」
ルーシーは発電機のスイッチを切ったことを確認してから、荷物の上から降りた。
そこに残されていたのは、何もなかった。水素と酸素は空気に溶け込んでしまい、最後に残された赤い球体もまた風に吹かれて消えてしまったのだから。
「どうやら、そのようだね。……それにしても、メタモルフォーズを何とか倒すことが出来た。これで何とかメアリーを探すことが出来る。いや、何とかなったね」
「まさか……ほんとうにあのメタモルフォーズを倒すことが出来るとは……!」
その声を聴いて、僕たちは入口のほうを向いた。
そこに立っていたのはドクターと呼ぶ男だった。
「ドクター……だったか。お前のメタモルフォーズは既に倒したぞ。もうこれ以上秘策があるとは思えないがな」
「ぐぬぬ……。解ったような口を聞きやがってっ! それくらい解っているというのに! ……ええい、解った。これ以上無駄に技術を使うわけにもいかないし、まだ我々には次のミッションが残されている。だからこそ……」
ドクターはポケットにある何かのボタンを――押した。
刹那、地面が揺れ始める。
立っていられないほどの、大きな揺れだった。
「お前、いったい何をした!?」
ルーシーがドクターに問いかける。
「何をした? 簡単なことだよ、証拠の隠滅だ。これ以上この場所を残していても我々シグナルのためにはならない。それどころか世間にメタモルフォーズの知識が広まってしまう。それだけは避けなくてはならない。避ける必要があるのだよ。いひひ! まあ、せいぜい死なないように逃げることだね」
それだけを言って。
ドクターは一目散に走っていった。
「おい、どうするんだ! メアリーを探さないといけないし、このままだと……!」
「それくらい解っている……! だが、今は逃げるしかない!」
ほんとうは僕だってこの状況からメアリーを探したかった。
けれど、今は逃げるしかなかった。潰されてしまうよりはマシだった。メアリーも無事であることを祈るしかなかった。
だから、出口へと向かう。
僕とレイナ、それにルーシーは先ほど入ってきたところへと――戻っていった。
メアリーが無事であるということを、ただただ祈りながら。
_ 僕たちが外に出た、ちょうどのタイミングで研究施設の入り口が崩落していった。
「……間一髪、だったのか……?」
ルーシーの言葉に、僕は頷く。
まさかここまでギリギリだとは思いもしなかった。正直な話、もう少し余裕があるものかと思っていたからだ。
それにしても、この建物が破壊されてしまったということは――。
「また、メアリーの情報が手に入らなくなった、ということか……」
そう考えると、とても頭が痛い。ようやくメアリーについての手がかりを見つけ、おそらく捕まっているであろう場所まで到着した――にも関わらず、
「どうやら、敵のほうが一歩先を進んでいた、ということになるのだろうね……。かといって、メアリーはいったいどこへ行ったのだろう? まさかこの瓦礫の中に――」
「ルーシー!」
僕はルーシーの言葉を聞きたくなかった。
その可能性だって、十分に考えられる話ではあるけれど。
今はできる限り、考えたくなかった。
「フル、ルーシー! ……ちょっと、こっちに来て!」
声を聴いて、僕たちはそちらへと向かった。
僕とルーシーを呼んだのはレイナだった。レイナは瓦礫の中に何かを見つけたらしく、それで僕とルーシーを呼びつけたようだった。
レイナが見つけたのは杖だった。その杖は林檎のデザインがされており、僕もルーシーもよく見たことのある杖だった。
「これは、メアリーが持っていた……!」
そう。
メアリーが持っていた、シルフェの杖だった。
それがそこにあったということは、メアリーがここにいた証拠になる。
けれど、
「でも、メアリーがどこかに行ったという証拠にはならない」
ルーシーの言葉は的確だった。
確かにその通りであったし、逆にメアリーがここに埋まっているのではないか? という最悪の答えを考える可能性もあった。
「メアリー・ホープキンは生きているよ。君たちの想像通りね」
声が聞こえた。
それは、僕もルーシーもレイナも、聞いたことのあるやつの声だった。
「バルト・イルファ……!」
頭上には、バルト・イルファが浮かんでいた。いったいどのような魔術を行使したのか、僕には解らなかったけれど、そんなことよりもどうしてバルト・イルファがそれを僕たちに伝えたのか――それが妙に気になった。
バルト・イルファは僕を見つめて、言った。
「どうやら君たちは気になっているようだね。どうして僕がメアリー・ホープキンの居場所を知っているのか。そして、それをなぜ教える必要があるのか。確かにそう考えるのは当然かもしれない。けれど、それは君たちに絶望を与えるためだといってもいいだろう。君たちにはもっと苦しんでもらいたいからね」
「貴様……! バルト・イルファ、お前だけは、絶対に許さない!」
僕はバルト・イルファを睨み付けて、そう言った。
けれど空を飛ぶ敵に対しての攻撃手段を僕は持ち合わせていなかった。
「……まあ、せいぜい頑張るがいいさ。そうだね、ここまでやってきた君たちにはリワードを与える必要があるだろう」
指をはじいたバルト・イルファは踵を返して、最後にこう締めくくった。
「メアリー・ホープキンは邪教の教会にいるよ。そこがどこにあるかどうかは、まあいう必要も無いだろう。そこまで言うとヒントではなくなって、それはもはや解答を示すことになってしまうからね。だから、そこは自分で考えたまえ。寒い場所だから、急がないと凍えてしまうかもしれないよ?」
そうしてバルト・イルファは、今度こそ姿を消した。
_ ◇◇◇
_ 帰り道。
僕たちは行きと同じように竜馬車に乗り込んでいた。
では、操縦者はだれか?
「……まさか、シュルツさんが生きているなんて思いもしなかったですよ」
僕はその思ったままのことを、口にした。
「確かにね。まさか、メタモルフォーズの足に踏みつぶされたと思わせておいて、ただ隠れていただけなんて」
シュルツさんが竜馬車でコーヒーブレイクをしていたのを発見した時は、驚きというよりも呆れてしまったと言ったほうが正しかった。
なぜ僕たちにも嘘を吐いていたのか――まずそこが理解できなかったし、なぜそんなことをしていたのか、とても気になった。
しかしシュルツさん曰く、
「別にそれについて言う必要もないだろう? ……あと、敵をだますなら味方から、というくらいだし」
現に岩山の陰にはメタモルフォーズの死体が倒れていた。
どうやら研究施設の入り口にカメラがあることを見破ったシュルツさんは、敢えて一回自分が死んだように見せかけて、カメラの死角となっている場所でメタモルフォーズを倒したのだという。いったいなぜカメラの死角が解ったのか――それについては、あまり教えてくれなかったけれど。
「取り敢えず、次の目的地は決まったのかい?」
最後に、シュルツさんは、言った。
その言葉に僕たちは大きく頷いた。
そして僕たちは次の目的地へと向かう。
そのためには一度、エノシアスタへと戻る必要があったわけだけれど。
_ ◇◇◇
スノーフォグ国軍大佐であるアドハムは部下からの報告を受けて、目を丸くしていた。
シュラス錬金術研究所を任せたはいいものの、まさかこうも簡単に破壊されるとは思いもしなかったからだ。
「それもこれも、ついこの間やってきたあのキメラのせいだ……!」
キメラ。
正確にはそうではないのだが、いずれにせよ彼にとってあまり理解していない分野のことだからそう説明するほうが正しいかもしれない。そのキメラはスノーフォグの王自らがそこへ向かわせたため、アドハムもそのキメラに従わざるを得なかった。
「まさかそこまで出し抜かれるとは思わなかった……」
「いかがなさいますか?」
部下の言葉に、アドハムは頷く。
「我々は我々で進めるしか無いということだよ」
窓から外を眺め、
「予言の勇者の抹殺。我々の計画はプランエーから、プランビーへ移行する。ほかの人間にもそう伝えておけ」
傅いた部下はそのまま部屋を後にした。
アドハムの思惑、そのやり取りは彼とその部下を除けば、空から眺める月くらいしか解らないことであった。
結論から言うと、僕たちがシュラス錬金術研究所からエノシアスタに戻るまで半日の時間を要することとなった。はっきり言って大して時間はかからないものだったのだが、案外竜馬車の疲労度がそれなりに高かったことが理由として挙げられたためだった。シュルツさんが厳しく否定したので、それについてはそうであると考えるしかない。
シュルツさんはベテランであり、竜馬車のプロだ。もちろん、本人はそんなことを気にも止めていなかったようだったけれど、僕たちにとってみれば唯一の専門家だった。それを考慮すれば、シュルツさんの意見を、ある意味鵜呑みにするしか手立ては無かった……ということになる。
それはそれとして。
シュルツさんはエノシアスタで僕たちを下ろしたあと、報酬の話をする暇もなく竜馬車のメインテナンスを行うためと言って小屋へと戻っていった。だからと言って僕たちもそこで報酬を踏み倒す気は毛頭無い。
よって僕たちはシュルツさんの小屋へと向かうのが当然であり望ましい結果だった。
「それにしてもシュルツさん……かなりあのドラゴンのことを思っているのだね」
そう言ったのは、レイナだった。
レイナはさらに話を続けた。
「竜馬車使いはドラゴンの心を理解することが出来る、とは聞いたことがある。シュルツさんもきっとそれに該当するのかな。恐らく、ではあるけれど。いずれにせよ、私にとってそれはあまり関係の無いことではあるけれど」
「特殊な技能を持っているとか、そういうことなのか?」
「たぶんおそらくきっと、そういうことになるのだろうね。別にそこまで珍しい話じゃないと思うよ。だって、竜馬車使い全員に言えることらしいからね。魔術でも錬金術でも召喚術でもない、第四の術ということになるね。魔術師は錬金術を使えないし、錬金術師は魔術を使えないけれど、竜馬車使いもまた、魔術や錬金術を使うことはできない。確かなんかの本にそんなことご書いてあった気がするよ」
こういう知識がすらすらと出てくるのは、メアリーの次に、意外にもレイナだったりする。レイナはもともと盗賊だったにもかかわらず、その生まれや育ちには決して比例しない(誠に申し訳ない発言ではあるのだが。なぜならこれは名誉毀損になるためだ)知識が蓄えられている。いったいどこの時間でそれほどの知識を蓄えることが出来たのだろうか? なんてことを思うときもあることにはあるが、しかしそれは極稀に過ぎない。非常にアブノーマルなケースに過ぎない。要するに滅多に発生することのない事象であり事実であり、しかしながら、それでいて真実だった。
話を戻そう。
僕たちはシュルツさんと別れて、とぼとぼと道を歩いていた。目的地はここに来て直ぐに確保した宿だ。決して安い宿ではないが、路銀自体はエノシアスタへの護衛の前金も含めて有り余るほどに持っているため、別にそれについては何の問題も無かった。
宿に到着し、階段を上る。二階の二部屋のうち、左はレイナだけの部屋、右は僕とルーシーの部屋になっている。とどのつまり、男女で部屋が分かれている状態になっている、ということだ。
分かれているのは確かだが、部屋の大きさはイコール。即ち体感的にはレイナだけの部屋の方が広く感じることだろう。シングルとかダブルとかあるわけだけれど、残念ながらここは異世界。僕の持っている常識が通用するはずもない。
ベッドに腰掛けた僕たちは、一先ず僕とルーシーの部屋に集まって、今後の会議をすることと相成った。
「とはいえ……これからどうするつもりだ? さっきまでは、手掛かりがあったからそこへ向かうことが出来た。しかし、今では? ヒントも何もない。その状況で世界を回っていくのは少々面倒なことだとは思うのだけれど」
ルーシーはそう言った。
しかしながら、手掛かりがないわけでも無かった。それはバルト・イルファが去り際に放ったあの言葉……。
「邪教の教会、だったかしら。あと寒い場所とも言っていたわね」
僕がそう思っていたところにレイナはそう付け足した。
僕は頷くと、話を続けた。
「レイナが言ったとおり、邪教の教会……それこそが今後の僕たちの旅にとっての、最大のヒントと言えるんじゃないか?」
「簡単に言うけれど……そもそも寒い場所かつ教会なんてたくさんあるんじゃないか? それこそスノーフォグは雪国だ。寒い場所なんていろんな場所にあると思うのだけれど」
「……いや、待てよ」
そこでルーシーは、レイナの言葉を遮った。
それを聞いて、レイナと僕はそれぞれ彼の方を向いた。
「ルーシー、何か知っていることでも? 何でも構わないぞ、今は有益か無益か解らなくても、何かピンと来たらそれについての情報をリストアップするしかない」
「……そう言われてしまうと、この情報が有益かどうか解らないけれど、スノーフォグには確か離島があったはずだよ。北側にあるはずだったから、その寒さも随一。常に雪が降り積もっているその島は秘境とも揶揄されている」
「その島の名前は?」
ルーシーには自信が無かったようだが、その情報はかなり有益なものだった。それをもとに調査を進めれば、或いは。
ルーシーは僕の言葉を聞いて、小さく溜息を吐くと、
「……フル。人の話は最後まで聞くように習わなかったのかい? まあ、べつにいいけれどさ、今は緊急時だからね。それと、その島の名前は確か……チャール島、って名前だったかな。召喚術の生みの親、マザー・フィアリスが暮らしていた島だ」
_ ◇◇◇
_ とある場所にて。
「……シュラス錬金術研究所が崩壊した、と?」
「はい」
バルト・イルファは隣にいるリュージュに短く答えた。
リュージュは水晶玉を見つめつつ、さらに話を続ける。
「まあ、あそこは最近有意義な研究ができていなかった、と思ったところだったし、別に問題ないかな。……それにしても、全員死んだということでいいのかしら?」
「いえ、ドクターとフランツ、それに僅かな人間が生き残ったものと……。彼らは恐らくあの巣から逃げ出したものかと思われます。実際、誰もいないと思われますから」
「あの場所から研究施設を削ったら、そこに残されるのはメタモルフォーズの巣になるからね。あの場所に生身の人間が生き残る環境があるとは到底思えないわ。あなたのように『作られたメタモルフォーズ』ですら、生き残ることは困難だと言われているというのに」
その言葉にバルト・イルファは何も言い返さなかった。
リュージュはさらに話を続ける。
「……『彼女』は別の場所に連れて行ったでしょうね?」
「それくらい当然だ。邪教の教会、今はあそこに連れて行ったよ」
「ああ、あのチャール島の……」
こくり、とバルト・イルファは頷いた。
「何しろ、けっこう大変だったよ? ちょうど転移魔方陣に乗せたタイミングで彼らが襲撃してきてね。時間がなかったところに、さらに彼らがメタモルフォーズを召喚してしまったものだから、面倒に面倒が重なってしまって」
溜息を吐き、バルト・イルファは肩を竦める。
「それでも、私の考えている道を歩んでいることだけは変わらないわ」
ふふ、と笑みを浮かべてリュージュは立ち上がる。
リュージュはバルト・イルファのほうを向いた。
バルト・イルファには何の感情も抱くことの無い出来事ではあったが、リュージュは絶世の美女といっても何ら過言ではないほど、美しい存在だった。白磁のような肌をもち、黒い髪はきめ細やかだ。彼女が神話と呼ばれるような時代から生きていた、と言われていても信じる人間は殆ど居ないことだろう。
いや、それどころか。
祈祷師は不老不死ではない。確かに長寿ではあるのだが、人間とは明らかに遅いペースで老化が進んでいく。だから、通常数十年で進む老化も数百年単位で進んでいく。
しかし、そうであったとしても。
リュージュは明らかに老化しなかった。同じ祈祷師であったラドームが疑問に感じる程度だった。どうして何百年も生きていてまったく姿が変わらないのか? 何か魔力を使っているのではないか? という疑問がすぐに降りかかる。
しかしながら、魔力をそのために使うには相当の魔力を要する。そういうわけだから、それを何百年も使いまくることは、ほぼ不可能に近かった。
だが、リュージュはそれを成し遂げていた。
だからこそその疑問が解決できなかった。けれど、リュージュはその疑問を解決していた。
「……リュージュ様、お薬の時間です」
三人目の声が聞こえた。
気が付けばそこには白いワンピースを着た青髪の少女が立っていた。お盆を持っており、カプセルが二つとグラスに注がれた水が載せられている。
それを聞いたリュージュは踵を返すと、
「あら。もうそんな時間だったかしら? ありがとう、ロマ。あなたのおかげでそれを忘れずに済むのだから」
そう言ってロマと呼んだ少女のもとに近づくと、カプセルを飲み口に水を含んだ。
そしてそのままそのカプセルを体内に飲み込んでいった。
このやり取りはバルト・イルファがリュージュの側近のような立場になってから、いや、正確に言えばそれよりも前から続いていることだった。実際に何をしているのか彼には理解できないし教えてもくれなかったのだが、決して彼女が病気では無いということから、それが何らかの習慣の一つであることしか、彼自身も知らなかった。
「……バルト・イルファ。このやり取りが気になっているようね?」
急に。
ほんとうに急にバルト・イルファに話が振られて、彼は一瞬困惑した。
「……す、すいません。しかし、確かにその通りです。実は少し気になっておりまして……」
「何もそれを過ちだとする必要はない。簡単なことだよ。これは、オリジナルフォーズのエキス……正確に言えば肉体の一部だ」
簡単に。
呆気なく。
リュージュはそのカプセルの正体を言った。
「私の美貌を保つにも時間と金と労力がかかってしまうものでね。色んな方法を試したものだよ。しかしながら、それはどれもうまくいかなかった。最終的にこの方法にたどり着いただけ、ということ。それは、永遠の治癒力と無限の力を秘めるといわれているオリジナルフォーズの力を体内に取り込むということ。なにせ、肉体はほぼ無限に復活する。そして、これくらいならばいくら取ろうが誤差に過ぎない。これを摂取しだしてから、私の美貌にはさらに磨きがかかった。いや、それどころではない。それどころか、さらに若さが増したようにも思える。魔力も満ち満ちている。これぞ、オリジナルフォーズの力と言えるだろう。体内に知恵の木の実を保持しているともいわれているからね、オリジナルフォーズは」
リュージュはそう言って、飲み干したグラスをロマに渡す。ロマは頭を下げると、そのまま姿を消した。
リュージュは再び自席に戻ると、水晶玉を見つめ始める。
そして、彼女は言った。
「それじゃ、観測を再開しようか。あの己惚れた国軍大佐がどういう作戦を立てて私を倒そうとするのか、見てみようではないか? まあ、どうせ人間のすることだから低能なことなのだろうけれどね」
薄ら笑いを浮かべて、リュージュは水晶玉を触れる。
「……さあ、せいぜい私を楽しませてくれよ?」
それは、すべて何もかも知っているような、そんな笑顔にも見えた。
_ ◇◇◇
_ その日の夜。
今日はとても疲れていたので、夕食を終えて簡単なミーティングを済ませたのち、それぞれの部屋に戻ってベッドに入っていった。
とっても疲れていた。正直ミーティングの後半は何をしていたかすら忘れてしまうほどだ。いや、それは訂正しておこう。もしルーシーがその事実を知ったら怒ることに違いない。
それはそれとして。
さあそろそろ眠りにつこうか、と考えていたちょうどそんなタイミングでのことだった。
音が聞こえた。
正確には、足音。それも複数の足音だった。
「……何だ?」
僕は起き上がる。そのタイミングでルーシーも身体を起こした。
「どうした、フル?」
「……何か、来る」
その瞬間だった。
僕たちの部屋の扉が強引に薙ぎ倒された。
「うわっ……!」
そして僕たちはその衝撃に、ほんの一瞬目を伏せてしまった。
「動くな!」
僕が目を開けたころには、もう僕たちは兵士に囲まれていた。
「……お前たち、いったい何者だ!」
「まあまあ、そう牙をむくな。簡単に終わらなくなるぞ?」
そう言って、兵士の向こうからやってきたのは、それよりも位が高いように見える男性だった。
「はじめまして、というべきかな。私の名前はアドハム。スノーフォグの国軍大佐を務めている。……まあ、このような行動をとった今、大佐というものはただの名前に過ぎないものになってしまったがね」
「国軍大佐……!」
ということは、今僕たちを取り囲んでいるのは……。
「国軍が、こんなことをしていいのか!?」
そう言ったのはルーシーだった。
そう。
僕たちの予想が正しければ、僕たちを取り囲んでいる兵士はスノーフォグの国軍だったということ。つまり、この行動はスノーフォグの国が理解している行動、ということだといえる。
「ああ、勘違いしないでもらいたい。スノーフォグの国軍に籍を置いているが、これは私独断の行動であるということだ。それに、この兵士も私独断の行動であることを理解している」
「……国を庇うつもりか?」
「若造が、知った風に話すな。……別にそのようなことではない。これは私の矜持の問題であるし、私自身の目的を果たすためだ」
「目的……だと?」
僕がそれについて、さらに話を進めようとしたちょうどその時だった。
背後に衝撃が走った。
そして、僕はそのまま倒れこむ。
そのまま、僕の意識は薄れていった――。
_ 次に目を覚ました時、そこは牢屋だった。
石畳の床に直に寝かされていたか、とても身体が痛かった。
「……ここは? 僕はいったい、何を」
「解らねえよ。とにかく、ここからどうするか。それを何とかするしかない。生憎、全員が別々の牢屋に入れられることは無かった。そこは唯一のグッドポイントといえるのかな」
そう聞いて、僕は牢屋を見渡した。
するとルーシーのいった通り、すぐにレイナの姿を見つけることが出来た。
「……となると、どうやってここを脱出すればいいか。それが問題だな……」
やはり、根本的なそれが残る。
その問題を解決すれば脱出は容易かもしれないが、しかしそう簡単にできる話でもない。
しかしながら、今はどうにも出来ない。
そう思って僕たちは一先ずお互い考えることに徹するのだった。
_ ◇◇◇
「うむ。なら、適当なタイミングで食事を与えておけ。彼らに死んでもらっては困るからな」
「……しかし、大佐。大佐はどうして彼らを捕まえておく必要があるのでしょうか?」
「簡単なこと。予言の勇者が出てこなければ、世界の災厄を食い止めることはできないのだろう? だから、それを実行するまでだ。簡単なことであり、非常にシンプル」
「……大佐、あなたは世界を滅ぼそうと……?」
「世界を再生するための、その第一歩だ」
「…………」
「さて、これ以上話す必要はあったか? 取り敢えず時間的にそろそろ食事のタイミングなのだろう? だったら大急ぎで向かいたまえ。予言の勇者を殺しておくのは、非常に目覚めが悪い」
「了解いたしました」
そうして部下とアドハムの会話は終了した。
_ ◇◇◇
「簡単だ。もう少し見ているべきかと思っていたが……まあ、どうにかするしかないだろう。あいつは、少々世界を舐めていた。正確に言えば、私という存在をも、の話になるが」
「では、出撃と?」
「僕も出撃するということかな?」
「バルト・イルファ。まあ、問題ないでしょう。序でにロマも連れて行きなさい。そろそろ『調整』も終わった頃でしょう?」
「確かに、そうだね。まあ、ロマも外に行きたくて仕方なかったし、そろそろいい塩梅かも。了解、それじゃ連れていくことにするよ。もうすぐ出発するかい?」
「はっ。もう兵士の準備はできております」
「それじゃ、そこにイルファ兄妹も一緒にね。仲良く行動すること、いいわね」
そうして闇の中の三人の会話もまた、静かに終了した。
_ ◇◇◇
_ 次に僕たちが目を覚ました時、それは扉が開かれてそこから部下とみられる男が姿を見せたときだった。
「外に出ろ」
僕たちはその言葉に、ただ従うしか無かった。
廊下を歩き、僕たちは一つの部屋へと到着する。
「失礼します」
ドアをノックしたのち、部下とみられる男は中へ入っていった。
そして僕たちも背中に銃を突き付けられ、半ば強引に中に入っていった。
そこにはリクライニングチェアに腰かけていたアドハムの姿があった。
「お前は……!」
「君たちに、なぜここに呼んだかというと簡単なことだ。私の目的を少しでも知ってもらおうと思ってね。まあ、理解してもらおうなどとは思っていない。ただ知ってもらうだけの話だ。ハードルはたいして高いものではない」
そうして僕たちは立ったまま、アドハムの話を聞くこととなった。
「簡単に話を進めるために、前提条件というか、そういうものを話していくこととしよう。この世界に起きている問題を、君たちはどれくらい知っているかね?」
「問題、って……ええと、貧困とか?」
「貧困。確かにそれも多い。現にこの町ではそれがピックアップされていないが、この町以外では貧困に苦しむ子供が多いといわれている。現に一般人の月収の十分の一未満で生活をしている人が世界人口の二割を占めるともいわれ、これは増加傾向にある。これは由々しき事態だよ。本来ならば世界で考えていかねばならない問題のはずだ。だが、国のトップは何も考えちゃいない。ただ私腹を肥やしているだけ……いいや、違う。それ以上の問題を孕んでいる」
「何で貧困になるんだ……?」
「いい質問だな、予言の勇者。それはシンプルにこう捉えることが出来る。『肥沃な土地が不足している』からだ。この世界の七割は土地の養分が少ない。だから食べ物を生産するのも難しい。エノシアスタでは人工植物を作りカバーしていることはしているが……、まだ大量生産には至っていない。この言葉の意味が理解できるか? まだ、世界の人間を養うほどの食べ物は、我々でも作ることが難しいということだ。かつて肥沃だった土地は、偉大なる戦いのとき、すべて分割して宇宙に放たれてしまったのだから」
肥沃な土地が不足している。
だから、そこで食べ物を作ることができない。
そして、食べ物を作ることができないけれど、限られた人が食べ物を寡占している。
結果として、貧富の差が広がっていく。
まるで僕がいた世界とあまり変わらない。いや、それどころかほぼ同じだと思う。
アドハムの話は続く。
「この世界は、裏ではリュージュ……スノーフォグが操っている。一応国としては三つに分かれているのだが、裏を見ている人間からすればそんなものはうわべだけに過ぎない。重要そうなことにかんしてはすべて、リュージュを通して実行される。彼奴がこの世界の王と言っても何ら過言ではないだろう」
「リュージュが……この世界の王……?」
ならば今、この世界がこうなっているのはリュージュが原因ということになるのか?
「そういうことになるだろう」
アドハムは、まるで僕が考えていたことを理解していたかのように、頷いた。
ただし、と言ってアドハムは話をさらに続ける。
「リュージュはこの世界では賢王だ。人々に愛され、リュージュも民を愛している。だから、人々からみればリュージュが政治を執り行うことは別に珍しい話ではないし、むしろ素晴らしいことだと思う人間が多いことだろう」
「……けれど、世界の裏ではリュージュが糸を引いている、と?」
「そういうことだ。だが、リュージュは何もしようとしない。正確に言えば、軍事力にその力を割いている、といっても過言ではないだろう」
「?」
「彼奴もまた、この世界の状況については理解している。なぜなら彼奴は祈祷師だ。未来を予言することができる。未来がどうなっていくかを一番理解することができる。だから、どうすれば未来を変えることができるかを、理解できるわけだ」
「……つまり?」
どんどん状況がおかしくなっていくのが、僕にも理解できた。
「この世界を変えるためにどうすればいいのか……いろいろと考えたのだろうが、彼女もまた最悪の指針を選択した、ということになる。リュージュはスノーフォグを軍事大国にして、どうしようと思っているか、分かるかね?」
「いったい何を……」
「リュージュはレガドールとハイダルクを滅ぼし、この世界を真に統一しようと考えている。いいや、そんな甘い話だけではない。そこで人々を選び……最終的にこの世界でシミュレートして生きていける人間の数だけ残すようにする。選民主義の国が誕生する、ということになる」
「選民主義の国……だって?」
アドハムの言ったことは、どちらかといえばあまり現実的なものではなかった。
けれど、もしそれが本当だったとすれば、リュージュはあまりにもとんでもないことを仕出かすのだということは、僕たちにも簡単に理解できることだった。
「でも、……どうすればいいんだ? 相手は一国の主だぞ。それを食い止めるとしたって……」
「そのために、我々は行動している。逆のことをしてしまえばいい。リュージュを倒すことで、この世界が守られるのならば、その犠牲は少なく済む。いや、もっと言えば……」
「?」
アドハムが一瞬言葉を躊躇ったので、僕は首を傾げた。
そして数瞬の時を置いて、アドハムはその続きを話した。
「……スノーフォグの人間を滅ぼす。この科学技術を、この世界には有り余るほどの科学技術を生み出したエノシアスタを滅ぼす。そのために我々はここにいるのだよ、予言の勇者よ」
「エノシアスタを滅ぼす……だって? そんなこと、許されるとでも!? できるわけがないだろう! 人間を、人間が殺すなんて!」
「別に人間が人間を殺してはいけないという理由は無い。その意味が解るかね? そもそも、なぜ人間は人間を殺すな、と言っているのか。それは簡単だ。人々が混乱してしまうから。では、混乱しなければいいのではないか? 正確に言えば、混乱すること以上に人間の危機が訪れているとすれば……人間を殺すことも厭わない。そうは思わないか?」
「それは……言いがかりだ! 言い訳に過ぎない。そんなこと、ゆるされるはずが……!」
「まあ、いい。所詮、予言の勇者とはいえ、ただの子供だったということだ」
そう言ってアドハムは右手を挙げた。
同時に僕たちは兵士に身体を強く引っ張られる。
面会の時間は終了した――ということだろうか。
いや、でも、まだ終わっちゃいない。
まだ話し足りない。
まだ話していないことが、たくさんある。
「アドハム、まだ話すことが――」
「連れていけ」
アドハムはその一言しかいうことはなかった。
そして僕たちはそのまま、兵士に引きずられる形で部屋を後にするのだった。
_ ◇◇◇
_ 牢屋に戻って、僕たちは作戦会議をすることとなった。なぜそう簡単に堂々と出来るかというと、兵士はそう扉から近いところに立っているわけではないためだ。そうではあるが、それでも声は聞こえる可能性があるためトーンを落として、ということにはなるのだけれど。
「……これからどうする?」
ルーシーの問いに僕は首を傾げるしかなかった。
今僕たちがどこにいるのか。ここからどう脱出すればいいか。逃げることができたとしてもそのあとも追っ手を撒くことは出来るのか。問題は山積みだった。
「……とはいえ、だ。問題は山積みだとはいえ」
「ルーシー、何か言いたいようだね?」
「フル。お前は気にしていないのか、メアリーのことを。もう一週間近く……メアリーは敵につかまっているんだぞ。その間、彼女がどうなっているのか、俺達には一切解らない。それでも全然気にしていないというのか?」
「気にしていないわけがないだろう。でも、今はどうにかしてここから脱出しないといけない。メアリーのことよりも重大だ。そうじゃないか?」
「そうかもしれないが……。ほんとうにお前、そう思っているのか?」
「……というと?」
「というと、じゃないよ。何か最近のお前は……」
「ちょ、ちょっと待って! 今はそう争っている場合ではないでしょう? とにかく今は……」
それを聞いて、僕とルーシーはお互いレイナの顔を見つめた。
そして暫し考えて、僕たちは向かい合って頷く。
「……そうだな。レイナの言うとおりだ。ここで争っている場合じゃない。今はメアリーを探さないといけない。そしてそのためにはここを脱出する必要がある。そうだろう?」
「そうだ。そのためにもまずは三人が協力しないと……」
そう僕たちが団結した、その瞬間。
ゴゴンッ!! と地面が大きく揺れた。
「何だ!?」
牢屋にある唯一の窓から外を眺めようとして――ああ、そうだった。この窓は僕たちの伸長では到底届くことのない高さだった。肩車をすれば何とか届くかもしれないが……。
しかし、そんなことをする必要もなく、徐々に緊迫した空気が外から伝わってきた。
「何事だ!」
「はっ。メタモルフォーズが襲撃してきました! そしてその上には、バルト・イルファが居るものかと……」
「バルト・イルファだと!? ……まさか、リュージュめ。我々を本格的に捨てに来たというのか! というか、いつ作戦があちらに判明してしまった?!」
「……それは解らない。それよりも大佐が緊急招集をかけている。急いで部屋へ向かうぞ!」
そして、扉のすぐそばにいた兵士はどこかへ消えていった。
これはチャンスだ。これをうまく使えば脱出することができるはず。
「でも、どうやって?」
レイナからの質問。
そしてそれはルーシーも僕も、思っていることだった。
どうやってここから出るか。その答えが出ていないのに、出ることが簡単に可能になるわけがない。
しかし、動きは以外にも外からあった。
ガチャリ、と扉が開く音がしたからだ。
「……誰だ?」
僕たちは咄嗟に戦闘態勢を取り、その人間が出てくるのを待った。
数瞬の時を置いて、入り口から誰かが入ってきた。
「……いやあ、君たちが居なくなったときは驚いたよ。報酬踏み倒されるかと思った。だが、怪しい人間に捕まった、と聞いてね。これは居ても立っても居られなくなってしまった、というわけだよ。……それにしても、今は外も煩くなってしまっている。何が起きているか、説明しようか?」
そう言って入ってきたのは、シュルツさんだった。
シュルツさんは見た感じ武器を持っていないようだったが、どうやってここまで来たのだろうか――?
そんな疑問を思わず考えてしまうけれど、それはいったん置いたほうがいいだろう。
「説明は……ある程度は把握しています。メタモルフォーズがここに襲撃してきているのでしょう?」
「ああ、その通りだ。だが、どうやらそれがもともと敵と同じ勢力だったようでね……。仲間割れをしているようなんだ。だから、逃げるなら今のうちだ」
成る程。
確かにここで時間を潰している場合じゃない。
そう思った僕たちは互いに頷くと、そのまま牢屋を後にするのだった。
_ ◇◇◇
_ そして。
バルト・イルファは空を眺めていた。彼自身空を飛ぶことが出来ないため、翼が生えているメタモルフォーズの背中に乗っている形になるのだが。
そこに見えたのは、エノシアスタの中心部にある要塞のような建物だった。そこはかつてスノーフォグ国軍の所有物だったが、国の財政悪化に伴い民営団体に売却。しかしながらその広大な敷地のうち、塔のような建物になっている部分は老朽化が進み、結果として改修する資金もなくそのまま廃墟のような形で残されていた。
「それがまさか、テロリストの本拠地になるとはね……」
「お兄様、これからいったいどうなさるおつもりですか?」
そう言ったのは、バルト・イルファにしっかりしがみついて離れない、白いワンピースの少女だった。髪はパステルブルー、背中まで届く艶やかで長いものであった。
バルト・イルファは彼女の言葉を聞いて、彼女のほうに目線を向けた。
「そうだね……。リュージュ様から言われた言葉の通り実行するならば、メタモルフォーズの侵攻と偽ってこの町もろとも灰燼に帰す、かな」
「それでは、この町を壊す、ということなのですね? なんと恐ろしい……」
そう言って彼女は目を細める。
しかし、バルト・イルファは表情を変えることなく、そのまま彼女に語り掛けた。
「何を言っているんだい、ロマ。そんなこと一回も思ったことが無いくせに」
それを聞いて、彼女――ロマは表情をもとに戻し、さらに笑みを浮かべた。
「さすがはお兄様。私のことを解っていましたのね?」
「そりゃあ、ロマは僕の妹だ。それくらい造作でもない」
「きゃーっ! さすがはお兄様!」
そう言ってロマはさらにバルト・イルファへと抱き着いていく。
バルト・イルファはそれについて気にすることなく、再び空を見上げた。
そしてぽつりと、一言呟いた。
「――時は、満ちた」
_ ◇◇◇
_ 対して、建物内のアドハムは冷や汗をかいていた。
「メタモルフォーズがこのタイミングで大量にやってくる……。それはつまり、我々のことをこの町もろとも殲滅するという算段なのだろう。リュージュらしいといえばらしいが」
「大佐! どうなさいますか!」
「我々はすぐにでも戦う準備は出来ております。大佐、ご決断を!」
アドハムの前には、すでに武器を装備している兵士たちが立っていた。
見る限り、アドハムの命令さえあればいつにでも戦う態勢を整えることは可能ということだった。
しかし、アドハムは長考していた。
いかにしてあのメタモルフォーズを捌き切ることが出来るのか、ということについて。
いや、正確に言えばメタモルフォーズだけならば人間の手のみで倒すことは可能だった。
しかし問題は一緒に来ているであろうイルファ兄妹だった。
バルト・イルファについては言わずもがな、問題は妹であるロマ・イルファ。
名前についてはそれしか知らない。アドハムほどの地位があっても、彼女の力については一切知らないのだ。
理由としては、『調整中だったから』の一言で解決してしまうらしいのだが、しかしそれがずっと続いていたため、彼女が戦力として数えられることは殆ど無かった。
だからこそ、アドハムにとってそこがネックだった。
もしバルト・イルファ以上の戦力となっているのだったら?
以上ではなかったとしても、それに比肩する戦力だったら?
メタモルフォーズ戦で疲弊したのちのイルファ兄妹との戦闘のことを考えると、そう簡単に出撃を命令することが出来なかった。
しかし、そう彼が考える間にも、メタモルフォーズの攻撃はこの拠点に向けられている。
つまりもう、手詰まりだった。
バッドエンド。
チェックメイト。
あるいは王手。
どう解釈を変えたとしても、その結論が変わることは無い。
「……だからといって、逃げるわけにはいかない、か」
仮にここで撤退したとしても。
リュージュがそれを許してくれるとは到底思えなかった。
だから、彼は。
漸く決意する。
立ち上がり、彼は兵士に告げた。
「……諸君。我々は今、窮地に立たされている。外を見てもらえれば解るように、空のバケモノが我々の城を破壊しようとしているのだ。だが、だからといって、それを許すわけにはいかない。あの空のバケモノに我々の城を破壊されるわけにはいかない。彼らに彼らの矜持があるというのなら、我々にも我々の矜持がある、ということだ。そして、それがどういう意味を為すか? この戦いは、我々の矜持と彼らの矜持、そのぶつかり合いだ。どちらが強くて、どちらが弱いか。それを簡単に決めることが出来る」
そこで。
一旦言葉を区切り、全員を見遣った。
再び、話を続ける。
「かつて人間は二千年以上も昔からあのバケモノに悩まされ続けてきた。しかしながら、それよりも昔は人間だけの楽園だった。なぜだ? 人間のほうがずっと昔から住み続けてきた。にもかかわらず人間はなぜあのバケモノに虐げられなくてはならない? 圧倒的な力を持っているからか? 圧倒的な肉体を持っているからか?」
首を横に振り、アドハムは目を見開いた。
「いいや、違う。あの肉体に畏怖を抱いているからだ。明らかに『異形』としか言いようがないあの身体。あれを見るだけで悍ましいと思う気持ちがあるからだ。そうして人々は逃げるしかなかった。倒せる手段は充分に存在するのに!」
剣を抜き、それを高く掲げる。
自然、兵士の目線も上に上がる。
「諸君、この戦いに勝つぞ。そして、我々が、この世界のトップに立っているのだということを、もう一度あのバケモノに思い知らせてやるのだ!」
それを聞いた兵士も雄叫びを上げ、アドハムの言葉に同意した。
そうして、一つの小さな戦争が、幕を開けた。
_ ◇◇◇
_ しかしながら。
メタモルフォーズと人間との戦い、その結果は火を見るよりも明らかだった。
メタモルフォーズは一体で人間何人分の戦力になるのか、単純に比較対象になるわけではないが、それがむしろ今回の戦いにおいて人間たちの油断に繋がった。
「……人間というのは、斯くも弱い生き物なのですね。お兄様」
ロマが廊下を歩きながら、隣に居るバルト・イルファに言った。
バルト・イルファは首を傾げながら、ロマの言葉に答える。
「うん? そんなこと、漸く気付いたのかい、ロマは。まあ人間はいつまで経っても愚かな生物だよ。そう、いつまで経っても……ね」
バルト・イルファはどこか遠い目つきでそう言った。
それを見ていたロマは違和感を覚えて首を傾げるが、それをバルト・イルファに訊ねることは出来なかった。
_ ◇◇◇
_ さて。
なんだか騒がしくなってきているが、僕たちは僕たちで行動していかねばならない。
いずれにせよ僕たちにとってその考えは正しいものだったと思うし、現状正しいか正しくないかを考える時間など無いに等しい。
通路を走っていく僕たちだったが、意外にも誰にも遭遇することは無かった。誰かと一回くらいは遭遇して戦闘に発展するものかと思っていたが、どうやらその予想は杞憂に終わってしまうようだった。
「……どうやら戦闘が思ったより激化しているようだ。これなら何とか逃げることが出来るはず……」
「やあ」
声が聞こえた。
その声は出来ることなら聞きたくなかった声だった。
「バルト・イルファ……っ!」
「私もいまーす」
そう言って、バルト・イルファの隣に居た白いワンピースの女性が手を上げた。
今まで見たことの無い人間だったから、少々驚いたけれど、バルト・イルファの隣に居るということは彼と同じ類の存在なのだろう。
バルト・イルファに比べて若干幼い容姿をしているそれは、バルト・イルファの妹のような存在にも見えた。
「……そういえば、君たちに紹介していなかったね。これは僕の妹だよ。名前はロマ。ロマ・イルファ。きっと君たちとはまた出会うことになるだろうからね。先ずは最初の自己紹介、といったところから始めようじゃないか」
「メアリーをどこにやった?」
僕はそんなこと関係なかった。
ただメアリーがどこに消えてしまったのか、それを知りたかった。
バルト・イルファは溜息を吐き、
「まあ。そう思うのは仕方ないことだよね。メアリーは君にとって、いや、正確に言えば君たちにとって大切な存在だ。そんな彼女がいったいどこに消えてしまったのか? それは気になることだというのは、充分に理解できるよ。いや、十二分に理解できる。けれど、僕も上司が居る。あるお方に仕えている。そのお方の方針には逆らえない。はっきり言わせてもらうけれど、いやいやではあったんだよ? 僕だって、女性をああいう風にするのは嫌だった。いや、ほんとうにそうだったんだ。それくらい理解してもらってもいいと思うのだけれどねえ?」
「お兄様。それ以上の発言は……。あのお方に何を言われるか解りませんよ。もしかしたら裏切り行為と思われる可能性も……」
「行為? そんなまさか。僕はあのお方に忠誠を誓っている。決してそんなことはしないよ」
「……お前はいったい、誰に仕えているんだ……。まさか、スノーフォグの王、リュージュだというのか?」
「だとしたら、どうする?」
バルト・イルファは否定も肯定もしなかった。
ただ僕の言葉を受け入れることしかしなかった。
「……お兄様。ここでお話をしている時間は無いものかと」
それを聞いたバルト・イルファは相槌を打った。
「ああ、そうだね。そうかもしれない。だったら、急ごう。僕たちがここにやってきた、本来の目的を果たすために」
「本来の目的、だと?」
「ああ、それは簡単なことだ。……一つだけ忠告しておこう。君たち、大急ぎでここから脱出したほうがいいと思うよ? どうせここはもう持たないから。あとできるなら、なるべく遠くに逃げたほうがいいね。商人の集団にも、出来ることなら関わらないほうがいい」
「バルト・イルファ。なぜおまえがそのことを……!」
「君たちは監視されているのだよ」
バルト・イルファは踵を返し、ただ一言だけそう言った。
「君は予言の勇者だ。それゆえに、世界から注目を浴びている。そして、その注目は君が思っている以上に高いのだということを、君はまだ理解しきっていない。それだけを、先ずは心にとどめておいてもらえればいいのだけれどね」
そして、バルト・イルファとロマ・イルファはそのまま僕たちの前から姿を消した。
バルト・イルファたちと別れて。
なおも僕たちは前に進んでいた。確かにバルト・イルファの言っていた言葉が妙に引っ掛かるけれど、それでも前に進むしかなかった。逃げることが前提ではあったのは確かだ。けれど、それよりも先に僕はバルト・イルファにどうしても聞きたいことがあった。
「……バルト・イルファにメアリーの行き先を聞きたい、だと?」
そう言ったのは、ルーシーだった。
「そうだ。バルト・イルファはメアリーを奪った張本人。ということはメアリーをどこに連れて行ったのか解るはずだろう? それに、シュラス錬金術研究所でもバルト・イルファは登場しなかった。それは即ち、バルト・イルファがメアリーとともに一緒にいたということを示す証にならないか。だから、僕はバルト・イルファに問いかけたかった。でも、あいつはさっさと姿を消した……!」
「でも、考えてみろよ、フル。あの場で僕たちとバルト・イルファが戦いになったとして、僕たちはバルト・イルファを倒すことが出来たか?」
その言葉に、僕は何も言えなかった。
確かにバルト・イルファと僕たちは一度として戦ったことが無い。それに隣には戦力未知数の彼の妹、ロマも居た。二人で戦って、僕たちは四人。戦力では二倍の差がつけられているが、それはあくまでも人数の話。単純に一個人が持つ戦闘力で比べれば、おそらくバルト・イルファのほうが圧倒的だろう。まだその差を埋めることは出来ない。
「じゃあ、じゃあ……。メアリーのことはあきらめろ、と言いたいのかよ?」
「そうは言っていないだろう。つまり、こういうことだよ。今はあきらめるしかない。そして、バルト・イルファを何とか倒すしかない。あとは……そうだな。世界を何とかめぐるか。それにしても少しくらいヒントが欲しいことも事実と言えば事実だけれど……」
僕たちが得ているメアリーの場所についてのヒント。
それはバルト・イルファ自身が示した寒い場所にある邪教の教会。
ただそれだけのヒントだったけれど、場所を示すものとしてはそれ以上のものは無い。
「寒い場所で邪教の教会、と言われるとなかなか難しいものがあるけれど」
そう話を切り出したのはシュルツさんだった。
「実はあれから調べてみたんだ。どこに行けばいいのか、と。そのヒントだけで結びつくものはないか……ということをね。そしたら、一個だけ見つかったものがある」
「あったんですか、邪教の教会が……」
こくり、とシュルツさんは頷いた。
「ああ。その通りだよ。チャール島にあるフォーズ教。その名のとおり、メタモルフォーズを神の使者と位置付けて信仰している邪教が居る。そして、その教会、その本部がある場所こそがチャール島だ。……まあ、それがほんとうにメアリーさんの居る場所かどうかは定かではないが、この世界にある邪教と言えばその程度しかない」
「フル」
ルーシーの言葉を聞いて、僕は彼のほうを向いた。
「この言葉、一度確かめてみる必要があるんじゃないのか? まあ、どこまで確かかはっきりとはしていない。きっとシュルツさんも書物とか文献とか口伝とか……そういう不確かなデータでここまでたどり着いたのだと思う。けれど、百聞は一見に如かず、ともいうだろ。まずはその場所に行ってみて、ほんとうにメアリーが居るかどうか、確かめてみる必要があるんじゃないのか。闇雲に進むよりかは、そちらのほうがベターな選択だとは思うけれど」
「……そうだな」
ルーシーの言葉は長い言葉ではあった。けれど、的確なアドバイスであることもまた確かだった。
僕は頷き、さらに前に進む。
「……じゃあ、一先ずここを出ることにしよう。バルト・イルファの言葉通りに従うのはちょっと気に入らないけれど……。今の僕たちには、それがベターな選択のようだ」
そうして僕たちは前に進む。
けれどさっきのように、不確かな考えではない。
一筋だけ見えてきた光の先に進むために、はっきりとした考えをもって進む。
目的はただ一つ。メアリーを、いち早く助けるために……。
_ ◇◇◇
_ そして。
アドハムは窮地に立たされていた。
あれほどたくさんいた兵士ももう彼を守る数人程の近衛兵しか居らず、しかもその殆どがバルト・イルファとロマ・イルファ――イルファ兄妹によって倒されたものだった。
「……まさか、イルファ兄妹が二人とも投入されるとは。それほどまでに我々は早急に対処すべき存在だと認定された、ということかね?」
「ええ。そうでしょうね。まあ、少なくとも僕はそこまで深いことは知りませんけれど。いずれにせよさっさと諦めたほうがいいとは思いますよ? あのお方が、裏切った人間をどう対処するかはあなただって知らないことでもないでしょう?」
「そうだ。だが、それで恐れていては今回のことなど進めることがあるものか」
アドハムはバルト・イルファを睨みつける。
バルト・イルファは溜息を吐いて、右手を彼らに差し出した。
目の前に立っていた彼らに炎の魔法が射出されたのはちょうどその時だった。
兵士は各々悲鳴を上げて自らの顔を手で覆い隠す。それでも炎の勢いが止まることは無い。それぞれは膝から崩れ落ち、それでも炎の勢いはとどまるところを知らない。地面を何とか回転して止めようと試みるがそんなことは不可能だと言ってもいい。
「無理だよ。そんな足掻きをして僕の炎が消えるとでも? 僕の炎魔法は特別だからね。そんな簡単に消えてしまう炎なんて使わないのさ」
「……何と酷いことを」
「だって仕方ないでしょう? 君たちは国を、スノーフォグを裏切った。だから言ったまでの話だ。そして実際行動に移したからわざわざ僕がここまで出てきて粛清しているということ。ただそれだけ」
確かに。
言葉を、真実を羅列すればその通りだ。
「だからといって……!」
「アドハム大佐。敬意を表して話をするけれど、あなた、いったい何をしたくて国を裏切ったんですか? 予言の勇者の力を借りたかったから? それとも予言の勇者を活用しようと考えていた国を出し抜きたかったから?」
「……」
アドハムは答えない。
それを見たバルト・イルファは笑みを浮かべる。
「答えられない。答えられないでしょうねえ! そんな簡単にボロを出してくれるとはこちらだって思っていませんよ。だってあなたは知略の将軍だ。知略のアドハムともいわれていたくらいですからね。……もっとも、裏では何か隠しているのではないかという噂が出回っていたくらいですが」
バルト・イルファの話は続く。
「でも、だからといってあなたのことを許すつもりなんて到底ありませんよ。僕にも、そしてスノーフォグ自体にも。そもそもあの国の方針からして裏切り者をそう簡単に許すはずがありません。あっと、それはあなた自身が良く知ることですよね? だって一時期はあなた自身が裏切り者の粛清を行っていたくらいなのですから」
「……だから、何だというのだ……! 貴様、バルト・イルファ、お前は何も感じないのか? 人間を殺すことについて。あれが、リュージュが言っているのは偽りの平和だ。あいつが言っていることを忠実にこなしたとしても、世界に平和は訪れんぞ!」
「だから、」
「は?」
「だから、どうしたというのです?」
バルト・イルファはにっこりと笑みを浮かべた。
まるで新しい玩具を与えられた子供のように。
まるで何も知らない無垢な子供のように。
アドハムを見下しているその表情を、彼は気に入らなかった。
彼の足元に静かに倒れこんでいる彼の部下たちのためにも、せめて一矢報いたかった。
「……バルト・イルファ。貴様、こんなことをして……。お前たちの考えは確実に世界を平和にするものではない! むしろその逆だ。世界を滅ぼしかねないことだぞ!」
「僕を説得するつもりですか? いや、この場合は説得ではありませんね。改心、なのかなあ? いずれにせよ、そんな薄っぺらい説得は無意味ですよ。むしろ、そんなことで解決するとでも? あなた、だとすれば勘違いも甚だしい。それに、僕の実力を見縊っていると言ってもいい。……まあ、だからこそ今回の反乱を起こしたのかもしれませんけれど」
溜息を吐いて、バルト・イルファは言った。
アドハムは腰につけていた剣に手をかけた。
それを見て、バルト・イルファは頷く。
「ああ。戦うのですね? だとしたらどうぞ。僕は刃を持たない人間とは戦いたくありません。出来ることなら臨戦態勢をとっている人間と戦いたいですし」
舐めている。
バルト・イルファは、戦闘を舐めている。
アドハムはそう思っていた。だからこそ、彼はバルト・イルファを許せなかった。
そもそもスノーフォグの軍について、簡単に説明する必要があるだろう。スノーフォグの軍は歩兵が優秀な軍隊として有名だった。ほかの二国が優秀な魔術師で軍隊を率いているのに対し、スノーフォグは未だに非魔術師をトップに置いていた。その時点でほかの国と違っている点と言えるだろう。
しかし、スノーフォグは優秀な魔術師を持っていないわけではなかった。バルト・イルファがその始まりと言われていた。
魔術師。それは人工的に作り出すことも出来るし、もともと自然に――正確に言えば、魔術師の家系から――生まれることもある。実際は後者が大半を占めており、その家系は元をただすと神ガラムドの血筋――祈祷師の血筋をひいているといえるだろう。
そしてバルト・イルファはスノーフォグが秘密裡に作り上げた、世界で最初の人工的に作り上げた魔術師だった。
「……魔術師風情が、軍の、戦いのノウハウも知らないで! ずけずけと戦場に上がり込みおって……。そして、そう見下すと? ふざけるな!」
「別に僕はあなたの人格そのものを否定するつもりはありませんが……正確に言えば、それは僕のせいではありません。時代のせいですよ、アドハム大佐」
悲しい表情で、バルト・イルファはアドハムを見つめた。
「若者が、魔術師が、何が解るというのだ! そんな解ったような眼で、私を見るなああああああああああああ!!」
そして。
剣を抜いたアドハムはバルト・イルファに切りかかった。
だが。
彼の剣が、バルト・イルファに届くことは無かった。
直後、彼の視界は水中に沈んでいったからだった。
「忘れていたかどうか解りませんが」
左から声が聞こえた。
そこに立っていたのは白いワンピースの少女――ロマ・イルファだった。
ロマ・イルファは冷ややかな視線を送りつつも。笑みを浮かべていた。
「……私も戦いの相手として、存在しているのですよ、アドハムさん?」
そうして、アドハムはそのまま水の檻に閉じ込められ――そのまま意識を失った。
_ ◇◇◇
リュージュは王の間にて報告を受けていた。
「アドハムは、最後までバルト・イルファに盾突き、反逆する意志が見られたために水死させたとのことです。詳細を確認しますか?」
「いや、いい。別にわざわざ人の死に様なんて確認したくない」
そう言ってリュージュは部下の報告を切り捨てると、窓から外を眺めた。
外は二つの月が見えていた。
「あの二つの月は、今日も我々を見つめている。我々が月を見つめているとき、月もまた我々を見つめている……。ふん、哲学とは難儀なものだ」
リュージュは目を瞑る。
「私はこれから少しの間眠る。絶対にこの部屋に誰も通すなよ」
「はっ」
敬礼をして、部下の男は部屋を立ち去って行った。
_ ◇◇◇
_ 僕たちがバルト・イルファに出会ってから少しして。
漸くその迷宮めいた場所から脱出した直ぐの出来事だった。
メタモルフォーズたちによって、アドハムの居城はいとも簡単に破壊されたのだった。
僕たちが居るにも関わらず、僕たちに攻撃をしてくるメタモルフォーズは一匹たりともいなかった。まるで今回は僕たちがターゲットではないと暗に示しているようだった。
「……メタモルフォーズたちのターゲットは、やはりアドハムだったということか……?」
「それにしても。バルト・イルファの言葉を真剣に受け止めると、これからあの商人たちのボディーガードをしないほうがいいのかもしれないな。もしかしたら、俺たちが原因で狙われる可能性も十分に有り得る」
言ったのはルーシーだった。
そして、その考えは僕も一緒だった。これ以上、他人には迷惑をかけられない。
だから、僕はシュルツさんに言った。
「シュルツさん、大変言い辛いのですが……」
「何を言っているんだ。まさか、こんなところまできて僕と離れるとは言い出さないだろうね?」
「え……?」
「だから、言っているんだ」
シュルツさんは溜息を吐いて、改めて僕たちに言った。
「僕もここまで来たら乗り掛かった舟だよ。僕もメタモルフォーズにはいろいろと未練があるからね……。まあ、はたから見ればただの勘違いと言われるかもしれないけれど、それでも僕にも戦う理由がある。それに、足も必要だろ?」
ちょうどその時だった。
シュルツさんの竜馬車が、僕たちのところにやってきたのは。
「……竜馬車はほかの馬車と違ってスピードが出る。さすがにトラック程のスピードは出ないけれど……。それでも、馬車に比べれば段違いだと思うよ。それに、徒歩でこのスノーフォグを、世界を歩くつもりだとするならば、それは少々無謀なことだと思うな」
やれやれと言った感じでシュルツさんはドラゴンの頭を撫でる。
ドラゴンは頭を撫でられてとても嬉しそうだった。
「……フル。確かにその通りじゃないか?」
ルーシーも賛同していた。
そしてレイナについても――もう表情を見た限りでは、何も言うことは無かった。
僕は頷く。
「シュルツさん、お願いできますか。僕たちのメンバーに」
「ああ、よろしく頼むよ」
こくり、と頷いたシュルツさんを見て、僕は彼に右手を差し出した。
そしてシュルツさんも右手を差し出して、僕たちは固い握手を交わすのだった。
_ ◇◇◇
メタモルフォーズの背に乗っていたバルト・イルファは、ロマの言葉を聞いて彼女のほうを向いた。
ロマはバルト・イルファの隣に、彼を見つめるように座っていた。
いつも彼女はこうだった。バルト・イルファとともに行動し、バルト・イルファの選択に追随する。
だから、彼の選択イコールロマの選択ということになる。
「……そうだね。僕としても彼らの行動には目を見張るものがあると思うけれど……、それ以前に僕たちはリュージュ様にお仕えしている身。そうともなれば結論は直ぐに見いだせるものだと思うけれど?」
「お兄様としては追いかけたい、ということでしょうか」
ロマははっきりとそう言った。
「そういうことになるね。興味がわいた、とでも言えばいいかな。ほんとうは任務をきちんとこなさないといけないのだけれど」
「いえ。別にお兄様を悪く言っているつもりはございません。ただ、私はただ、お兄様の考えをお聞きしたかっただけなのです。お兄様がどのような行動をとられるのかが、気になって……」
「まあ、そうだね。僕の考えはつまり、そういうことだよ。今から戻ったとしても、どうせ報告は別の誰かがしているだろうからね。それに、リュージュ様も僕たちの行動を、逐一とは言わずとも監視魔法で確認していることだろうし」
「それでは。やはり、予言の勇者を追いかけることはしない、と」
「出来ないなあ。それはやはりリュージュ様への裏切りになってしまう。それだけは避けておきたい。だって、僕たちはリュージュ様に作られ、リュージュ様のために生きている。そうだろう?」
ロマは頷く。
それが相槌であるのか、肯定であるのかバルト・イルファにはいまいち判別がつかなかった。
「……とにかく、僕は考えをまとめているということだ。いずれにせよ、予言の勇者が次にどういう行動をとるのかはとても気になるけれどね。もし次に行くとすれば……」
そう言って、バルト・イルファは立ち上がり――呟くように続けた。
「東にある港町にして、スノーフォグの首都。ヤンバイトだろうね」
そして、彼らを乗せたメタモルフォーズもまた、東に向かって飛び去っていくのだった。
竜馬車に乗って数日。
結局僕たちはあれから商人の人たちに何も言うことなく、エノシアスタを後にした。バルト・イルファの発言を真に受けたわけではないけれど、いずれにせよ、僕たちはその影響を考えなさ過ぎていたことも事実だった。
予言の勇者という冠は、僕たちの想像以上に、僕たちを苦しめていた。
「……見えてきたぞ」
シュルツさんがぽつりとそう言った。
それを聞いて僕は我に返り、窓から外を眺めた。
荒野の中に突如として現れた青い海と、港町と思われる城壁。そして城壁の中には堅牢な城が建っている。
「あれが、スノーフォグの首都……ヤンバイト」
「そうだ。あれがスノーフォグの首都にして世界有数の港町、ヤンバイトだ。それゆえ、あの町は食の都と呼ばれているよ。世界から様々な食べ物がやってくるからな。そういわれるのは当然といえば当然だろう」
「ヤンバイト……食の都、か。なかなか美味しいものがたくさんあるのかな?」
「そりゃあ、食の都っていうくらいだからたくさんの食べ物があると思うぞ。それに量だけじゃなくて、種類も多いと思う」
レイナの言葉に僕はそう答えた。
そうしてそれぞれの思いを抱きながら、僕たちはヤンバイトへと向かうのだった。
_ ◇◇◇
_ 通りを歩くたびに、いろいろな香りが鼻腔を擽る。
店の前に立っているいろんな人は商品と思われるものを手に持ちながら、それぞれの商品が一番素晴らしいことをアピールしながら、声をかけていた。商品を売ることが商人にとって一番の儲けになるから無理やりでも売ろうと思う気持ちは解らないでもないけれど、あまり押しつけがましいことをしてしまうと、購買意欲を削いでしまうことになる。
だから、商人は適度なバランスで客寄せを行うことが求められる。まあ、そんなことは消費者には関係ないことだと言ってしまえば、それ以上どうしようもない事実ではあるが。
「……それにしても、ほんとうにすごくたくさんの商品が販売されているね……。食の都、とは言うけれどそれ以上に物が溢れすぎているのかもしれないな」
僕は冷静にそう分析してみたけれど、
「そうかもしれないけれど、やっぱり物って集まるべくして集まるものだと思うよ。実際に、ヤンバイトの人口は世界で二番目。それに港町として港運が発達しているから……。それだけを考えると、世界のどこよりも物がたくさんやってくるのは頷けるんじゃないかな。まさに、集まるべくして集まった、という感じだよ」
どうやらルーシーもルーシーで冷静に分析していたようだった。
それは僕にとっても想定外のことだったけれど、その『想定外』は嬉しい誤算だったといえるので別にどうでもいいことだった。
「それにしても問題は宿、か……。まだ夕方とはいえ、人が多い。ヤンバイトの宿はたとえどれほどグレードが高い場所であっても金さえ払えば満室に一つ空きを作ることだって出来る。……それだけを言うと荒くれものの街に見えるかもしれないけれど、でも実際はそんなことなんてなくて、正確に言うと、金さえあればどうとでもなる。それがこの町の常識とでもいえるだろうね」
「……成る程。金さえあれば、ね……」
要はまともに行政が動いていない、ということだろう。
あまりにも人が増えすぎて、それに行政が追い付いていない、ということなのかもしれないが。
「それにしても、人が増えたってことだよな? 人が増えたってことは、やっぱり物も増えるという感じでいいのか?」
「そうだね。人が増えた、ってことだろうね。ここは港湾としても有名だから、ここからハイダルクやレガドールに移動することもできるし。世界中を移動している船だっているからね。だから増減は激しいと思うよ」
船、か。
やっぱり船が必要なのかなあ……。また前みたいに定期船を使う手もあるけれど、そうなると定期船がない場所には移動できない、ということになってしまうし。うーん、RPGみたく、特定の場所にワープできる魔法でもあればいいのだけれど。
「やっぱり船かあ……」
「さすがに竜馬車は海を泳げないからねえ」
シュルツさんはそう言って、空を見つめた。
もし竜馬車が海を泳げるのならば、それを使って海を泳ぐことも可能かと思っていたのに、さすがにそこまで都合よく物事が進むことは無かったようだった。
「とりあえず、もし船が欲しいと思うのならば船を見に行くのもいいんじゃないかな? 生憎、この街にはドックがあったはずだし……」
「ドック?」
「船を作ったり修理したりする施設のことだよ。船自体どれくらいの値段がするのか解らないけれど、まずは見てみないと何も解らないし」
確かにそれもそうだった。
ただ、お金がないこともまたまぎれもない事実だった。
一先ずドックに行ってみないと何も進まない。そう思った僕はシュルツさんのいうことを信じて、ドックへと向かうのだった。
_ ◇◇◇
_ ドックは当然のことながら、海の近くに存在する。
「ドックなんて来たことないけれど、こんな活気のある場所なんだね……」
ルーシーはきょろきょろと周りを見渡しながら、そう言った。
はっきり言ってそういう行為は目立ってしまうのでできればやめてほしかったのだけれど、今の彼にきっとそんなことを言っても無駄なのだろう。
「おう。どうした、こんなところに子供がいるなんて。ここは子供がうろつく場所じゃないぞ?」
そう言ってやってきたのは筋骨隆々のタンクトップを着た男性だった。何かの資材を運搬しているようで、汗をかいていた。
男性の話は続く。
「……まさかとは思うが、船が欲しいのか? だったらここじゃなくて、販売所に言ったほうがいいぞ。ここはあくまでもドックだ。ドックの意味を理解しているか? ドックは船を開発・建造する場所。対して販売所は名前の通り船を販売する場所だ。船は開発しない限り、販売することは出来ないがドックで船の販売は出来ない。建前上、別々にしておく必要があるというわけだからな」
ぶっきらぼうに見えるけれど、案外丁寧に教えてくれるんだな。
僕はそう思って男性の話を聞いた後、男性にお礼を言って、販売所のほうへと向かうことにした。
_ 販売所はそう遠くない距離にあった。正確に言えばドックの内部、その中心部にあった。
中に入ると恭しい笑みを浮かべて髭面の男がさっそく声をかけてきた。
「おやおや、いらっしゃいませ。若いのに、船を買いに来た。そういう感じでございましょうか? それにしても、最近の若者はかなり堅実ですねえ。ちょいと驚いちゃいましたよ。おっと、これはオフレコでお願いいたしますね。……はてさて、どのような船をお望みですか?」
早口でまくし立てるように話をする男は、いつもこのように話をするのだろう。先手必勝を地で行くとはまさにこのことだと思う。
「……いや、とりあえず少し船を見に来ただけです。欲しいことは欲しいのですけれど」
「さようでございますか。それではごゆるりと。何か用事がございましたらまた私に言ってください。それでは、以上よろしくお願いします」
そう言って男はカウンターの向こうへと姿を消した。まあ、いつもずっとついてくるよりかはマシかな。こういう店員は最初だけ簡単に対応しておけば問題ないだけのこと。
はてさて。
問題はここからだ。
僕たちが乗ることのできる船を、如何にして調達するかということについて。
当然、非合法的手段はあまりよろしくない。ラドーム学院の生徒、という称号がある以上それを後ろ盾に悪さをすることは無理だ。というか不可能と言って過言でない。
だったらどうすればいいか。
一番まっとうな手段で挑むならば、船を購入するに尽きる。けれど、船を購入するといっても――。
「……やっぱり、それなりにするね」
販売所には実際に船が置かれているわけではない。船の写真と値札が置かれており、店員にその船を指定して見せてもらうことが出来る仕組みになっているらしい。どうして知っているかというとショーウインドーにそう書かれた紙が置かれているからだった。
船の値段の相場が実際にどれくらいになるのかは定かではないが、並んでいる商品はすべて僕たちがもっている全財産をはるかに上回るものだった。仮にハイダルク王からもらった路銀を一切消費せずにここまでやってきたとしても、あまりに足りない。
「やっぱり購入するのは無理か……」
僕は店員に聞こえない程度のボリュームでそう呟いた。
「いらっしゃいませ。……おや、どうなさいましたか?」
カウンターのほうから声が聞こえて、僕たちはそこでまたお客さんがやってきたのだと理解した。それにしても船を買うなんて安い買い物では無いと思うのだけれど、よくお客さんがやってくるのだと思った。もしかして金持ちはシーズンで買い替えることもあるのだろうか? それこそ、衣服か何かのように。
「はあ。……わかりました。別にあなたたちに逆らうつもりなんてありませんよ。誰を求めているのか、お上の意向はさっぱり理解できませんが、とにかくお探しください」
カウンターの店員のトーンがすっかり下がっているのに、少しだけ時間を要した。
いったいどうしたのだろうか。そう思って僕は踵を返して――。
「フル・ヤタクミだな?」
そこに立っていたのは兵士だった。冷たい目をしていた。
兵士はこちらに目線を向けたまま、言った。
「国王陛下がお呼びだ。何を目的としているのかさっぱり解らないが……とにかく、予言の勇者を一目見たいと仰っている。このまま王城に来てもらうことになるが、構わないな?」
「……解りました」
その言葉に、ノーとは言えなかった。
_ ◇◇◇
_ 高台に位置するヤンバイト城までは、ハイダルクと同じように馬車を利用した。ちなみにシュルツさんの竜馬車はこの町にやってきて早々に確保していた宿で留守番をしている。珍しい馬車であることには変わりないが、『操縦するのは僕だけしか出来ないから、盗まれることは先ずあり得ない』と言っていたので問題ないのだろう。たぶん。
兵士は馬に乗ったままこちらに会話を投げかけることは無かった。馬車の中では僕たちがただ静かに目的地に着くのを待つだけだった。
会話が生まれない時間は、はっきり言って不毛だった。けれど、皆緊張していたのだと思う。ハイダルクではない別の国のトップに謁見する。しかもこちらから申し込みなどしたのではなく、先方からの要望だというのならば猶更。
高台にある雪の城。
それは見るものを圧倒させる、荘厳な雰囲気を放っていた。
ヤンバイト城を見たとき、僕はファーストインプレッションとしてそう感じ取った。
ヤンバイト城に到着し、僕たちは馬車から降り立つ。
「こっちだ」
しかし兵士はそのまま息を吐く間も与えず、僕たちを誘導していく。
「いったい、兵士は何を考えているのだろうね? ……ふつう、少し休憩の時間くらい与えてくれるものじゃないか?」
「余程急いでいるんじゃないか。そんなに早く僕たちに出会いたいのか、という話に繋がるけれど」
僕とルーシーは兵士に聞こえない程度のトーンでそう言った。
「そうなのかなあ……。だとしてもこんなに客人を焦らせることttえあるのかい? まあ、国ごとの風習みたいなものがあるのかもしれないけれど。そうだとしてもちょいと不愛想な感じではあるよね」
そんなことを言っている暇などない。
まずは兵士の後をついていく。ただそれだけだった。
そして僕たちは兵士の後を追いかけていくのだった。
_ ヤンバイト城、国王の間。
荘厳な雰囲気を放っているその空間は、やはりなかなか慣れるものではなかった。
一度ハイダルクで経験したことがあるといえ、あまり経験しても意味はないのだと思い知らされる。
それはそれとして。
「突然呼び立てて済まなかったな、フル・ヤタクミにルーシー・アドバリー。それに、その仲間たちよ」
声が聞こえた。
とても優しい声だった。
僕たちは慌てて跪き、首を垂れるが、
「よい。特にそのようなことをせずとも、先ずは話がしたかっただけだ」
そう言って笑みを浮かべるだけだった。
その女性はとても美しかった。赤と白を基調にした服装――僕がもともと居た世界では巫女服とでもいえばいいのだろうか? 白い服に、赤い袴をアレンジした雰囲気、といえばいいのかもしれない。ああっ、くそ。こういうときに語彙力があればもっと伝わるのにな。なんというか、もう少し本を読んでおくべきだったかもしれない。
「名前と職業は知っているだろう。だから簡単に説明しておこう。私の名前はスノーフォグ国王、リュージュだ。こんな遠いところまでよくやってきてくれた。さて……なぜここまでやってきたのか、先ずはそれをお聞かせ願えないかな、予言の勇者殿」
「ここに来た理由、ですか……」
ここで僕は悩んだ。
正直に言ってしまっていいのだろうか、ということについてだった。
正直に言ってしまえば、メタモルフォーズがこの国から飛来してきたから、と言ってしまえばいい。だが、この国の王の前でそう言ってしまって何が起きるか解ったものではない。だから出来ることならそんな危険な賭けはしたくなかった。
では、適当に嘘を吐けばいいのか?
いや、でもすぐにそんな都合のいい嘘が浮かぶほど頭の回転が速いわけではない。
ならば、どうすればいいか。真実を告げるのも嘘を吐くのもリスキーだ。
それ以外の、第三の選択肢を考えないといけないのだが――。
「別に、言葉を飾る必要は無いぞ?」
そう言ったのはリュージュ王だった。
リュージュ王は、優しく、柔和な笑みで微笑んだまま、僕のほうを向いて、
「何か言葉を考えているように思えるが……もしかしてここでは言い辛いことだったか? 別にそんなこと関係ない。私の心は寛大であるからな。予言の勇者殿が一つ二つ失言したところで私の機嫌が損なわれることはない。むしろそんな程度で損なわれてしまっては、国王失格というものだよ」
「そういうものですか……?」
「ああ。だから安心して言ってもらっていい。さあ、この国に来た目的は?」
そう言ったのならば、正直に言うしかないだろう。逆にここで嘘を吐いてしまってはそれこそ何が起きるかわからない。逆鱗に触れてしまい折檻される可能性も考慮しないといけないだろう。
だからこそ、慎重に言葉を選んで、僕は言った。
「――実は、この国からメタモルフォーズが飛来してきました。僕たちはそれを調査するためにこの国にやってきました」
「ほう。メタモルフォーズがこの国から……。成る程。それは私の前では言えないことだな。その言葉は即ち我が国をメタモルフォーズの発生源として疑っているということに繋がるわけだからな」
「実際、軍部の人も……名前は確か、アドハムだったかと思いましたが……メタモルフォーズの開発に関与していました。研究施設があって……そこでメタモルフォーズを研究していたようなのです」
「ふむ。……メタモルフォーズの研究施設、だと? それにアドハムが関与していた、と言いたいのか?」
ずい、と身体を起こしてリュージュ王は言った。
流石に言い過ぎたか――そう思って僕は謝る準備をしていたのだが、
「成る程。しかし、まさかあのアドハムがそのようなことをしていたとは。ほかには? アドハムがした行為でもいい。君たちがこの国で得られたメタモルフォーズについての情報を教えてくれないか。もしかしたら、力になれるかもしれないぞ」
「え、……ええ。確か、アドハムは別の勢力に倒されてしまいました。バルト・イルファ……だと思います。とても強い魔術師が居るんです。きっと彼に殺されてしまったものかと……」
「その、バルト・イルファとやらはとても強い魔術師なのか?」
僕はその言葉にこくり、と頷いた。
それは真実だ。そこで嘘を吐いて虚勢を張る必要はなかった。虚勢を張ったところで僕の危険が増すだけだ。ならばここは正直に言ってしまったほうが後が楽だと――僕はそう思った。
「……そうか、それほど強い魔術師がアドハムとともに、少しの間であったとしても行動していたとは。そしてアドハムの勢力は何らかの理由でその魔術師の勢力と意見の相違があったのだろう。そうして倒されてしまった。力こそすべてだ。言葉がうまく通じなかったら、力の強い弱いですべてが決まってしまう。ほんとうに、ひどく残念な世界だよ。今の世界は」
リュージュは溜息を吐き、肘あてに肘をつく。
そして僕たちを舐めるように見つめると、大きく頷いた。
「それにしても、魔術師に狙われるほど、お前たちは何か喧嘩を買ったということ……ではないだろうな。いずれにせよ、『予言の勇者』というレッテルが君たちの運命をそうさせているのだろう。レッテルを張られた人間というのも滑稽で可哀想な存在だ。……っと、当事者の前で言う話ではないかもしれないが」
「?」
リュージュの発言はもうどこかに飛んで行ったような感覚だった。
正確に言えば、独り言。
もっと言えば、虚言。
……さすがにそこまで行くのは言い過ぎかもしれないが、いずれにせよ、そういう判断に至る可能性があるほど、リュージュは周りの人間を放っている発言しかしていなかった。まるでフルフェイスのヘルメットを被って綱渡りをしているように。
実に危険。
実に奇妙。
それほどにリュージュの発言はどこか的外れで、見当違いで、不明瞭だった。
「……とにかく、これ以上の発言を君たちから得られることは出来ないだろう」
リュージュの発言は僕たちに対する諦観よりも、自分自身の考えの掘り下げがうまくいかないことへの気持ちを表しているようだった。
リュージュは隣の兵士に指示を仰ぎ、
「いずれにせよ、予言の勇者ご一行はひどく疲れているようだ。もうここの宿は決めたかね? 決めていないのであればこの城の宿舎を使用するがいい。生憎、設備こそ古いものではあるが浴場もある。食堂もある。それに……私も一つ君たちにある依頼をしたい。そのためにも、先ずはそれくらいの前払いをしたいというものだ」
「前……払い?」
「知恵の木の実について、どれくらい知っている?」
知恵の木の実。
リュージュの発言は簡単なことだった。
知識の説明を、明示。
正確に言えば、どこまでその単語について知っているか、知識量の提示。
いずれにせよ慎重に解答する必要がある質問であることには何ら変わりなかった。
「……知恵の木の実は代償無しで錬金術を行使することのできる夢のアイテムだ。正確に言えば、知恵の木の実はその名前の通り、この星の知識が詰め込まれている。いや、この場合は知識というよりも記憶といったほうがいいべきか。いずれにせよ、そのエネルギーは莫大なエネルギーだ。だからこそ知恵の木の実は伝説のアイテムとして知られていて、それを欲している錬金術師も少なくない」
僕がどう答えるか考えているうちに、リュージュが先にそう答えた。はっきり言ってまさか先に言われるとは思っていなかったのだが、しかし言われてしまったものは仕方が無い。
リュージュの話は続く。
「だが、その伝説のアイテムをいとも簡単に開発することの出来る物。それが開発されたとしたら?」
それを聞いて、僕たちは目を丸くした。
伝説のアイテム――知恵の木の実の錬成。それが簡単にできるアイテムが開発された?
もしそれを使って知恵の木の実を量産されてしまったら……正直、考えるだけでも恐ろしい。というより、なぜそのようなアイテムを開発したのか――という点が気になるところではあるけれど。
「もともと、わが国の軍事技術の転用のために開発されたそのアイテムだが、もう平和になってしまったからな。使わずに設計図は放置されていたのだよ。……だが、それをあいつが奪った。そのアイテムの開発者であるタイソン・アルバが、な」
「タイソン・アルバ……」
僕はリュージュから聞いたその名前を反芻する。
リュージュはそれを聞いてこくりと頷くと、ある書状を差し出した。
「今日はもう遅いから……明日、正式にこれを通知することになるが、いまドックには完成したばかりの船が数多く並んでいる。その中でも最新の船を君たちに与えよう。これは、それが記載された書状だ。これをドックの人間に見せればすぐにそれを渡してもらうことができるはずだ」
それって……!
つまり、願ったりかなったりじゃないか!
僕たちにとってみれば、メアリーを助けるためにも船が欲しかったところだ。
その船を、しかも無料で、最新のモノが手に入る!
僕は勝手に心の中でうれしく小躍りしていた。
「……ただし、条件をつける。その船の書状を渡すのは……タイソン・アルバという科学者を探してここに連れてくる。それが条件だ。ああ、もちろん、タイソン・アルバは海の向こうに逃げたという可能性も考えられるから、そのために船を与えると思ってもらえばいい。もちろん、タイソン・アルバを捕まえたあとも返してもらう必要はない。それは君たちの船になるわけだからな」
そこまで言って、リュージュは立ち上がる。
「……さあ、ここで改めて質問しようか? タイソン・アルバを捕まえてくれるかな。もちろん、拒否してもらうことだってかまわない。君たちは予言の勇者と呼ばれている存在。その第一目標は世界を救うことなのだから」
僕たちに、選択肢なんて無かった。
リュージュは犯罪者を捕まえてほしい。
僕たちはメアリーを助けるためにも船がほしい。
双方の目的が、これまで以上に合致している。
そうして、僕たちは――その言葉にしっかりと頷いた。
_ ◇◇◇
_ はてさて。
結局、その日僕たちはヤンバイト城の部屋にて眠ることとなった。食べ物も食堂にある料理を食べていい、ということだったので有り難くそちらを頂くことにした。そこについては国王の許可を貰っているので遠慮なく頂いたほうがいいだろう。もし何かイチャモンをつけてくる人間が居れば、そう発言して処理すればいい話だし。
しかし、生憎――というか結局、僕たちのことをとやかく言う人は居なかった。どうやら早くに根回しをしてくれたらしい。それはそれで大変有り難いことだと思う。
さて。
夕食は美味しいものだったかといわれると、はっきり言って普通だった。『普通』をどの段階で言えばいいのか……という話になってしまうかもしれないが、正確に言えば、だれも僕たちが居ることについて疑問を持たなかった。
「……味はそれほど、という感じなのかな」
プレートに乗せられているのは、それぞれ様々な種類の色をしたペーストだった。話によれば機械で作られているためか、そのような形式がここでは主流なのだという。栄養もしっかり管理されているので何ら問題はないらしい。
とはいえ。
「……食べた感じはしないけれどね」
ルーシーの言葉に、僕は一瞬頷くかどうか躊躇ったが、少しして僕はルーシーの言葉に同意するように頷くしか無かった。
確かにこれなら栄養はきちんと管理されているのだろう。けれど、『食べた』という感じが得られない。……何と言えばいいのだろうか、ええと、満足感? そういうものが獲得出来ない、とでも言えばいいのだろうか。いずれにせよ、僕たちはそれに不平不満を言うことはなかなか出来るものではなかった。
_ 客室。
正確には、兵士詰所内部にある一室。
一応貸し切りとはしてくれたものの、部屋のスペースは四人で宿泊するには狭い。ベッドが二つしか無いということもあるが。
一応敷布団と掛布団は貸してくれたけれど、板張りの床にそれを敷くと腰が痛くなりそうだ。
いずれにせよ、寝ない限り明日はやってこない。
結局ベッドに寝るのは僕とレイナ、ルーシーとシュルツさんが布団で眠ることとなった。
本当は僕ではなくてシュルツさんが眠るべきだと思ったのだけれど、
「君が予言の勇者という地位にいることははっきり言って知らなかった。だからこそ、ここは君にその場所を譲るべきだと思うよ。それに、君が僕にここを譲ろうとしている一因は、年長者だからという単純な理由からなのだろう? もしそうであるならば、そんなことは気にしてもらわなくていい。君は予言の勇者なんだろ。だったら余計なことは考えないほうがいい」
……という、長い理由を述べたまま頑として動かなくなってしまったので仕方なくベッドに眠ることになった、ということだった。
「……ということで、眠ることになったわけですが」
床に布団を敷いてしまうともう歩くスペースがない。足の踏みどころがない、とでもいえばいいのだろうけれど、まさにその通り。結局、僕とレイナがベッドに腰かけ、ルーシーとシュルツさんが布団に座っている形になっていた。これだけ見るとお泊り会か何かか、と疑われてしまうかもしれないがそんなアットホームな雰囲気が流れていることもまた事実なのであんまり強く言えない。
「明日の予定を改めて、説明しておくことにしようかと思う。この場合、説明というよりも整理になるのかもしれないけれど。……ええと、明日は朝起きて書状をもってドックへ向かいます。そして、新しい船を手に入れる。だけれど、問題はそこから。そこからどうするか? そのタイソン・アルバを捕まえることは別に問題ないのだけれど、彼がどこへ向かってしまったのか? それは国王……ですら解らなかった」
「確かに。それは問題だよな。それは話を聞いていて思っていた。どこへ向かったのか、はっきりしていない。海に逃げた、とは言っていたがそれはあくまでも可能性にすぎない。その可能性が消えている可能性だって十分、いや、十二分に有り得るわけだし」
「そうだよね……。ルーシーもフルもそう思っているよね。私も実はそう思っていた。けれど、国内の土地をやみくもに探すよりかはそちらのほうがいいんじゃないかな、って思うのよ。それに、もし海に逃げたのならばドックの人に聞いてみるのもいいアイデアなんじゃない? ドック、あるいは港は海からやってきた人も多くいるはず。そういう人たちなら海の向こう、あるいは海で得た情報を教えてくれるかもしれないし」
シュルツさんは僕たちの言葉にただ無言で頷くだけだった。
というわけであっという間に結論が出た。
僕は溜息を吐くと、ゆっくりとベッドから立ち上がる。
「……それじゃ、満場一致ということで、明日朝ドックで船を受け取るとついでに、港やドックでタイソン・アルバの情報を収集する。そうして改めて海に出る。……それでいいかな?」
その言葉に、誰も言い返さなかった。
僕はそれを了承という意味で受け取ると、右手を掲げる。
「それじゃ、何だか寄り道のように見えるかもしれないけれど……、メアリーを助けるためにも、明日からがんばるぞ!」
その言葉に、僕たちは大きく頷くのだった。
_ ◇◇◇
_ 王の部屋。
……その単語を聞いてどういうイメージを思い浮かべることが出来るだろうか。
正確に言えば、その部屋は王といろんな人間が出会うことの出来る部屋ではなく、王のプライベートの部屋ということになる。だから、そこに入ることが出来る人間は数少ない。
改めて、王の部屋について質問しよう。
その単語を聞いて、どのようなイメージを抱くだろうか?
王の部屋はプライベートな空間だ。だから簡単にほかの人が入ることは許されない。だから、正確に言えば、王が認めた人間しか入ることを許されない。それ以外の人間が勝手に入ってしまっては、賊か何かと疑われてしまう可能性もある。
王の部屋に一人の男が跪いていた。
バルト・イルファ。
炎属性の魔術を得意とする魔術師。それがいま王の前で敬意を表している。
「……予言の勇者がやってきたわ。やはり実物は違うわね。ずっと透視魔法を通して見つめていたからかしら。心なしかもっと溢れるオーラが違う。はっきり言って、あのまま放っておいてはマズイわね。非常にマズイ」
「では、どうするつもりでしょうか? 僕とロマはあなた様の命令でいつでも動く準備が出来ていますが」
「予言の勇者についていきなさい。もちろん、気づかれない程度のスニーキングでね」
「……言われている意味が解りませんが?」
「タイソン・アルバは、私が今もっと必要としている人物。当然よね。知恵の木の実を抽出する装置を開発するのだから。けれど、彼を探すのも予言の勇者に手伝ってもらおうって話。もしも、彼らがそのままタイソン・アルバを捕まえてそのまま連れてきてくれればいいのだけれど、連れてこなかったら……」
「僕が確保してこい、ということだね?」
「その通り。だからこそ、あなたには頑張ってもらいたい。その意味が解るわね、バルト・イルファ。あなたに今から任務を与えるわ、今からタイソン・アルバを探して、先ずはあの研究を再開するか否か聞くこと。そうしてその解答によっては……」
「燃やしてしまって構わない、と?」
「ええ。もし帰らないというのであれば、非常に残念ではありますが……彼は必要ありません。さっさと殺してしまいなさい。私たちの目的と、彼の研究が外部に漏れないためにも」
「了解。それじゃ、僕も明日から本格的に行動する、ということでいいのかな? 予言の勇者一行はさすがに深夜に外出することはしないでしょ」
「当然。それくらいはしてもらわないとね。それに、仮に深夜に外出するようだったら兵士に理由を聞いてあまり深夜外出するメリットが無さそうなら朝に外出するように促すよう言っているからそれについては問題ないでしょう。……予言の勇者が人の言葉を単純に無視するような大馬鹿者じゃなければ、の話だけれど」
「……それについては問題ないでしょう。何回か予言の勇者と邂逅したことがありますが、どれも人の話に噛みついてきたことばかり。それがヤバイ状況であるにも関わらず、です。売り喧嘩に買い喧嘩とはよくいいますが、それを地で行く感じですよ。だから、彼は周りの仲間が止めなければどんどん自分が良いと思った方向にしか進まない。……あれはそう遠くないうちに自滅するタイプですよ」
「……随分と、予言の勇者のことを調査したのね」
「それは、もう」
バルト・イルファは立ち上がり、踵を返す。
「それでは、僕はこれで。眠って準備をしておかないと」
「眠る……。ああ、そうだった。あなたは眠らないといけないのよね。別に身体の仕組みとしてはしなくても問題ないのだけれど、それをしないと気分的に」
「そうですね、まあ、人間時代からの残った忌まわしき風習じゃないですか? 今の身体ではそんなことする必要はないって言いますけれど、何か寝ないとはっきりしないというか。気持ちがリセットしない、とでもいえばいいのでしょうかね?」
「人間はそういう無駄な構造が多いからね。ま、私もそういう人間の一人ではあるけれど」
そう言ってリュージュは立ち上がると、バルト・イルファの顔を見つめる。
バルト・イルファはなぜ自分が顔を見つめられているのかわからず、首を傾げる。
「……あの、何かありましたか?」
「いいや、何でもない。とにかく、明日からタイソン・アルバを追いかけること。いいわね?」
はい、と言ってバルト・イルファは部屋を出て行った。
部屋に残されたリュージュは枕元のランプを消してベッドに横になる。
天井を見つめながら、彼女は呟いた。
「……人間の機能がメタモルフォーズに受け継がれている。それは、彼とロマだけ。そもそも彼らの素体は人間だ。人間ベースで生まれたメタモルフォーズだから、人間の仕組みがそのまま残ってしまった、ということなのかしら……?」
メタモルフォーズベースで人間のDNAを組み込んだところでそのようにはならない。
元々の形が人間であるからこそ、バルト・イルファとロマ・イルファは人間の形で行動出来るのである。
「まあ、小難しい話はあとで適当に科学者に話しておけばいい。あいつらは適当に科学の話をすれば平気で食いついてくるからな……」
科学者に任せてしまえばいい。
問題は一つ。
彼女にとっての問題は、現状一つしかなかった。
「予言の勇者の脅威がどこまで広がるか……」
予言の勇者は仲間を集めて、これからどんどんその勢力を増していく。
それがいずれ、彼女の計画に立ち塞がるようになったとしたら?
そして、バルト・イルファ等彼女の戦力を削ぐような戦力をあちらも保持するようになっていたら?
「そしたら、かなり厄介よね……。確かに私の目的には、あの予言の勇者が必要。だからそのためにも、彼らをあの場所に連れて行かねばならない……。いたって、いたって自然な形で」
ならばどうすればいいのか。
一体全体、どのように行動を誘導していけばいいのか。
「一先ず、あのタイソン・アルバを探してから考えるしかないわね。いずれにせよ、こちらもそう簡単に手を出せないし……」
そうして。
予言の勇者一行とリュージュ。
それぞれの夜はそれぞれの思惑や考えを張り巡らせたまま、ゆっくりと過ぎていった。
_ ◇◇◇
_ 次の日。
僕たちはドックに居た。いつも通り、という様子でドックの人間はただ僕たちを見て通り過ぎていくだけだった。
ドック内にある売店に入り、カウンターへと向かう。
「いらっしゃい。……昨日来ていたガキどもか。一応言っておくが、冷やかしだけはやめておくれよ。船を買うだけの金が無いなら、最初から船を欲しいなんて思わないほうがいい。メインテナンスも面倒だからな」
店員が不貞腐れたような様子で僕に言った。どうやら船はあまり売れていないらしい。その鬱憤を僕にぶつけたいようだが、とはいっても、僕にぶつけられたところで何も物事が変化するわけではない。まあ、ストレス解消くらいにしか思っていないのだろう。はっきり言ってそれは悪循環の第一歩にしか過ぎないと思うけれど。
それはそれとして。
僕は書状を見せる。それは国王たるリュージュの書いた船を提供するよう求めている書状だ。許可状といってもいい。これを見せることで船が一艘手に入るという、大変便利な書状だ。
それを見た店員は目を丸くして書状と僕を交互に見ていく。
そして、ゆっくりと、恐る恐る呟いた。
「……あんた、この書状を一体どこで……? いや、それはどうだっていい。とにかく、船を一艘ということだよな。国王陛下のご命令ならば、最新鋭の船を差し上げねば! おおい、ちょっと来てくれ!」
そうして店員は裏へと消えていった。正確には裏の扉を開けて、外に出て行っただけだが。
……何か、想像以上に面倒なことになりそうだぞ。
そんなことを思った僕だったが、もう遅かった。
_ 十分後。
「うへえ、あなたが船を所望している、と? しかも、国王陛下から直々に……ちょいと書状を見せていただいても……。ああ、成る程。これはすごい。素晴らしい。本物ですね。まぎれもない、本物です。きちんとした印も押されています。では、これはやはり、本物であると。へへえ、流石ですね。それにしても、どうしてそんな……。ふむふむ、おやあ! まさかあなたは予言の勇者様であると? 成る程、成る程。そのために、世界を救うためにここの船を使っていただけるとは! 国王陛下も、流石です」
……長い話をするのが好きそうな、恭しい笑みを浮かべた小太りの男が突然やってきて、僕たちに相槌をさせる暇も与えることなくずっと話をしていた。
ちなみに今の話の最中、相槌を入れようにも入れる暇が無い――というのはまさに文字通りの意味で、まるで何かを隠し通そうとしているくらいに間が無かった。
「とにかく、いずれにせよ、あなたたちに素晴らしい船を差し上げねば! そう、それは、最新鋭。世界のどこにもない、『錬金炉』によってエネルギーを転換させる技術を利用した、システム! これに名前を付けるなら……、いや、それは、いいでしょう。それは、所有者たるあなたたちが決めること。私たち、商人にとっては、どうだっていい話なのですから」
「錬金炉……って?」
そこで漸くルーシーが相槌、もとい質問をすることが出来た。
小太りの男はそれを聞いて大きく頷くと、踵を返す。
「あ、あのー……?」
「ここで説明するよりも、本物を見せたほうが、いいでしょう! あなたもそうは思いませんか? 確かに、説明することも立派な仕事です。ですが、見せながら説明することで、理解度が上がるはず! 現にこれから半永久的に利用されるのは、ほかではない、あなたたちなのですから!」
ああ、成る程。
そうならそうとはっきり最初から言ってくれればよかったのだが……、まあ、別につべこべ言う必要もないか。
そうして僕たちは船へと向かうべく、その小太りの男についていくのだった。
小太りの男が足を止めたのは、ちょうど船の目の前だった。
そこにあったのは大きな木造の船だった。はっきり言って四人で使うには大きすぎる。ただ、竜馬車は入ることが出来るのでそれについては問題なかった。
「この船は、設計から開発、そして完成まで、十年以上の歳月をかけています。ですから、我々の中でも自信作といっても、過言ではありません! ……さあ、中へお入りください」
それに従って、中へ入る。
甲板から階段を下りると、中央に巨大な機械が置かれていた。
「……これは?」
「これが、先程お伝えした、錬金炉になります。海水を取り出して、それを真水に分解します。そうして炉の中にある錬成陣……それにより酸素を作り上げます。一度、火をつけることでその火は消えることなく燃え続けます。そして、水は蒸気となりタービンを回して、エネルギーとなるのです。そうすることで、この船は、風が吹いていない凪の状態でも、動くことが出来るのです。どうですか、この船は」
つまり蒸気機関が搭載されている、ということか。
それにしてもこの世界の科学技術ってすごく発展しているように思える。まあ、もともと僕がいた世界に比べれば雲泥の差なのかもしれないが、魔術と錬金術が発達している時代であるというのに、これほどの科学技術を搭載した船を開発できる環境にあるということ、それについてはほんとうにこの世界の人たちが優秀なのだということが理解できる。
「船についての説明は、以上になります。何か質問はありますか?」
僕たちは何も言わなかった。
同時に、僕たちがこの船を選択した瞬間でもあった。
_ ◇◇◇
_ 海原を甲板から見つめていた。
この世界の海を見たのは、実に二回目になる。一回目は自分たちの船では無かったが、今回は自分たちの船。一回目と比べると少々余裕が生まれている感じになる。正確に言えば、今回の船だって自分自身で手に入れたものではなくリュージュの温情によって手に入れたものになるのだけれど。
「……どこへ向かうつもりだい?」
同じく甲板に立っていたルーシーが僕にそう問いかける。
「先ずはチャール島へ向かおうと思う。タイソン・アルバの足取りがはっきりとしないわけだし……、この広い海を闇雲に探すよりかはそちらのほうがいいんじゃないかな」
「確かにそうかもしれない。けれど、タイソン・アルバの話は無下にしても別に問題ないような気がするけれど……」
それを聞いて、僕は思わず振り返る。
約束を反故にするなんて、ルーシーらしくない発言だ。いったいどういう風の吹き回しなのだろうか?
ルーシーの話は続く。
「確かに人と交わした約束は守るべきだ。それに約束を交わした相手が国の王ならば、猶更ね。けれど、それ以上にやらないといけないことがあると思うんだよ。そうは思わないか? まあ、君は予言の勇者として世界を救うという目的があるから、小さいサブミッションをこなすことも大事なのかもしれないけれど……」
「それはそうだよ。やっぱり、世界を救うことは大事だ」
そうは言ってみたものの、やっぱり世界を救う――その大まかな流れはどうすればいいかはっきりとしていなかった。だってそもそも世界が壊れるような大きな問題に発展していないのだから。
そもそもこの世界はほんとうに壊れていくものなのだろうか。実際、メタモルフォーズによって徐々に世界が蝕まれていくのは解る。けれど、僕たちが旅をするほど重要なことなのだろうか、と考えると答えは出てこない。
「……世界を救うこと、か。フルは強いんだな。俺には全然出来ないよ、そんなこと」
「僕は――」
強くない、と言いたかった。
けれど、それは出来なかった。
ルーシーの期待を、裏切ることになってしまうと思ったから。
ルーシーに申し訳ない気持ちになってしまうから。
「おい、二人とも。そんなところで話している場合じゃないぞ!」
レイナの言葉を聞いて、僕たちは踵を返した。
そこに立っていたレイナは真っ直ぐと海の向こうを指さしていた。正確に言えば僕たちの船の進行方向でもあったわけだが。
「何が向かっている……?」
「マストに上って確認してみたけれど、あれはどうやら海賊船みたいだ! ……急がないと、このままだとぶつかってしまう!」
「ぶつかる……だって?! 相手は認識している、だろうな。だから、避けることは難しい……。となると、後、残された選択肢は」
戦うか、逃げるか。
そのいずれかしか残されていない、ということになる。
ともなれば、どうすればいいか。
「フル」
ルーシーが、僕の隣に立って、言った。
「……こういうとき、メアリーなら何て言うと思う?」
それを聞いて僕は頷いた。
「……きっと、メアリーならこう言っていただろうな。『戦おう』って」
剣を構えて、海賊船を見つめる。
それを見ていたレイナとシュルツさんは小さく溜息を吐いて、
「仕方ないわね……。私たちも準備することにしますか」
「戦いはあまり好きじゃないのだけれど……。まあ、仕方ないよね。避けられないというのであれば、猶更だ」
そうして僕たちは、それぞれの武器を構えて――海賊船を見据えた。
_ 海賊船が僕たちの船にぴたりと並ぶように停止したと同時に、僕たちの船も停止した。
そして、僕たちは海賊船の甲板に居る戦闘員たちをまじまじと見つめる。
「……人、多くない?」
ルーシーの抱いた第一印象――それは人の多さだった。
海賊船の人員がどれくらいかははっきりしていなかったとはいえ、四人で捌ききれる量だと勝手に思い込んでいた。
しかし、海賊船の乗組員は少なくとも五十人は居るだろう。その全員がサーベルを片手にこちらの船を見つめていた。
「人が多すぎ……。あーっ、でも、やるっきゃない!!」
レイナが覚悟を決めて、乗り込んでくるであろう戦闘員を待ち構えた、ちょうどその時だった。
先頭に立っていた赤いマントの男が右手を掲げた。
海賊が被るような黒い帽子を被っていた男は、おそらく船長だろう。赤いマントの下には黒い白衣――言葉が矛盾しているようだが、正確に言えば研究者が着用するような白衣だ――を身に着けていた。
男は言った。
「一言だけ言っておこう。我々は戦闘をする気はない。……そちらの船の面々とお話しがしたいだけだ。君たちは、おそらく私の名前を知っているだろう?」
そう言ってニヒルな笑みを浮かべる。
そして、僕はその顔を見て――失礼なことにその男を指さし、こう言った。
「お前は……まさか、タイソン・アルバ……!」
そう。
そこに立っていたのは、リュージュから捜索を依頼された、行方不明の科学者――タイソン・アルバだった。
「ん? その様子だと、もうリュージュから私の話を聞いている、ということになるな。結構、結構。できることならそちらのほうが大変有り難かった。一度初めから話をするのは非常に面倒だからな」
「……あなたは、いったい何者なんですか。確か、知恵の木の実を作り出すものを生み出した、と……」
「正確に言えば、そいつは間違っている。私はいろいろなものを研究し、そして実際に生み出した。しかしながら、それは大いなるリュージュ様のためを思って、そして、世界のために作り出したものに過ぎない。あのころの私は……はっきり言っておかしかった。風変りだった、といってもいい。けれども、私は研究が楽しかった。大好きだった。それを、あの女に付け込まれたといってもいいだろうな……」
そう言って。
タイソン・アルバはゆっくりとこちらの船に乗り込んできた。
僕たちはタイソン・アルバが何を仕出かすのか解らず、戦闘態勢を取った。
それは相手も同じだった。タイソン・アルバ以外の乗組員も皆、同じように戦闘態勢に入る。
しかし、タイソン・アルバだけが冷静に、それでいて普通に、踊るように歩いていた。
「……何を考えている? タイソン・アルバ。僕はあなたのことは知らない。知らないからこそ、訳が分からない。一体全体、あなたは何を……」
「私から言わせてみれば、君たちのほうがおかしい考えを持っている、ということになるよ。予言の勇者一行、とでも言えばいいかな?」
「……それをどうして?」
「知らないわけがない。リュージュはずっとそれを望んでいた。ずっと、予言の勇者がこの世界にやってくることを欲していた」
「……つまり、リュージュはずっと」
「ああ、知っていたとも。知っていたからこそ、計画を実行に移すことを考えていた」
徐々に、タイソン・アルバが恐ろしくなってきた。
いや、実際には予言の勇者――つまり、ぼくのことだけれど――を何らかの計画に組み込もうと考えていたリュージュが恐ろしいのだが、それ以上に、タイソン・アルバが恐ろしい。どうして彼はそこまで事実を知っているのか、ということに驚いている。そこまでぺらぺらと語られてしまうと、ほんとうに彼の言っている言葉は正しい言葉なのかどうか解らなくなってしまう。
「タイソン・アルバ。あなたはいったい、何を知っている? そして、何をしようとしている?」
「私は何もしようとは思っていないさ。……ああ、いや、それは間違いだったね。正確に言えば、私は間違いを正そうとしている。ただ、そのためには力が必要だよ。だからこそ、それは間違いだったと思っている、その自分を正すことと等しい。私はいったい何をしていたのか、気づくまでにあまりにも時間がかかりすぎた」
「それは……」
「リュージュに従って行った研究は、最終的に人間を滅ぼす悪魔の研究だった、ということだ」
その言葉は、端的であったが全てを表していた。
リュージュが求めていたもの――その意味が漸く解ってきた。
タイソン・アルバの話は続く。
「……正確に言えば、ずっと私の研究は私のメリットがあるものしかしてこなかった。それは当然だ。それが研究者たる所以と言っても過言ではない。けれど、あの研究を始めたとき……私はもう、あの女王にはついていけないと思った。知恵の木の実は、この惑星の長い記憶をエネルギーにすることで、それを錬金術の素材としている。そして、それを人工的に作るとすれば、……はてさて、何が必要だったと思う?」
「まさか……!」
ルーシーの言葉に、タイソン・アルバは大きく頷いた。
「そこの君はもう解っているようだね。……そうだ、知恵の木の実は記憶エネルギー。つまりその記憶エネルギーを濃縮させたものが知恵の木の実。……人間の記憶エネルギー一人分ならばたいしたエネルギーではないかもしれないが、それが何十人と集まれば、どうなるか? あっという間に知恵の木の実の完成だ」
「人を殺した、というのか?!」
僕は思わずタイソン・アルバを睨み付けていた。けれど、そうなるのも当然だ。つまり、私利私欲のためにタイソン・アルバはたくさんの人間を犠牲にしたのだから。
タイソン・アルバは憂う目で僕たちを見つめた。
「……そう言う気持ちも解る。だが、激高せずに最後まで聞いてほしい。私は確かにそれを望んだかもしれない。だが、それを作り出していくうちに、私は何をしているのか……解らなくなってきた。老人も、少年も、青年も、子供も……私は容赦なく彼らの記憶を知恵の木の実という器に満たしていった。それによって、私の精神は……壊れた。そう、壊れてしまった」
「それで――リュージュから逃げた、ということか?」
こくり。タイソン・アルバはそうしっかりと頷いた。
タイソン・アルバの話を聞いているうちに、僕たちは共通の見解を示すようになった。
_ ――リュージュは僕たちにとって、害のある存在ではないだろうか?
_ リュージュを害のある存在とは思っていなかった。別に百パーセントの善人であるとは到底思っていなかった。とはいえ、国を治める人間だからある程度の信用を置いていた。
しかし、今思えばそれが間違いなのかもしれない。
「リュージュはメタモルフォーズの研究をしていた。その指導者であったよ。正確に言えば、研究自体は研究者に任せて、彼女はその統括を行っていた……ということだ。私はその中で一研究員に過ぎなかったが……、その研究内容が高評価だったためか、かなりの確率でリュージュに途中経過を報告することが多かった」
「そこでリュージュに出会った、と」
再び、タイソン・アルバは頷いた。
「リュージュは、私の研究にかなり力を注いでいるようだった。シュラス錬金術研究所……今はどうなっているのか知らないが、あそこの所長がよく私に言っていたよ。メタモルフォーズの研究よりも、最近はそちらのほうに熱が入っている、と」
シュラス錬金術研究所といえば、この前入った場所だろう。メアリーをかくまっていたらしいが、僕たちがやってくる前にバルト・イルファが別の場所に護送したらしい。だから会うことは出来なかったのだが、最後に水を操るメタモルフォーズが出てきたのは覚えている。あいつはかなり強敵だった。レイナの機転が無ければ倒すことが出来なかったかもしれない。
ということは。
タイソン・アルバは別に悪い人間ではない――ということなのだろうか。確かに、話だけ聞いてみればタイソン・アルバは研究について自分の探求心を貫いてきただけであって、結局悪いことをしていたわけではない。むしろそれを命令したリュージュが悪い、という結論になるのだろうが。
「私の研究は長く続けられることとなった。潤沢な資金も入り、人を集めることもできるようになった。そうして、人はどんどん知恵の木の実になっていった。私はそれを毎日献上していった。それを目の前でリュージュは一口齧り、その味を確かめていた。……知恵の木の実に味があるのかは、食べたことのない人間には解らない話ではあるがね」
「……一つ質問なのだけれど、記憶エネルギーを失った人間はどうなる?」
「死ぬよ。記憶には色々な種類がある。記憶は行動を起こすと電気信号に変換され、脳のネットワーク内を縦横無尽に駆け巡る。そして最終的に長期的に記憶を保管する場所に記憶として保管される。そしてその容量は無限大といっても過言ではない。もちろん、星の記憶と比べれば微塵にも満たないがね。その記憶が一切失われた状態……それは即ち、赤ん坊と同じ状態になる。本来は生きていてもおかしくないのだが……、はっきり言って生きるのは不可能だと思うよ。だから、正確に言えば、死ぬのではない。『生きることが社会的に難しくなる』ということだ」
「新たに記憶を覚えることもできない、と?」
「簡単に言えば、記憶を覚えることと記憶を思い出すこと、この処理は有限だ。つまり回数を増やしていけば、それほど昔の記憶は思い出せなくなってしまう。記憶エネルギーの取り出しは通常の記憶を思い出すことよりも脳に負荷をかけてしまう。だから、記憶エネルギーを完全に吸い出されてしまったあとの脳は、記憶力がほぼ皆無と化してしまう。すぐに物事を忘れてしまうことや、メモを使わないと日常生活を送れなくなるほど。というか、自分が何者であるかすら解らないからね。まずはそこから覚えてもらう必要があるけれど」
タイソン・アルバはそこまで言って、会話を区切った。
僕たちとタイソン・アルバ、それにタイソン・アルバの船の乗組員たちの間で、静寂が広がる。
静寂を破ったのは、シュルツさんだった。
「……それで、今まで話を聞いてきたわけだけれど、一つ解らないことがある。タイソン・アルバ……だったかな。君はいったいどうしたい?」
「どうしたい、とは……どういうことだ?」
タイソン・アルバはシュルツさんのほうを見て言った。
睨み付けているように見えるが、敵意を抱いているのだろうか?
そんなことはないと思うが、シュルツさんもそれに負けじと同じように睨み付けるようにタイソン・アルバのほうを見て、
「つまり、簡単なことだ。タイソン・アルバ、あなたはずっと海で生活をしてきたのだろう? おそらく、リュージュから逃げるように。だけれど、彼らに話をしたということは、何らかの意味があったから。そして予言の勇者であるということを知っていたのならば、猶更だ」
「……そういうことか。確かにその通りだ」
タイソン・アルバは頷いて、僕のほうに向きなおすと、
「フル・ヤタクミ。リュージュを止めてくれないか」
唐突に話題が変わってしまい、僕はたじろいでしまった。
しかし、タイソン・アルバは今までの話を聞いていれば、リュージュは悪い奴だとしか言っておらず、助けてほしいなど一度も言ってはいなかった。いったい、どういう風の吹き回しなのだろうか?
しかしながら、タイソン・アルバの目は嘘を吐いているようには見えない。となるとやはり、ほんとうにリュージュを止めてほしいと思っている?
「信じてくれないかもしれない。だが、リュージュはきっと、何か考えがあって、それを行おうと思っているのだろう。それがどれほどの作戦の規模になるかは解らない。だが、そのために人間を……世界を危険に晒す必要なんて無い。それならば、何か別の方法があるはずだ。それを模索しないと、何も始まらない。そうではないか?」
「……つまり、あなたはリュージュは悪いことをしている一方、考えとしては悪いことをしていない、と?」
「そうは言っていない。ただ、殺すのはどうか、という話だ。戦うことは間違っていないだろう。なぜなら彼女は人道に反したことを行っているわけだから。けれども、そうだと言って、そのまま殺してしまうのはどうか、という話だ」
……タイソン・アルバはリュージュの味方でありたいのか、敵で居たいのか?
解らなくなってきたが、それを簡単に質問するわけにもいかない。
「だから、私はそのためにできることをする。まずはこれを君にあげよう」
そう言って、タイソン・アルバは知恵の木の実を差し出した。
けれど、それは人の記憶が詰め込まれたものだ。もっと言うなら、人の命がその一つ作ることによってどれくらい失われたのだろうか。それを考えると、素直にそれを受け取ることは出来なかった。
タイソン・アルバは僕が困っている様子を理解したのか、首を傾げて、そちらを見た。
「……もしかして躊躇しているのかね? ならば、それはあまり考えないほうがいい。これを開発した私が言うのも何だが……。この知恵の木の実にはまだ人間の生きたいという意思が込められている。どうか使ってはもらえないか? そうでないと、記憶エネルギーを吸われた人間が浮かばれない。あくまでも、これは勝手なエゴになるわけだが……」
命はまだ生きようとしている。
このような姿になっていたとしても。
まだ生きたいと願っている。
おそらく――もう元の姿に戻れないと知っていたとしても。
「……じゃあ、僕は、僕たちは、これをどう使えばいい?」
「おい、フル! この科学者(マッドサイエンティスト)のいうことを聞くのか?!」
ルーシーが僕とタイソン・アルバの会話に入ってくる。それにしても、本人の目の前でマッドサイエンティスト呼ばわりというのはどうかと思うが……。
それはそれとして。
タイソン・アルバは溜息を吐いて、頷く。
「それで、どうする? これを受け取るか、受け取らないか。これがどう作られたかはさておいて、知恵の木の実はこの世界において重要なアイテムだと思うが?」
「それは……」
知恵の木の実さえあれば、どれくらい戦闘が楽になるか。それは僕だって解っていた。けれど、やはりそれが生まれた由来がどうしても気になってしまう。人間の記憶エネルギーを濃縮することで作り上げた、人工の知恵の木の実。それを使うことは、命を蹂躙することにほかならないだろうか?
「知恵の木の実は重要なアイテム。それは解っている。けれど、それは人の命を使って生み出されたものなのだろう? だったらやっぱり受け取ることは出来ないと思うのだけれど、どう思う。フル? これはあくまでも僕の考えだ。だから、君が受け取るべきと言うのであれば、受け取って構わないと思うよ」
つまり。
ルーシーとしては別にどうだっていいが、どちらにせよ、人の命を使って生み出したものであることには変わりないということだ。
それは僕だって解っているし、理解している。けれど、知恵の木の実さえあれば大分戦略的に余裕が生まれる。
じゃあ、どうすればいいか。
一体全体、僕はどう選択すればいいか。
タイソン・アルバは話をつづけた。
「……私は君たちに、世界を救ってもらいたいと思っている。そして、その第一段階で手助けをしたい。これは私自身の贖罪だ。君たちにこれを使ってもらって、世界を救ってほしい。その一助になれば……私はそう思っているのだよ」
それは、勝手な言葉だった。自分勝手な言葉だった。
タイソン・アルバの、自分自身の贖罪という言葉を果たすための。
自分勝手な言い訳に過ぎない。
「……もう、その研究はしていないんだよな?」
僕はタイソン・アルバに訊ねる。
それは、ほんとうに贖罪の意志があるのか――その確認でもあった。
タイソン・アルバは間髪入れることなく、はっきりと言い放った。
「ああ。もうその研究はしていない。それに関する資料は破棄している。そして、これが人の記憶エネルギーを使って作り上げた最後の知恵の木の実だ。ああ、あと言わないでいたが、ここに居る乗組員は大半が私の研究を手伝ってくれた人たちだ。だから、彼らも私の味方ということになる」
「……それを聞いて、少しだけ安心した」
僕はそう言って、タイソン・アルバが持っていた知恵の木の実を受け取った。
「おい、フル。……いいのか、そいつを受け取って?」
「ああ。別に何の問題もない。……この世界を救うためにも、僕たちはこれを使うべきだ。そうじゃないと、この知恵の木の実に蓄えられてしまった命が無駄になってしまう」
「そう言ってくれて、とても嬉しいよ」
タイソン・アルバはポケットに入っていたコンパスを差し出した。
「……これは?」
「これは不思議なコンパスでね。探し物を見つけることが出来る。普通のコンパスは向いた方角を指すだろう? だが、これは違う。探したいものを、その思いを込めることでコンパスが方角を指すということだ。これも君に差し上げよう。……恐らく、何か探し物をしているのだろう?」
「なぜ、それを……」
「まあ、色々と解るということだよ」
タイソン・アルバはただそれしか言わず、踵を返した。
「……これから、どうするつもりだ?」
「これから、か。まあ、簡単なことだ。私たちにはもう居場所はない。ただ海を彷徨うだけだよ。港に到着して、食料を調達して、……一応海賊行為はしていない。そんなことをしてしまえば返り討ちにあうのがオチだ。だから我々は平和な行動しかしていない。これがいつまで続くかは解らないがね」
_ ◇◇◇
_ 僕たちは、タイソン・アルバとの船と別れた。
徐々に、タイソン・アルバの船が小さくなっていく。乗組員の人たちも、どんどん小さくなっていった。どうやら彼の言った通り、ほんとうに優しい人ばかりなのかもしれない。
「なあ、フル。ほんとうにこれを受け取って良かったのか?」
ルーシーは僕が持っている知恵の木の実を指さして、言った。
「まだ言っているのか、ルーシー? 別に僕は問題ないと思うよ。いや、正確に言えば問題ないわけじゃないけれど、このまま後ろ向きに物事を考えていちゃダメってこと。前向きに考えないと。僕たちはこの世界を、救わないといけないのだから」
「そう……かもな」
ルーシーはあっさりと納得してくれた。
「ところで、メアリーはどこへ向かったのかしら?」
レイナは僕の目の前にあったコンパスを覗き見る。
タイソン・アルバからもらったもう一つの品。金色に輝くコンパス。普通に考えると富豪が持つ嗜好品のように見えるが、彼曰く、探し物を見つけるためのコンパスなのだという。
だから、僕はその言葉を信じて、メアリーを探した。
するとそのコンパスは北西の方角を指した。
「……北西だ」
「北西。オーケイ、それじゃ向かおうじゃないか。メアリーを助けに!」
そうしてルーシーは舵を取ると、船を北西へ向けていくのだった。
チャール島が――僕たちの視界がそれを捉えるまで、そう時間はかからなかった。
_ ◇◇◇
「何がだね」
そのころ、タイソン・アルバの海賊船では、部下の一人とタイソン・アルバが話をしていた。
タイソン・アルバは部下の言葉を背中で受けて、踵を返した。
「予言の勇者に最後の一つを差し出して。確かにあれが一つあればリュージュを油断させることも出来ましょう。しかし、あれは我々の切り札だったはず。それを差し出すことで、我々には打つ手なしということになってしまいます。もしこの状況でリュージュの手先がやってくるようだったら……」
「それは、その時に考えるしかあるまい。神が我々の生きる時間がそこまでと定めたならば、それに従うまで、だ」
「しかし……!」
焦る部下を他所に、タイソン・アルバはその言葉を手で制した。
「積もる話もあるが、一先ずここまでとしよう。……なぜなら、」
彼の背後には、一人の少年が立っていた。
燃えるような赤い髪に、赤いシャツ。そしてその赤を引き立てるような白い肌。
バルト・イルファが、タイソン・アルバの背後に立っていた。
それを確認するように背後を見つめて、タイソン・アルバは言った。
「――上客がやってきたようだからな」
踵を返し、タイソン・アルバはバルト・イルファと対面する。
バルト・イルファは笑みを浮かべて、両手を広げた。まるで、自分には戦う意思が無いということを見せつけるかのように。
バルト・イルファは一歩近づき、
「お久しぶりです、タイソンさん。どれくらいぶりでしょうね? あなたが僕の調整役から離れて……ということになるので、もう五年近くになりますか? まさか、このような形で再会することになるとは……。いやはや。運命とは皮肉なものですね」
「バルト・イルファ……。私もまさか、このような状況で再会することになるとは、思いもしなかったよ。それに、これほどまでに時間がかかったのは、ただ手古摺っただけでは無いのだろう? 例えば、そう……。予言の勇者と私を邂逅させるために、それまで待機していた、とか」
それを聞いてバルト・イルファは目をぴくりと痙攣させた。
「……解っていましたか。さすがは、リュージュ様がお目を掛けていただけはある」
「舐めるなよ、メタモルフォーズと人間の合成獣が。私はお前をそのような戦闘兵器にするために開発したわけではないのだ。人間の進化の可能性に賭けていた……ただ、人間の進化、そのためだけに……!」
「舐めているのはお前のほうだよ、タイソン・アルバ」
バルト・イルファは今までと口調が変わった――冷淡な口調でタイソン・アルバに言い放った。
タイソン・アルバが驚いている様子を見せていると、バルト・イルファはそれに気付いて溜息を吐く。
「第一、僕が何を言っているか解っていない。もっと言うならば、なぜここにやってきたのか解っていない。タイソン・アルバ、お前は解っているつもりでその発言をしたのかもしれないが、リュージュ様はもともと人間の進化の可能性で僕たちを開発したんじゃない。いや、リュージュ様直々に開発したわけじゃないから、正確にはその命令をしただけではあるが。リュージュ様はもともと一つの結末に向けて、すべてそれのために物事を実行しているだけに過ぎない。僕たちを開発したり、メタモルフォーズの研究をしたり……」
「まさか……、そんな、まさか! そんなはずがあり得ない! リュージュが、もともと、人間の進化の可能性を考えずに……。では、もともとその得体のしれない計画を実行していた、ということなのか!?」
こくり、とバルト・イルファは頷いた。
それを聞いて、タイソン・アルバは信じられなかった。それは即ち、自分の研究がずっと裏切られていた――ということなのだから。
バルト・イルファの話は続く。
「リュージュ様は誰にもその計画を話したことはない。だが、僕たちの研究はもっと大きな計画によって実行されていたことは、僕たち自らが調べ上げて知ったよ。まあ、だからといって何も変わらない。リュージュ様に対する忠誠は変わることがない、ということさ」
「リュージュへの忠誠……。違う、それはきっと、プログラミングされたものに過ぎない! リュージュは自らの臣下に置くメタモルフォーズを開発する際、彼女の命令を聞くように、彼女の忠誠心を常に持つように思考をプログラミングしろ、というのがあった。だから、それによって……」
バルト・イルファはもう話を聞くのが面倒になったのか、頭を掻いた。
そうして、深い溜息を吐いて、バルト・イルファは言った。
「あんた、いろいろと煩いよ?」
バルト・イルファは右手に炎を作り上げた。ノーモーションで生み出す魔術は、彼自身が魔術の仕組みを理解していることと、それについての代償が存在していないと不可能だ。しかし、それが実行できているということは……、その二つが成し遂げられているということを意味していた。
それを見たタイソン・アルバは、もう逃げられないと悟った。
だからこそ、彼は言った。
「……こうやって邪魔者を消していく、というわけか。差し詰め、お前はリュージュにとっての邪魔者を消す暗殺部隊ということになる……わけか」
「何が言いたいのですか? 哀れみ? 憐み? それとも、悲しみ? もしその感情を抱いているのならば、無視していただいて構いませんよ。あなたにとって、それは関係のないことですし、そもそもあなたはその対象に殺されようとしているのですから」
「バルト・イルファ……!」
「一応、リュージュ様に言われていたので、最後に確認しておきましょうか」
バルト・イルファは右手に火球を構えたまま、タイソン・アルバに訊ねた。
「もし今、ここで『戻る』と言ってくれればあなたの命は保証しましょう。後ろにいる、正確に言えばこの船に乗っている研究員の方々の命ももちろん保証します。しかし、ノーというのであれば……」
「存在価値があるから、殺すのが惜しいということか。リュージュも切羽詰まっている、ということだな」
バルト・イルファは何も言わなかった。
「……図星か。ならば、答えは最初から決まっているよ」
タイソン・アルバは目を瞑り頷くと、バルト・イルファに向き直った。
「私はもうあの場所には戻らない。人間を危険に晒すような研究をわざわざやりに戻るほど、私も馬鹿な人間じゃない」
バルト・イルファはどこか遠くを見つめたような表情をして、頷く。
「……そうですか。それは非常に残念です。タイソンさんは非常に優秀な研究者であることから、戻る意思があるのならば丁重に扱うようリュージュ様からも言われていましたから……」
そうして。
バルト・イルファの持っていた火球が徐々にその大きさを増していく。
バルト・イルファの顔から、笑顔が消えて――彼は言った。
「ならば、あなたの逃亡生活もこれで終わりです。タイソン・アルバ。あなたがずっと過ごしてきたこの船と、あなたを信じてついてきた研究員とともに海の藻屑と消えなさい」
直後。
タイソン・アルバの乗っていた海賊船は、火球により真っ二つに分断された。
_ ◇◇◇
_ チャール島に到着したのは夕方だった。スノーフォグ本土、ハイダルク島と比べると非常に小さい島であり、海岸線及び港の周りに建造物があることから、そこが島の中心なのだろう。
港にある橋に船を停泊させ、碇を下す。
「着いた。ここが……チャール島だ……!」
僕はそう言って、チャール島の大地に足を踏み入れた。
ルーシー、レイナ、シュルツさん、それぞれ荷物を持って同じように大地に降り立つ。
「それにしてもとても小さい町だね……。もしかして、ここがチャール島の中心街なのかな」
ルーシーの問いに、僕は答えることはできなかった。
それよりも町に広がる異様な気配が、とても気になっていた。
夕方なら、町に活気があってもおかしくない。それどころか、民家に明かりが灯っていない。
「どうして、人気が全く無いんだ……?」
チャール島の港町、フィアノにはただ風の吹く音だけが空しく聞こえるだけだった。